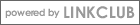Complete text -- "2010和洋女子大学公開授業 テキスト公開"
27 October
2010和洋女子大学公開授業 テキスト公開
Fate stay nightノートプロローグ第1日目、凛がサーヴァント召喚を行うあたりで、この仮構世界の基本原理を形成すると思われる特殊な概念とそれらの織りなす独特の関係性が紹介されている。興味深いのは、文字列とそこに振られた読みがな(ルビ)とが意味を乖離した二重構造を形成するという、一種のタイポグラフィーの工夫を活用してこの概念操作が行われている点である。
プロローグ
「Schliessung(ロック)、 Verfahren(コード)、 Drei(3)。」
聖杯戦争に参加する条件。それはサーヴァントと呼ばれる使い魔を招集し、契約する事のみだ。サーヴァントは通常の使い魔とは一線を画す存在だ。その召喚、使役方法も通常の使い魔とは異なる。
……サーヴァントはシンボルによって引き寄せられる。強力なサーヴァントを呼び出したいのなら、そのサーヴァントに縁のあるモノが必要不可欠なのだ、かぁ……つまり、そのサーヴァントが持っていた剣とか鎧とか、紋章とか、そういうとんでもない値打ち物だ。
「閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。」
繰り返すつどに五度。ただ、満たされる刻を破却する。
「―Anfang(セット)。」
……指先から溶けていく。否、指先から満たされていく。取り込むマナがあまりにも濃密だから、もとからあった肉体の感覚が塗りつぶされていく。だから、満たされるという事は、同時に破却するという事だ。魔術刻印は術者であるわたしを補助する為、独自に詠唱を始め、わたしの神経を侵していく。取り入れた外気(マナ)は血液に。始めよう。取り入れたマナを“固定化”する為の魔力へと変換する。視覚が閉ざされる、目前には肉眼で捉えられぬという第五要素。故に、潰されるのを恐れ、視覚は自ら停止する。
「Vertrag(令呪に告げる)….! Ein neuer Nagel(聖杯の規律に従い、) Ein neues Gesetz(この者、我がサーヴァントに) Ein neues Verbrechen(諌めの法を重ね給え)-- 」
―右手に刻まれた印が疼く。三つの令呪。聖杯戦争の要、サーヴァントを律するという三つの絶対命令権が行使される。
「……はあ。いいかね。令呪はサーヴァントを強制的に行動させるものだ。 それは“行動を止める”だけでなく、“行動を強化させる”という意味でもある。」
「そっか。サーヴァントは聖杯に呼ばれるけど、呼ばれたサーヴァントをこの世に留めるのは。」
「そう、マスターの力だ。サーヴァントはマスターからの魔力供給によってこの世に留まる。」
『FATE』では魔法使いによって召喚された“英霊”、つまり神話・伝説上の英雄的存在達が互いに戦い合い、莫大な願いを叶える力を備えているといわれる“聖杯”を勝ち取るゲームを展開する訳だが、ここで興味深いのは召喚の対象となる英雄達の素性である。彼等は、各々がギリシア神話や古代アイルランド神話等の中で活躍した、“英雄”と目されるものであったのだが、それぞれの存在する次元界面が異なっているために、互いに関わり合いを持つことがあり得ない独立したキャラクター同士だった。しかしこの『FATE』という一つのフィクションの中において、彼等の存在性向を束縛していた次元的断絶が超克され、一つのルールのもとに“戦い合う”という関係性を賦与されて、結果的にこれらのキャラクター達を媒介軸として、複数の神話・伝説の世界の統合と融和がなされる結果が招来していることになる。そればかりでなく、召喚された英霊の一人の佐々木小次郎などは、本人が自分が神話や伝説を通して醸成された存在とは異なる、純粋にフィクションの中の一切の現世的実体性を持たない存在であることを自覚しているのである。このゲームにおいては、何らかの歴史的事実を核としてその存在傾向を確定させていた神話・伝説上の存在達に加えて、さらにとりとめの無い空想上のキャラクターまでもが同一空間に勢揃いして、互いの存在論的意義性を付託し合うことが可能となっていることになる。このような世界観断絶の跳躍が可能となる可能世界次元として、『FATE』というフィクション空間を成立せしめている世界の肌理の構成単位、あるいは宇宙論的“場”がいかなる特質を持っているものとして仮定されているのかが、重要な論考の対象となるはずである。システム理論的には、この『FATE』というゲームにおけるオリジナルの“英雄”像であるアーチャーの存在までもがさらに付け加えられていることが、見逃すことのできない構造的特質となる。
Fate 2日目(2月1日)の重要箇所と思われる部分のテキスト。魔法とサーヴァントとの関連が、固有の専門用語を通して語られている。殊に興味深いのが、“英霊”とされるものの存在論的内実だろう。
聖杯に選ばれた魔術師はマスターと呼ばれ、マスターは聖杯の恩恵により強力な使い魔(サーヴァント)を得る。―――マスターの証は二つ。サーヴァントを召喚し、それを従わせる事と。サーヴァントを律する、三つの令呪を宿す事だ。アーチャーを召喚した事で、右手に刻まれた文様。これが令呪。聖杯によってもたらされた聖痕(よちょう)が、サーヴァントを召喚する事によって変化したマスターの証である。強大な魔力が凝縮された刻印は、永続的な物ではなく瞬間的な物だ。これは使う事によって失われていく物で、形の通り、一画で一回分の意味がある。
「……あいつの記憶が戻るまで法具(きりふだ)は封印か……思いだせないんじゃ使いようがないしね。」
「ああ、そういう事か。」
「それも問題ではない。確かに着替える必要はあるが、それは実体化している時だけでね。サーヴァントはもともと霊体だ。非戦闘時には霊体になってマスターにかける負担を減らす。」
「あ、そっか。召喚されたって英霊は英霊だものね。霊体に肉体を与えるのはマスターの魔力なんだから、わたしが魔力提供をカットすれば。」
「自然、我々も霊体に戻る。そうなったサーヴァントは守護霊のようなものだ。レイラインで繋がっているマスター以外には観測されない。もっとも、会話程度は出来るから偵察ならば支障はないが」
「マスター、私のクラスは何か忘れたのか。遠く離れた敵の位置を探るなど、騎士あがりにできるものか。」
――――固有結界。魔術師にとって到達点の一つとされる魔術で、魔法に限りなく近い魔術、と言われている。ここ数百年、“結界”は魔術師を守る防御陣と相場が決まっている。簡単に言ってしまえば、家に付いている防犯装置が極悪になったモノだ。もとからある土地・建物に手を加え、外敵から自らを守るのが結界。それはあくまで“すでにあるもの”に手を加えるだけの変化にすぎない。だが、この固有結界というモノは違う。固有結界は、現実を浸食するイメージである。魔術師の心象世界――心のあり方そのものを形として、現実を塗りつぶす結界を固有結界と呼ぶ。……周囲に意識を伸ばす。精神で作り上げた糸を敷き詰め、公園中を索敵する。
「……わたしじゃ見つけられない。アーチャー、貴方は?」
***************************************
ここで“レイライン”と呼ばれているものは、大地の気の流れとして知られるあの“ley line”とは異なる、独特の造語である“霊ライン”なのだろう。
“固有結界”についての説明の、“現実を浸食するイメージである。”という部分が、英霊の存在性と等質の存在論的仮説に基づいていることが分かる。このあたりの裏設定を理解するためには、物理現象の生成に関する“観測効果”についての理解を深めておく必要がある。
続いてFate 第3日目(2月2日)の前半。
人間存在あるいは英霊を規定する概念の中で、“たましい”と“精神”という言葉がいかなる背景のもとに理解されているかが、殊に興味深いものとなる。類例としては、「魂」と「魄」の関係性などを挙げることもできるだろう。
2月2日
一時的にこの呪刻(けっかい)から魔力を消す事はできるけど、呪刻(けっかい)そのものを撤去させる事はできない。術者が再びここに魔力を通せば、それだけで呪刻(けっかい)は復活してしまうだろう。内部の人間から精神力や体力を奪うという結界はある。けれど、いま学校に張られようとしている結界は別格だ。これは魂食い。結界内の人間の体を溶かして、滲み出る魂を強引に集める血の要塞(ブラッドフォート)に他ならない。古来、魂というものは扱いが難しい。在るとされ、魔術において必要な要素と言われているが、魂(それ)を確立させた魔術師は一人しかいない程だ。魂はあくまで“内容を調べるモノ”“器に移し替えるモノ”に留まる。それを抜き出すだけでは飽き足らず、一つの箇所に集めるという事は理解不能だ。だって、そんな変換不可能なエネルギーを集めたところで魔術師には使い道がない。だから、意味があるとすれば、それは。
「アーチャー。貴方たちってそういうモノ?」
知らず、冷たい声で問いただした。
「……ご推察の通りだ。我々は基本的に霊体だと言っただろう。故に食事は第二(たましい)、ないし第三(せいしん)要素となる。君たちが肉を栄養とするように、サーヴァントは精神と魂を栄養とする。」
地面に描かれた呪刻に近寄り、左腕を差し出す。左腕に刻まれたわたしの魔術刻印は、遠坂の家系が伝える“魔道書”だ。ぱちん、と意識のスイッチをいれる。魔術刻印に魔力を通して、結界消去が記されている一節を読み込んで、あとは一息で発動させるだけ。
「Abzug(消去) Beldienung(摘出手術) Mittelstnda(第二節)。Es ist gros(軽量)。 Es ist klein……(重圧)!!」
サーヴァント。七人のマスターに従う、それぞれ異なった役割(クラス)の使い魔たち。それは聖杯自身が招き寄せる、英霊と呼ばれる最高位の使い魔だ。 サーヴァントとは、それ自体が既に、魔術の上にある存在(モノ)なのだ。率直に言おう。サーヴァントとは、過去の英雄そのものである。神話、伝説、寓話、歴史。真偽問わず、伝承の中で活躍し確固たる存在となった“超人”たちを英霊という。人々の間で永久不変となった英雄は、死後、人間というカテゴリーから除外されて別の存在に昇格する。……奇跡を行い、人々を救い、偉業を成し遂げた人間は、生前、ないし死後に英雄として祭り上げられる。そうして祭り上げられた彼らは、死後に英霊と呼ばれる精霊に昇格し、人間サイドの守護者となる。これは実在の人物であろうが神話上の人物であろうが構わない。英雄を作り出すのは人々の想念だ。聖杯は英霊たちが形になりやすい“器(クラス)”を設け、器に該当する英霊のみを召喚させる。予め振り分けられたクラスは七つ。
剣の騎士、セイバー。槍の騎士、ランサー。弓の騎士、アーチャー。騎乗兵、ライダー。魔術師、キャスター。暗殺者、アサシン。狂戦士、バーサーカー。
この七つのクラスのいずれかの属性を持つ英霊だけが現代に召喚され、マスターに従う使い魔――サーヴァントとなる。サーヴァントとは、英雄が死後に霊格を昇華させ、精霊、聖霊と同格になった者を指す。かつて、竜を殺し神を殺し、万物に君臨してきた英雄の武器。サーヴァントは自らの魔力を以てその“宝具”を発動させる。言うなれば魔術と同じだ。サーヴァントたちは、自らの武器を触媒にして伝説上の破壊を再現する。敵サーヴァントを打破するには、その正体を知ることが近道となる。自分の正体さえ知らないバカものは例外として、サーヴァントにとって最大の弱点はその“本名”なのだ。サーヴァントの本名―つまり正体さえ知ってしまえば、その英霊が“どんな宝具を所有しているか”は大体推測できる為だ。言うまでもないが、サーヴァントは英霊である以上、確固たる伝説を持っている。それを紐解いてしまえば、能力の大部分を解明する事ができる。サーヴァントがクラス名で呼ばれるのは、要するに“真名”を隠す為なのだ。なにしろ有名な英雄ほど、隠し持つ武器や弱点が知れ渡っているんだから。サーヴァントとなった英霊は決して自分の正体を明かさない。サーヴァントの正体を知るのはそのサーヴァントのマスターのみ。
「願い?そんなの、別にないけど。」
「――なに?よし、よしんば明確な望みがないのであれば、漠然とした願いはどうだ。例えば、世界を手にするといった風な。」
「なんで?世界なんてとっくにわたしの物じゃない。」
「あのね、アーチャー。世界ってのはつまり、自分を中心とした価値観でしょ?そんなものは生まれたときからわたしの物よ。そんな世界を支配しろっていうんなら、わたしはとっくに世界を支配しているわ。」
気配が、気配にうち消される。
ランサーというサーヴァントの力の波が、それを上回る力の波に消されていく。……瞬間的に爆発したエーテルは幽体であるソレに肉を与え、
実体化したソレは、ランサーを圧倒するモノとして召喚された。
********************************************************************
凛の「願いや野望なんてものは別にない」という醒めた認識が、かつての伝説を形成した英雄達の保持していた筈の世界観とは明らかに異なる、はなはだ現代的な生の感覚をあらわしている。戦いの目的や偉業を成し遂げることなどの基幹原理に対する率直な疑問を提示する、常に反省的な意識がむしろこの作品の基調となっているのである。“英雄”の意味と“正義”の内実の再検証がこのエロゲーの中心的関心事なのである。
“エーテル”という概念については、物理学と宇宙論に関する歴史的な意味の変化を調べてみると興味深い。
遠坂凛の登場するプロローグは、魔法という主題に関してかなりややこしい裏設定のあるこのゲーム世界を解説する役割を果たしていたようである。プロローグであると同時に、凛パートでゲームを進めた場合の、ゲームオーバーを迎える一つの結末としても理解できるのが、ここまでの進行であった。
士郎パートの本編1日目の重要部分を以下に抜き出す。
Fate stay night
プロローグ
両親とか家とか、そのあたりが無くなってしまえば、小さな子供には何もない。だから体以外はゼロになった。要約すれば単純な話だと思う。つまり、体を生き延びらせた代償に。心の方が、死んだのだ。
1月31日
テーブルに朝食が並んでいく。鳥ささみと三つ葉のサラダ、鮭の照り焼き、ほうれん草のおひたし、大根とにんじんのみそ汁、ついてにとろろ汁まで完備、という文句なしの献立だ。古びた電気ストーブに手を触れる。普通、いくらこの手の修理に慣れているからって、見た程度で故障箇所は判断しにくい。それが判るという事は、俺のやっている事は普通じゃないってことだ。視覚を閉じて、触覚でストーブの中身を視る。――途端。頭の中に沸き上がってくる一つのイメージ。伝熱管がイカレてたら素人の手には負えない。その時は素人じゃない方法で“強化”しなくてはいけなかったが、これなら内部を視るだけで十分だ。それが切嗣に教わった、衛宮士郎の“魔術”である。
そう。衛宮士郎に魔術の才能はまったく無かった。その代わりといってはなんだが、物の構造、さっきみたいに設計図を連想する事だけはバカみたいに巧いと思う。実際、設計図を連想して再現した時なんて、親父は目を丸くして驚いた後、「なんて無駄な才能だ」なんて嘆いていたっけ。物事の核である中心を即座に読み取り、誰よりも速く変化させるのが魔術師たちの戦いだと言う。
「せーのっ、起きろー、タイガー。」
全員が声を合わせたわりには、呟くような大きさだった。
「……まったく、人が良いのも考え物だな。衛宮がいてくれると助かるが、他の連中にいいように使われるのは我慢ならん。人助けはいい事だが、もう少し相手を選ぶべきではないか。衛宮の場合、来る人拒まず過ぎる。」
「? そんなに節操ないか、俺」
「早く呼び出さないと死んじゃうよ、お兄ちゃん。」
鶏肉はじっくり煮込めば煮込むほど硬くなってしまう。故に、面倒でも煮る前に表面をこんがりと焼いておくと旨味を損なわずジューシーな仕上がりになる。
「じゃあ話しちゃおう。これがねー、士郎は困った人を放っておけない性格なのよ。弱きを助け強きをくじくってやつ。子供の頃の作文なんてね、ボクの夢は正義の味方になる事です、だったんだから。」
深夜零時前、衛宮士郎は日課になっている“魔術”を行わなくてはならない。
「―――――」
結跏趺坐に姿勢をとり、呼吸を整える。頭の中はできるだけ白紙に。外界との接触はさけ、意識は全て内界に向ける。
「―――同調(トレース)、開始(オン)。」
自己に暗示をかけるよう、言い慣れた呪文を呟く。
否、それは本当に自己暗示にすぎない。魔術刻印とやらがなく、魔道の知識もない自分にとって、呪文は自分を変革させる為だけの物だ。……本来、人間の体に魔力を通す神経(ライン)はない。それを擬似的に作り、一時的に変革させるからには、自身の肉体、神経全てを統括しうる集中力が必要になる。魔術は自己との戦いだ。例えば、この瞬間、背骨に焼けた鉄の棒を突き刺していく。 その鉄の棒こそ、たった一本だけ用意できる自分の“魔術回路”だ。これを体の奥まで通し、他の神経と繋げられた時、ようやく自分は魔術使いとなる。それは比喩ではない。実際、衛宮士郎の背骨には、目に見えず手に触れられない“火箸に似たモノが、ズブズブと差し込まれている。
「―――僕は魔法使いなのだ。」
そう言った衛宮切嗣は、本当に魔術師だった。数々の神秘を学び、世界の構造とやらに肉薄し、奇跡を実行する生粋の魔術師。その切嗣に憧れて、とにかく魔術を教えてくれとねだった幼い自分。だが、魔術師というのはなろうとしてなれる物ではない。持って生まれた才能が必要だし、相応の知識も必要になってくる。で、もちろん俺には持って生まれた才能なんてないし、切嗣は魔道の知識なんて教えてくれなかった。
なんでも、そんなモノは君には必要ない、とかなんとか。今でもその言葉の意味は判らない。それでも、子供だったじぶんにはどうでも良かったのだろう。 ともかく魔術さえ使えれば、切嗣のようになれると思ったのだ。しかし、持って生まれた才能―――魔術回路とやらの多さも、代々積み重ねて来た魔術の業も俺にはなかった。切嗣の持っていた魔術の業……衛宮の家に伝わっていた魔術刻印とやらは、肉親にしか移植できないモノなのだそうだ。魔術師の証である魔術刻印は、血の繋がっていない人間には拒否反応が出る。だから養子である俺には、衛宮家の刻印は受け取れなかった。
いやまあ。実際、魔術刻印っていう物がなんなのか知らない俺から見れば、そんなのが有ろうが無かろうがこれっぽっちも関係ない話ではある。で、そうなるとあとはもう出たトコ勝負。魔術師になりたいなら、俺自身が持っている特質に応じた魔術を習うしかない。魔術とは、極端に言って魔力を放出する技術なのだという。魔力とは生命力と言い換えてもいい。魔力(それ)は世界に満ちている大源(マナ)と、生物の中で生成される小源(オド)に分かれる。大源、小源というからには、小より大のが優れているのは言うまでもない。人間一人が作る魔力である小源(オド)と、世界に満ちている魔力である大源(マナ)では力の度合いが段違いだ。どのような魔術であれ、大源(マナ)をもちいれる魔術は個人で行う魔術をたやすく凌駕する。そういったワケで、優れた魔術師は世界から魔力をくみ上げる術に長けている。それは濾過器のイメージに近い。
魔術師は自身の体を変換回路にして、外界から魔力(マナ)を汲み上げて人間でも使えるモノ、にするのだ。この変換回路を、魔術師は魔術回路(マジックサーキット)と呼ぶ。これこそが生まれつきの才能というヤツで、魔術回路の数は生まれた瞬間に決まっている。一般の人間に魔術回路はほとんどない。それは本来少ないモノなのだ。だから魔術師は何代も血を重ね、生まれてくる子孫たちを、より魔術に適した肉体にする。いきすぎた家系は品種改良じみた真似までして、生まれてくる子供の魔術回路を増やすのだとか。
……まあ、そんな訳で普通の家庭に育った俺には、多くの魔術回路を望むべくもなかった。そうなると残された手段は一つ。切嗣曰く、どんな人間にも一つぐらいは適性のある魔術系統があるらしい。その人間の“起源”に従って魔力を引き出す、と言っていたけど、そのあたりの話はちんぷんかんぷんだ。確かな事は、俺みたいなヤツでも一つぐらいは使える魔術があって、それを鍛えていけば、いつか切嗣のようになれるかもしれない、という事だけだった。だから、ただその魔術だけを教わった。それが八年前の話。
切嗣はさんざん迷った後、厳しい顔で俺を弟子と認めてくれた。
「――――いいかい士郎。魔術を習う、という事は常識からかけ離れるという事だ。死ぬ時は死に、殺す時は殺す。僕たちの本質は生ではなく死だからね。魔術とは、自らを滅ぼす道に他ならない― 」
幼い心は恐れを知らなかったのだろう。強く頷く衛宮士郎の頭に、切嗣は仕方なげに手を置いて苦笑していた。
「――君に教えるのは、そういった争いを呼ぶ類いの物だ。だから人前で使ってはいけないし、難しい物だから鍛錬を怠ってもいけない。でもまあ、それは破ったって構わない。一番大事な事はね、魔術は自分の為じゃなくて他人の為にだけ使う、という事だよ。そうすれば士郎は魔術使いではあるけど、魔術師ではなくなるからねーー」
……切嗣は、衛宮士郎に魔術師になってほしくなかったのだろう。それは構わないと思う。俺が憧れていたのは切嗣であって魔術師じゃない。ただ切嗣のように、あの赤い日のように、誰かの為になれるなら、それはーー
衛宮士郎は魔術師じゃない。こうやって体内で魔力を生成できて、それをモノに流す事だけしかできない魔術使いだ。だからその魔術もたった一つの事だけしかできない。それが――
「――構成材質、解明。」
物体の強化。対象となるモノの構造を把握し、魔力を通す事で一時的に能力を補強する“強化”の魔術だけである。
「――、基本骨子、変更。」
目前にあるのは折れた鉄パイプ。これに魔力を通し、もっとも単純な硬度強化の魔術を成し得る。
そもそも、自分以外のモノに自分の魔力を通す、という事は毒物を混入させるに等しい。衛宮士郎の血は、鉄パイプにとって血ではないのと同じ事。異なる血を通せば強化どころか崩壊を早めるだけだろう。
今朝のメニューは定番の他、主菜でレンコンとこんにゃくのいり鶏が用意されていた。朝っぱらからこんな手の込んだ物を作らなくとも、と思うのだが、きっと大量に作って昼の弁当に使うのだろう。
十年前。まだあの火事の記憶を忘れられない頃は、頻繁に夢にうなされていた。それも月日が経つごとになくなって、今では夢を見てもさらりと流せるぐらいに立ち直れている。……ただ、当時はわりと酷かったらしく、その時からうちにいた藤ねえは、俺のそういった変化には敏感なのだ。
「……気のせいか、これ。」
なのに、目を閉じると雰囲気が一変する。校舎には粘膜のような汚れが張り付き、校庭を走る生徒たちはどこか虚ろな人形みたいに感じられる。青い方のソレに、吐き気がするほどの魔力が流れていく。周囲から魔力を吸い上げる、という行為は切嗣に見せてもらった事がある。それは半人前の俺から見ても感心させられる、一種美しさを伴った魔術だった。だがアレは違う。水を飲む、という単純な行為も度を過ぎれば醜悪に見えるように。ヤツがしている事は、魔力を持つ者なら嫌悪を覚えるほど暴食で、絶大だった。
こみ上げてくる物を堪えながら、手近な教室に入る。おぼつかない足取りのままロッカーを開けて、雑巾とバケツを取り出した。
「……あれ……なにしてるんだろ、俺……。」
まだ頭がパニックしてる。とんでもないモノに出会って、いきなり殺されたっていうのに、なんだってこんな時まで、後片付けをしなくちゃいけないなんて思ってるんだ、馬鹿。
「――――同調(トレース)、開始(オン)。」
自己を作り替える暗示の言葉とともに、長さ六十センチ程度のポスターに魔力を通す。 あの槍をどうにかしようというモノに仕上げるのだから、ポスター全てに魔力を通し、固定化させなければ武器としては使えないだろう。
「――――構成材質、解明。」
意識を細く。皮膚ごしに、自らの血をポスターに染み込ませていくように、魔力という触覚を浸透させる。
「――――構成材質、補強。」
こん、と底に当たる感触。ポスターの隅々まで魔力が行き渡り、溢れる直前、
「――――全行程(トレース)、完了(オフ。)」
「ゴーストライナー……?じゃあその、やっぱり幽霊って事か?」
とうの昔に死んでいる人間の霊。死した後もこの世に姿を残す、卓越した能力者の残留思念。だが、それはおかしい。幽霊は体を持たない。霊が傷つけられるのは霊だけだ。故に、肉を持つ人間である俺が、霊に直接殺されるなんてあり得ない。」
「幽霊……似たようなものだけど、そんなモンと一緒にしたらセイバーに殺されるわよ。サーヴァントは受肉した過去の英雄、精霊に近い人間以上の存在なんだから」
「――――はあ?受肉した過去の英霊?」
「そうよ。過去だろうが現代だろうが、とにかく死亡した伝説上の英雄を引っ張ってきてね、実体化させるのよ。ま、呼び出すまでがマスターの役割で、あとの実体化は聖杯がしてくれるんだけどね。魂をカタチにするなんてのは一介の魔術師には不可能だもの。ここは強力なアーティファクトの力におんぶしてもらうってわけ。」
「ちょっと待て。過去の英雄って、ええ……!?」
セイバーを見る。なら彼女も英雄だった人間なのか。いや、そりゃ確かに、あんな格好をした人間は現代にはいないけど、それにしたって――――
「そんなの不可能だ。そんな魔術、聞いた事がない。」
「当然よ、これは魔術じゃないもの。あくまで聖杯による現象と考えなさい。そうでなければ魂を再現して固定化するなんて出来る筈がない。」
「……魂の再現って……じゃあその、サーヴァントは幽霊とは違うのか……」
「違うわ。人間であれ動物であれ機会であれ、偉大な功績を残すと輪廻の枠から外されて、一段階上に昇華するって話、聞いたことない?英霊っていうのはそういう連中よ。ようするに崇め奉られて、擬似的な神様になったモノたちなんでしょうね。降霊術とか口寄せとか、そういう一般的な“霊を扱う魔術”は英雄(かれら)の力の一部を借り受けて奇跡を起こすでしょ。けどこのサーヴァントっていうのは英霊本体を直接連れてきて使い魔にする。だから基本的には霊体として側にいるけど、必要とあらば実体化させて戦わせられるってワケ。」
2月3日朝
「そうなると原因はサーヴァントね。貴方のサーヴァントはよっぽど強力なのか、それとも召還の時に何か手違いが生じたのか。……ま、両方だと思うけど、何らかのラインが繋がったんでしょうね。」
「ライン?ラインって、使い魔と魔術師を結ぶ因果線の事?」
「あら、ちゃんと使い魔の知識はあるじゃない。なら話は早いわ。ようするに衛宮くんとセイバーの関係は、普通の主人と使い魔の関係じゃないってコト。見たところセイバーには自然治癒の力もあるみたいだから、それが貴方に流れてるんじゃないかな。普通は魔術師の能力が使い魔に付与されるんだけど、貴方の場合は使い魔の特殊能力が主人を助けてるってワケ。」
「聖杯を手に入れる為にマスターがサーヴァントを呼び出す、じゃない。聖杯が手に入るからサーヴァントはマスターの呼び出しに応じるのよ。」
「マスター同士で和解して、お互いに聖杯を諦めれば話は済むと思っていたけれど、サーヴァントが聖杯を求めて召還に応じて現れたモノで、けして聖杯を諦めないのならば、それじゃ結局、サーヴァント同士の戦いは避けられない。 ……なら。自分を守るために戦い抜いてくれたあの少女も、聖杯を巡って争い、殺し、殺される立場だというのか。……なんてことだ。英霊だかなんだか知らないけど、セイバーは人間だ。昨日だってあんなに血を流してた。」
「あ、その点は安心して。サーヴァントに生死はないから。サーヴァントは絶命しても本来の場所に帰るだけだもの。英霊っていうのはもう死んでも死なない現象だからね。戦いに敗れて殺されるのは、当事者であるマスターだけよ。」
「そうよ。けれどサーヴァント達は私たちみたいに自然から魔力(マナ)を提供されている訳じゃない。基本的に、彼らは自分の中だけの魔力で活動する。それを補助するのがわたしたちマスターで、サーヴァントは自分の魔力プラス、主であるマスターの魔力分しか生前の力を発揮できないの。けど、それだと貴方みたいに半人前のマスターじゃ優れたマスターには敵わないって事になるでしょ?その抜け道っていうか、当たり前って言えば当たり前の方法なんだけれど、サーヴァントは他から魔力を補充できる。サーヴァントは霊体だから。同じモノを食べてしまえば栄養はとれるってこと。」
「簡単でしょ。自然霊は自然そのものから力を汲み取る。なら人間霊であるサーヴァントは、一体何から力を汲み取ると思う?まず、呼び出される英霊は七人だけ。その七人も聖杯が予め作っておいた役割(クラス)になる事で召還が可能となる。英霊そのものをひっぱってくるより、その英霊に近い役割を作っておいて、そこに本体を呼び出すっていうやり方ね。口寄せとか降霊術は、呼び出した霊を術者の体に入れて、なんらかの助言をさせるでしょ?それと同じ。 時代の違う霊を呼び出すには、予め筐(はこ)を用意しておいた方がいいのよ。」
「役割(クラス)――ああ、それでセイバーはセイバーなのか!」
「そういう事。英霊たちは正体を隠すものだって言ったでしょ。だから本名は絶対に口にしない。自然、彼らを現す名称は呼び出されたクラス名になる。」
「それもあるけど、彼らの能力を支えるのは知名度よ。生前何をしたか、どんな武器を持っていたか、ってのは不変のものだけど、彼らの基本能力はその時代でどのくらい有名なのかで変わってくるわ。英霊は神さまみたいなモノだから、人間に崇められれば崇められるほど強さが増すの。存在が濃くなる、とでも言うのかしらね。信仰を失った神霊が精霊に落ちるのと一緒で、人々に忘れ去られた英雄にはそう大きな力はない。」
「彼らにはそれぞれトレードマークとなった武器がある。それが奇跡を願う人々の想いの結晶、貴い幻想とされる最上級の武装なワケ。」
何故だろう。聖杯には、嫌悪感しか湧かない。望みを叶えるという杯。それがどんなモノかは知らないが、サーヴァントなんていうモノを呼び出せる程の聖遺物だ。どんな望みも叶える、とまではいかないにしても、魔術師として手に入れる価値は十分すぎる程あるだろう。それでも―俺はそんなモノに興味はない。実感が湧かず半信半疑という事もあるのだが、結局のところ、そんな近道はなんか卑怯だと思うのだ。それに、選定方法が戦いだっていうのも質が悪い。……だが、これは椅子取りゲームだ。どのような思惑だろうと、参加したからには相手を押し退けないと生き残れない。その、押し退ける方法によっては、無関係な人々にまで危害を加える事になる。だから、――喜べ衛宮士郎。俺の戦う理由は聖杯戦争に勝ち残る為じゃなくて、――君の望みは、ようやく敵う。どんな手を使っても勝ち残ろうとするヤツを、力づくでも止める事。
サーヴァントは英霊だ。その正体はあらゆる時代で名を馳せた英雄である。 彼らはクラス名で正体を隠し、自らの手の内をも隠している。サーヴァントの真の名はおいそれと知られてはならないもの。だが、同時にマスターだけは知っておかなければならない事でもあるのだ。何故なら、英霊の正体が判らなければ正確な戦力が判らない。マスターとサーヴァントは一心同体。どちらかが隠し事なんてしていたら、まともに戦える筈がない。
「ええ、それなのですが、……おそらく、これはもう私たちでは解決できない事です。私たちサーヴァントはマスターからの魔力提供によって体を維持する。だからこそサーヴァントはマスターを必要とするのですが、それが――」
「……俺が半端なマスターだから、セイバーが体を維持するのに必要なだけの魔力がないって事か?」
「違います。たとえ少量でもマスターから魔力が流れてくるのなら問題はないのです。ですが、シロウからはまったく魔力の提供がありません。本来繋がっている筈の霊脈が断線しているのです。」
ザッと考えて、まず揚げ出し豆腐。汁物は簡単な豆腐とわかめのみそ汁に。
下ごしらえが済んでいる鶏肉があるので、こいつは照り焼きにして主菜にしよう。豆腐の水切り、鶏肉の下味つけ、その間に大根をザザーと縦切りにしてシャキッとしたサラダにする。大根をおろしてかけ汁を作ってししとうを炒めて――
「協力体制を決めていただけよ。安心なさい、別に貴方のセイバーをとったりしないから。」
「――――!」
カア、と顔が赤くなるのが判る。
遠坂に言われて、自分が何に怒っていたのかに気づいてしまった。
……恐らく。
あの瞬間、自分の中にあった“殺される”という恐怖より、セイバーを“救えない”という恐怖の方が、遥かに強かっただけの話。
「そうですね。それが正常な人間です。自らの命を無視して他人を助けようとする人間などいない。それは英雄と言われた者たちでさえも例外ではないでしょう。ですから――そんな人間がいるとしたら、その人間の内面はどこか欠落しています。その欠落を抱えたまま進んでは、待っているのは悲劇だけです。」
20:25:56 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック