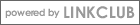Complete text -- "講演会テキスト"
13 February
講演会テキスト
ユニコーンとレッド・ブル
原作 The Last Unicorn に読み取れる
“アドワイト”あるいは“monism”の原理を反映する存在・現象記述
レッド・ブルとの遭遇
The Red Bull did not know her, and yet she could feel that it was herself he sought, and no white mare. Fear blew her dark then, and she ran away while the Bull’s raging ignorance filled the sky and spilled over into the valley.
p. 109
レッド・ブルはユニコーンがユニコーンであるとは分らないのだった。けれどもユニコーンは彼が白い雌馬などではなく、自分のことを捕まえようとしていることが分った。その時恐怖が彼女に襲いかかり、体の輝きを失わせた。そしてユニコーンは踵を返して逃げ始め、牡牛の猛り狂う無知は空を覆い、溢れて谷間に流れ込んだ。
何故かユニコーンは、漸く登場したこの怪物の体現する謬質の無知というおぞましい性向に気付くや、かつて知ったことのない恐怖感に襲われ、当初の目的であった筈の戦いを忘れて、一方的な逃走へと追いやられてしまうのである。そして走り去るユニコーンの後を追っていく牡牛に関する描写は、以下のようなひときわ興味深いものとなっているのである。
Yet without looking back, she knew that the Red Bull was gaining on her, coming like the moon, the sullen, swollen hunter’s moon.
p. 110
けれども振り返る必要もなく、ユニコーンはレッド・ブルがむっつりとして膨れ上がった狩人月のように迫ってくるのが分っていた。
圧倒的な力でユニコーンを追い立て、軽やかで素早いユニコーンにもたやすく追い付くことさえできる不可思議な能力を備えた妖獣レッド・ブルが、距離感と大きさの感覚の双方を失わせる、無気味な月の姿に喩えて語られているのである。あまりにも彼方の遠方にあり、そしてまた並外れて巨大なために地上の日常感覚を幻惑させてしまい、実際には静止しているはずなのに、いつまでも離れることなく後を追い続けてくるような異様な錯覚を与える月と同様に、莫大な体躯とは裏腹に、どこか実体感を欠いた現象世界から遊離したような希薄な印象さえ帯びている奇妙な怪物が、全てのユニコーンを世界から駆逐してしまったという、このレッド・ブルなのである。ここでこの新たなる神話的存在が喩えられている月の暗示する存在性向における際立った不定性あるいは非在性の感覚は、彼についてこの後も繰り返し語られることとなっているのである。
He had been huge when she first fled him, but in the pursuit he had grown so vast that she could not imagine all of him.
p. 110
レッド・ブルは最初にユニコーンが彼の前から逃げ出した時、既に巨大な体躯をしていた。けれどもユニコーンを追い立てていくうちに、彼の身体の大きさはさらにふくれあがり、もうユニコーンには彼の身体の全てを頭に思い浮かべることもできない程になっていたのだった。
この場面は、レッド・ブルの質量としての存在属性の不定性と、さらにまた材質と性向、あるいは実体と表象という存在傾向あるいは発現様相の占める筈の形相をも分別すること自体が全く意味をなさなくなる、ひいては他者の主観の内部に得られた一印象に過ぎないものとしての疑似存在性向までをも含めた、総合的連続体としての独特の原存在的非在性を強く暗示する部分なのである。そして現象物あるいは現象界を越えた超越的存在を記述の対象として選ぶにあたっての、一意的な客観的対象把握の原理的不能性を先鋭に自覚するこの感覚は、『最後のユニコーン』の物語全体を支配する、際立った思想的特質を反映するものともなっているのである。
言うならばレッド・ブルとはむしろ一個の存在物であるばかりでなく、全てを包含する自然界そのものの現す、多面的な様相の網羅的叙述の一側面のごときものでもまたあるらしい。次の描写の部分が、このような解釈の可能性に対して説得力のある弁護を与えると思われる実例を提供してくれている。
Now he seemed to curve with the curve of the bloodshot sky, his legs like great whirlwinds, his head rolling like the northern lights.
p. 110
今はもう、レッド・ブルの身体の輪郭は、血の色に染まった空の輪郭と重なっていた。彼の足は巨大なつむじ風のようで、彼の頭は極光のように旋回しているのだった。
ハガード王の城におけるアマルシア姫の心中の感覚
…魔法使いシュメンドリックの魔法の力によって死すべき(mortalな)人間の姿を与えられ、ハガード王の城の中で本来不死(immortal)であるユニコーンの永遠性の属性を失いつつあるアマルシア姫の覚える感覚は、彼女自身の独白の言葉として、以下のように語られていたのであった。
“...Even when I wake, I cannot tell what is real, and what I am dreaming as I move and speak and eat my dinner. I remember what cannot have happened, and forget something that is happening to me now. People look at me as though I should know them, and I do know them in the dream,...”
p. 157
「私は目を覚ましている時でさえ、身体を動かしたり口をきいたり食事をしたりしながらも、何が本当なのか、何が私が見ている夢に過ぎないのか、区別がつかないのです。私は起きたことのある筈のないことを覚えていて、今起こりつつあることを忘れてしまっているのです。人々は私が彼等のことを知っているに違いないという目つきで私の方に顔を向けます。けれども私が彼等に出会ったのは夢の中だった筈なのです。」
夢と現実、現象と妄想の間に本質的区別を持たない時間性を超越した永遠の存在の内部感覚が読み取られる。
大広間の不気味な骸骨の助言
“But the important thing is for you to understand that it doesn’t matter whether the clock strikes ten next, or seven, or fifteen o’clock. You can strike your own time, and start the count anywhere. When you understand that─then any time at all will be the right time for you.”
p. 175
「だが大事なことは、お前が時計が次に10時を打とうが7時を打とうが、15時を打とうが、そんなことはどうでもいいということを理解することなんだ。お前は自分の時を自分で打って、どこからでも好きなところから時を数え直すことができる。それさえ理解すれば、いつだってお前にとっての正しい時ということになるんだよ。」
ハガード王の城の大広間における骸骨の謎解きにおいては、語られた文言の秘匿された内実を掘り下げ、曖昧で全体像を正しく反映することのないと思われていた不明瞭な字句に適正な焦点を与えることによって、攪乱されていた総体としての意味性を再構築することを可能にするべく、矛盾と無意味の全てを再統括する力を発揮して玄妙な解式へと収斂させようとする類いの、伝統的な謎解き行為が導かれている訳ではない。むしろ彼の助言は、見出すべき意味と行うべき行為の目的性そのものを拡散させ、謎を成立させていた初期条件の関係性自体を無化させることによって問題性の解消を図ろうとする類いの、脱システム的解法となっているのであった。しかしながらこの謎解きの手法は、謎の立脚するシステム構造性のほころびを突き、謎の占めていた問題性を崩壊させることによってのみ目下の難題を回避しようとするような、姑息な手段が弄された例を示す訳でもない。
実際のところ、この無気味な助力者によって提示されているのは、“意識”という新規の次元軸を加えた際に得られる、全てを含んだ統合的宇宙構造に対する極限解式としての、時・空・精神連続体理論における精巧な修正版の時間論なのであろう。骸骨の語る時間論においては、主観主義、もしくは唯心論、あるいは我全主義(solipsism)の観点から統括した、全一的宇宙論の原則に従った極限の至高点からの時間意識が語られていると言ってもよい。このようにして得られた宇宙構造方程式においては、機械的な記述様式の変換を施すことにより、意識の内部機構として時間・空間の連続体が存在する、との新たな解式を導くこともまた当然可能であることになる筈なのだ。“時間”という次元をめぐって、『ピーターとウェンディ』におけるNeverlandの暗示していたものと同等の、“意識内世界”の特異な感覚が改めて提示されることになっていると考えてもまたよいものだろう。
地下の洞穴におけるレッド・ブルの描写
But its course was the impossible way of a dream: pitched and skewed, rounding on itself; now dropping almost sheer, now seeming to rise a little; now working out and slowly down, and now wandering back to take them, perhaps, once again below the great hall where old King Haggard must still be raging over a toppled clock and a shivered skull.
p. 181
けれどもこの通路の道筋は、夢の中の体験のような、あり得ないものなのだった。通路は速度を増し、歪み、いつの間にかもとの処に戻り、突然転がり落ちるように傾斜したかと思えば、いつの間にかまたゆっくりと昇っており、ようやく上りきってまた下りになり、そうするうちに再び曲がりくねって、ひょっとしてあの城の広間にまた戻ってしまい、そこではハガード王が崩れ落ちた時計と粉砕された骸骨を見下ろして猛り狂っているのではないかと思えるのだった。
上の描写において殊に顕著であるように、この生真面目な諧謔と詩的な斬新さと思弁的な野心に満ちたアンチ・ファンタシーのお伽話においては、運動と位置、存在と様態、実質と作用等の、本体となるべきものとその位相とされるべきものとの間の関係の絶え間ない逆転と変換の有り様が、ポー的な詩学的修辞法を彷彿とさせる極性転換のシステム理論に従って、周到に語り続けられているのである。
………
当然の事ながらユニコーンとシュメンドリックと相対することになる彼等の宿敵レッド・ブル自身の姿もまた、その担わされている対極的存在属性を忠実に反映して、上の場合と全く同質の記述手法の適用を受けなくてはならないことになるのである。
But he had come silently up the passageway to meet them; and now he stood across their sight, not only from one burning wall to the other, but somehow in the walls themselves, and beyond them, bending away forever.
p. 187
しかし牡牛は音も立てずに通路をたどり、彼等の許へやってきていたのであった。そして今牡牛は、彼等の眼前に姿を現していた。燃え上がる通路の壁の端から端までをふさいでいるばかりでなく、壁の内部にまで、そして壁の向こう側にまで突き抜けて、限りなく曲がりくねったその先までを牡牛の体が占めてさえいるのだった。
いよいよハガード王の城の内部で、再びレッド・ブルがユニコーン達一行の前にその姿を現した場面の描写は、上に引用したような極めて異様なものだったのである。ここにおいては、レッド・ブルの桁外れな程の巨大さが再び反転的に彼の実体性の欠如と、むしろ主観の中にのみ存在し得る悪夢的イメージとしての、非在物的要素を強く暗示しているばかりでなく、実は姿を現したものは通路の奥底に潜む牡牛であっても、あるいは牡牛の潜む通路であっても、あるいは通路を進むユニコーンの一行のそれぞれの主観の中に浮かぶ、とりとめのない焦燥と不安のいずれであっても、一向に構わないという類いのものなのだ。
ユニコーンとレッド・ブルの最後の対決の様
The unicorn lowered her head one last time and hurled herself at the Red Bull. If he had been either true flesh or a windy ghost, the blow would have burst him like rotten fruit. But he turned away unnoticing, and walked slowly into the sea.
p. 194
ユニコーンは最後にもう一度頭を低く下げ、赤い牡牛に飛び掛かった。もしも牡牛が本当の肉体を持っていたか、あるいは朧げな霊のようなものでさえあったなら、ユニコーンの一撃は牡牛を腐った果物のように粉砕したことだろう。しかし牡牛はその一撃に気付きさえもせずに、ゆっくりと海の中に足を踏み入れていったのだった。
この場面でもユニコーン達の姿の描写が行われた場合と正確に対称をなして、レッド・ブルの姿が再び現象世界的実体性を持たない、徹底的に観念上のものとして記述されていることが確認されるだろう。“real”な存在はmortalな人間が概念として把握する“true flesh”でも、あるいは“windy ghost”でさえもあり得ないものだというのである。
解放されて世に満ちたユニコーン達
“It was an earthquake,” one man murmured dreamily, but another contradicted him, saying, “It was a storm, a nor’easter straight off the sea. It shook the town to bits, and hail came down like hoofs.” Still another man insisted that a mighty tide had washed over Hagsgate; a tide as white as dogwood and heavy as marble, that drowned none and smashed everything.
p. 204
「あれは地震だった。」一人の男が夢の中のようにつぶやいた。けれども別の男が打ち消して言った。「あれは嵐だった。海から吹き付けてくる、北東風だった。風が町中をばらばらにして、馬の足音のように霰が吹き付けたんだ。」さらに別の男が、巨大な津波がハグスゲイトの町を襲ったのだと主張した。ハナミズキのように白く、大理石のように重い波が押し寄せて、誰も溺れさせることなく、全てのものを打ち壊したのだと言うのだった。
魔法や永遠の真実に関わることは、現象世界においては常に歪んだ形で把握され、その本質自体は決して理解し得ないのである。現象世界において具現する事象は、様々な要素の重ね合わせの一時的な発現形の一つに過ぎないのだ。その要素の各々を感知する者の主観に従って、様々のそれぞれ矛盾した偽りの“真実”があるに過ぎない。そこには夢における奇跡を統合的直観として認める感覚はあっても、夢と現実を峻別する分析的意識は全く認められないのである。
『アンチ・ファンタシーというファンタシー2 Peter S. Beagle 「最後のユニコーン論」』より抜粋
20:57:38 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック