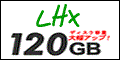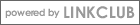Archive for 31 January 2006
31 January
Peter and Wendy 『ピーターとウェンディ』読解メモ 76
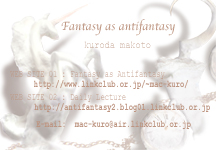
Chapter 5
THE ISLAND COME TRUE
Feeling that Peter was on his way back, the Neverland had again woke into life. We ought to use the pluperfect and say wakened, but woke is better and was always used by Peter.
In his absence things are usually quiet on the island. The fairies take an hour longer in the morning, the beasts attend to their young, the redskins feed heavily for six days and nights, and when pirates and lost boys meet they merely bite their thumbs at each other. But with the coming of Peter, who hates lethargy, they are under way again: if you put your ear to the ground now, you would hear the whole island seething with life.
On this evening the chief forces of the island were disposed as follows. The lost boys were out looking for Peter, the pirates were out looking for the lost boys, the redskins were out looking for the pirates, and the beasts were out looking for the redskins. They were going round and round the island, but they did not meet because all were going at the same rate.
All wanted blood except the boys, who liked it as a rule, but to-night were out to greet their captain. The boys on the island vary, of course, in numbers, according as they get killed and so on; and when they seem to be growing up, which is against the rules, Peter thins them out; but at this time there were six of them, counting the twins as two. Let us pretend to lie here among the sugar-cane and watch them as they steal by in single file, each with his hand on his dagger.
They are forbidden by Peter to look in the least like him, and they wear the skins of the bears slain by themselves, in which they are so round and furry that when they fall they roll. They have therefore become very sure-footed.
ピーターが戻りつつあるのを感じて、ネバーランドは再び活気づきました。“活気づいていました”と言わなければならないところですが、ピーターはいつもこう言うので、この方がいいのです。
ピーターがいないと、島では物事は何もかも穏やかに進みます。妖精達は、朝1時間余分にゆっくりします。野獣達は子供の世話をし、インディアン達は6昼夜たっぷりと栄養を蓄えます。そして海賊達とロスト・ボーイズ達が出会った時には、親指を噛む仕草をし合って相手を馬鹿にするだけです。けれども、だらけたことが大嫌いなピーターが現れると、誰もが元のやり方に戻るのです。もしも今地面に耳を押し当ててみたならば、島中が生気をみなぎらせてたぎっている音がすることでしょう。
この日の晩は、島における主要な勢力分布は以下のような状況にあった。ロスト・ボーイズ達はピーターを探しに出撃しており、海賊達はロスト・ボーイズ達を求めて出撃しており、インディアン達は海賊達を求めて出撃しており、野獣達はインディアン達を探し求めていた。4つの勢力は島をぐるぐると巡り続けていたが、皆同じ速度で進んでいたため、接触することはなかった。
少年達を除いて、他のどの勢力も流血を望んでいた。子供達も普段は同様だったのだが、今晩は首領のピーターを出迎えなければならなかった。島の少年達の人数は、殺されるなど折々に変化するので、当然ながら一定ではなかった。さらに子供達が大きくなってしまったような場合は、これは規則に違反することなので、ピーターが数を間引くのであった。けれども現時点では、子供達の人数は双子も2人と数えて、6人であった。サトウキビの茂みに身を隠したつもりになって、子供達が一列になり、一人一人短剣に手を乗せて気配を隠して進んで行くのを眺めてみることにしよう。
子供達はピーターによって、ピーターの姿に似た様子をするのをかたく禁じられていたため、自分で殺した熊の毛皮に身を包んでいたので、毛むくじゃらでころころとしていて、いったん転ぶと転がってしまうほどだった。だから彼等の足取りは、この上なく確かだった。
ネバーランドとピーターは、互いに緊密に連関した存在として描かれている。両者は同一物の示す発現形態の偏差の現れとして、あるいは共軛的に現れた二つの属性として解釈することも出来るだろう。
この島におけるロストボーイズ達と海賊達とインディアン達の行う堂々巡りの運動は、複雑系における円環的無限性を暗示しているようである。永劫回帰的な非発展性は、同時に調和と安定の具現化でもある。進歩と変化に対する忌避反応として、疑似中世的無時間性の世界創成に対する願望が、多くのファンタシー作品を生み出してきたのであった。魔法を科学の優位に置こうとする欲求は、統一原理に対する希求の念の現れであると共に、歴史的変化に対する抹殺願望の反転的現れでもあったのである。これらの要素に対してピーターという存在が及ぼす影響は、はなはだ暗示的である。
ロストボーイズ達は、海賊やインディアンという敵によって殺されることもあるし、逆にこれらの敵や島の野獣などを殺すこともある。ネバーランドは夢の世界ではあるが、そこで行われる体験の苛酷さは、現実のものといささかも変わるところは無い。
作者の読者に対する呼びかけは、make-believe(ごっこ遊び)として、その物語世界の構築活動に参入することを要求するものである。このメカニズムは、この物語世界の中のものとして語られている、ピーターとロスト・ボーイズ達の行うmake-believeと全く同等の機構のものとなっていることが興味深い。
用語メモ
pluperfect:“過去完了”。ピーターは、難しい言い回しを行うことができないのだという。記述の結果物語世界が生成するのではなく、記述以前に本来の物語世界の存在が碓としてあるかのような記述が行われている。記述行為のあり方を強く意識した記述である。
bite oneユs thumb:侮辱の身振り。子供達は、このような下品で粗野な仕草が大好きである。
「ミクシィ」でコミュニティ「アンチ・ファンタシー」を開設しました。
◆「最後のユニコーン」に関するSue Matheson氏の論文の解説等を行っています。
◆ アニメーション版「最後のユニコーン」における視覚表現についての解説を公開中です。
◆ ピーター・ビーグルに関する書誌データを公開中です。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=427647
参加希望の方は、以下のアドレスにご連絡下さい。招待メールをお送りします。
kuroda@wayo.ac.jp
メインページurl http://www.linkclub.or.jp/~mac-kuro/
論文、“アンチ・ファンタシーというファンタシー2:ファンタシーにおける非在性のレトリック─『最後のユニコーン』のあり得ない比喩と想像不能の情景”を新規公開中
00:00:00 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks