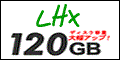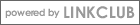Archive for 07 January 2006
07 January
Peter and Wendy 『ピーターとウェンディ』読解メモ 52
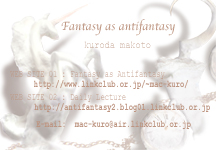
"Surely you know what a kiss is?" she asked, aghast.
"I shall know when you give it to me," he replied stiffly, and not to hurt his feeling she gave him a thimble.
"Now," said he, "shall I give you a kiss?" and she replied with a slight primness, "If you please." She made herself rather cheap by inclining her face toward him, but he merely dropped an acorn button into her hand, so she slowly returned her face to where it had been before, and said nicely that she would wear his kiss on the chain around her neck. It was lucky that she did put it on that chain, for it was afterwards to save her life.
When people in our set are introduced, it is customary for them to ask each other's age, and so Wendy, who always liked to do the correct thing, asked Peter how old he was. It was not really a happy question to ask him; it was like an examination paper that asks grammar, when what you want to be asked is Kings of England.
"I don't know," he replied uneasily, "but I am quite young." He really knew nothing about it, he had merely suspicions, but he said at a venture, "Wendy, I ran away the day I was born."
「でも、キスくらい知っているでしょう。」ウェンディは、唖然として尋ねました。
「君がくれたら分かるさ。」ピーターは、ちょっとこわばった感じで答えました。ウェンディはピーターの気持ちを傷つけないように、キスの替わりに指ぬきを差し出しました。
「じゃあ、僕もキスをあげようか。」ピーターが言いました。「そうなさりたいのなら。」ウェンディは、幾分とりすました感じで答えました。ウェンディが顔をピーターの方に傾けてしまったのは、どうも安っぽい仕草であったかもしれません。でもピーターはドングリのボタンを一粒ウェンディの手の平に乗せただけでした。ウェンディはゆっくりと顔をもとの位置に戻すと、このキスを鎖につけて首にかけておくわ、と言いました。ウェンディがこのドングリを鎖につけておいたことは、後になって彼女の命を救うことになりました。
普通私達の社会では、人とお付き合いを始める時には、お互いの年齢を尋ねるのが当り前です。そこでウェンディも、ピーターの年がいくつか尋ねました。ウェンディはみんながする通りちゃんとするのが好きなのです。でもこれは、ピーターにとっては聞かれて楽しいことではありませんでした。これは英国の王様達のことを尋ねて欲しい時に、文法のことを質問する試験問題みたいなものでした。
「僕は、自分の年は知らないんだ。」ピーターは、ちょっと落ち着かない感じで答えました。「でも僕はとても若いよ。」ピーターは本当に自分の年齢について、何も知りませんでした。ただなんとなく思うことがあっただけです。ピーターは、思いつくままに言いました。「ウェンディ、僕は生まれたその日に逃げ出したんだ。」
胸に着けたドングリが将来ウェンディの命を救うことになる、というのは、物語の進行を予期した記述となっている。物語性を自覚した物語の語りとして、本作品のメタフィクションの機構に関わってくる部分である。殊に作者の存在を、一人の登場人物として際立たせる効果を担っている点も見逃せない。
ピーターは考えることがなく、物事を覚えていることさえもないので、常に彼の語る言葉は、直感にのみ従った口からのでまかせである。このことは、ピーターという存在の特徴を決定付ける要素となると共に、この物語の根幹的主題とも深く関わることとなる。
用語メモ
set:ここでは“社会”、“仲間うち”のことである。
「ミクシィ」でコミュニティ「アンチ・ファンタシー」を開設しました。
◆「最後のユニコーン」に関するSue Matheson氏の論文の解説等を行っています。
◆ アニメーション版「最後のユニコーン」における視覚表現についての解説を公開中です。
◆ ピーター・ビーグルに関する書誌データを公開中です。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=427647
参加希望の方は、以下のアドレスにご連絡下さい。招待メールをお送りします。
kuroda@wayo.ac.jp
メインページurl http://www.linkclub.or.jp/~mac-kuro/
論文、“アンチ・ファンタシーというファンタシー2:ファンタシーにおける非在性のレトリック─『最後のユニコーン』のあり得ない比喩と想像不能の情景”を新規公開中
00:00:00 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks