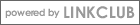Archive for October 2007
26 October
学園祭公開授業詳細
例年大学祭の公開授業として行ってきた催しは、今年は来年度から開設される「英語・英文学類 模擬授業」として開催されます。時間、場所は以下の通りです。13:00〜16:00(随時入室可)
東館11階 演習室4
3時間ずっと何かしゃべったり、映画を上映したりしていますので、気の向くままに出たり入ったり、質問してみたりおしゃべりしてみたりして下さい。
これまでに発表したビーグル研究は以下の通りです。
『最後のユニコーン』研究論文一覧
「アンチ・ファンタシーのポストモダニズム的戦略
―ビーグルの『最後のユニコーン』と"漫画性"」
「不毛の王国の貪欲なストイスト
―フック的アンチ・ヒーローと神格化された無知」
「ユニバーサル、ユニコーン
─『最後のユニコーン』におけるユニコーンの存在論的指標」
「ファンタシーにおける非在性のレトリック
―『最後のユニコーン』のあり得ない比喩と想像不能の情景」
「アンチ・ファンタシーの中のヒーロー
―『最後のユニコーン』のアンチ・ロマンス的諧謔性とファンタシー的憧憬」
「荒唐無稽とアナクロニズムとペテン的言説
─『最後のユニコーン』における時間性と関係性の解体と永遠性の希求」
「意味消失による意味性賦与の試み
―『最後のユニコーン』における夢と魔法と矛盾撞着と曖昧性」
「レッド・ブル―無知と盲目の影」
他にも色々資料や文献などを用意しておきます。ご希望があればプリントして差し上げます。
22:53:23 |
antifantasy2 |
8 comments |
TrackBacks
20 October
和洋女子大学学園祭公開授業
2007年学園祭公開授業内容ピーター・ビーグルと『最後のユニコーン』
担当:英文学科 黒田 誠
* 最新情報と旧作の出版状況、映画シナリオ制作の仕事、作者の現況と批評界における評価等
* 2006年度ネビュラ賞(Nebula Award)の受賞。
(ファンタシー短編部門、脚本部門は「ハウルの動く城」の宮崎駿)受賞作“Two Hearts”は『最後のユニコーン』の続編(後日談)
* アニメーション版「最後のユニコーン」の上映
*ボッシュの絵画「地上の快楽の楽園」等の研究The Garden of Earthly Delight、ジーンズアートの写真集の解説American Denim等、隠されていた意外な仕事の紹介
*『最後のユニコーン』(The Last Unicorn)の秘された主題“影の原理と多義性”の解説
研究資料、著作目録、研究論文等を差し上げます。
質問等にお答えしながら、作品に対する思いを自由に語り合っていきましょう。
------------------------------------------------------
参考講座テキスト
レッド・ブルと“影”の主題
―意味と実質が反転するシステム原理
『最後のユニコーン』でユニコーンの宿敵の役を演ずる“レッド・ブル”という存在には、ファンタシーの源流となっているロマン主義思想の根幹的理論となるものを確定するための重要な手掛りが隠されている。先ずはこの物語において採用されていたこの不可解な怪物に関する記述の実体を、ストーリーの展開に即して入念に追い直していってみることにしよう。
失われた仲間達を求める探求の旅の目的地であると思われるハガード王の城を間近にしたユニコーンとその一行の前に、突然蝶の予言に語られていたあの牡牛が姿を現した時の記述である。
The Red Bull did not know her, and yet she could feel that it was herself he sought, and no white mare. Fear blew her dark then, and she ran away while the Bullユs raging ignorance filled the sky and spilled over into the valley.
レッド・ブルはユニコーンがユニコーンであるとは分らないのだった。けれどもユニコーンは彼が白い雌馬などではなく、自分のことを捕まえようとしていることが分った。その時恐怖が彼女に襲いかかり、体の輝きを失わせた。そしてユニコーンは踵を返して逃げ始め、牡牛の猛り狂う無知は空を覆い、溢れて谷間に流れ込んだ。
初めてユニコーンの前にその姿を現した宿敵レッド・ブルとユニコーンとの対決の有り様は、通例のロマンスやファンタシーの場合とは決定的に異なった角度から描かれている。他の全てのユニコーン達をこの世から駆逐してしまったと述べられていた強大な力を秘めたこの怪物は、実は天敵であるユニコーンを視認し同定することさえも出来ない愚鈍極まりない無知の持ち主だというのである。ここでは彼の与える莫大な体躯とその驚異的な力のもたらす恐怖感以上に、彼の固有の特質である無気味なばかりの無知性が、独特の修辞法を用いて強調されていることがむしろ興味深い。この怪物の保持する極めて不可解な属性である無知は、空気や水のように特有の材質性を持ち、目に見え、手に触れることさえもできるものなのである。
何故かユニコーンは、漸く登場したこの怪物の体現する謬質の無知というおぞましい性向に気付くや、かつて知ったことのない恐怖感に襲われ、当初の目的であった筈の戦いを忘れて、一方的な逃走へと追いやられてしまうのである。そして走り去るユニコーンの後を追っていく牡牛に関する描写は、以下のようなひときわ興味深いものとなっている。
Yet without looking back, she knew that the Red Bull was gaining on her, coming like the moon, the sullen, swollen hunter's moon.
けれども振り返る必要もなく、ユニコーンはレッド・ブルがむっつりとして膨れ上がった狩人月のように迫ってくるのが分っていた。
圧倒的な力でユニコーンを追い立て、軽やかで素早いユニコーンにもたやすく追い付くことさえできる不可思議な能力を備えた妖獣レッド・ブルが、距離感と大きさの感覚の双方を失わせる、無気味な月の姿に喩えて語られているのである。あまりにも彼方の遠方にあり、そしてまた並外れて巨大なために地上の日常感覚を幻惑させてしまい、実際には静止しているはずなのに、いつまでも離れることなく後を追い続けてくるような異様な錯覚を与える月と同様に、莫大な体躯とは裏腹に、どこか実体感を欠いた現象世界から遊離したような希薄な印象さえ帯びている奇妙な怪物が、全てのユニコーンを世界から駆逐してしまったという、このレッド・ブルなのである。ここでこの新たなる神話的存在が喩えられている月の暗示する存在性向における際立った不定性あるいは非在性の感覚は、彼についてこの後も繰り返し語られることとなっているのである。
He had been huge when she first fled him, but in the pursuit he had grown so vast that she could not imagine all of him.
レッド・ブルは最初にユニコーンが彼の前から逃げ出した時、既に巨大な体躯をしていた。けれどもユニコーンを追い立てていくうちに、彼の身体の大きさはさらにふくれあがり、もうユニコーンには彼の身体の全てを頭に思い浮かべることもできない程になっていたのだった。
この場面は、レッド・ブルの質量としての存在属性の不定性と、さらにまた材質と性向、あるいは実体と表象という存在傾向あるいは発現様相の占める筈の形相をも分別すること自体が全く意味をなさなくなる、ひいては他者の主観の内部に得られた一印象に過ぎないものとしての疑似存在性向までをも含めた、総合的連続体としての独特の原存在的非在性を強く暗示する部分なのである。そして現象物あるいは現象界を越えた超越的存在を記述の対象として選ぶにあたっての、一意的な客観的対象把握の原理的不能性を先鋭に自覚するこの感覚は、『最後のユニコーン』の物語全体を支配する、際立った思想的特質を反映するものともなっていると思われる。
言うならばレッド・ブルとはむしろ一個の存在物であるばかりでなく、全てを包含する自然界そのものの現す、多面的な様相の網羅的叙述の一側面のごときものでもまたあるらしい。次の描写の部分が、このような解釈の可能性に対して説得力のある弁護を与えると思われる実例を提供してくれている。
Now he seemed to curve with the curve of the bloodshot sky, his legs like great whirlwinds, his head rolling like the northern lights.
今はもう、レッド・ブルの身体の輪郭は、血の色に染まった空の輪郭と重なっていた。彼の足は巨大なつむじ風のようで、彼の頭は極光のように旋回しているのだった。
このようにレッド・ブルの身体は、一個の生命体あるいは存在物としての限界性を捨て去り、ともすれば世界そのもの、自然そのものと同化しようとさえするものであるかのように、入念な暗示的記述の手を加えられているのである。世界の中に含まれる個別の存在物として発現すると同時に、統合的連続体としての世界そのものの示す局相の一つでもまたあり、あるいはギリシア神話の神々がそうであったように、事象性と対極にある抽象概念としてもまた同等に確としてあり得るかのごとくである。そして彼の保持するであろう抽象概念としてのもう一つの名は、おそらく“盲目”というものなのであった。
His nostrils wrinkled and rumbled as he searched for her, and the unicorn realized that the Red Bull was blind.
レッド・ブルはユニコーンを探し求めて鼻をうごめかし、途轍も無い鼻息を立てた。そしてユニコーンは彼が盲目であることに気が付いた。
ユニコーンさえ立ち向かうことが出来ない圧倒的な力を持ったレッド・ブルの、不可解な属性である盲目性が、無知性という特質に引き続いてここで言及されているのである。この物語の主題上の核を形成しているユニコーンの存在属性も、むしろ彼女を脅かす悪漢の役を担って登場したこの怪物の存在性向を中心に据えてみることによってこそ、その実相がより明らかになってくる筈なのだ。
例えば以下の引用が、この考察を支持するであろう説得力を持つ証言の最初の一つとしてあげられるに違いない。
With low, sad cry, she whirled and ran back the way she had come: back through the tattered fields and over the plain, toward King Haggard's castle, dark and hunched as ever. And the Red Bull went after her, following her fear.
低い、悲しげな叫び声をあげて、ユニコーンは身体の向きを変え、今来た道を引き返した。引き裂かれた畑をまた戻り、草原を横切り、元のまま黒く背を丸めたままのハガード王の城の方へと行くのだった。そしてレッド・ブルは彼女の怯える心の後を付いて行くのだった。
追うものが追われるものに対してその追跡という行為により恐怖感を与える、という基本的な主客の関係の許に成立する筈の因果関係が逆転し、あまりにも無知なるが故に本来の目的性も独自の意志をも持つことがあり得ないこの怪物は、ユニコーンの怯える心によって生成し、その恐怖の後に付き従うことによって始めて、個別の行動とそしてその存在をも具現化するのであるかもしれない。そしてレッド・ブルの存在属性を照射すると思われる同様の反転的因果関係を示す記述は、追う牡牛と追われるユニコーンの後をあたふたと着いて行く、シュメンドリックとモリーの姿を語った以下の描写にも再び繰り返されているのである。
Molly and the magician scrambled over great tree trunks not only smashed but trodden halfway into the ground, and dropped to hands and knees to crawl around crevasses they could not fathom in the dark. No hoofs could have made these, Molly thought dazedly; the earth had torn itself shrinking from the burden of the Bull.
モリーとシュメンドリックは巨大な木々の残骸の上を乗り越えて進んで行った。それらは打ち砕かれているだけでなく、踏み付けられて地面の中に半分埋まり込んでいるのだった。四つん這いになって、暗闇の中では深さも知れない地の裂け目を避けて進まなければならなかった。モリーは頭をくらくらさせながら思った。「レッド・ブルの蹄がこんな裂け目を穿った筈はない。牡牛の重さを嫌って、地面の方が自分から裂けてしまったのだ。」
レッド・ブルの途轍も無い巨大さが残した破壊と蹂躙の痕跡として、倒された木々や裂けた地面が確かに残されてはいる。しかしそのあまりの凄まじさに、実際にこのような出来事が起こったとは俄に信じ難いばかりではなく、むしろ破壊行為の原因となる牡牛自身の実体性そのものに、却って疑念が持たれてしまうのである。事象の生成に対して、動作を行った主体と変化をもたらされた客体という本来あるべき関係性の見事な喪失の有り様が、ここに改めて明示されているのである。レッド・ブルとはむしろポジティブな存在性を持つことのない、他の何者かのネガティブな自壊、あるいは喪失、もしくは逡巡さもなければ保持する性向あるいは属性の一部分の放棄が形象化したものであると呼んだ方が、より適切なものであるのかもしれないのだ。そう言えば最初にあの蝶がレッド・ブルの名を口にした際も、この牡牛は「ユニコーンを追い立てて行った」とは語られてはいなかった。「レッド・ブルは、走り去るユニコーン達の後を走って行った」と述べられていただけなのであった。
現代の世界観を支配する科学的因果関係の理解に従えば、先ず現象を起こすべき本体が予め存在し、一方がもう一方の存在物に対して何らかの動作を働きかけるものとされる。そこには能動と受動の関係が、時間軸の単一方向的支配の許に局所的作用として厳然と存在せねばならないのである。しかしこれに対して、例えば古代世界あるいは伝統的な東洋思想における事象の生成とは、絶えず遷ろい変化し続ける全体のある意識の主体に対して仮に示す、一つの相対的な局相として理解されるに過ぎないものであった。行為を行うものとその働きを被るものとを峻厳に分別する感覚は、統括的な全体性を前提とする古代の思想の裡には、もともと存在しなかったのである。
ユニコーンを狩るレッド・ブルと、レッド・ブルによって狩られるユニコーンは、それぞれ個別の存在性向を保持する実体であるのではなく、仮定された一つの存在あるいは現象の示す、対極的に分離した二つの位相でもあるかのごとくである。だから彼等の身体が実際に触れ合うことは、おそらく決してあり得ないのだ。
Molly Grue, a little crazy with weariness and fear, saw them moving the way stars and stones move through space: forever falling, forever following, forever alone. The Red Bull would never catch the unicorn, not until Now caught up with New, Bygone with Begin.
モリー・グルーは、疲れと恐怖のために正気を半分失ってしまい、星や石が宙を移動していくのを見るような気持ちで、ユニコーンとレッド・ブルの姿を見ていたのだった。彼等はいつまでも二人きりで、いつまでも一方は落ち続け、いつまでももう一方がその後に続いていくかのようだった。「レッド・ブルは決してユニコーンに追い付くことはないのだろう。“今”が“新た”によって追いつかれ、“過去”が“始まり”によって追いつかれるまで。」
逃げるユニコーンと追う牡牛の姿を見守るモリーの視点は、奇妙なことに現世的束縛から離れて、無限遠の彼方から全てを俯瞰するかのごとく浮き上がっているのである。時間の奴隷として些末な現象性に翻弄されるがままに生き続ける人間の主観の裡に、束の間永遠の彼方を見通す超越的把握力の来訪が可能であることを暗示するかのごとくである。これは肉体的疲労と精神的緊張の極みが、あたかも宗教的苦行の結果のように瞬間的にモリーに与えた、全体性の知覚あるいは経験以前の記憶とも言うべきものなのであろう。そこでは時間軸の向きの影響と因果関係の辿る方向性の支配をも受けることなく、総ての関係性の本質が全方位的に把握され得ることとなる。瞬間の背後に存在する永遠性の本質に従えば、ユニコーンとレッド・ブルは、磁石の両極のように常に不即不離の関係を保つ、実はこの上なく近接したもの達である筈なのだ。
The unicorn fled once more, pitifully tireless, and the Red Bull let her have room to run, but none to turn.
ユニコーンはもう一度、レッド・ブルの許から逃げ出した。その疲れを知らない走り方が、哀れなほどに思えるのだった。そして牡牛は、走り続けるだけの猶予は彼女に与えたものの、向きを変えるだけの余裕を与えることはないのだった。
疲れを知らないほどに軽やかに走るユニコーンの姿だからこそ、却ってその素早い身のこなしが哀れに感じられてしまうというのである。しかしそのユニコーンをレッド・ブルは余裕たっぷりに追いつめていく。けれども牡牛は彼の餌食を決して捕まえてしまおうとはせず、執念深く一つの方向へと追い立てていくばかりなのである。あるいはユニコーンの動きに引き付けられて、その直後に従順につき従っているだけなのかもしれないからである。あるいはまたユニコーンによる誘引という作用自体が、彼の現象界への具現化の条件となる第一要因であるからかもしれないからである。
だから魔法使いシュメンドリックの魔法の力によって人間の娘へと変身させられてしまった、彼の先導者であるべきユニコーンを見失ったレッド・ブルの姿は、やはり決定的に実体性を欠くものとなってしまわざるを得ないのである。
The Red Bull raised his huge, blind head and swung it slowly in Schmendrick's direction. He seemed to be waning and fading as the gray sky grew light, though he still smoldered as savagely bright as crawling lava. The magician wondered what his true size was, and his color, when he was alone.
レッド・ブルはその巨大な盲目の頭を上げて、ゆっくりとシュメンドリックの方に向けた。その牡牛の姿は、地面の上を這って流れる溶岩のようにまだ荒々しくくすぶっていたにもかかわらず、薄暗い空が明るさを増すに連れて、薄くかすんでいくように思われたのだった。シュメンドリックは、牡牛が一人きりになった時、牡牛の本当の大きさはどのくらいなのだろう、本当の色はどんな色をしているのだろうと思わず考えた。
レッド・ブルの圧倒的な体躯の大きさと相反して、彼のあっけない程の実体感の脱落の様が、改めてその具体的な大きさと実際の色合いに焦点を当てて、ここでも再び言及されているのである。 “牡牛が一人きりになった時”とは、つまり“ユニコーンの姿が見えなくなった時”と同様である。ユニコーンがその輝きに満ちた姿を隠したと同時に、牡牛の姿も突然色褪せてしまったというばかりではない。ユニコーンという一方の存在があって初めて、この牡牛の存在自身がかろうじて可能となるのだ。単独では存在物としての実体性すら満足に維持することがあり得ないのが、全てのユニコーン達が遭遇したと語られたあまりにも巨大過ぎるという、そして後にはユニコーンよりもさらにオールドであるとさえ語られていたこの怪物の唯一の実質なのだろう。ユニコーンの存在をある種の核として持つことによってのみ、レッド・ブルの身体の大きさもその色合いも、そしてその力もまた、堅固で明瞭な具象性あるいは意味性を保有するものとして感じ取られることとなるのである。とすればやはり、ユニコーンがその本質的な属性あるいは形状を失ってしまった時には、牡牛の存在性そのものが揮発性の残像として瞬時に失われてしまうことになるのも、至極当然のこととなるのであろう。
Schmendrick had a last vision of him as he gained the rim of the valley: no shape at all, but a swirling darkness, the red darkness you see when you close your eyes in pain. The horns had become the two sharpest towers of old King Haggard's crazy castle.
レッド・ブルが最後に谷間の端まで来た時、シュメンドリックには彼の途轍も無い大きさが改めて分った。それは形といってよいものではもはや無く、痛みに思わず目を閉じた時に感じられる赤い視界のような、渦巻く暗闇だった。牡牛の二本の角は、ハガード王の馬鹿げた城の二本の細い尖塔に重なっているのだった。
ユニコーンとの初回の遭遇の折に、レッド・ブルが最後にその姿を消そうとするこの場面においては、レッド・ブルの圧倒的な巨大さに相反するその実体性の希薄さがさらに極まり、自然界に実在する客観的存在物としてではなく、個人の意識の内部機構に属する主観的幻影あるいは錯覚でさえもあるかのように、よりいっそう退縮した様態を通して語られているのである。その存在性は発現当初の印象に反して重厚な実体性を限りなく喪失した結果、むしろ朧げな心象あるいはとりとめの無い奇想にさえ近い、はなはだ危う気な別物に転換してしまっているのであった。意識内部の仮想的概念として、あるいは印象的疑似存在物としての超自然的な非在性をも含めたその純観念的存在性向は、アンチ・ファンタシーとしての特質を誇示した先行的な作品であった、『ピーターとウェンディ』において語られていたネヴァランド(Neverland)という疑似世界/意識機構と、そしてまたこの陥穽に満ちたお伽話の表層の主人公を演じていたピーターという抽象概念/心象とも、共通する部分が極めて大きいもののようにも思われる代物なのだ。
だからレッド・ブルが次にその不可思議な姿を現す場面では、その有り様は以下のような言葉で語られることになる。
But he had come silently up the passageway to meet them; and now he stood across their sight, not only from one burning wall to the other, but somehow in the walls themselves, and beyond them, bending away forever.
しかし牡牛は音も立てずに通路をたどり、彼等の許へやってきていたのであった。そして今牡牛は、彼等の眼前に姿を現していた。燃え上がる通路の壁の端から端までをふさいでいるばかりでなく、壁の内部にまで、そして壁の向こう側にまで突き抜けて、限りなく曲がりくねったその先までを牡牛の体が占めてさえいるのだった。
ハガード王の城の秘密の通路の内部で、再びレッド・ブルがユニコーン達一行の前にそのおぞましい姿を現した場面の描写は、上に引用したような極めて異様なものだったのである。ここにおいては、レッド・ブルの桁外れな程の巨大さが再び反転的に彼の実体性の欠如と、むしろ主観の中にのみ存在し得る悪夢的イメージとしての、非在物的要素を強く暗示しているばかりでなく、実は姿を現したものは通路のはるか奥底に潜む牡牛であっても、あるいは牡牛の潜む通路であっても、あるいは通路を進むユニコーンの一行のそれぞれの主観の中に浮かぶ、とりとめのない焦燥と不安のいずれであっても、一向に構わないという類いのものなのだ。
同等の論理に従って、現象認識として語らざるを得ない事象の引きずる不確定性は、この後ユニコーンの行った筈の牡牛との戦いという決定的事実ですら、以下のような形で語られることしか許さないこととなる。
She might have been stabbing at a shadow, or at a memory.
ユニコーンが角を突き立てようとしていた相手は、あるいは影であったか、あるいは記憶に過ぎないものであったのかもしれなかった。
ここにもレッド・ブル自身の実体性の欠如が再び反復して言及されていることが確認されるだろう。文字通り、この怪物の正体は本体から取り残された影であり、誰か分からぬものの心の中に潜む悪夢にほかならないものに違いない。
ユニコーン達の世界からの消失を招く直接の原因となるものであったとされるレッド・ブルとユニコーンの間の関係そのものが、見事に対照的に、そしてそれが故に対極的に連関して、無限遠の延長線上においては再び連接すべき同一物となるべきものとしての秘された存在性向をも暗示して、彼らの最後の対決の有り様が語られていくことになるのである。
The unicorn lowered her head one last time and hurled herself at the Red Bull. If he had been either true flesh or a windy ghost, the blow would have burst him like rotten fruit. But he turned away unnoticing, and walked slowly into the sea.
ユニコーンは最後にもう一度頭を低く下げ、赤い牡牛に飛び掛かった。もしも牡牛が本当の肉体を持っていたか、あるいは朧げな霊のようなものでさえあったなら、ユニコーンの一撃は牡牛を腐った果物のように粉砕したことだろう。しかし牡牛はその一撃に気付きさえもせずに、ゆっくりと海の中に足を踏み入れていったのだった。
この場面でもレッド・ブルの姿が再び現象世界的実体性を持たない、徹底的に観念上のものとして記述されていることが確認されるだろう。この物語においては二者択一の選択肢を設け、任意の一方の可能性を論駁することにより他方の存在の妥当性を主張しようとするような古典物理学的論証の手法は、容易に通用することはない。すべてが複数の意味の重ね合わせによる多義性の記述として読み取られなければならないのである。
The hugest waves broke no higher than his hocks, and the timid tide ran away from him. But when at last he let himself sink onto the flood, then a great surge of the sea stood up behind him: a green and black swell, as deep and smooth and hard as the wind. It gathered in silence, folding from one horizon to the other, until for a moment it actually hid the Red Bullユs humped shoulders and sloping back.
もっとも大きな波でさえも、牡牛の膝のあたりの高さで砕け散っていた。そして潮流は怯えて牡牛の体を避けているのだった。けれどもようやく牡牛が海の中にその体を沈めると、巨大な波が黒と緑の山となって、風のように深く滑らかにそして激しく、牡牛の背後に沸き立った。巨大な波は静かに合わさって一方の水平線ともう一方の水平線をたたみ込み、一瞬の間牡牛の盛り上がった肩と傾斜した背中を呑み込んだ。
ユニコーンに追い立てられた牡牛がその身体を海に没する際にもやはり、レッド・ブルの巨大さが、現象世界的具体性を持たない、夢の中の出来事のように主観的イメージのみの存在であることを暗示するものとして改めて言及されているばかりか、ユニコーンと牡牛の対決という物語の大団円を形成する筈の象徴的行為さえもが、それが果たして戦いであったのか、その結果があるいは一方の勝利であったのか、あるいはそれ以外の別の言葉で語り得る何物かであったのかさえ、飽くまでも定かなものとなされることはあり得ないのである。そして牡牛の姿が失われたのと呼応するかのようにようやくその姿を現すユニコーン達も、やはり彼等の対立物であった牡牛の場合と全く変わることなく、飽くまでも現象的実体性を伴うことなく、その来訪と顕現の有り様が徹底して描かれることとなっているのである。
Molly never saw them clearlyムthey were a light leaping toward her and a cry that dazzled her eyes.
モリーにはユニコーン達の姿がはっきりと見えることは決してなかった。彼らは彼女の方に飛び跳ねてくる光であり、彼女の目を眩ませる叫び声だった。
主体と客体、現象と実在、視覚と聴覚の及ぼす効果と印象を転倒させ、これらの位相を混淆して錯綜の渦の中で描くことを試みようとする、ポー的な反転的記述原理に従った詩学的修辞法を最大限に活用しながら、永遠なるものたちの現象的実体性の欠如を通して、見事に極限の美と歓喜が描かれている場面である。
起こりえぬ筈の奇跡の到来が実現し、解放されたユニコーン達が再び世界に満ちあふれたとしても、回復されたそのユニコーン達の姿は、作品中の一登場人物でもあり、やはり架空の世界に属するとはいえ一個の人間存在でもあるモリーの目を通しては、現象世界的具体性を決して持つことのない、夢の中の出来事のように主観的イメージのみの存在であることを暗示するばかりのものとして、改めて語られているのである。
ならば物語の終局に描かれるに至ったユニコーン達の到来とは、レッド・ブルの消失という事実のもう一方の知覚あるいは認識、あるいは全てを包含する統一的実在の位相の遷移に対して選択された記述様式の手法の一つであったのかもしれない。
There was no sign of him when they looked out to sea, though he was surely too vast to have swum out of sight in the short time. But whether he reached some other shore, or whether the water drew even his great bulk down at last, none of them knew until long after; and he was never seen again in that kingdom.
彼等が海の方へ目を向けた時、わずかな時間に目の届く範囲の外に行ってしまうには、彼の躯はあまりにも大き過ぎたのだが、牡牛の姿はどこにも見当たらなかった。けれども彼がどこか余所の岸辺に辿り着いたのか、あるいは海が巨大な牡牛の躯さえも終には呑み込んでしまったのか、ずっと後になるまでは、誰にも分からなかった。牡牛はこの王国でその姿を見せることは二度と無かった。
レッド・ブルの体の大きさの不明瞭さがここでも重ねて言及されているばかりではない。彼の肉体の占める空間的延長の範囲のみならず、その属性、来歴等々、レッド・ブルの体現する曖昧性は、本作品の影の主題に対するはなはだ自意識的な操作と重要な関連を持つこととなっている。例えば電子と陽電子の生成あるいは消滅という関係の場合のように、一方の欠如がもう一方の発現という形で逆転的に記述されるだけの、一種の反転的属性の許にこそ緊密に連関する、全体性の宇宙の示す独特の存在性向までをも、見事に連想させるものとなっているのである。しかしながらファンタシーの思想的主題の基軸である全一性という概念を時間次元にまで拡張して捉え直すならば、むしろこれは当然の帰結として認められるべき結論でもあるだろう。
かくしてユニコーンもレッド・ブルも、この物語のキーワードとして提出されていた現象界を超越した永遠の存在を呼ぶ“old”という概念を支えるべき、究極的な実体の影として観念空間の裡に昇華し、魔法の根幹的原理そのものと正確に対応するものでなければならないことになるのである。
ユニコーン達の解放と世界への復帰という出来事は、そのままこのお伽話の世界が経験した奇跡的な魔法の発現の場面となり、その有様はこの世界の住民達によって、以下のような言葉を用いて語られることとなるからである。
"It was an earthquake," one man murmured dreamily, but another contradicted him, saying, "It was a storm, a nor'easter straight off the sea. It shook the town to bits, and hail came down like hoofs." Still another man insisted that a mighty tide had washed over Hagsgate; a tide as white as dogwood and heavy as marble, that drowned none and smashed everything.
「あれは地震だった。」一人の男が夢の中のようにつぶやいた。けれども別の男が打ち消して言った。「あれは嵐だった。海から吹き付けてくる、北東風だった。風が町中をばらばらにして、馬の足音のように霰が吹き付けたんだ。」さらに別の男が、巨大な津波がハグスゲイトの町を襲ったのだと主張した。ハナミズキのように白く、大理石のように重い波が押し寄せて、誰も溺れさせることなく、全てのものを打ち壊したのだと言うのだった。
魔法や永遠の真実に関わることは、現象世界においては常に歪んだ形で把握され、その本質自体は決して理解し得ないのである。現象世界において具現する事象は、様々な要素の重ね合わせの一時的な発現形の一つに過ぎないのだ。その要素の各々を感知する者の主観に従って、様々のそれぞれ矛盾した偽りの“真実”があるに過ぎない。そこには夢における奇跡を統合的直観として認める感覚はあっても、夢と現実を峻別する分析的意識は全く認められないのである。
このお話のエピローグを形成する、ユニコーンの解放とレッド・ブルの消滅が訪れた後の世界の様相の変化を語る描写は、以下のようなものとなっている。
But when they came to Hagsgate, deep in the afternoon, a strange and savage sight awaited them. The plowed fields were woefully torn and ravaged, while the rich orchards and vineyards had been stamped down, leaving no grove or arbor standing. It was such shattering ruin as the Bull himself might have wrought;
けれども彼等が夕刻近くにハグズゲイトの町にたどりついて来てみると、荒れ果てた不思議な光景が彼等を待ち受けているのであった。美しく耕されていた畑は、引き裂かれたように蹂躙されていた。豊かな果樹園や葡萄畑も徹底的に踏み付けられ、木一本も残されているものは無かった。それはまるであの牡牛が自ら行ったかのような破壊の痕跡であった。
ユニコーン達が通り過ぎた後に残された破壊と蹂躙の痕跡が、ここでもやはりレッド・ブルが残した形跡とあたかも同等のものであるかのように記述されているのである。本体とその影があたかも巴の紋章あるいはウロボロスの表象のように反転を繰り返す不定性の交替原理の中に、深遠なる宇宙の真理が隠されているかのごとくである。この生真面目な諧謔と詩的な斬新さと思弁的な野心に満ちたアンチ・ファンタシーのお伽話においては、運動と位置、存在と様態、実質と作用等の、本体となるべきものとその位相とされるべきものとの間の関係の絶え間ない逆転と変換の有り様が、時に純粋な憧憬に満ち、また時には荒唐無稽な詩学的修辞法を活用した極性転換のシステム理論に従って、周到に語り続けられているのである。
[Read more of this post]
00:34:16 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks