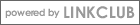Archive for 23 February 2011
23 February
『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 2
省察15「悪夢のクイズSHOW」において思弁的映像作品『エルゴ・プラクシー』の採用する世界とプラクシー存在の表象は、さらに観念的な抽象的特質を先鋭化させたものとなっている。この回のエピソード自体が一編のクイズ番組の形で提示され、この仮構作品の基幹設定そのものがクイズ問題の設問の各々として司会者MJQによってヴィンセントに質問され、作品の鑑賞者である我々に対してばかりでなくこの仮構の中心人物であるヴィンセント自身に、模範解答の形で物語世界の基本情報が教授されることになっているからである。そのようにして与えられた『エルゴ・プラクシー』世界の基幹設定に属する諸事実は、例えば以下のようなものである。それは未来の地球を舞台に起こった運命的悲劇と、人類の辿った悲惨な行く末なのであった。「メタン・ハイドレイト層の連鎖崩壊により、地球上の生物の85パーセントが死滅した。」/「荒廃した地球環境を見捨てて人類が宇宙空間に避難するのに用いた宇宙船の名は“ブーメラン・スター号」/「人類再生の計画“プラクシー・プロジェクト”によって全世界に放たれたプラクシーの数は300体。」/「世界再生を果たした人類にとってプラクシーは最も不要な存在となった。」/「“始まりの鼓動”とは、プラクシー・プロジェクトの終了。」/「“唯一の勝者”はプラクシー・ワン。」
ここで“プラクシー・ワン”という未知の存在がゲームの設問に対する正解の一つとして唐突に語られるのは、SF的仮構理解の基本ルールにおいては当然許され得ない逸脱行為である。15話「悪夢のクイズSHOW」のクイズ設問と解答の中で与えられている諸情報が、典型的SF的背景に属するものとなっていることをいかに評価するかが重要課題となる。観客に対して何らかの表現行為を行う作品としての自己言及的行為として、この映像作品は自身をSFとして読解されることを拒否する姿勢を表明していることになるからである。『エルゴ・プラクシー』の基軸となるべきほとんどのSF的設定がクイズ番組の設問という形で提示され、番組内に示された解答例としてあっけなく実態が明かされてしまっている。この作品の展開する主題はSFの代表する自然科学にあるのではなく、哲学的には自然科学の対照概念の位置を占めるものとなる宗教の分野に属する関心が展開されることが暗示されているのである。つまり質量点として変換記述し得る空間的延長性を持ち、座標上の空間的位置関係を一意的に特定することができる“存在物”という粗形を用いて世界の全てを捉えようとするデカルト・ニュートンの構想した科学に対して、そのような描像を得ること自体が原理的に不可能なものとして世界と個物それぞれの関係性を捉えようと試みるのが、“心霊的”理解に基づく宗教的発想であった。心霊的解釈によれば一つの存在物が、例えば肉体の死と共に魂が分離して蝶の姿で分かれていくプシュケーとしての様相を取り得るように、あるいは死後鳥の姿になって飛んでいく日本武尊の魂の位相遷移の例のように、跳躍的かつ多面的に分化して具現することが可能となる。つまり空間的延長性や意味的一意性を保持する必要がない、現象世界において複数の並列的な“様相”を多元的に示すことができる原存在として、“心霊”の原理的特質は理解されるのである。
SF的設定要素を多分に含んだ観念アニメである『エルゴ・プラクシー』は、このエピソードにおいて自然科学的方法論自身を変転させた“自己言及的作品解題”を試みているのである。フィクション世界はSFがそうであると信じられて来たように、必ずしも一個の独立した客観世界として現象世界と同様の完結した形を保持して具現している訳ではなく、作品の本体が意識の主体である観客に対する諸概念の提示という情報伝達形式をとった、様々に変換可能な意味構築の手法そのものであっても良い。各種アルゴリズムを通じて網羅的に様態の変化を現出することが可能な原形概念と変換記述手順の数学的定式化の間にある微妙な関系性は、ダグラス・ホフスタッターが『メタマジック・ゲームズ』(Metamagical Themas)において紹介と批判的論考を行った、ドナルド・クヌースの論文“メタフォントの概念” (Donald Knuth, “The Concept of a Meta-Font”)において提唱されたメタ存在概念の発想と照らし合わせて、“プラクシー”概念と深く関わるものであると思われる。14話「貴方に似た誰か」において出現したプラクシーの正体として、既にこの“メタ存在”に対する示唆が行われていたのであった。原理的には異種の仮構作品相互におけるジャンルを跳躍した変換記述や、任意の概念の全くの別次元界面に属する概念への位相変換の試み等が様々に“共変性”の原理に従って実現されることが可能であることを仮定して、ここでは『エルゴ・プラクシー』のSF的基本設定に相当する部分を“クイズ・ショー”変換した形式で観念伝達がなされる、一つの“ゲーム世界”が提示されていることを過たず理解しておく必要がある。
この後に続く省察17「終わらない戦い」において、我々観客が視聴して確認しつつある変換後のプレゼンテーション・モードを、フィクション世界内の存在であるはずのラウルやデダルス達が人工衛星による中継映像として“SF的”に認知している場面が挿入されることにより、典型的な“メタフィクション”の図式を“フィクション”という次元の制約外に拡張して異次元平面の跳躍的連接を企てるのも、やはり“現実=フィクション連続体”としての“ゲーム世界”提示の手法のアクチュアリズム的展開例の一つとして看為し得ることになる。我々は“SF的リアリティ”と“観念アニメ的アクチュアリティ”の位相のそれぞれのプレゼンテーションの成果を確かに見届けながら、知覚と意味の複合体である“擬似現象世界”としての仮構の実相を過たず受容していかねばならない。
『エルゴ・プラクシー』が純正のSF作品であったならば、プラクシーという存在の誕生や彼等が行った行為の具体的内容の実質的提示が科学的手法に則って正確に遂行されることが、読者/観客によって厳しく要求されねばならないことになるのだが、この作品の関心は、むしろこれらの概念の上に成り立つ“形而上的”思考の模索の方にある。仮構作品が特定の情報を特有の様式と技法に基づいた方式で受け手に伝達することで成り立っている意味世界であるならば、必ずしも現象世界として独立した別世界を一定の角度から瞥見し、記述するという過程を踏襲して描かれなければならない原理的制約がある訳ではない。むしろ厳密な意味におけるSF的設定に属する情報については最低限の枠組みだけ欄外で語っておけばいい、という制作者側の選択した自覚的なスタンスがここには窺われる。人類が地球を捨てて宇宙空間に脱出するのに用いた“ブーメラン・スター号”建造や、荒廃した地球環境との宥和を試みた“人類再生プラクシー・プロジェクト”に関するクイズ番組内での唐突な言及は、そのような意味で『エルゴ・プラクシー』が意味の複合体としての一編の仮構であることを先鋭に意識した、典型的なメタフィクション的記述の思弁的展開の一例であるに違いない。
しかしながら仮構世界としての概念的位相変換の操作を施されて“クイズ番組”変換された「悪夢のクイズ・ショー」が、総体としてのアニメ/ゲーム作品『エルゴ・プラクシー』の同一性を確かに維持していると看為し得る一貫性の要素は、“死の代理人”であるプラクシーのヴィンセントがやはりこの回においても他のプラクシーと思われるものの抹殺を実行する結果となっている点である。最終的にクイズ・バトルというこの勝負の勝者はヴィンセントと決定し、対戦相手である司会者はクイズ番組のルールに従って敗者として死を与えられることになる。司会者MJQは番組終了を宣言して最後に言い残す。「仕方ない、これもプラクシーの戦い方。」風刺や政治的批判を目的とするパロディーやバーレスクやカリカチュアなどの場合とは本質的に異なる独特の概念操作を施された、根源的基質において多面的な様相を無数に保持している潜勢力の一斑がこのような形で“観測”と“描写” に頼らず伝達し得ると理解するならば、同時にこのフィクション世界で導入されている“プラクシー”(代理人)という概念の暗示するものの実質が改めて見えてくることだろう。
だからこそクイズ番組の設問としてヴィンセントに課せられた様々の雑学的知識は、ドノブ・メイヤーやデダルスのアントラージュ達の名前に暗示されていた哲学者達の名と同様に、やはり観客の想念の裡で醸成されてこの意味の複合体である仮構世界の内実を複合的に構築することになっている。最初のクイズ問題の答えであるブルワー・リットンの“ペンは剣よりも強し”という言葉に暗示されるペンと剣の概念的位相変換が超現象世界的に可能であるという“共変性”の原理を掬い取ってみるならば、これらの設問はそれぞれが巧妙に反響し合って、この“観念アニメ”のフィクションとしての成立条件の妥当性を主張しているものと理解することができるだろう。“ドップラー効果”も、従来のニュートン力学的科学思想が前提としていた、いかなる視座から観測を行っても同一の描像が得られる“客観的現象把握”の成立不能性を指摘する検証結果の一つとして理解できるものである。“水の最高密度温度”が摂氏3.98度である事実は、宇宙の生成と知性体の誕生を可能とするために超越的な存在によって巧みに設定されたかのようにも思われる“宇宙定数”のファイン・チューニング説を支持する身近な例の一つとして採用されるかもしれない。ダーウィンの『種の起原』は、“適者生存”と“自然淘汰”という概念を提示することによって、従来のキリスト教のスコラ哲学的世界観や古代世界を支配していた意味のある世界としてこの宇宙を認識する万物の有機的連関を前提とする象徴哲学的な思想を、根底から覆すものであった。その結果選び取られた“科学思想”は、宇宙と自己の双方の存在の根幹的意味そのものを認めることを全面的に否定する“虚無主義”に基づく“新思想”だったのである。生物学者リチャード・ドーキンスの唱えた“利己的な遺伝子”などの説が、この無目的的宇宙観をさらに裏打ちするものとなっている。霊的内実の向上を前提とする“進化”などという幻想を打ち捨てたところにこそ、“進化論”の思想的意義性があった。このような世界認識を決定する諸見解を踏まえて様々な意味で未来の科学技術の進展と、そこで人類が直面する新たな問題点をSFとして予見した、アーサー・C・クラークの存在を集約して伝えてくれているのが、映画『スペース・オデッセイ』(『2001年宇宙の旅』)であった。この映画の中でコンピュータ“ハル”の反逆が描かれていたのは、『エルゴ・プラクシー』のオートレーブ達を冒すコギト・ウィルスとの関連を思い出させるものである。“冥界の帝王”のエピセットの保有者として語られた心理学者ユングは、単に人間個々の心の中の意識のメカニズムを研究したのではなく、むしろ従来の科学の果たした現象理解をも含めた“時空精神連続体”としての宇宙全体の“心霊的”理解を試みた思想家として理解すべきだろう。
これらの知識を反映して“私”と“世界”の内実に対する反省的考察が展開され、“プラクシー”という概念に示された意識体の特有の存在属性が掘り起こされていくこととなる。規定された基本設定の許にストーリーとキャラクターを配した現象世界的“物語”を通じてこれらの意味連関の構築を図ろうとするのではなく、むしろゲーム的な断片知識の羅列によって極めて直裁な情報伝達を図る“記述”の手法は、“仮構”という概念の意味拡張の可能性を見事に具現している。模擬実験的擬似現象世界として構想された19世紀的“リアリズム小説”や科学的世界観に準拠した“合理的”仮構であることを前提とした“自然主義”の産物のみが仮構としての意義性を認められねばならないことはない。むしろその本質においては、超自然の支配する歪曲された断片的小世界や決してあり得ない不可能世界の脱臼的見通し図のみならず、数式や抽象的思弁の中にこそより豊かな真正の“仮構”の展開を期待することも十分に可能な筈である。哲学体系や宗教的教義が純然たる知性的関心の対象として主張し得る本質的意義性もまた、そこに見出されるべきであると言わねばならない。
00:00:00 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks