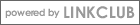Archive for 25 February 2011
25 February
『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 4
省察18「終着の調べ」の冒頭では、ラプチャーらしきミサイルに攻撃されて壊滅する都市と廃虚を見つめる怪人の姿が示されている。その手には“?”のナンバーのあるペンダントがある。一方、旅の目的地モスクに漸く辿り着いたヴィンセントは、自らの故郷であった筈のこの都市の破壊の惨状を確認して旅の途上で目撃したラプチャーの航跡を思い浮かべる。「あの光だ。あの光がモスクを焼き払ったのかもしれない。俺の過去を消すために。」ロムドでは執国のコンピュータ達によって、ラプチャーの発射を実行したラウルの罪を問う審判が行われている。ラウルは臆することなく、モスクの難民を受け入れた執国の心の弱さを指摘する。「あの男、ヴィンセント・ローを受け入れたことが全ての悲劇の始まり。」さらにラウルはドノブ・メイヤーを問いつめて言う。「かつてあなたは神を求め、裏切られた。」/「私は違う。我等を救わぬ神など求めはしない。ただ滅ぼすのみ。」/「滅亡が必然だとしても、抗い続けるならばロムドは存在し得る。」/「だが、今は変わらねばならぬのです。神を必要としない存在へと。私に絶望はない。」執国とロムドの体制に反逆を企てたラウルが、被告としてコンピュータの哲学者達の裁きを受けながら、むしろ堂々と彼等の弾劾に対して自らの反逆行為の正当性の論証を行ってみせているのが印象的である。支配者によって下付される希望に縋る脆弱な心性を、絶望を用いて滅却しようとする強靭な意思には、もはや絶望はない。“神なき後の世界”に生きる人間の実存的生のあり方が、ここに語られたラウルの言葉に集約されている。
彼の主張する自立的な人間存在として選び得る悲壮な個人的決断は、実は19世紀末にニーチェ等によってキリスト教的束縛から解放され霊的自由を得た現代人がその自由と引き換えに直面させられることとなった、恩寵として賜った“生存理由”の放擲に対する覚悟として選び取るべきものであった。課せられた安寧よりもむしろ選び取られた痛苦の方を善しとする同様の思念が、アルベール・カミュの『シジフォスの神話』に描かれた永劫に続く苦役をこそ生き甲斐としようとする覚悟や、ウィリアム・フォークナーの『野生の棕櫚』の中で語られた「悔恨と無との間からならば、悔恨の方を選び取りたい」という台詞などに窺うことができる。神の支配による束縛を被ることの無い霊的に自由な世界とは、ラウルがこのような決死の覚悟として理解せねばならない残酷な内実を秘めたものであった。信仰の桎梏を取り払った“与えられた自由”の中に必然的に生起するこのあまりにも苛酷な現実をすっかり忘れさせてくれようとするのが、ディズニー・アニメに代表されるアメリカの享楽的な現世主義の怖いところなのだが、実はその意味では教育委員会やPTAと同様政府の教育政策も全く変わるところは無い。ラウルの決死の覚悟を認め彼の権限復帰を認めたものの、ラウルの糾弾に対しては一切の返答を試みようとしないまま無言を通していた執国は、ラウルが去った後に漸くアントラージュの声を借りて絞り出すようにして言う。「ラウルよ、お前はやがて知るだろう。…我らの真の絶望を。」自らは言葉さえ発することのない執国ドノブ・メイヤーの胸の裡に秘められた絶望の内実は、未だ明かされていない。
ロムド・シティのウーム・シスをこれまで稼働させていたのは、外部から強奪してこのドームにもたらされたプラクシーなのであった。この事実は、プラクシーの秘密を語るデダルスによってリルにも既に示されていた。「我々は、あれを“モナド・プラクシー”と呼んでいた。」/「そしてあれは、モスク・ドームから我々が奪い取ってきたものだ。」そのモスクに辿り着きヴィンスをセンツォン号に残してモスクの塔の上の部屋にやって来たリルは、怯えるピノに「私には懐かしいな。」と不思議なことを言う。玉座に腰をかけたリルの周囲に、ロムドから侵攻してきたオートレーブの兵士達の発射した銃弾が飛び散る映像が映し出されるが、これもまたラウルの眼前に姿を現していたヴィンセントらしき者の映像と同様に、果たして彼女の幻想なのかあるいは記憶の残像であるのか定かではない。ヴィンセントに記憶を呼び戻すように促していたリルであるが、リル自身もお爺様のことばかり語っていて、自身の両親のことは全く頭にないのはやはりどこか不自然である。さらに「何故プラクシーがなければ人は生きられないのか?」と、プラクシーの謎と人間存在の関係に飽くまでも人として考え込むリルなのだが、彼女もまたラウルと同様に自分たちの現状の背後にある残酷な真実を確証し得ていないのである。
破壊し尽くされたと見えたモスクの都市の中に奇跡的に保全されていた建物の一室があり、何者かがヴィンセントの持っていたペンダントをキーとして使い、部屋の入り口を開けようとしている。隔離された聖域を守っていた“記憶の番人”アムネジアは、やって来たものを迎え入れて言う。「あなた様をお待ちしていたのです、お客人。分かれたものは、一つにならなければなりません。」ヴィンセントの放擲した記憶の守護者として配置されていたこのオートレーブが語る言葉の中に、宇宙の物理現象とさらに人間心理内部の情動的メカニズムにまでも通貫して機能する、超物理法則パターンがあることを形而上界面において確認することができるだろう。ウィリアム・ブレイクの『4ゾア』やエドガー・アラン・ポーの『ユリイカ』等にも語られている、分裂と再統合の作用の裡に潜む引力と斥力の原理として現れる、自と他の関係性を支配する心霊的力学とその過程に関与すると思われる“知”の本源的特質については、ルネサンス哲学における“個と宇宙”の関係性について統括的な洞察を成し遂げたエルンスト・カッシーラーが極めて示唆的な着眼を語ってくれている。
認識論に関して言えば、すでに中世の新プラトン主義的―神秘主義の文献 は、認識と愛を相互に分ちがたく結合していた。と言うのも、精神は愛のはたらきによって対象へ駆り立てられなければ、純理論的な考察においてその対象に向かうことはできないからである。このような根本直観は、ルネサンス哲学のうちでは、パトリツィの教説においてその再興と組織的展開を見ることになる。認識のはたらきと愛のはたらきは目標を同じくする。両者とも存在の諸要素の役割を解消し、それらの本源的統一へと還帰することを目指すからである。知とはこうした還帰の道における一定の階程に他ならない。それは志向の一形態ですらある。実際、いずれの知にとってもその対象への「志向」は本質的である。最高の知性が知性となり、思惟する意識となったのは、まさにそれが愛に駆り立てられてそれ自身のうちで自己を二分化し、一つの知的対象の世界を自らに考察の対象として対置することによってであった。しかしながら、本来の一性を多性へ引き渡すというこうした二分化を堤立する知のはたらきは、再びこの二分化を克服するものでもある。なぜなら、一つの対象を認識するとは、その対象と意識のあいだの隔たりを否定し、その対象とある意味で一つになることだからである。「認識とは、いわば認識可能なものとの合一に他ならない」のである。
ここには“知”という抽象概念の存在そのものが世界の分裂と分れた“個”の再統合を不可欠なものとする、宇宙論的根本原理の存在が示唆されている。さらに“分かれたものが一つになる”という局所的因果関係の連鎖を越えた動作原理は、仮構内部の意味的関係性における普遍法則の存在を暗示するものでもある。仮構世界内の意味的機構においては、失われたものを求めて辺境の地へ赴く探求の旅/冥界への下降/天上への上昇/禁忌の場所の侵犯などの試みの全てが、真の結末を隠し持つ最終目的地が出発地点であった故郷であることを教える鍵として機能するという物語的原型パターンが、“還帰”の相対物として同定されるからである。分裂と統合/引力と斥力を支配する“知”の自己充足の原理が、物理現象としての宇宙存在と精神現象としての意識と人の準創造行為である仮構のそれぞれにおいて共変的実質として統括して関連づけられた時、“仮構論”はその究極的なシステム理論としての意義性を改めて主張することができることになる。“分かれたものが一つになる”ことは、物理法則意味論と仮構力学を通貫した“原型質宇宙”に対して適用可能な原理法則の存在を示唆しているのである。
ラウルは重大な決心を抱いて、局長としてデダルスに命じることになる。「文字通り変わるのだ。我々自身をあるべき姿へ変身させてみろ。」不完全な人間性からの脱却を企て、完全性を具現する神性に対する還帰を目指すのは、人間存在の精神の奥裡に潜伏する本源的な作動因である知の作用の反映に他ならない。しかし局長室に戻ったラウルのもとに、再びヴィンセントの姿をしたものが現れる。ラウルはこれを「立ち向かうものの象徴」と呼び、「いいだろう、滅ぼしてやる。」と宣言する。だが“立ち向かうもの”として覚知される“象徴”の実態を、ラウルはまだ把握していない。ラウルが語る彼の主観の中の“象徴的存在”は、我々が視認しつつあるこの仮構世界における客観的物理存在として、意外な正体を示すこととなるのである。
アムネジアの部屋に入ったリル達は、そこに破壊された記憶の番人の残骸を見出す。かろうじて起動したアムネジアは、ただ同じ言葉を繰り返すだけである。「分かれたものは一つにならねばなりません。」リルは、壁の上に書き込まれた “awakening”の文字を見て言う。「残されたメッセージ。同じものをロムドで見た。」その時、アムネジアの発する言葉が変化する。「別れたものは、ロムドへ、ロムドへ…」リルもまた、失われた真実探求の目的地が彼等の出発地点であったロムドであることを知る。「モナドとヴィンセントを繋ぐ鍵、その答えはきっとあの場所にある。」様々の神話的物語の祖形に従って、思弁的映像作品『エルゴ・プラクシー』もまた、出発点への還帰をその終結の場所として選ぶのである。
00:00:00 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks