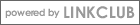Archive for September 2012
10 September
召喚魔法と個人存在 ―『Fate/stay night』における存在・現象・人格概念 3
こうして凛パートが3日目を迎えたところで唐突にこのルートは収束を強要され、あっけない幕切れを迎える。東坂凛の体験するストーリーの可能性の一つとしてあった、頓死によるゲームオーバーが具現化するのである。このエピソードを迎えた後になってようやく、士郎パートの本編1日目(1月31日)が開始されることとなる。本編における志郎の特異な生い立ちを語る“プロローグ”がここでさらに別個に導入されている事実は、このゲーム的仮構のメタレベルにおける自己言及的記述として看做し得る、興味深い要素でもあるだろう。“魔法”という世界解式と大きく関わる主題と平行してこの伝奇活劇ビジュアルノベルの重要主題を構築しているのが、主人公衛宮志郎の偏向した固定観念である“正義”と、一個の意識存在としての融通性を喪失させることとなった、彼の幼少の苛酷な体験だったのである。個人の精神内部の問題として倫理と仮構世界と現象世界の全てを含む心霊的関係性を捉えようと企図するこのエロゲーの仮構的立脚点が、改めて提示されるこのプロローグに示されている。志郎の独白からなるかなり長大なプロローグの前半部分だけを、以下に抜き出してみることにしよう。1日目 『Rebirth』
――気がつけば、焼け野原にいた。大きな火事が起きたのだろう。見慣れた
町は一面の廃墟に変わっていて、映画で見る戦場跡のようだった。――それ
も、長くは続かない。世が明けた頃、火の勢いは弱くなった。あれほど高か
った炎の壁は低くなって、建物はほとんどが崩れ落ちた。……その中で、原
型を留めているのが自分だけ、というのは不思議な気分だった。
この周辺で、生きているのは自分だけ。よほど運が良かったのか、それとも
運の良い場所に家が建っていたのか。どちらかは判らないけれど、ともかく、
自分だけが生きていた。生きのびたからには生きなくちゃ、と思った。いつ
までもココにいては危ないからと、あてもなく歩き出した。まわりに転がっ
ている人たちのように、黒こげになるのがイヤだった訳じゃない。……きっ
と、ああはなりたくない、という気持ちより。もっと強い気持ちで、心がく
くられていたからだろう。
それでも、希望なんて持たなかった。ここまで生きていたことが不思議だっ
たのだから、このまま助かるなんて思えなかった。まず助からない。何をし
たって、この赤い世界から出られまい。幼い子供がそう理解できるほど、そ
れは、絶対的な地獄だったのだ。そうして倒れた。酸素がなかったのか、酸
素を取り入れるだけの機能がすでに失われていたのか。とにかく倒れて、曇
り始めた空を見つめていた。まわりには黒こげになって、ずいぶん縮んでし
まった人たちの姿がある。暗い空は空をおおって、じき雨がふるのだと教え
てくれた。……それならいい。雨がふれば火事も終わる。最後に、深く息を
はいて、雨雲を見上げた。息もできないくせに、ただ、苦しいなあ、と。も
うそんな言葉さえこぼせない人たちの代わりに、素直な気持ちを口にした。
――それが十年前の話だ。
その後、俺は奇跡的に助けられた。体はそうして生き延びた。けれど他の部
分は黒こげになって、みんな燃え尽きてしまったのだと思う。両親とか家と
か、そのあたりが無くなってしまえば、小さな子供には何もない。だから体
以外はゼロになった。要約すれば単純な話だと思う。つまり、体を生き延び
らせた代償に。心の方が、死んだのだ。
物心のつかない幼い頃に“体を生き延びらせた代償に、心の方が死んだ”という特異な体験を背負った主人公衛宮志郎の意識を支配している行動原理である正義が、救済と依存の関系を顛倒させたある種の脱臼した異常心理として語られるところに、魔法の原理と倫理の問題を中心主題とした「エロゲー界の倫理学」と呼ばれるこのビジュアルノベルの見逃すことが出来ない特質がある。
志郎の独白によるプロローグはこの後さらに暫く続けられるのだが、彼の生い立ちを要約すれば、孤児となった志郎を引き取ってくれたのが魔術師衛宮切嗣であり、“魔術協会”の支配から離れた 異端的なこの魔術師に最小限の魔法の知識のみを教授された後に偶然に聖杯戦争に巻き込まれてしまうことになるのが、主人公衛宮士郎である。衛宮士郎パートの本編では暫くの間、英霊存在についての知識も聖杯戦争に関する備えも一切持たない志郎のごく平凡な日常生活の有様が物語られていくことになる。唯一志郎の日常生活が一般の人間達と異なるのは、彼なりに魔術師としての修行を日々行っている点である。この辺りは聖杯戦争という主題との密接な関係を持った東坂凛のプロローグが語っていた魔法の原理的特質に対して、むしろ裏面から間接的に魔法と人格特性の本質を掘り下げる本作の主題を物語ることになっている。
志郎の魔法能力は、“強化”という、魔法の能力としてはいささか傍流的なものである。彼は破損した家庭用品の修理屋という特殊能力を備えているのだが、この特技の反映する魔術的側面は以下のように語られている。
古びた電気ストーブに手を触れる。普通、いくらこの手の修理に慣れている
からって、見た程度で故障箇所は判断しにくい。それが判るという事は、俺
のやっている事は普通じゃないってことだ。視覚を閉じて、触覚でストーブ
の中身を視る。――途端。頭の中に沸き上がってくる一つのイメージ。伝熱
管がイカレてたら素人の手には負えない。その時は素人じゃない方法で“強化”
しなくてはいけなかったが、これなら内部を視るだけで十分だ。それが切嗣
に教わった、衛宮士郎の“魔術”である。
士郎の魔術能力は、事物の本質的組成を知覚の一つである“触覚”のように、直感的に感知することにある。意識と事物あるいは主観と対象物の間の断絶を認めない連続性の存在原理に基づく世界観は、しばしば魔法の主題の思想的な根幹的要素とされるものである。しかし志郎の特殊能力は、魔術師の世界の常識からすれば異端以下の無駄そのものでしかない。ただ受け入れ、理解すること以外にことさら能力を発揮する術を知らない魔術師が、この伝奇活劇ビジュアルノベルの主人公の正体なのである。
そう。衛宮士郎に魔術の才能はまったく無かった。その代わりといってはな
んだが、物の構造、さっきみたいに設計図を連想する事だけはバカみたいに
巧いと思う。実際、設計図を連想して再現した時なんて、親父は目を丸くし
て驚いた後、「なんて無駄な才能だ」なんて嘆いていたっけ。物事の核である
中心を即座に読み取り、誰よりも速く変化させるのが魔術師たちの戦いだと
言う。
時に“メタモルフォシス”という言葉を用いてその要諦が語られるように、魔法の本質はしばしば現象世界の限界を超えた“変成”をこの世にもたらす超自然的な技術であるところに、その思想的意義性が主張されるものである。現象世界に束縛された仮象でしかない存在同一性を超克し、あらゆる存在物の裡に秘匿された様々の“同一性”次元の拡張を図ることによって世界の内奥の真実を捕捉することが、魔法の根本理念である。しかし士郎の場合は願望という確固とした意思を持つことがないので、変成の目標物を自身の積極的な意図として自覚することがまずできない。凛の語っていた「世界を支配することなど求めない」という願望否定の言葉とは裏腹に、凛は自分の暫定的な行動目的を正に自己本来のエゴの中に見出していたのだが、もとより「世界が自分を中心に存在する」ことを実感することが出来ないのが、主人公士郎の自我の基底から遊離した意識構造なのである。士郎の行動原理は、「自分に対して何かを求める他者のために働く」ことにしかない。“助力”という態を装った他者に対する全面的な依存という歪な形でしか生の根源的エネルギーを解放することができないのが、生きるものとしての根本理由を喪失した士郎の精神のあるがままの姿である。 しかし凛の魔術施行とは対照的ではあるが、志郎にも彼なりの流儀で行う確固とした魔術の修行の“日課”がある。この辺りの記述は、むしろ武道の鍛錬や宗教的な修行を思い起こさせるものとなっている。
深夜零時前、衛宮士郎は日課になっている“魔術”を行わなくてはならない。
「――――」結跏趺坐に姿勢をとり、呼吸を整える。頭の中はできるだけ
白紙に。外界との接触はさけ、意識は全て内界に向ける。「――同調(トレース)、開始(オン)。」
自己に暗示をかけるよう、言い慣れた呪文を呟く。否、それは本当に自己暗
示にすぎない。魔術刻印とやらがなく、魔道の知識もない自分にとって、呪
文は自分を変革させる為だけの物だ。……本来、人間の体に魔力を通す神経(ライン)は
ない。それを擬似的に作り、一時的に変革させるからには、自身の肉体、神
経全てを統括しうる集中力が必要になる。魔術は自己との戦いだ。例えば、
この瞬間、背骨に焼けた鉄の棒を突き刺していく。その鉄の棒こそ、たった
一本だけ用意できる自分の“魔術回路”だ。これを体の奥まで通し、他の神経
と繋げられた時、ようやく自分は魔術使いとなる。それは比喩ではない。実
際、衛宮士郎の背骨には、目に見えず手に触れられない“火箸に似たモノが、
ズブズブと差し込まれている。
“神経”という語に“ライン”というルビが振られ、東坂凛のパートに登場していた“レイライン”との関連が暗示されている。17世紀から18世紀にかけて、イギリスではウィリアム・ハーヴェイ等の医学者達による解剖学研究の影響の許にトマス・ウィリス等の研究によって神経組織の存在が理解され、知覚と神経をあらわす述語を用いて世界の霊的機構を思念し記述することを目論む宇宙論的思弁がロマン主義を中心とする様々の文学者達の手によって展開された。ウィリアム・ブレイクの『4ゾア』や『エルサレム』等にも心霊学的な発想が解剖学的な用語を用いて語られている特徴的な箇所があったが、士郎の行う修練の場面にもそれに類した世界に伸長する個人意識とでも言うべき神経感覚を窺うことができる。宇宙と事物の全体像を空間的乖離を超えて“触覚的”に捕捉しようとするこれらの試みは、むしろ世界に漲る心霊(psyche)の根源性に関する直観的理解を深めようと欲する、伝統的心理学に属する知的関心であった。凛パートに登場した魔術原理と相補的な関係性を示して語られているのが、士郎の視点を介したこれらの魔術に関する記述なのである。
いやまあ。実際、魔術刻印っていう物がなんなのか知らない俺から見れば、
そんなのが有ろうが無かろうがこれっぽっちも関係ない話ではある。で、そ
うなるとあとはもう出たトコ勝負。魔術師になりたいなら、俺自身が持って
いる特質に応じた魔術を習うしかない。魔術とは、極端に言って魔力を放出
する技術なのだという。魔力とは生命力と言い換えてもいい。魔力(それ)は世界に
満ちている大源(マナ)と、生物の中で生成される小源(オド)に分かれる。大源、小源とい
うからには、小より大のが優れているのは言うまでもない。人間一人が作る
魔力である小源(オド)と、世界に満ちている魔力である大源(マナ)では力の度合いが段違
いだ。どのような魔術であれ、大源(マナ)をもちいる魔術は個人で行う魔術をたや
すく凌駕する。そういったワケで、優れた魔術師は世界から魔力をくみ上げ
る術に長けている。それは濾過器のイメージに近い。
魔術師は自身の体を変換回路にして、外界から魔力(マナ)を汲み上げて人間でも使
えるモノ、にするのだ。この変換回路を、魔術師は魔術回路(マジックサーキット)と呼ぶ。これこ
そが生まれつきの才能というヤツで、魔術回路の数は生まれた瞬間に決まっ
ている。一般の人間に魔術回路はほとんどない。それは本来少ないモノなの
だ。だから魔術師は何代も血を重ね、生まれてくる子孫たちを、より魔術に
適した肉体にする。いきすぎた家系は品種改良じみた真似までして、生まれ
てくる子供の魔術回路を増やすのだとか。
凛パートで語られていた“マナ”という全体性の宇宙観を暗示する発想を集約した語に対応して、その理念を個人存在に対して適用した“オド”というもう一つの概念が補足され、これらは“大源”と“小源”という漢字表記の各々に対して付されたルビとして記述されている。魔術とは魔術師自身の身体を回路として用いてそのマナをオドに変換する技であるとされている。その行為を行う動作の主体と、動作目的となる対象の間には存在論的な断絶は無い。科学の前提とは対照的に、行為者から隔絶された客観的対象物が存在し得ないのが魔術の原理であり、その特有の方法論である。世界に満ち満ちている生命力の奔流を、我が身そのものを“回路”の一部として用いて魔術師は“濾過”する。そのような全体性への没入的行為として、士郎は物品の属性を変性する“強化”の魔術に臨むのである。
衛宮士郎は魔術師じゃない。こうやって体内で魔力を生成できて、それをモ
ノに流す事だけしかできない魔術使いだ。だからその魔術もたった一つの事
だけしかできない。それが――「――構成材質、解明。」物体の強化。対象と
なるモノの構造を把握し、魔力を通す事で一時的に能力を補強する“強化”の
魔術だけである。「――、基本骨子、変更。」目前にあるのは折れた鉄パイプ。
これに魔力を通し、もっとも単純な硬度強化の魔術を成し得る。
そもそも、自分以外のモノに自分の魔力を通す、という事は毒物を混入させ
るに等しい。衛宮士郎の血は、鉄パイプにとって血ではないのと同じ事。異
なる血を通せば強化どころか崩壊を早めるだけだろう。
世界の本質に対する知的理解と術者自身の存在性向の実際の変化と外部の対象物に対する物理的操作が、同一線上の等価物として認められ得る存在論的メカニズムの許に語られているところに、魔法の本質的意義が含められていることが理解されるだろう。このような主体と客体の連続体としての宇宙論を暗示する語が“エーテル”であった。客観的物理存在の及ぼす局所的作用として主観から分離された“事象”という概念を否定することによって、魔法は“反科学”の思想的立脚点を誇示するものである。こうして東坂凛の視点で語られていた魔術の原理は、士郎パートでは反転した視界からそのシステム理論的特質を語られていくことになるのである。士郎の一般論的な魔法の知識が聖杯存在の影響の及ぼす特殊な魔術と接点を持つことになるのは、3日目(2月2日)を迎えてそうと知らぬうちにいつの間にか聖杯戦争の抗争に巻き込まれ、槍を手にして迫ってくる見知らぬ英霊であるランサーから身を守る術を模索し始めた場面においてである。
「――同調(トレース)、開始(オン)。」自己を作り替える暗示の言葉とともに、長さ六十センチ
程度のポスターに魔力を通す。あの槍をどうにかしようというモノに仕上げ
るのだから、ポスター全てに魔力を通し、固定化させなければ武器としては
使えないだろう。「――構成材質、解明。」意識を細く。皮膚ごしに、自らの
血をポスターに染み込ませていくように、魔力という触覚を浸透させる。
「――構成材質、補強。」こん、と底に当たる感触。ポスターの隅々まで魔力
が行き渡り、溢れる直前、「――全行程(トレース)、完了(オフ)。」
こうしてプロローグにあった凛ルートとの内実的合流を果たし、聖杯戦争に巻き込まれた主人公衛宮士郎の内と外が一通り語り終えられることになる。本編においては先例として数度あったとされる聖杯戦争とは例外的な展開が選択され、志郎はライバルである魔術師の東坂凛と協調路線を結ぶことになる。その結果、魔法と聖杯戦争の関連について全く無知であった志郎に対して凛が様々の知識を補完的に教授するという形で、さらに魔法と英霊存在の特質に関する情報が語られて行くことになるのである。以下は士郎と凛の間で交わされる、サーヴァントと英霊に関する会話である。
「ゴーストライナー……?じゃあその、やっぱり幽霊って事か?」とうの昔
に死んでいる人間の霊。死した後もこの世に姿を残す、卓越した能力者の残
留思念。だが、それはおかしい。幽霊は体を持たない。霊が傷つけられるの
は霊だけだ。故に、肉を持つ人間である俺が、霊に直接殺されるなんてあり
得ない。
「幽霊……似たようなものだけど、そんなモンと一緒にしたらセイバーに殺
されるわよ。サーヴァントは受肉した過去の英雄、精霊に近い人間以上の存
在なんだから」
「――はあ?受肉した過去の英霊?」
「そうよ。過去だろうが現代だろうが、とにかく死亡した伝説上の英雄を引
っ張ってきてね、実体化させるのよ。ま、呼び出すまでがマスターの役割で、
あとの実体化は聖杯がしてくれるんだけどね。魂をカタチにするなんてのは
一介の魔術師には不可能だもの。ここは強力なアーティファクトの力におん
ぶしてもらうってわけ。」
「ちょっと待て。過去の英雄って、ええ……!?」セイバーを見る。なら彼
女も英雄だった人間なのか。いや、そりゃ確かに、あんな格好をした人間は
現代にはいないけど、それにしたって――「そんなの不可能だ。そんな魔術、
聞いた事がない。」
「当然よ、これは魔術じゃないもの。あくまで聖杯による現象と考えなさい。
そうでなければ魂を再現して固定化するなんて出来る筈がない。」
「……魂の再現って……じゃあその、サーヴァントは幽霊とは違うのか……」
「違うわ。人間であれ動物であれ機械であれ、偉大な功績を残すと輪廻の枠
から外されて、一段階上に昇華するって話、聞いたことない?英霊っていう
のはそういう連中よ。ようするに崇め奉られて、擬似的な神様になったモノ
たちなんでしょうね。降霊術とか口寄せとか、そういう一般的な“霊を扱う魔
術”は英雄(かれら)の力の一部を借り受けて奇跡を起こすでしょ。けどこのサーヴァン
トっていうのは英霊本体を直接連れてきて使い魔にする。だから基本的には
霊体として側にいるけど、必要とあらば実体化させて戦わせられるってワケ。」
聖杯の作用の許に行われる召喚魔法は、過去から時空を超えて既存の人格を呼び寄せるような技術とは全く異なったものである。本来は人間存在としてあったものが、英雄的行為に対する人々の崇敬を得た結果、その人格特性に意味的な内実を蓄積することによって“擬似的な神様”へと昇華することができるのだという。これは、物質が保有するエネルギー値に対応して個体・液体・気体等の位相の変化を得る“相転移”を行う物理現象と類比的に、人格が崇敬という意味的エネルギーを得て霊的存在属性の位相跳躍を行い得ることを示している。物質粒子とその振動様態に限って科学の世界で受容されて来た跳躍的な位相変換の可能性を、意識体と想念の相関においても見出すことによって“意味的相転移”の存在を認め、その過程が“受肉する”とキリスト教神話の中にしばしば用いられて来た異界面の概念を適用して語られることになっているのである。さらにこの過程は“人格”を仮想する意識作用によって遂行されるものなので、その対象物は「人間であれ動物であれ機械であれ」区別を選ぶ必要はないのである。
人として一個の主体的人格を形成するに足らない霊的欠損と、自身が陥った聖杯戦争という周囲の状況に対する全くの無知を抱え込んだ主人公である衛宮士郎は、本来はライバルである筈の凛との合体を果たして、愈々『Fate/stay night』の物語は本格的にそのストーリーの内実を拡充させて行くように見える。しかしこのビジュアルノベルの実態は、通常“伝奇活劇ロマン”という言葉で理解されているものとはいささか異なったものとなっている。以下は4日目(2月3日深夜)を迎えた本編士郎パートの続きである。凛とアーチャーの例に見られたのと同様に、英霊存在自身との知的会話を通してサーヴァントに関する魔術的知識が掘り起こされていくことになる、士郎と志郎のサーヴァントとなったセイバーとの会話である。セイバーは士郎が聖杯戦争におけるマスターとしては全く例外的に、サーヴァントに対する魔力供給を行うことが出来ていないことを告げるのである。
「ええ、それなのですが、……おそらく、これはもう私たちでは解決できな
い事です。私たちサーヴァントはマスターからの魔力提供によって体を維持
する。だからこそサーヴァントはマスターを必要とするのですが、それが―
―」
「……俺が半端なマスターだから、セイバーが体を維持するのに必要なだけ
の魔力がないって事か?」
「違います。たとえ少量でもマスターから魔力が流れてくるのなら問題はな
いのです。ですが、シロウからはまったく魔力の提供がありません。本来繋
がっている筈の霊脈が断線しているのです。」
凛とアーチャーの会話を通して語られていた“レイライン”というマスターとサーヴァントの間の心霊的関系を構築する回路あるいは力が、マスターとしての士郎には全く欠損していることを士郎はサーヴァントのセイバーから宣告されるのである。それにもかかわらず、召喚者としての自覚を全く持つことの無かった士郎の許に何故か彼のサーヴァントとして現界したのが、セイバーとして実体化した英霊であった。その理由を語るべき彼女の正体を示すこの英霊の“真名”は、まだここでは明かされていない。
ストーリーが聖杯戦争を中心にした魔術師達の抗争を軸に進行を始めたかのように見えても、むしろこの伝奇活劇ビジュアルノベルが執拗に描くのは主人公衛宮士郎の人間存在としての精神的欠陥を暴く瑣末なエピソードである。マスターからの魔力供給の無いままに圧倒的な力量を持つバーサーカーとの戦いを強いられ、すんでのところで両断されかねなかったセイバーを、士郎は聖杯戦争を戦う魔術師としての基本戦略を無視して身を挺して守るという暴挙に出る。それは共闘者である東坂凛の聖杯戦争参加者としての判断に従えば、全くの無意味行為以外の何物でもない。しかしこの愚挙に対する士郎の内面の論理は、以下のようなものである。
……恐らく。あの瞬間、自分の中にあった“殺される”という恐怖より、セイ
バーを“救えない”という恐怖の方が、遥かに強かっただけの話。
生命を規定する筈の原初的生存本能に値するものを、士郎は保有していない。彼の行動原理を導く筈の衝動は、自身の生命の維持には反する全く別の次元から及ぼされる“恐怖”にある。自己犠牲に及ぶことさえもない士郎の行動はセイバーの窮地を救うものでは決してなかったが、思わぬ展開に従ってセイバーと士郎の両者ともこの危機的状況を脱することができる。しかし、自分のマスターとなった者の精神的状況を冷徹に判断する彼のサーヴァントであるセイバーの指摘も、凛のそれと全く変わらぬ視点に基づいた以下のようなものである。
「そうですね。それが正常な人間です。自らの命を無視して他人を助けよう
とする人間などいない。それは英雄と言われた者たちでさえも例外ではない
でしょう。ですから――そんな人間がいるとしたら、その人間の内面はどこ
か欠落しています。その欠落を抱えたまま進んでは、待っているのは悲劇だ
けです。」
主人公士郎の抱く無私の博愛主義も純粋極まりない倫理観も、このゲーム作品の主題的見通し図の中では全面的意義性を保障する概念軸に接することは決してないのである。 サーヴァントに対する“魔力供給”というマスターとしての不可欠の機能を発揮することが出来ないばかりか、士郎は逆にサーヴァントであるセイバーの霊的能力である治癒効果によって自身の肉体の損傷を癒されることになる。本来なら致命傷である筈の甚大な外傷を敵サーヴァントに負わされた士郎が理不尽な回復を示した理由を、東坂凛は以下のように推測して語る。4日目、2月3日の朝を迎えた士郎と凛の会話である。
「そうなると原因はサーヴァントね。貴方のサーヴァントはよっぽど強力な
のか、それとも召還の時に何か手違いが生じたのか。……ま、両方だと思う
けど、何らかのラインが繋がったんでしょうね。」
「ライン?ラインって、使い魔と魔術師を結ぶ因果線の事?」
「あら、ちゃんと使い魔の知識はあるじゃない。なら話は早いわ。ようする
に衛宮くんとセイバーの関係は、普通の主人と使い魔の関係じゃないってコ
ト。見たところセイバーには自然治癒の力もあるみたいだから、それが貴方
に流れてるんじゃないかな。普通は魔術師の能力が使い魔に付与されるんだ
けど、貴方の場合は使い魔の特殊能力が主人を助けてるってワケ。」
あらゆる細目において聖杯戦争における例外事項を現出することになっていた衛宮士郎とセイバーの間の関系は、マスターとサーヴァントの間に存在する原初的人格概念の裡に秘められた、未知なる“同一性”あるいは“相当性”の存在を指し示すこととなるのである。エロゲー『Fate/stay night』の仮構作品としての最も興味深い主題は、そのような意味における人格同一性解釈の拡張論議の裡にある。さらに凛との会話を通して士郎は、セイバー達サーヴァント存在とマスターである魔術師達の関系性の深奥と英霊存在の根本属性を学ぶことになる。
「聖杯を手に入れる為にマスターがサーヴァントを呼び出す、じゃない。聖
杯が手に入るからサーヴァントはマスターの呼び出しに応じるのよ。」
「マスター同士で和解して、お互いに聖杯を諦めれば話は済むと思っていた
けれど、サーヴァントが聖杯を求めて召還に応じて現れたモノで、けして聖
杯を諦めないのならば、それじゃ結局、サーヴァント同士の戦いは避けられ
ない。……なら。自分を守るために戦い抜いてくれたあの少女も、聖杯を巡
って争い、殺し、殺される立場だというのか。……なんてことだ。英霊だか
なんだか知らないけど、セイバーは人間だ。昨日だってあんなに血を流して
た。」
「あ、その点は安心して。サーヴァントに生死はないから。サーヴァントは
絶命しても本来の場所に帰るだけだもの。英霊っていうのはもう死んでも死
なない現象だからね。戦いに敗れて殺されるのは、当事者であるマスターだ
けよ。」
現象世界での生死の断絶を超えた概念的存在である英霊は、闘争における敗北が自らの死を意味する魔術師達とは全く異なり、サーヴァントとしての“クラス”を解放されるだけである。本来英霊とされるもの達は、物質と生命の世界とは全く異なる別個の次元に帰属するものだからである。凛は英霊存在と人間存在の間にあるこの次元の異なりについて、“自然霊”と“人間霊”という言葉を当て嵌めて語る。
「そうよ。けれどサーヴァント達は私たちみたいに自然から魔力(マナ)を提供され
ている訳じゃない。基本的に、彼らは自分の中だけの魔力で活動する。それ
を補助するのがわたしたちマスターで、サーヴァントは自分の魔力プラス、
主であるマスターの魔力分しか生前の力を発揮できないの。けど、それだと
貴方みたいに半人前のマスターじゃ優れたマスターには敵わないって事にな
るでしょ?その抜け道っていうか、当たり前って言えば当たり前の方法なん
だけれど、サーヴァントは他から魔力を補充できる。サーヴァントは霊体だ
から。同じモノを食べてしまえば栄養はとれるってこと。」
「簡単でしょ。自然霊は自然そのものから力を汲み取る。なら人間霊である
サーヴァントは、一体何から力を汲み取ると思う?まず、呼び出される英霊
は七人だけ。その七人も聖杯が予め作っておいた役割(クラス)になる事で召還が可能
となる。英霊そのものをひっぱってくるより、その英霊に近い役割を作って
おいて、そこに本体を呼び出すっていうやり方ね。口寄せとか降霊術は、呼
び出した霊を術者の体に入れて、なんらかの助言をさせるでしょ?それと同
じ。時代の違う霊を呼び出すには、予め筐(はこ)を用意しておいた方がいいのよ。」
「役割(クラス)――ああ、それでセイバーはセイバーなのか!」
「そういう事。英霊たちは正体を隠すものだって言ったでしょ。だから本名
は絶対に口にしない。自然、彼らを現す名称は呼び出されたクラス名になる。」
「それもあるけど、彼らの能力を支えるのは知名度よ。生前何をしたか、ど
んな武器を持っていたか、ってのは不変のものだけど、彼らの基本能力はそ
の時代でどのくらい有名なのかで変わってくるわ。英霊は神さまみたいなモ
ノだから、人間に崇められれば崇められるほど強さが増すの。存在が濃くな
る、とでも言うのかしらね。信仰を失った神霊が精霊に落ちるのと一緒で、
人々に忘れ去られた英雄にはそう大きな力はない。」
人々の崇敬と信仰がその存在を“濃くする”と凛が語るところに、英霊の概念的な存在特質が端的に窺える。かつては神として敬われていたものが人々の意識から遠のくことによって精霊という姿に堕落し、あるいは悪魔として反転的なイメージに変身を遂げてしまうこともあるのだろう。人間存在の“影”として措定される汎神論的位相として神や聖霊を理解する心霊学的機構の裡に英霊存在も認められるものだろう。人の意識空間の中に醸成される空虚な観念的イメージであると共に、観念論的実在としての“原存在”の意義性をも実は同様に担っているのが、この伝奇活劇ビジュアルノベルが語る英霊達の素性なのである。そこには現代の科学思想が意図的に封印してきた実念論的存在・現象解釈の復権が確かに窺われる。その顕著な実例となるのがサーヴァント達の能力と彼等の携える武器である。英霊存在の振るうとされる彼等の武器の桁外れの強大さは、そのまま神話的人物像を語り伝える人々の願望と理想を具現化したものなのである。凛はさらに続けて語る。
「彼らにはそれぞれトレードマークとなった武器がある。それが奇跡を願う
人々の想いの結晶、貴い幻想とされる最上級の武装なワケ。」
凛の挙げる英霊存在と概念的に一体化した武具の典型的な例となると思われるのが、アーサー王の保持していた伝説の剣“エクスカリバー”である。幼少のアーサーに国王となるべき資格を与え、幾多の戦いと勝利を通じてこの人物のアイデンティティを完成させた伝説の剣の名とその謂れには諸説があるが、この伝奇活劇ビジュアルノベルでは「予め約束された勝利の剣」としてその名を判読している。この剣の名は、逆賊モードレッドとの戦いで負った傷を妖精の国で癒した後、いつか再びブリテンの国に再来して王国の再建を果たしてくれることを待ち望まれる「帰還すべき王」として後世の人々の想念を支配した、復活の約束に縛られたアーサー王の人格同一性概念と直裁に繋がるものなのである。
英霊の本質と聖杯戦争の実態を理解した衛宮士郎は、改めてこの苛烈な闘争に参入することの意義を彼なりに見出す。しかしそれは、むしろ“伝奇活劇ロマン”という物語世界の肌理に抗う、顛倒した目的意識なのである。士郎は、仮構世界と現実世界の双方の意味的内実を支える筈の、ゲーム内設定条件の無化というある種の脱システム的解法を試みようと決心するのである。
何故だろう。聖杯には、嫌悪感しか湧かない。望みを叶えるという杯。それ
がどんなモノかは知らないが、サーヴァントなんていうモノを呼び出せる程
の聖遺物だ。どんな望みも叶える、とまではいかないにしても、魔術師とし
て手に入れる価値は十分すぎる程あるだろう。それでも――俺はそんなモノ
に興味はない。実感が湧かず半信半疑という事もあるのだが、結局のところ、
そんな近道はなんか卑怯だと思うのだ。それに、選定方法が戦いだっていう
のも質が悪い。……だが、これは椅子取りゲームだ。どのような思惑だろう
と、参加したからには相手を押し退けないと生き残れない。その、押し退け
る方法によっては、無関係な人々にまで危害を加える事になる。だから、
――喜べ衛宮士郎。俺の戦う理由は聖杯戦争に勝ち残る為じゃなくて、――
君の望みは、ようやく敵う。どんな手を使っても勝ち残ろうとするヤツを、
力づくでも止める事。
物語が物語としての完結した意味を構築せねばならないという制約を負っていることを物語あるいは物語の中の登場人物自身が明確に意識しているという構造は、20世紀ファンタシー文学におけるメタフィクション戦略の一つの典型になっていたが、21世紀におけるゲーム的仮構世界はその特有のメタフィクションの戦略として、時に物語の意味性を基底から破綻させるメタ物語的構図を導入することとなる。類型的な“物語性”を破却してそこに主張されるのは、記述システムとしての仮構が保持する純然たる思弁性なのである。純思弁的伝奇活劇ビジュアルノベルである『Fate/stay night』は、概念存在たる英霊と概念人格たるサーヴァントに加えて、さらに“概念魔法”という概念を提示することによって、仮構世界の観念空間の全面的拡張を図ることとなる。彼等の前に現れたバーサーカーの、いかなる攻撃をも無化する程の圧倒的なサーヴァントとしての能力を推し量って、セイバーは士郎に語るのである。
「……これは憶測ですが、バーサーカーの宝具は“鎧”です。それも単純な鎧
ではなく、概念武装と呼ばれる魔術理論に近い。おそらく――バーサーカー
には、一定の水準に達していない攻撃を全て無効化する能力がある。私の剣、
凛の魔術が通じなかったのはその為でしょう。」
セイバーの語る“概念武装”は、ゲーム世界を枠外から瞥見する視点に従えばゲーム内仮構を進行するための各種設定条件の一つとしてプログラムされた、規定の相関関係と設定値に還元される情報概念に他ならない。ゲーム的仮構の中に導入された魔法と超自然的存在の示す特殊能力について、このビジュアルノベルは際立って自省的な視点を有しているのである。概念情報の集積として物語化されたゲーム作品は一つの独立した可能世界であると共に、“現実世界”という可能世界の中で体験される一個のゲーム世界でもある。ゲームをプレイするプレイヤー/鑑賞者は、概念を抽出して一つの可能世界の世界観を構築する意識の主体として、事象性に拘束されない次元跳躍的な複眼的視点をゲーム的メタフィクションの機構として提供されているのである。セイバーはさらに続けてバーサーカーの概念魔法について語る。
「はい。宝具と通常攻撃では比べるべくもない。宝具のCランクは、通常攻
撃に変換すればA、ないしA+に該当します。……ですが、バーサーカーを
守る“理(ことわり)”は物理的な法則外のものです。アレは、たとえ世界を滅ぼせる宝
具であれ、それがAランクに届いていないものならば無力化する、という概
念です。」
「バーサーカー……ヘラクレスは神性適正を持つ英霊だ。神の血を受けた英
霊には、それと同等の神秘でなければ干渉できない。」
個人人格と心霊的宇宙観とゲーム理論的情報概念を“概念としての宇宙”という場の中で実念論的仮構として再統合することを目論む思弁が、この伝奇活劇ビジュアルノベルの持つ一つの相貌なのであった。そこには神と魔法と想念が宇宙定数を支配する欠かせない要因として認められているのである。
15:13:12 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
06 September
召喚魔法と個人存在 ―『Fate/stay night』における存在・現象・人格概念 2
『Fate/stay night』においては、取り分け“魔術”という知と技術のメカニズムの裡に暗示される“召喚魔法”において具現化された“英霊”と呼ばれる存在の選別的特性が人格概念に対する再考察を要請する思弁的企図として提示されており、さらにキャラクターの保持する“萌え”要素、即ちエロ・ファクターの構築にも重要な役割を果たす結果になっている。『Fate/stay night』では本編が開始する前に予備的に展開されるプロローグとして、主人公とは異なる別の人物の視点を採用することにより、英霊召喚とされるものの具体的手順とその根本理念を紹介して、召喚技術と魔法原理に関する科学概念を跳躍した思弁的設定が語られることとなっている。しかしこの“プロローグ”は、一見したところ本編の物語開始以前の序章に当たる枠外のエピソードであると共に、実はメインストーリーの中で“バッドエンド”を迎える最初の分岐ストーリーの展開の役目をも果たしているのである。中心と辺境の概念的差異を失った現代的宇宙観の思想的位相を反映した仮構世界的対応物として、この演出的特質を踏み込んで捉えることも可能だろう。
プロローグの第1日目、聖杯戦争において主人公衛宮志郎のライバルとなるヒロイン遠坂凛がサーヴァント召喚を試みるあたりでは、この仮構世界の基本原理を形成すると思われる特殊な概念群とそれらの織りなす特有の関係性が様々な手法を用いて紹介されている。興味深いのは、文字列とそこに振られた読み仮名(ルビ)とが意味を乖離した二重構造を形成するという、独特のタイポグラフィーの工夫を活用してこの概念操作が試みられている点である。凛の用いる魔法の呪文はドイツ語表記を基本とするものになっているが、ドイツ語の文章に添えられた英語読みのカタカナ表記等の例に見られるように、様々な様相におけるルビの活用によって魔法の裡に秘められる概念次元の越境と存在様相の跳躍の可能性が示唆されることとなっているのである。例えば最初に凛の発する魔法の呪文は以下のような表記を用いて示されている。
「Schliessung(ロック). Verfahren(コード). Drei(3).」
これに続いて、召喚魔法の実施を試みようと魔法陣の敷設に臨む魔術師である東坂凛の独白を通して、魔法技術の基幹設定を暗示する諸概念とその基底にある原理機構が具体的に語られて行くことになる。
「聖杯戦争に参加する条件。それはサーヴァントと呼ばれる使い魔を招集し、
契約する事のみだ。サーヴァントは通常の使い魔とは一線を画す存在だ。そ
の召喚、使役方法も通常の使い魔とは異なる。」
魔術師同士の直接の対決よりもむしろその分身とも言える“サーヴァント”の間の抗争が中心となって競われるのが、このゲーム世界の中心主題となる“聖杯戦争”の仕組みだが、ここでは魔法を題材にした仮構世界にしばしば登場する魔法使いの下僕的存在である“使い魔”(familiar)を引き合いにして、召喚されるサーヴァントとの類似と相違がさりげなく語られている。この場合のような周知の類似概念に対する対比的言及に留まらず、この後には慣習的に容認された述語の本来の意味を乖離する意図的な越境的使用が行われていることが、『Fate/stay night』の採用したさらに巧妙なテキスト操作として指摘することができるのである。その布石として導入されていた語が、キリスト教伝説の中の秘跡である筈の“聖杯”であった。このような概念と表象の次元跳躍的連繋の試行は、この哲学的企図に基づくビジュアルゲーム作品における一つの創作戦略となっているようである。
「……サーヴァントはシンボルによって引き寄せられる。強力なサーヴァン
トを呼び出したいのなら、そのサーヴァントに縁のあるモノが必要不可欠な
のだ、かぁ……つまり、そのサーヴァントが持っていた剣とか鎧とか、紋章
とか、そういうとんでもない値打ち物だ。」
召喚魔法の施行に関する重要案件として、対象となるサーヴァント存在との歴史的な意味上の連関を備えた固有の物品の保持が、この魔法の成否に関わるものであるとされているのである。キリストが最後の晩餐の際に口をつけた器である聖杯であるとか、その亡骸を包んだとされる聖骸布とか、さらに延長概念としては磔刑に処されたキリストの掌と足の甲に残された聖痕等が、これと同様の意味的連係を備えた具象物である。ここに示唆されている事物の中に歴史を通して醸成された、通常“機縁”という言葉で理解されている意味性の保持する質料概念との相関あるいはそこから類推される概念と存在のアナロジーを介した原形質的変換記述の可能性は、宇宙の全体性の中で局所性を跳躍した存在物同士における相関として現れる“エンタングルメント”という概念を通じて、空間的断絶の裡にも主張し得る“同一性”の一側面に対する再考察を要求することともなるものだろう。ここに示唆されている物質的延長性を超越した相関性とその基盤にある相当性は、魔法概念の枢軸を形成する基本原理であると共に、人格概念そのものの意義性に関する根幹的検証にもこの後深く関わって来ることになる、『Fate/stay night』の中心主題なのである。
凛の発した次の魔法の呪文は、日本語表記に対してさらに異なった内実の日本語の読み仮名を重ねて配した、概念と記法の二重構造性をことさら強く意識したものとなっている。同一性と相違性の双方が重ね合わせ的に指摘し得る曖昧性の論理空間の中でこそ、魔法の原理はその特質を主張されるのである。
「閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。
繰り返すつどに五度。ただ、満たされる刻を破却する。」
存在と現象と概念の位相変換的相関を多義性の存在論空間の中に切実に模索することを意識した、科学が目を塞いだ/破却した裏の世界の多元的なシステム理論構造である魔法の原理の特質を端的に示唆している記述である。各概念が意味の多元立体空間に浮遊しており、それぞれの概念観の同等性と相当性を決定することになる論理座標軸もまた無数に漂っている。だからある特定の座標軸配置においては、“満たされる”が“破却する”に直裁に連接し得ることとなる。
「―Anfang(セット)」
「……指先から溶けていく。否、指先から満たされていく。取り込むマナが
あまりにも濃密だから、もとからあった肉体の感覚が塗りつぶされていく。
だから、満たされるという事は、同時に破却するという事だ。魔術刻印は術
者であるわたしを補助する為、独自に詠唱を始め、わたしの神経を侵してい
く。取り入れた外気(マナ)は血液に。始めよう。取り入れたマナを“固定化”する為
の魔力へと変換する。視覚が閉ざされる、目前には肉眼で捉えられぬという
第五要素。故に、潰されるのを恐れ、視覚は自ら停止する。」
凛の召喚魔法施行の過程を記述する上の文章において“外気”という日本語表記に添えて振り仮名として配された片仮名表記の“マナ”は、イギリスの宣教師コドリントンによって著書『メラネシア人』の中で報告された、太平洋島嶼において保持されている呪術的概念と重なるものだろう。東洋思想における“気脈”や古代ギリシア哲学における“プネウマ”とも一脈通じるところのあるこの概念は、科学思想が力学として仮定した存在単位としての座標性を備えた質量点相互の局所的作用として措定された“現象”という描像とは、全く相容れないものである。ニュートンの構築した力学的世界観の裡で厳密に定義づけられた存在物と現象という概念を超出する異界面の論理に従った言語体系の許で主張される、世界に漲る“被人格的力”に相当するこの概念は、他の同位体的概念との併置を通してさらにこの仮構世界における“魔法”と魔法使いの関連を暗示する主要概念として、意識存在と客観的物理存在の裡にあるさらなる緊密な関係性を物語ることとなるのである。そのための布石として“固定化”や“第五要素”等の語が用いられている。
引き続いて凛の行う呪文詠唱は、やはりドイツ語表記と日本語表記の併記を用いてその記述が行われている。
「Vertrag(令呪に告げる)….! Ein neuer Nagel(聖杯の規律に従い、) Ein neues Gesetz(この者、我がサーヴァントに) Ein neues Verbrechen(諌めの法を重ね給え)
--」
「―右手に刻まれた印が疼く。三つの令呪。聖杯戦争の要、サーヴァントを
律するという三つの絶対命令権が行使される。」
圧倒的な存在密度と力量を保持する英雄達を、一介の人間存在に過ぎない魔術師がサーヴァントとして使役することを可能にする基本原理が、上に語られた“霊呪”である。東洋神秘思想の裡で“書”や“護符”の中に仮定されていた、形象の中そのものに充填し時に放出することもまた可能な想念との相関を持つ“意味的エネルギー”の存在が、ここに暗示されている。この場面での凛のサーヴァント召喚は半分成功し、半分は失敗に終わるのだが、当初の意図とは異なり未知の要因に従って召喚されてしまった意外な英霊存在である“アーチャー”との会話を通して、次のように“霊呪”という言葉を通して魔術原理の核心と、召喚される英霊存在との間の潜伏した関係が語られることになる。
「……はあ。いいかね。令呪はサーヴァントを強制的に行動させるものだ。
それは“行動を止める”だけでなく、“行動を強化させる”という意味でもある。」
――
「そっか。サーヴァントは聖杯に呼ばれるけど、呼ばれたサーヴァントをこ
の世に留めるのは。」
「そう、マスターの力だ。サーヴァントはマスターからの魔力供給によって
この世に留まる。」
魔術師であるマスターは召喚された英霊であるサーヴァントに対して禁令の権限と彼等の能力促進の権能を同時に持つ訳だが、これらは実は同質のメカニズムに基づく潜在力であるのだろう。マスターはサーヴァントに対して“魔力供給”という概念を用いて語られる特殊な霊的関係性を持つとされているが、この魔力の授受という関係性は、力学的宇宙観による因果関係的能動/受動という構造に束縛されない、現象性を超えたメタレベルでのある種の“同一性”という概念をも示唆することとなるのである。
こうして『Fate/stay night』では魔術師によって召喚された“英霊”、つまり神話・伝説上の英雄的存在達が“サーヴァント”としてマスターである魔術師に仕え、戦いを繰り広げて行くことになる訳だが、ここで興味深いのは召喚の対象となる英霊達の素性である。彼等は、各々がギリシア神話や古代アイルランド神話等の中で活躍した、“英雄”と目されるものであったのだが、それぞれの存在する次元界面が異なっているために、本質属性においては密接な共通性を持つがためにむしろ互いに関わり合いを持つことがあり得ない、独立したキャラクター同士だった。しかしこの『Fate/stay night』という一つの仮構世界の中において、彼等の存在性向を束縛していた次元的断絶が超克され、聖杯を中心とした一つのルールと見通し図のもとに“戦い合う”という関係性を賦与されて、結果的にこれらのキャラクター達を媒介軸として、複数の神話・伝説の世界の統合と融和がなされる結果が招来していることになる。
そればかりでなく、聖杯戦争に召喚された英霊の一人の佐々木小次郎などは、本人が自分が神話や伝説を通して醸成された歴史上の存在とは根本的に異なる、純粋にフィクション作品の中に捏造された一切の現世的実体性を持たない擬似的存在であることを自覚しているのである。このビジュアルノベルにおいては、何らかの歴史的事実を核としてその存在傾向を民衆の想念の中に確定させていた神話・伝説上の存在達に加えて、さらにとりとめの無い個人の空想上の妄想的キャラクターまでもが同一空間に勢揃いして、互いの存在論的意義性を付託し合うことが可能となっていることになる。このような断絶した筈の世界間の跳躍が可能となるメタ可能世界次元として、『Fate/stay night』というフィクション空間を成立せしめている世界の肌理の構成単位、あるいは宇宙論的“場”がいかなる特質を持っているものとして仮定されているのかが、重要な論考の対象とならなければならないはずである。取り分けシステム理論的には、この『Fate/stay night』という伝奇活劇ビジュアルゲームにおけるオリジナルの“英雄”像であるアーチャーの存在までもが、召喚された英霊達の一人として潜伏してさらに付け加えられていることが、見逃すことのできない構造的特質となるのである。
凛パートのプロローグは更に引き続き2日目(2月1日)を迎える。魔法とサーヴァントとの関連が固有の専門用語の導入を通して語られている重要箇所と思われる部分のテキストを、続けて以下に示していくことにしよう。やはり殊に興味深いのが、“英霊”とされるものの存在論的内実を語る独特の概念と、その記述のあり方なのである。
「聖杯に選ばれた魔術師はマスターと呼ばれ、マスターは聖杯の恩恵により
強力な使い魔(サーヴァント)を得る。―――マスターの証は二つ。サーヴァントを召喚し、
それを従わせる事と。サーヴァントを律する、三つの令呪を宿す事だ。
アーチャーを召喚した事で、右手に刻まれた文様。これが令呪。聖杯によっ
てもたらされた聖痕(よちょう)が、サーヴァントを召喚する事によって変化したマスタ
ーの証である。強大な魔力が凝縮された刻印は、永続的な物ではなく瞬間的
な物だ。これは使う事によって失われていく物で、形の通り、一画で一回分
の意味がある。」
ここでは既に導入されていた“聖杯”という語と並んで、“聖痕”というキリスト教神話の中で語られていた特有の概念が導入されているが、そこには“よちょう”という異界面の概念を示すルビが施されている。“予兆”を暗示する振り仮名を配して呼ばれた英霊に対する命令権を具現した“刻印”は、手の甲に記された一つの記号であると共に、時間順序を跳躍して因果関係の顛倒を及ぼす超自然的な力を示唆する、現象性を超越した概念とも連接するものとなっているのである。そのようなプログラム記述を可能にする“場”でもあり、“エーテル”のように全てに充満して世界を満たしている材質/力とされているのが“マナ”であるのだろう。厳密な定義の許に純思弁的な記号記述を行う数学の記法とは対蹠的に、一般言語による暗示的な記法を通して既存の知識と連想の全てを参照しながら、いかなる既存の体系にも束縛されることなく独特の仮構記述を進めることができる、文学的創作技法の極まった手法がここに指摘出来るだろう。
凛のサーヴァントとして現れたアーチャーは、意外なことに本来の自身の素性を忘却してしまっていた。彼の正体である“真名”と彼が凛の召喚に応じることになってしまった隠された因縁と関係性が、このビジュアルノベルというフィクションのミステリー的要素として、さらに人格同一性に関する主題性を掘り下げる鍵となって機能することとなるのである。
「……あいつの記憶が戻るまでまで法具(きりふだ)は封印か……思いだせないんじゃ使いようがないしね。」
この仮構世界の中で採用された、サーヴァントの用いる魔力の籠った特殊な武器である“宝具”に対しては、“きりふだ”という振り仮名が適用されている。“きりふだ”と“宝具”の相当性が認められる概念決定軸は、魔術師の行動原理と英霊存在の属性記述が偶々合致する聖杯戦争という背景の裡において仮定される見通し図の一つである。主題形成上の要点となるルビの使用において統一的な一貫したメカニズムに従うことを避けて多元的なシステム構造を敢えて当て嵌め、自然言語の保持する多義性と曖昧性を見事に参照しながら独特の仮構記述の進展が図られている部分である。魔法概念に関する描写においては、一意的な推論手順に従った線的論理記述とは対蹠的な、言うなれば経路総和法的な過程が意図的に選択されているのである。
現界したサーヴァント存在の現象世界における存在様相は、“霊体”という特異な言葉を用いてその特質の一斑が語られることになっている。
「それも問題ではない。確かに着替える必要はあるが、それは実体化してい
る時だけでね。サーヴァントはもともと霊体だ。非戦闘時には霊体になって
マスターにかける負担を減らす。」
「あ、そっか。召喚されたって英霊は英霊だものね。霊体に肉体を与えるの
はマスターの魔力なんだから、わたしが魔力提供をカットすれば。」
「自然、我々も霊体に戻る。そうなったサーヴァントは守護霊のようなもの
だ。レイラインで繋がっているマスター以外には観測されない。もっとも、
会話程度は出来るから偵察ならば支障はないが」
現象世界にサーヴァントとして発現した英霊の姿は、言わばマスターの存在との相互作用として現象界面に投影された原形質存在の重ね合わせ的位相として理解されるものなのだろう。ここで“霊体”と共に殊更説明手順を弄することなくその概念の媒介軸として用いられた“レイライン”という語は、イギリスのウェールズ地方やフランスのガリア地方等に伝えられる地のエネルギーの“気脈”を呼ぶ“レイライン”(ley line)とは明らかに異なる、“霊”の原存在的連携を暗示する造語となっている。英霊存在の本来の姿であり、また彼等がサーヴァントとなった際に選択し得る位相の一つとして“霊体”という概念を持ち出し、さらにマスターとの関係性を“レイライン”という概念で語ることによって、科学的存在/現象解釈の超出を図ることを可能にする極めて戦略的な記述手法が用いられていることが確認出来るのである。そのような意味で、物理存在とは原理的に異なる“霊体”という言葉で仮称されたものが、既存のいかなる概念連合とどのような関わりを持つものとして読み取り得るのかが、この伝奇活劇ビジュアルノベルをプレイする上での最重要関心事項となるだろう。
英霊存在を周辺から定義づけることになるであろう補足情報を、このゲーム作品はさらにいくつか用意している。
「――――固有結界。魔術師にとって到達点の一つとされる魔術で、魔法に
限りなく近い魔術、と言われている。ここ数百年、“結界”は魔術師を守る防御
陣と相場が決まっている。簡単に言ってしまえば、家に付いている防犯装置
が極悪になったモノだ。もとからある土地・建物に手を加え、外敵から自ら
を守るのが結界。それはあくまで“すでにあるもの”に手を加えるだけの変化
にすぎない。だが、この固有結界というモノは違う。固有結界は、現実を浸
食するイメージである。魔術師の心象世界――心のあり方そのものを形とし
て、現実を塗りつぶす結界を固有結界と呼ぶ。……周囲に意識を伸ばす。精
神で作り上げた糸を敷き詰め、公園中を索敵する。」
サーヴァントが保持する空間を操作する魔術的な能力の成果である“固有結界”についての凛の言葉の、“現実を浸食するイメージである”という部分から、英霊自身の持つ霊体としての存在性と等質の形而上的存在論仮説に基づいた“場”の理論が想定されていることが理解できる。それは敵対的な攻撃に対して防壁を施す、単なる“バリヤー”のような物理的機能とは明らかに異なるものである。ニュートン物理学的3次元空間とは位相を違える、意識との連続体として定義可能な拡張次元空間が、魔術で用いられるという“固有結界” なのであろう。これは重力定数やシュヴァルツシルツ半径等の規定値によって出現が確定するブラックホール等の事象地平現象とはまた異なる、時空と精神の統合体が時に発現し得る想念の一種の概念的相転移を暗示する発想であると思われるものである。あるいはまたこの造語は、科学の世界でも実験の結果として確証されている、物理現象の生成に関与する意識体による“観測効果”の事例を反映した概念として理解することもできるだろう。宇宙に現出する客観的物理現象とされるものの生成における欠かせない要因として、知性を備えた意識存在の関与が仮定されねばならないことは、既に周知の事実になっているからである。観測効果が及ぼされて波束の収束を得る以前の量子的“原存在”は、相反する無数の可能性が互いを打ち消し合っている中和状態にある。このような多義性の原形質“存在”を“現実”の事象として確定させるのが、“コヒーレンス”である。これは高等な知性を備えた意識の干渉という、観測効果による可能性の一部の抽出としてもたらされる。“シュレーディンガーの猫”の名で知られている逸話が、この観測者による原形質への干渉と事象発現のメカニズムの原理を語る著名な例である。効果的な量子的干渉によって具現化した特定の現象的様態が同期性を失って崩壊した状態が、“デコヒーレンス”“と呼ばれるものである。エヴェレットの唱えた“多世界解釈”の発想の発端となった量子存在の多義的特質による重ね合わせ的打ち消し合いという特質と、その数学的記法として採用された全ての可能な運動経路を素粒子である電子の軌跡として仮想的に記述する手法であるファインマンの“歴史総和法”にも多大な影響を与えた原形質次元での量子存在の“不確定性”という認識は、既に多くのエロゲーにおいて様々の優れた仮構的反映が試みられているものである。“魔術師の心象世界――心のあり方そのものを形として、現実を塗りつぶす結界”という表現が、意識が現実世界の具現化に作用する根本原理をさらに踏み込んで導入した、『Fate/stay night』の選んだ文学的記述である。オッカムのウィリアムに代表される直裁な一意的論理至上主義の影響の許に、20世紀に至るまで唯物論的発想と共に唯名論的世界観が支配していたモダニズム的思想状況の後を受けて、ポストモダン以降の特質としてこれに対立する多義性と実念論的発想の復権が強く認められるのが、現在のエロゲー界の趨勢のようである。
続いて凛パート第3日目(2月2日)では、人間存在あるいは英霊を規定する概念の中で、“たましい”と“せいしん”という言葉がいかなる背景のもとに関連づけられているかが、殊に興味深い魔法原理の構造的枠組みを構築するものとなっている。対応すべき歴史上の類例としては、霊的組成において“魂”と“魄”を分別するような形而上的思弁における意識と精神の複合的関係性に対する考察があったことなどを挙げることもできるだろう。あるいはウィリアム・ブレイクの成し遂げた心霊的位相により構築された神話体系として語られた宇宙像を思い浮かべることもできるだろう。世界を物理現象として力学的作用に還元して記述する操作に対する反転的試行として、心霊的作用として全一的宇宙論の構築を企図する方策は様々な表象と仮想的概念を生み出してきたのである。
そのような思惑の許に試みられたと思われる『Fate/stay night』の次の概念操作例は、凛とアーチャーが他の魔術師の仕掛けた攻撃性の固有結界を発見した際の、凛の独白による記述である。
「一時的にこの呪刻(けっかい)から魔力を消す事はできるけど、呪刻(けっかい)そのものを撤去さ
せる事はできない。術者が再びここに魔力を通せば、それだけで呪刻(けっかい)は復活
してしまうだろう。内部の人間から精神力や体力を奪うという結界はある。
けれど、いま学校に張られようとしている結界は別格だ。これは魂食い。結
界内の人間の体を溶かして、滲み出る魂を強引に集める血の血の要塞(ブラッドフォート)に他な
らない。古来、魂というものは扱いが難しい。在るとされ、魔術において必
要な要素と言われているが、魂(それ)を確立させた魔術師は一人しかいない程だ。
魂はあくまで“内容を調べるモノ”、“器に移し替えるモノ”に留まる。それを抜
き出すだけでは飽き足らず、一つの箇所に集めるという事は理解不能だ。だ
って、そんな変換不可能なエネルギーを集めたところで魔術師には使い道が
ない。だから、意味があるとすれば、それは。」
上の記述においては、“呪刻”という漢字表記に“けっかい”という平仮名表記がルビとして添えられているのが興味深い事実である。主観意識にとっては動作目的として措定される対象とその結果をもたらすために選択される手段は概念地平において全く異なるものとなることもあるが、原因と結果あるいは手段と目的に対して超出的に包括的な看取を行い得るメタレベルにおける視点においては、これらは一つの上位概念の許に統合記述の方策を得ることも可能なのである。そのような意味で示唆に富むのは、“魂”に関する「調べる」、「移し替える」、「集めるという事は理解不能」等の具体的記述であろう。奇しくも現代物理学が“エネルギー”という概念を用いて存在物の示し得る様々な様相の位相変換を上位概念による統一記述として語ろうと試みたのと同様の発想で、ここでは“たましい”が物質あるいは“意識”に変換される統合記述を可能にする“エネルギー”の等位概念として用いられ、この仮構世界の魔術的システム機構の核心が言及されていることになる。“光”というエネルギーと同様に“たましい”も“移し替える”ことはできるものの、そのままの形で“蓄積する”ことは想定不能なのである。
次はこの場面に引き続く凛とアーチャーとの会話を通して、英霊存在そのもののシステム理論的特質を示すと思われる基幹情報が、さらに“たましい”という語を軸にして語られている部分である。
「アーチャー。貴方たちってそういうモノ?」
知らず、冷たい声で問いただした。
「……ご推察の通りだ。我々は基本的に霊体だと言っただろう。故に食事は
第二(たましい)、ないし第三(せいしん)要素となる。君たちが肉を栄養とするように、サーヴァン
トは精神と魂を栄養とする。」
“マナ”が先程“第五要素”とされていたのに対応して、“たましい”は“第二要素”、せいしんは“第三要素”とされている。ここでアーチャーによって語られている“霊体”という概念と“たましい”及び“せいしん”という概念をそれぞれ分別しながらも魔法を媒介軸として統括的に記述することを可能にする心霊的“統一理論”の構築が、『Fate/stay night』では極めて野心的な創作戦略として企図されているのである。それは当然のことながら英霊存在の定義を語るのみならず、我々人間存在の人格特性再検証にも深く関わることとなるだろう。現実―仮構統一場における存在・現象・人格同一性を連続的に記述する包括的システム理論が、そこに提示されようとしているからである。
このような認識手順を経ながら、凛は愈々結界消去の魔術を発動させることになる。
地面に描かれた呪刻に近寄り、左腕を差し出す。左腕に刻まれたわたしの魔
術刻印は、遠坂の家系が伝える“魔道書”だ。ぱちん、と意識のスイッチをい
れる。魔術刻印に魔力を通して、結界消去が記されている一節を読み込んで、
あとは一息で発動させるだけ。
「「Abzug(消去) Beldienung(摘出手術) Mittelstnda(第二節)。Es ist gros(軽量). Es ist klein……(重圧)!!」
英霊存在の特有の心霊的位相あるいは超物理的様相を理解する上で重要な鍵となるのが、聖杯戦争のために彼等を召喚する際にその“器”として用いられるという、“クラス”という概念である。“役割”という語に添えられたルビとして、“クラス”という語は導入されている。
サーヴァント。七人のマスターに従う、それぞれ異なった役割(クラス)の使い魔たち。
それは聖杯自身が招き寄せる、英霊と呼ばれる最高位の使い魔だ。
サーヴァントとは、それ自体が既に、魔術の上にある存在(モノ)なのだ。率直に言
おう。サーヴァントとは、過去の英雄そのものである。神話、伝説、寓話、
歴史。真偽問わず、伝承の中で活躍し確固たる存在となった“超人”たちを英
霊という。人々の間で永久不変となった英雄は、死後、人間というカテゴリ
ーから除外されて別の存在に昇格する。……奇跡を行い、人々を救い、偉業
を成し遂げた人間は、生前、ないし死後に英雄として祭り上げられる。そう
して祭り上げられた彼らは、死後に英霊と呼ばれる精霊に昇格し、人間サイ
ドの守護者となる。これは実在の人物であろうが神話上の人物であろうが構
わない。英雄を作り出すのは人々の想念だ。
東坂凛のような魔術師達が用いる“魔術”という“技”の“上位レベル”のものとして、サーヴァントとして召喚可能な“英雄”存在があるというのである。魔法を支配する原理的視点上には動作手段と行動目的対象の間に概念的差異は存在せず、魔術という技法とその行使の結果顕現する英霊は、連続的な“同一”概念の上に配置されたそれぞれの位相なのであろう。ここから理解出来るように“英雄”という概念は、個人の成し遂げた業績や達成などに関する厳密な具体的行為からのみ定義付けられるものではない。本来の人間存在からはむしろ乖離した、“人々の想念”によって形成された願望の集積体である“情報存在”として位置づけられているところに、召喚の対象となる“英霊”存在の特質がある。さらに英雄が人間存在から“除外される”という断絶があると共に“昇格”して“精霊”となるという部分には、存在と概念の間に相転移的な位相跳躍を認めると同時に、確たる“同一性”が連続的に維持されている事実も示唆されているのである。このような人間/英霊存在の位相の類似と相違の内実を語る補助的概念として採用されているのが、上の記述に導入されている“クラス”という一際興味深い語である。
聖杯は英霊たちが形になりやすい“器(クラス)”を設け、器に該当する英霊のみを召
喚させる。予め振り分けられたクラスは七つ。
剣の騎士、セイバー。槍の騎士、ランサー。弓の騎士、アーチャー。騎乗兵、
ライダー。魔術師、キャスター。暗殺者、アサシン。狂戦士、バーサーカー。
この七つのクラスのいずれかの属性を持つ英霊だけが現代に召喚され、マス
ターに従う使い魔――サーヴァントとなる。サーヴァントとは、英雄が死後
に霊格を昇華させ、精霊、聖霊と同格になった者を指す。かつて、竜を殺し
神を殺し、万物に君臨してきた英雄の武器。サーヴァントは自らの魔力を以
てその“宝具”を発動させる。言うなれば魔術と同じだ。サーヴァントたちは、
自らの武器を触媒にして伝説上の破壊を再現する。
観測効果に従って意識体が原形質次元から現象性として確定させた事物を呼び出すように、“聖杯”と呼ばれる魔術の情報集積体は“クラス”として波形を収束させたサーヴァントを抽出する。英霊を呼び出す魔術も呼び出される英霊も、英霊が振るう“宝具”と呼ばれる武器もみな、“同じ”概念の集積体なのである。ならば英霊をサーヴァントとして呼び出し使役するマスターたる魔術師も、やはり“同じ”念積体であるのだろう。そしてそれら全てが無数の意識の主体によって共有される情報でもある。
敵サーヴァントを打破するには、その正体を知ることが近道となる。自分の
正体さえ知らないバカものは例外として、サーヴァントにとって最大の弱点
はその“本名”なのだ。サーヴァントの本名―つまり正体さえ知ってしまえば、
その英霊が“どんな宝具を所有しているか”は大体推測できる為だ。言うまで
もないが、サーヴァントは英霊である以上、確固たる伝説を持っている。そ
れを紐解いてしまえば、能力の大部分を解明する事ができる。サーヴァント
がクラス名で呼ばれるのは、要するに“真名”を隠す為なのだ。なにしろ有名
な英雄ほど、隠し持つ武器や弱点が知れ渡っているんだから。サーヴァント
となった英霊は決して自分の正体を明かさない。サーヴァントの正体を知る
のはそのサーヴァントのマスターのみ。
個別の伝説や仮構世界内部においては、神話や伝説の中に登場する英雄存在の例外的権能や弱点等の特質情報と、さらに彼等の運命を支配した存在特性の秘密に関する知識は、他の大部分の人々にとって未知のものであることが暗黙の了承とされている。しかしこれらの神話・伝説及びそれらを題材にした種々の仮構世界の存在を、文学的素養に関する情報としてむしろ鮮明に弁えているのが、現実の我々の教養的枠組みを成す集合的想念なのである。『Fate/stay night』においては、仮構世界の登場人物達の保持する意識レベルは、この点において現実世界の我々のものと何ら変わることがなく、仮構世界的特例や暗黙の了承を棄却しているという意味で、見事にメタフィクションの要素を具現している。そしてメタフィクションの特質を開示するフィクションは、存在論的位相としては現実世界と“同じ”ものを主張することとなる。
伝説を形成する抽象的な意味情報の集積の具現化したものが英霊であるならば、それは個人存在であると共に様々な人々の想念が醸成した幾多の矛盾を含む概念の複合体である。そのような情報集積体を一定の“器”の中に具象化することが、召喚魔法とされるものの内実なのであった。“器”と呼ばれるものは、その英霊存在達の、聖杯戦争という背景の許で発揮される選別的能力として濾過された特質の具象化である。さらにそれとは別個に、伝説存在が情報として保有する人格的基盤となるべき能力や特質や性向があるとされるというのである。そういう意味では“真名”は、聖杯戦争という背景とサーヴァントという枠組みを持たなくとも英霊存在が本来的に保持する、人格としての原初的な本体的位相ということになる。
そうした英霊存在が根源的に保持する願望あるいは指向が、召喚魔法において“クラス”という器にその情報集積体を移し入れる際のパラメータとなり、願望器である聖杯を勝ち取ることを意図するマスターとなるべき魔術師との精神的同調が行われることとなる。 機縁と指向性において時間と空間の次元的断絶を超えた“同一性”の許に結ばれた意味的関係性を担っているのが、召喚者のマスターとサーヴァントとなる英霊存在なのである。そして取り分け興味深いことは、この伝奇活劇ビジュアルノベルの主人公である衛宮志郎も、彼のライバルとしてあるいはサブヒロインとして重要な役割を果たすことになる東坂凛も、彼等と各々のサーヴァントとして召喚に応じた英霊達との“同調”の内実については、全く無知であったという事実なのである。偶然に凛のサーヴァントとなってしまったアーチャーと、衛宮志郎のサーヴァントとしてあまりにも思いがけなく現れたサーヴァントであるセイバーの“真名”が明らかにされるのは、聖杯戦争の成り行きがかなり展進した、後半になってからのことなのである。召喚魔法には、術者である魔法使い自身の思いの及ばない隠れた選択原理が存在していたのである。
多くの仮構の従う暗黙の了承を破却してメタ仮構的リアリティの構築を目論む『Fate/stay night』では、東坂凛が聖杯戦争に参加した動機とされるものも極めて例外的な判断基準に基づくものとされている。万能の願望器である聖杯を取得すべき根本動機について交わされるアーチャーと凛の会話は、以下に示すようにかなりちぐはぐなものとなっているのである。
「願い?そんなの、別にないけど。」
「――なに?よし、よしんば明確な望みがないのであれば、漠然とした願い
はどうだ。例えば、世界を手にするといった風な。」
「なんで?世界なんてとっくにわたしの物じゃない。
あのね、アーチャー。世界ってのはつまり、自分を中心とした価値観でしょ
?そんなものは生まれたときからわたしの物よ。そんな世界を支配しろっ
ていうんなら、わたしはとっくに世界を支配しているわ。」
凛の語る、手に入れた聖杯に対して要求すべき「願いや野望なんてものは別にない。」という醒めた認識が、かつての伝説を形成した英雄達の保持していた筈の限定的な価値観に束縛されていた世界観とは明らかに異なる、はなはだ現代的な生の感覚をあらわしている。神話や伝説の中で当然のごとく受け入れられて来た王国の再建や聖地の奪還や異教徒の駆逐などの高邁な願望は、残念ながら硬直した価値観に拘束された仮構世界の中の暫定目的ではあり得ても、生身の人間存在の想念を支配する具体的なパースペクティブを構築することはあり得ないのである。次元界面を違えた様々の伝説世界の英雄達が勢揃いする『Fate/stay night』の意識空間は、おそらく我々の生きる現実世界の価値基準を支配している富や地位などの脆弱な疑似原理の制約をも超出するものであるに違いない。神話世界を支配していた戦いの目的や偉業を成し遂げることばかりでなく、現代の産業資本主義の課する競争や達成や保有などの妄想的な暫定原理に対する率直な疑問を提示する、常に反省的な意識がむしろこのビジュアルノベルの基調となっているのである。偉大な業績を成し遂げたとされる“英雄”の蒙る本質的評価と、全方位的真実を備えているとされる筈の“正義”の内実の再検証が、このエロゲーの中心的関心事となっているのである。
凛パートのプロローグの終末は、凛とアーチャーが本編の主人公衛宮志郎のサーヴァントとなった強力な英霊との邂逅を果たす場面によって導かれる。志郎がそうと理解することなく無意識の裡に召喚してしまったサーヴァントであるセイバーが現界する様を、凛の視点から記述したのが以下の文章である。聖杯の持つ魔法の力によって、想念としての意味次元にあった英雄存在が魔術師自身の人格情報を触媒として現実世界に具現する様なのである。
気配が、気配にうち消される。
ランサーというサーヴァントの力の波が、それを上回る力の波に消されてい
く。……瞬間的に爆発したエーテルは幽体であるソレに肉を与え、実体化し
たソレは、ランサーを圧倒するモノとして召喚された。
ここで語られている“エーテル”という語も、“レイライン”や“聖痕”の場合と同様に、既存の内包と外延を持つ周知の概念を敢えて説明無しに異界面の意味性を担わせて導入するという、この作品の独特のレトリック操作を適用したものである。当然この場合のエーテルは、光を伝導する機能を持って全ての空間に充満していると仮定された、相対性理論完成以前に物理学の世界の関心を支配していたあの疑似物質概念とは異なるものだろう。むしろニュートン的宇宙論の提示した絶対真空空間に浮遊する質量点としての存在単位という基本発想以前に神学者達によって採用されていた、この世の存在物を構成する“コーポーリアル体”に対して天使や霊魂等を組成する非物質的別存在様態を示す材質として構想された“アストラル体”などの概念に近接するものを持つのが、ここで用いられている“エーテル”なのであろう。
アーチャーと遠坂凛は、いきなり姿を現した志郎のサーヴァントのセイバーに瞬時に切り伏せられて、ここでバッドエンドを迎えてしまうことになるのだが、『Fate/stay night』のヒロインとして中心的役割を占めるセイバーの凄みを持つサーヴァントとしての印象を敢えて外的視点から描き出すことに役立っていたのが、東坂凛を中心にしたこのプロローグであった。さらに、魔術師としての専門的知識を持つ遠坂凛の観点からストーリーの承前を描いたプロローグパートは、魔法という主題に関してかなり複雑な裏設定のあるこのゲーム世界を解説するマニュアルの役割を果たしていたようでもある。しかし実はプロローグであると同時に、本編として凛パートでゲームを進めた場合の、バッドエンドとしてゲームオーバーという結末を迎えなければならない一つの選択肢としても理解できるのが、ここまでの進行なのであった。
16:04:50 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
05 September
召喚魔法と個人存在 ―『Fate/stay night』における存在・現象・人格概念
『Fate/stay night』は、Type Moon 社により2004年に発売された奈須きのこのシナリオによるエロゲーである。魔法の力により神話や伝説の世界から召喚された英雄達をサーヴァントとして使役し、絶大な願望を叶える力を持つ聖杯を勝ち取るための魔術師達の戦いを題材としたこのゲームは、最初はウィンドウズ版のコンピュータソフトとして発売されていたが、現在ではいくつかの家庭用ゲーム機にも移植されて一般作として広く受け入れられている。他にも『Kanon』や『Clannad』等の水準の高いエロゲーの多くがこれと同様の経過をたどって一般ゲーム作品やアニメ作品として当たり前に世間に受容されることとなっているのは、現在の日本の最先端の仮構表現と仮構世界創出の場の実態を語る一際興味深い事実であると思われるのである。作品世界の賞玩においてエロ要素を鑑賞あるいはプレイの動作目的にしたゲーム作品は一般的に総称して “エロゲー”と呼ばれているが、作品毎の内容的特質を反映してエロゲーも種々の下位区分に分類されており、それぞれ毎の個別カテゴリー名称が付け加えられていることも多い。『Fate/stay night』の場合は、“伝記活劇ビジュアルノベル”というサブジャンル名称が平行して与えられている。文学作品において歴史小説や恋愛小説や推理小説等の種々のカテゴリー区分があり、また映画作品においてサスペンスやアクションやロマンス等の様々なジャンル名称が認められるのと同様に、“ゲーム”という形で現出した仮構メディアの中においても、いくつかの選別的特質が作品固有の傾向を醸成することとなっているのである。殊にゲーム作品の場合は“エロゲー”や“ホラーゲーム”等の題材的要素から分類される範疇区分のみならず、プレイヤーによる操作手順の側面からも特有のカテゴリーが構築され、いくつかの特徴的なコンピュータ・ゲームとしての下位ジャンルが形成される結果となっている。アドベンチャー・ゲーム(ADV)、シミュレーション・ゲーム(SLG)、アクション・ゲーム(ACT)、ロールプレイング・ゲーム(RPG)、テーブル・ゲーム(TBL)、シューティング・ゲーム(STG)等がその代表的なものである。
これらのサブジャンル区分は、小説や詩の読者あるいは演劇や映画の観客の場合のように作品世界の展開に対して受動的な鑑賞者としての視座に留まることのない、双方向的関与を行って仮構世界の推進を行う“プレイヤー”の存在を前提とする新種の仮構世界の実質を具体的に物語る実例として、殊に興味深いものと思われるのである。それのみならず、既存の種々のメディアにあった先行例となる諸要素にかつての文藝作品や映像作品には存在し得なかった新規の諸要素が順列組み合わせに従って網羅的に適用された結果、多様性に満ちた芸術表現の複合形態が能動的鑑賞/個人的体験の対象となるゲーム作品として実際に制作され、種々の妙味ある仮構作物として具現化しつつあるのである。仮構とメディアの連続的な複合体として文学作品世界とゲーム作品世界を包括的に捉えるならば、従来の伝統的な文学作品はいわばページをめくって文字を読み進めることによってのみプレイを進行する、機能を大幅に制約されたゲームの一形態であるとも看做し得ることになるだろう。
エロゲーにおけるジャンル区分はかなり一般的に認知されて既にジャンル呼称が定着したものもあるが、現状では基本的に制作者側の申告による恣意的な名称賦与がなされているので、個別の作品に付加された実際の下位ジャンル名称を確認してみると、エロゲー作品の総体的な概念的枠組みの展開軸の範囲を改めて考察する上で取り分け興味深い指標となりそうなものも数多くある。以下にエロゲー専門雑誌に掲載された付加的ジャンル名称の印象的な実例のいくつかを挙げてみることにしよう。
『Fate/stay night』:伝奇活劇ビジュアルノベル
『マブラヴオルタネイティブ』:あいとゆうきのおとぎばなし
『To Heart 2 XXRATED』:ビジュアルノベル
『ef』:インタラクティブ・ノベル
『CHAOS; HEAD』:妄想科学ノベル
『戦国ランス』:地域制圧型SLG
『つよきす』:強気っ娘攻略ADV
『D. C. ~ダ・カーポ』:こそばゆい学園恋愛ADV
『夜明け前より瑠璃色な』:月のお姫様ホームステイADV
『君が望む永遠』:多重恋愛ADV
『恋姫+無双』:妄想満載煩悩爆発純愛歴史ADV
『プリズム・アーク』:S RPG style ADV
『Really? Really?』:想い出修復ADV
『ここより、はるか』:新たな世界で大切な何かを掴み取るADV
『彼女×彼女×彼女』:同居型エロ萌えADV
ゲーム作品の多くが複数のキャラクターを登場させストーリーを持つ“物語”の特質を保持することから、“ビジュアルノベル”や“インタラクティブ・ノベル”等の文学作品との類比とこれに対する付属的な特質を示唆するカテゴリー名称が与えられていることが理解出来るだろう。それと同時に物語系ゲーム世界独特の様式として“アドベンチャー・ゲーム”(ADV)という呼称が定着し、このジャンルの主流を形成しつつあることもまた分かる。上に例示した題名とサブジャンル名称の選択に反映される一見純朴でありながらも極まった諧謔性を備えた捻転したアイロニー感覚は、これらの仮構作品制作者達と受け手であるゲーマー達双方の決して固着した価値基準に容易に束縛されることのない、実はかなり高踏的な意識のあり方を反映しているものだろう。しかも “エロゲー”としての主軸となる“エロ”要素を補完あるいは延展的に拡張して多様性に富む題材と手法が様々に導入され、このジャンルの秘める潜在的特質が全方位的に展開されつつあることがここに読み取れる。
実は殆どの芸術作品の主軸を成す基幹的要素は、生に対する鋭敏な感受性と偽らざる現実認識を可能にする熾烈な知性とさらに判断を制約されることのない柔軟なアイロニーを凝縮した結果であるエロとグロとナンセンスにある筈なのである。だから演劇や文学や映画等の魅力の核心となる“芸術性”の実質がこれら三つの要素に還元されるのも、実は至極当然のことなのであった。古典的な文学作品や美術作品に内在する“エロ要素”の占める意義性は今更言うに及ばないが、いわゆる“エッチ”要素を作品的特質として明示的に掲げる“エロゲー”における“エロ”の選別的特質については、改めてその実質を確認してみる必要があるだろう。
システム的には、様々な芸術表現において創作行為と鑑賞を有機的に連関する価値基準を構築する内在原理が、“パースペクティブ”として個々の作品中に必然的に仮定されることとなる。それと同様に、“エロゲー”における作品世界鑑賞の基軸あるいはプレイヤーとしての能動的体験試行を実行するための固有の流儀は、個々のヒロインを対象としてそれぞれ毎の“攻略”を行うための選択肢の抽出を推進するという特有の様式の裡にある。攻略対象となるヒロインの基本属性に従って予め設定された“好感度”等の条件の蓄積が一定水準に達すると用意されていた“イベント”が発生し、ヒロイン個々との可能的関係性として潜在していた“ルート”の発現が確認され、最終的には攻略対象となるヒロインとのエッチシーンが導かれることにより進め手のヒロイン攻略の試行が完遂されることとなる。これは恋愛小説や冒険小説あるいはアクション映画やミステリー映画等それぞれの仮構世界において暗黙の了解として仮定されていた、仮構作品賞玩における意味的基盤を形成する目的意識や価値基準等を裏付ける基幹座標軸と等質の契約事項なのである。エロゲー世界の進行を支配するこの内在的ルールは、読み手の意識内に仮構が意味をなす世界として受容されるための前提条件となる意味性構築機構を決定する、純システム的な暫定原理なのである。特徴的なことは、エロゲーの大部分においてヒロイン攻略ルートは線的に単一の結論へと収束することは想定されておらず、むしろ選択肢の組み合わせの結果相反する物語描像が個別的に現出して、複数の拡散した“ストーリー収束”場面が実際に導かれることにある。 多くの場合プレイヤーの満足度を満たさないこれらの派生的収束結果は“バッドエンド”と呼ばれて再プレイを要求する転回軸となるが、これらも実は厳密な一可能世界のストーリー描像としては確かな“結末”の一つであったことには変わりはない。これは完結した“意味を持つ世界”でなければならないという制約を背負った従来の文芸的仮構が保持することを困難にしていた、期待に反する“無意味的収束”というはなはだ即物的で極めて“現実的”な様相を包含する機能をゲーム的仮構が新たに獲得したことを示す実例なのである。さらにこの事実は、複数の期待外れの結末として同位体的に発散した無意味的収束結果の対置を図ることにより、意味性構築機構の背後にある多世界に通貫的に存在するメタレベル的な世界の意義性そのものを検証する原理的特質を、ゲームという仮構形態が積極的な要因として備えていることをも示している。ゲーム作品は現実世界がそうであるように波束を収斂した“現象”として捕捉されるべきものではなく、波束の重ね合わされた原形質的な多義性のままにこそその“個別性”を判断されるべき新種の仮構世界なのである。
仮構世界的意味性を一定水準で完結させるだけの説得力を備えたエッチシーンが導かれた後も、ゲームのプレイ自体がそこで終結することは実は稀である。多くの場合ゲーム世界はそこから“裏ワールド”へと進展し、既に体験した筈の同形のストーリーを文字通り新たな視点から再び辿り直して拡張次元における反転的世界描像を検証し直すこととなる。 この手順は通例攻略対象となり得るヒロイン毎に用意されており、数度に渡って繰り返されることが普通である。その結果得られた新たな統括的仮構世界描像は、時に次元超出的な秘匿された世界解式の存在を確証する跳躍的手順をも示すこととなるのである。 各ヒロイン個々に対する個別の具体的攻略手順であると共に、世界レベルにおいては分岐した無数の平行世界の内実の網羅的な経験による検証と、さらに意識存在にとって世界の原理的意味性賦与を支配する情報次元の展開範囲の延展をも暗示する、従来の芸術作品においてこれまでかつて具現され得なかった新様式の構築が実現されていると看做し得る顕著な特質がこの辺りにある。
“聖杯戦争”に参加した7人の魔術師達がパートナーとして一人ずつ歴史上の英雄達を召還して戦いを繰り広げ、魔術的願望器である聖杯を勝ち取ろうと互いに競い合う、というのが『Fate/stay night』の伝奇活劇的な基本設定であったが、このビジュアルノベル作品は決して既存の神話や伝説等の依拠する固定した世界観を暗示する類型的パターンに収束してしまうことはなく、ストーリーを裏で支える仮構内存在者達の保持する価値判断や目的意識等が様々な側面から深く掘り下げられ、存在と現象と世界自体の意義性に関わる懐疑と再定義を企図する熾烈な主題性が窺える演出となっている。つまり召還される英雄の一人一人のキャラクターを、伝説を裏付けていたかつて英雄を英雄足らしめていた一意的な価値基準に基づく狭隘な見通し図に束縛されることなく、むしろこれらを反転的に脱却させてみせる大胆な思考操作を通じて伝説的存在を幻想を配した生身の人物像として再検証することにより、歴史上の“英雄的行為”や“悪逆行為”とされてきたものの内実について徹底的に批判的な精査がなされる結果となっているのである。本作の中心主題として採用された“聖杯戦争”という語に導入された“聖杯”も、実はアーサー王伝説における騎士ガラハドやパルシヴァル等との関連において語られて来た聖杯とは直接の関連を持たない呼称上の類比概念なのである。同様に、英雄存在を一般人と截然と分つことになる筈の“運命的出来事”と、平凡な一個の人間存在が日々の体験として実際に享受する飲食や性行為などの日常茶飯的出来事の双方が、ゲームプレイヤー自身の疑似体験としてあるがままの経験的事実であるかのようにごく自然に等価的に受け入れられることにより、一個の意識体にとっての切実な経験としての生の実相に対する徹底的な内省的検証もなされていく。神話を彩った神々の姿を語り伝えるのではなく、神話を個人の想念の中にまざまざと生きることを可能にしているのが、これら様々のゲーム作品の功績である。
だからこそ『Fate/stay night』においてそれぞれの主要女性キャラクターが繰り広げるエッチの過程と、極めて丁寧に描き出される日々のお料理の献立 の双方に見られる細部へのこだわりは、具体性を持つ陰影の豊かなストーリーの展開と人間関係の緻密な構築を目論むという仮構世界的リアリズム達成のための演出的要請以上に、むしろ枢軸的な主題的必然性を主張するものなのである。崇高性を帯びた英雄的行為と卑近な日常的瑣末性の双方の内実を、予め方向軸を定めたフィクション世界構築の都合のための陳腐な類型に決して陥ることなく探査し尽くし、そこに取得される実存的な真の運命性をとことん可能世界の中で味わい尽くそうという、苛烈な覚悟がその背後に潜んでいることが窺えるからである。
さらにまた『Fate/stay night』に限らず大半のビジュアルノベルでは、プレイヤーが特定場面で選択肢を選び取るという形でゲームとしてのストーリーを進行させるため、設定上の枢軸となっている前提条件に対して選択可能な結末の展開が複数に分岐し、物語世界の描像は可能態の順列組み合わせのすべてをなぞることができる仕組みとなっている。 こうしたゲーム的可能世界の束としての仮構の全体像は潜在的に想定される事象の各々を網羅的に具現し、結果としてそこに得られる状況の各々の収束が示すそれぞれの事象の発現形に対し考え得る限りの角度からその倫理的本質と実存的意義性を確証することができるという構造になっている。これは時間軸に沿った因果関係の連鎖という線的な事象発現の記述という制約を負った従来の“物語的仮構”が原理的に棄却することを選択することによって成り立っていた“物語”性に対立する、一種背反的な仮構的特質なのである。ゲーム的仮構様式の保持するこのような傾向は、さらに“タイムループ”や“平行宇宙間移動”などの多世界間の貫同一性概念再考察に深く関わる固有の主題を導入することによって存在と現象の“個別性”概念の再検証を要請するものとなり、“個人存在”という概念の新たな位相の発見にも深く関わることになるのである。現在“エロゲー”として受容されている一連の仮構作品の要求する歴史的・文化的評価は、実はこのようなコンテクストの中にこそ確証されるべきものなのである。
『Fate/stay night』とその続編とされる『Fate/hollow ataraxia』においては、魔法概念を通じて量子的存在論と心霊的宇宙論の合一を図ろうと企図する、既にエロゲー界の伝統ともなった科学的世界観の仮定に満足することがない頑強な全方位的知への願望が、やはり制作者の根幹的な問題意識としてあることが読み取れる。 殊に『Fate/stay night』において特徴的な状況設定としては、過去の自分である主人公衛宮士郎を抹殺することを決心した未来の自分である英霊となったアーチャーを志郎が倒すことにより、生と存在の不毛なループを選び取るという可能性が潜行して示唆されている事実が挙げられる。また続編の『Fate/hollow ataraxia』における、成果の得られない4日間の聖杯戦争を時間軸を捻転させて限りなく繰り返すなどという、ループ構造性とその主観意識的反映である永劫回帰という可能性に対する覚悟への偏執的な程のこだわりも同様で、これらは実存的生のあり方を不断に意識する制作者の精神の類い稀な強靭さを感じさせるものなのである。
ここに見られるようなゲームの中の仮構的な人物像をゲームプレイヤーとしてその役割を演じながら進行させていくというシステム的機構と、双方向的な選択行為により世界の全体像が多義的に変化するというゲームの枠組み的特質自体をゲームの中に箱庭的に挿入して、一つの仮構世界を成り立たせる存立条件そのものとして採用した入れ子的枠構造の導入の試みは、全方位的反射性に対する鋭敏な意識と共に、アルゴリズムを超えたアルゴリズムをどこまでも探索していこうとするメタ構造性に対する尽きない探求心を主張するものでもあるのだろう。
だから本編『Fate/stay night』に対置された続編『Fate hollow ataraxia』の関係自体も、単に前作の設定をなぞってストーリー的にフィクション世界を時間軸上に伸展させた後日談的なものとはなっておらず、断片的な疑似体験のパッチワークを繋ぎ合わせて概念空間の背後に隠された基幹設定を論理的に焙り出そうとする、純観念的な情報操作的ゲーム構造となっている。 その結果浮かび上がってくるメタレベルにおける副次的物語像は、むしろ前作の示した切実な意図と壮大な達成の意義性自体を反転させ、その結論として選ばれたものを敢えて転覆したところに、さらなる仮構的真実の考究の主題性を開拓することを企図するものとなっているのである。あたかも、キリストに対してユダに敢えて焦点を当てることによってキリスト教の本質を語ろうとするような、反転的描像の対置を試みる試行を通じて無限遠の思想的焦点を措定しようと試みる思い切った記述の趣向がそこに採用されているのである。そしてこのような捻転的主題性は、実は本編『Fate/stay night』において既に可能態として暗示されていた、潜伏した基底的主題性と看做すべきものでもまたあったのである。『Fate』シリーズのこのような複合的な視点を理解するための両編における重要な通貫的キャラクターが、アヴェスター語で“アンリマユ”と呼ばれるゾロアスター教の悪神である。常に正義の味方であらんと偏執的に欲する主人公衛宮士郎の性格的・存在的危うさが正しく理解されなければ、この思想的内実豊かなエロゲーである伝奇活劇ビジュアルノベルの本質を読み取ることはできないと思われる。常に善人の側に自身を置いておきたい人間達の都合によって作られた哀れな生け贄としての“絶対悪”は、それらの人々の心の身勝手な願望に忠実に従って悪を演じ続けているからである。
[Read more of this post]
23:01:32 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
佐倉セミナーハウス文化教養講座 第2部
例年と同様に今年も最初の90分は予定の主題を語りますが、後半の90分は前半の質疑応答に加えて第2部としてプラスアルファの雑談を行います。第2部の主題としては、現在研究中のフィギュア作品を多数持ち込んで鑑賞と論考、さらに現在執筆中の”ゲーム論”として『Fate / stay night』を対象にした論文を紹介する予定です。宮沢賢治の思想と芸術、フィギュア製品における人格概念の考察とゲームにおける存在・現象解釈は全て一連の繋がりを持つものです。
関連資料
フィギュアにおける人格概念研究
「仮構とフィギュアと自己同一性」
http://www.linkclub.or.jp/~mac-kuro/anti/figure/figure.htm
20:29:36 |
antifantasy2 |
1 comment |
TrackBacks
04 September
佐倉セミナーハウス文化教養講座テキスト
“詩と科学と宗教を一つのものにする”“心象スケッチ”
例えば賢治の代表作と言えるであろう、精神と霊的知覚の極限を模索した『銀河鉄道の夜』の舞台を提供する進行中の鉄道車両という印象的なシチュエーションが、等速直進運動を行いつつある慣性系における時間・空間の位相を再考察するためにアインシュタインの採用した思考実験の機構に触発されたものであることに間違いはないと思われる。そればかりでなく、相対性理論の提示した素粒子の存在論的解釈とその哲学的影響を巡って1920年代に切実な関心を持って論議されつつあった、量子理論の開拓した波動論あるいは確率論的解釈法についても、賢治が“心象スケッチ”において敏感に同時代的反映を示したことが分かっている。1924年9月17日の作である『春と修羅』第2集に所収の作品番号304、「半蔭地撰定」などに、その顕著な実例を見ることができる。量子論理における実在の存在論的解釈を巡る、ボーアやハイゼンベルグの論議の影響を直接反映していることが確実である例として該当すると思われる箇所を、下に引用してみよう。
半透明な緑の蜘蛛が
森いっぱいにミクロトームを装置して
虫のくるのを待ってゐる
にもかゝはらず虫はどんどん飛んでゐる
あのありふれた百が単位の羽虫の輩が
みんな小さな弧光燈(アークライト)といふやうに
さかさになったり斜めになったり
自由自在に一生けんめい飛んでゐる
それもああまで本気に飛べば
公算論のいかものなどは
もう誰にしろ持ち出せない
むしろ情に富むものは
一ぴきごとに伝記を書くといふかもしれん
宮澤賢治という個人の存在の反転的写像である、彼を取り巻く風景に対する主観的描写の中に採用された“公算論”(probability)という語が、物質粒子あるいは一個の生命体すらも“確率関数”として記述することを主張する、古典力学における運動方程式に代替するものとして量子力学が提示した存在性記述理論を示唆するものである。アインシュタインの提示した相対性理論の主要な課題点である時空連続体としての世界認識と慣性系における作用伝達の新解釈についてばかりでなく、素粒子の振る舞いについての存在論的考察としてそこから必然的に展開した実在と記述の相関についての様々な議論を、賢治は量子論理生成期の同時代人として重大な関心を持って把握していたのだった。そしてこの従来の決定論的現象解釈に取って代わるべき新機軸の実在記述理論の誕生が、結局は賢治に対しては揺るぎない信仰の道と情熱的な科学の探求の道の双方を包含する統合的世界解釈として、生の哲学の実践の道への接点を提供することになったのである。それは、『春と修羅』の序詩として提示された以下の創作理念の宣言に、あまりにも直裁に語られるものとなっている。
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち、その電燈は失はれ)
これらは二十二箇月の
過去とかんずる方角から
紙と鉱質インクをつらね
(すべてわたくしと明滅し
みんなが同時に感ずるもの)
ここまでたもちつゞけられた
かげとひかりのひとくさりづつ
そのとほりの心象スケツチです
これらについて人や銀河や修羅や海胆は
宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら
それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが
それらも畢竟こゝろのひとつの風物です
たゞたしかに記録されたこれらのけしきは
記録されたそのとほりのこのけしきで
それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで
ある程度まではみんなに共通いたします
(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに
みんなのおのおののなかのすべてですから)
けれどもこれら新生代沖積世の
巨大に明るい時間の集積のなかで
正しくうつされた筈のこれらのことばが
わづかその一点にも均しい明暗のうちに
(あるひは修羅の十億年)
すでにはやくもその組立や質を変じ
しかもわたくしも印刷者も
それを変らないとして感ずることは
傾向としてはあり得ます
けだしわれわれがわれわれの感官や
風景や人物をかんずるやうに
そしてたゞ共通に感ずるだけであるやうに
記録や歴史、あるひは地史といふものも
それのいろいろの論料(データ)といつしよに
(因果の時空的制約のもとに)
われわれがかんじてゐるのに過ぎません
おそらくこれから二千年もたつたころは
それ相当のちがつた地質学が流用され
相当した証拠もまた次次過去から現出し
みんなは二千年ぐらゐ前には
青ぞらいつぱいの無色な孔雀が居たとおもひ
新進の大学士たちは気圏のいちばんの上層
きらびやかな氷窒素のあたりから
すてきな化石を発堀したり
あるひは白堊紀砂岩の層面に
透明な人類の巨大な足跡を
発見するかもしれません
すべてこれらの命題は
心象や時間それ自身の性質として
第四次延長のなかで主張されます
大正十三年一月廿日 宮澤賢治
賢治がここで「わたくし」と名乗る自らを“存在”とは呼ばず“現象”と定義づけ、“透明な幽霊”すなわち心霊あるいはペルソナの“複合体”であると認識するのは、相対性理論の成し遂げた実在解釈の方法論の革変に見事に対応している。おそらく賢治にあっては、全体性の示す一様相を意味単子として構想するライプニッツのモナド論の発想は、相対性理論の示す宇宙観に対する考察を通して受け入れられたものであろう。そしてアインシュタインの提示した時間と空間の連続体としての世界像に対しては、この序詩では“時空”という言葉ばかりでなく、さらに“第四次延長”という言葉をも用いてその骨子が反映されている。“因果の時空的制約”という言葉にあるように、事象と存在の記述とその意識の主体の認識において示される様々な様相の等価原理的な相異なった具現化という基本認識そのものが、相対性の原理の実存的反映としてこの序詩の全体に展開する基幹理念となっている訳だが、これらは仏教思想的関連から“六道”の発想を暗示させもする“人や銀河や修羅や海胆”といういかにも賢治らしい大胆な字句を用いて、また集約的に語られ直すことになっている。これらに代表される考え得る限りの種々様々の存在物達が“宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら”各々の知覚や思考アルゴリズムに従って、“それぞれ新鮮な本体論”を考えることがあろうとも、おそらくはそのどれ一つとして“ほんとうの真実”ではあり得ない。しかし賢治には、“それらも畢竟こゝろのひとつの風物です/たゞたしかに記録されたこれらのけしきは/記録されたそのとほりのこのけしきで/それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで /ある程度まではみんなに共通いたします”という一つの得心がある。おそらく賢治の得た確信に当たるものを物理的事象解釈の例に置き換えるならば、宇宙の基幹概念として想定されるものが「真空」であっても、「エーテル」であっても、あるいは「場」と呼ばれるさらに別の概念であっても一向に構わない、これらを通じて感知される関係性そのものの主観的解釈という動的意義性に還元されるものとして、“真実”が捉えられているからだ。しかし賢治の創作理念において最も枢要な相対性理論と量子力学の存在解釈を反映した思想的核心が述べられていると思われる部分は、実は“すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから”という一節であろう。この言明に示唆される全と個の反転的合一を前提とするシステム理論的存在解釈こそが、近代西洋思想が結局は帰着してしまった、存在性における意味の喪失と生の根本原理の破綻を救済するための、重要な契機を提供するものだからである。
ニュートンの古典力学体系を推進する王立協会組織として設立されたロイヤル・ソサエティに代表される近代的な科学思想と応用技術をいち早く発展させ、他国に先んじて産業革命を成功させてヨーロッパ随一の強国となったイギリスに、その先進国としての思想と文化の本質を学ぶために明治政府によって留学生として派遣された夏目漱石は、20世紀初頭の俗物主義の王国イギリスにおける実際の思想的現状に、学ぶべき理想とはかけ離れた現代科学文明の病理と共に、古典力学とその示唆する哲学そのものの限界点をいち早く痛感することとなり、世界の将来の思想的展望に対する深い憂慮に捕われることになったのであった。科学思想と個人主義の抱え込んだ思想上の根幹的限界性は、後には“断絶”(deracination)という言葉で広く一般に理解されるようになったが、漱石はいち早く人間存在の基本的意義性の全体性の宇宙からの乖離をもたらす近代西洋思想の問題点を見極め、一人暗然とした思いにかられたのであった。黎明期の量子力学が突きつけた、あまりにも革新的な伝統理論体系に対する破壊的側面を、漱石は留学先のイギリスで身をもって体感していたのである。しかし漱石に現代文化の展望に対する思想的懐疑に導かれた深い懊悩を与えることとなった20世紀の新知識は、逆に少しばかり時代を下って賢治の心中においては、反転的に既存の宗教と思想の限界点を跳躍することを可能にするであろう、科学的/宗教的発心となり得たのである。その力強い希望に満ちた宣言を、『春と修羅』に収められた心象スケッチの作品の全編を通して確かに窺うことができるのである。そしてこれら全ての詩作理念の根底としてあるのが、先ほど見た“すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから”という宇宙論的/存在論的確信だったのである。
しかしながらこの信念を確証すべく『春と修羅』において賢治の採用したこれらの科学的発想と新感覚の専門用語は、“心象スケッチ”としてまとめられた詩作品の各々の中では、孤独な精神世界を逍遥する作者自身の姿と、その心眼に映ったとりとめのない夢想を語る一つの道具立てとして用いられていることはあっても、これらの述語の示す科学上・思想上の本来の微妙な意義性が、ことさら個々の作品自体の内部機構において主題的に緊密に構築された関係性を与えられて、計算づくの結果語られている訳ではないように思える。飽くまでも“心象”の“スケッチ”としての断片的な独白の中で、これらの全体性の世界観を示唆する新機軸の科学用語は、賢治の駆使する一般の諸分野の専門用語に紛れて、単に恣意的に挿入されているばかりのようにも思えてしまうのである。だからこれらの専門知識の保持する科学的・哲学的発想と現代物理学と現代思想の微妙な関連についての基礎知識に対する十分な理解を持たない者にとっては、賢治の使用する“科学用語”は、時として機械論的な古典力学的科学観や、エジソンによって代表される科学的応用技術(テクノロジー)をのみ示唆するものであるかのように、誤った理解をされてしまうこともあるだろう。これらの該博な知識が暗示する筈の、自省的な創作行為を行いつつある重要なメッセージの発信者としてはあまりに不用意なものとも見なされかねない用語の選択が、素朴なほどに無計画になされてしまっているかのように見えてしまうのである。このように宮澤賢治という本来は極めて思想的な要素の色濃い詩人においては、読み手の側の新傾向の専門用語と思想的発想に対する理解の程度を推し量り、これらの一般には極めて難解であった筈の思想あるいは知識を作品世界に導入する上で、書き手として払うべき説明的顧慮を全く欠いたかのように思われる、言わば独善的な創作行為を行っていると判断されかねない危うい部分が確かにあるのである。多くの人々に時として疑心を抱かせる、賢治という思想家/芸術家の裡にある一見したところ極めて不可解な矛盾点がここにある。
しかしながらこれらの、全くの説明不足としか言い様のない程の素朴な語の選択と無軌道で放埒なほどの発話行為こそが、むしろ賢治の詩作上の特徴的な傾向であると同時に、彼の芸術哲学の基底をなす根本理念ともなっているのである。賢治の詩作行為における、読者の確実な理解を省みない独善的とも見なされかねないこの野放図な用語の使用を許した根拠としてあるものこそが、このかつて例を見ない独特の思索者/行動者の本質を語る重要な手がかりとなるべきものである筈なのである。実は『春と修羅』の中に散見されるアインシュタインの相対性理論とハイゼンベルグ、ボーアその他の展開した量子力学理論に関する言及の例にも増して、むしろ相対性理論の発想が賢治に与えた重大な確信の直截な影響を見ることができるのは、「グスコーブドリの伝記」の中の以下の一節である。物語の序盤で、主人公ブドリが彼の人生の師となる科学者クーボー博士の授業を始めて目にする際の場面である。
…向こふは大きな黒板になっていて、そこにたくさんの白い線が引いてあり、さっきのせいの高い眼がねをかけた人が、大きな櫓の形の模型をあちこち指しながら、さっきのままの高い聲で、みんなに説明して居りました。
ブドリはそれを一目見ると、ああこれは先生の本に書いてあった歴史の歴史といふことの模型だなと思ひました。先生は笑ひながら、一つのとってを廻しました。模型はがちっと鳴って奇體な船のやうな形になりました。またがちっととってを廻すと、模型は今度は大きなむかでのやうな形に變りました
みんなはしきりに首をかたむけて、どうもわからんといふ風にしていましたが、ブドリにはただ面白かったのです。
「そこでかういふ圖ができる。」先生は黒い壁へ別の込み入った圖をどんどん書きました。
クーボー先生の語る講義の主題を具現化したものであると思われる、ブドリが教室で目にした不思議な模型が示す“歴史の歴史”という概念のメタ構造と、さらにまた“歴史の模型”という異次元的意味空間の交錯が撚り合わされた、とりわけ興味深い観念性の記述の例が、ここにあることを確認することができる。賢治が詩作と人生の統一スローガンとして掲げた、“詩と科学と宗教の統合”という理想を可能にすることができる、おそらく賢治にとっての宗教的回心として作用していたに違いないシステム理論的根拠を照射する理念が、実はここに浮上しているのである。何故ならばこのメタ構造概念は、アインシュタイン自身が彼の相対性理論の着想に多くを頼っていることを言明していた、マッハの哲学の以下のような原理性志向的関心を見事に反映しているからである。
「経験的所与のあいだの諸関係」を函数的に表現し、それら函数の函数を定式化しようとする
つまり、極限の真実追求を旨とする科学者/思想家にとっては、意味空間の中で多元的に分岐して個々の内実を主張し得る“函数”としての概念/現象の全体像を正しく把握して論考に組み入れるためには、“函数に関する函数”としてのメタ数理理論化の手順が不可欠であり、常に構想し得る限りの種々の座標界面を構築し得る基体となるべき、従来の理性の及ぶ範囲であった限界ある次元を跳躍した、多元空間/多元概念座標における関係性の函数的表現を柔軟に行う不断の行為と思索こそが、自身の生の哲学として切実に模索されねばならなかったのである。同様にまた宗教あるいは文学の探求者においては、欺瞞行為に対する究極の弾劾精神から行われたイエス・キリストの“目にて犯すことなかれ”という言明の反転相を考えるならば、日々の性行為や飲食等その他の日常生活の瑣末事の全てにおいてこそ、倫理や哲学の問題が真剣に考慮されなければならないのは、むしろ当然のことなのである。法廷や教場や説教檀等の限定された場にのみ構築された倫理や真理は、むしろ実存的な原理の探求者にあっては典型的な欺瞞の産物であり、それこそが唯一の確証可能な悪の実体であると判断されることにもなるからである。現実世界の倫理は、残念ながら現象世界の諸制約を負っているが故に、結局は限りある暫定倫理でしかあり得ない。むしろ仮構世界において確証される倫理こそ、生起可能な全ての条件と起こりえないあらゆる状況にも適合する究極倫理あるいは絶対倫理として、真の普遍倫理を体現し得るものであるのかもしれない。多世界における推移可能な真実の全てに通貫してある不変の倫理というパラドクスの結実が、仮構の中には求められなければならないこととなるのである。かつてサドやワイルドやドストエフスキーや、そしてル・グインが“サイコ・ミス”において追求したように、仮構はいかなる非倫理的な主題をもその中に含み得るからこそ、永遠性の倫理にのみその照準を合わせる、影の道徳を隠し持っているのである。
永遠的真実の探求を企図する求道的精神においては、カオスの内部に押し込められた、信仰の力によってかろうじて神々の支配の領域として確保された、閉じられた城塞のような孤絶したコスモスを生きることに満足するのではなく、むしろカオスを基盤に捩れと捻りを軸に伸展する全方位的存在性の展開を許容する閉塞を知らない世界構築理論が新たに構想され、考え得る限りの全てを含む本来の意味での普遍性の宇宙に意識を開放せねばならないこととなる。その結果例えば、歴史哲学を実存哲学へと変換し、あるいは楽曲を絵画へと翻訳することにより、乖離した次元界面における潜伏した同一性や共通性もしくは対照性を目ざとく読み取ることによって、現象世界における意味の断絶や矛盾を克服することが始めて可能となるのである。意味の関係性を切り離した質点あるいは波動として量化された数値のみに着目して、力学あるいは波動関数としての数式的構造性を抽出することばかりで終わりとするのではなく、むしろ意識体の保持する相関した主観的意味単位である感覚性にこそ焦点を当てて、それらの相互変換作用を含めた網羅的な意味の関係性を記述することを企図した場合には、時として視覚が聴覚に、あるいはまた触覚等の別種の感覚に置き換えられて語られ得るように、“クオリア”の相互変換性がむしろ意図的に開拓され、記述されねばならないこととなるからである。先鋭的なロマン派の詩人エドガー・アラン・ポーがその詩作の上で印象的に行ってみせたような視覚と聴覚等の感覚の交錯の記述は、単なる斬新な表現技法としてのレトリックの技巧の模索の範疇に止まらず、全体性の宇宙の原理的な記述と普遍相における意味の把握にこそ係わる、思想上の枢要な基幹原理を示すものとなっていたのである。こうして全ての不和と矛盾と差異を言わば意味の函数化を介して調和させることのできるアルゴリズムを、数学的演算処理のみならず、その処方そのものに適用することによって、実際の現象物体(マテリア)自身の奇跡的な変身(メタモルフォシス)と、そればかりでなくプレローマ的場の根幹的意味性そのものの変成を具現化する手立てが発見され得るのである。そのような意味で人格や個別性の裏面に横たわる同一性や対称性が再発見された時、改めて『春と修羅』の序詩の「すべてがわたくしの中のみんなであるように/みんなのおのおののなかのすべてですから」の一節が示唆する、量子論理的/仏教理念的な、宇宙理解/世界救済の可能性も垣間見えてくることだろう。
六道の発想の根幹にあったような、“世界の中の私”と“私の中の世界”という反転的描像が共軛的に成り立ち得るような精神界面においてこそ、真に創造的な仮構の記述は成立するのである。このような意味で常に切実な思惟を巡らせ、見て語り全ての事物に霊的に関与し、一つの個人の生を深く生きることによって全ての生と現象を意義づけ、大乗の教えを具現化して他者あるいは“みんな”の救済をも実際に企てることが可能にもなるのである。時・空・精神連続体の全体性を構想する場合に理解や把握の基礎単位を形成すべき“意味”とは、物質主義的宇宙観を前提としていた現代科学が仮定していたような、属性や特質として質量や現象の中に帰属するものとして仮定された、量化して読み取られるべき仮象情報としてあるのでは決してなかった。宇宙の根源的実質単位として存在すべき“意味”とは、“質量”や“エネルギー”や“波動”や“場”を生成する原形質として本源的に全てに先立って存在すると同時に、むしろこれらの現象を観測し記述する意識の主体とそれらの行為自身との相互作用という描像それ自身と等価的な定義を保持するものとして、その他のあらゆる個々と全体との関係性を常に意義性の階梯と機縁を増幅しながらさらに新たな固有の意味としてその流動的な内実を賦与されつつ、総合的に展開していくべき基礎概念だったのである。記述者からは独立して厳然としてある客観的な事象の存在という仮定と、機械論的過程に従った模擬実験による科学的真実の普遍的物理法則としての確証という、“ノヴェル”が担っていた硬直した幻想により損なわれてしまった仮構のエネルギーを再び解放することに成功したのが、“心象スケッチ”と宮澤賢治が名付けた、文学的表現技法の枠を超えた芸術的生のあり方であった。
“意味”の中に見いだされるべき、これによって全ての概念が共変的に変換されるべき“意味を形成する意味”とは、常に能動的にあるいは恣意的に構築され、個々の意識の主体によって意図的に賦与され得るものでもあったからこそ、現象性の中の些末な事象への任意的関与とその恣意的記述そのものが、賢治にとっては意味の複合的連鎖として紛れも無く世界の総体としての真言と共振し、人にとっての“真実の言葉”となり得ていた訳なのであった。この優れて祭礼的/祝祭的/祈祷的実例を、『春と修羅』に収録された他のいくつもの心象スケッチの中に豊富に見いだすことができるのである。そのうちでも最も特徴的な成功例の一つとして挙げ得る作品が、「アンネリダタンツェーリン」であろう。
蠕虫舞手(アンネリダタンツエーリン)
(えゝ 水ゾルですよ
おぼろな寒天(アガア)の液ですよ)
日は黄金(きん)の薔薇
赤いちひさな蠕虫(ぜんちゆう)が
水とひかりをからだにまとひ
ひとりでをどりをやつてゐる
(えゝ 8(エイト) γ(ガムマア) e(イー) 6(スイツクス) α(アルフア) ことにもアラベスクの飾り文字)
羽むしの死骸
いちゐのかれ葉
真珠の泡に
ちぎれたこけの花軸など
(ナチラナトラのひいさまは
いまみづ底のみかげのうへに
黄いろなかげとおふたりで
せつかくをどつてゐられます
いゝえ けれども すぐでせう
まもなく浮いておいででせう)
赤い蠕虫舞手(アンネリダタンツエーリン)は
とがつた二つの耳をもち
燐光珊瑚の環節に
正しく飾る真珠のぼたん
くるりくるりと廻つてゐます
(えゝ 8(エイト) γ(ガムマア) e(イー) 6(スイツクス) α(アルフア) ことにもアラベスクの飾り文字)
背中きらきら燦(かがや)いて
ちからいつぱいまはりはするが
真珠もじつはまがひもの
ガラスどころか空気だま
(いゝえ それでも
エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字)
水晶体や鞏膜(きようまく)の
オペラグラスにのぞかれて
をどつてゐるといはれても
真珠の泡を苦にするのなら
おまへもさつぱりらくぢやない
それに日が雲に入つたし
わたしは石に座つてしびれが切れたし
水底の黒い木片は毛虫か海鼠(なまこ)のやうだしさ
それに第一おまへのかたちは見えないし
ほんとに溶けてしまつたのやら
それともみんなはじめから
おぼろに青い夢だやら
(いゝえ あすこにおいでです おいでです
ひいさま いらつしやいます
8(エイト) γ(ガムマア) e(イー) 6(スイツクス) α(アルフア) ことにもアラベスクの飾り文字)
ふん 水はおぼろで
ひかりは惑ひ
虫は エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字かい
ああくすぐったい
(はい まつたくそれにちがひません
エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字)
『春と修羅』に収められたこの心象スケッチの短詩においては、詩を詠む作者の姿自身が反転的に作品の中に描き込まれている。その作者は手水鉢の底に沈んでうごめいている蠕虫という、現象世界の具現する小さな一側面に目を留め、これを観察・記録するという体を装いながら、実は神話と科学と音楽を綯い交ぜにしたとりとめのない夢想を心中に展開しているのである。一見したところ伝統的な “叙情詩”と呼ばれてきたものと同等の道具立てに基づいた、孤絶した内面世界を描いた作品空間がここにはある。しかし“心象スケッチ”としてのこの作品の成立基盤は、一般の叙情詩の類型に従って、作者個人の孤独や哀れの想い等を歌った、感情の吐露や想念の告白として成立するものとは、実は全く異なるところに立脚するものなのである。
他の心象スケッチの作品群と同様に、「アンネリダタンツェーリン」においては、意識の主体たる“私”によって、様々な“見立て”による実に豊かな“連想”が行われていることが分かる。“日は黄金(きん)の薔薇”という鮮烈なフレーズに見られるように、“私”を媒介として放埒極まりない程の概念と表象が、種々の科学的・思想的・文化的知識と共に瞬間的な連想として“連接”され、単に一匹の蠕虫の姿を写実的に描写/形容するばかりでなく、むしろ甚だしく恣意的/主観的に、あるいはむしろ際立って創造的/造形的に、あえて自然法則の枠組みに従うことなく自由に奔放に世界の一断面が語られていくのである。そこには様々の神話や生物学や音楽等の専門用語や学術的語彙の各々が、それらの本来保持していた系の内部機構の意味連関の全てを担わされて、さらに他の分野の系の種々の意味連関と跳躍的に連接されることにより、“超自然”の意味の複合体を活性化させているのである。
太陽の光の差し込む手水鉢の中の水は、記録を行いつつある観察者には特有の質感を持って見えるらしく、“寒天(アガア)”という一般には菌類の培養素地として用いられる半透明の材質つまり“ゲル”(膠質)を語る言葉で記述されている。この語からの連想としてここではさらに、特有の分子活動を与えるコロイド状の“ゾル”という混雑溶液を呼ぶ言葉が採用されることとなる。コロイドの中で観察される独特の分子の不規則運動は、微細なパスタであるバーミセリにあたかも生命体であるかのような有機的な動作を与えることから、無生物の生命化現象と誤認されてかつて科学界で様々な論争を引き起こしてきたものであった。後に植物学者ロバート・ブラウンによって、水面上に浮かべた花粉から容出した微粒子の示す不規則運動として研究され、“ブラウン氏運動”と名付けられたこの現象は、1905年にアインシュタインによって、コロイド溶液中にもたらされる特有の不規則な分子運動として、物理学的に解明されたものであった。ノーベル賞受賞論文である「光量子論」と「特殊相対性理論」に並んでこの年に発表された「ブラウン氏運動の理論」は、宇宙の現象としての具現化過程を条件づける素粒子の量子的ゆらぎの発見に先行して、実は根本的宇宙認識のニュートンモデルからの修正を迫る重大な科学的事実の一つなのであった。20世紀初めの科学思想の世界において、自然の中にある根幹的意義性を再検証する上で殊に注目の的となっていたのが、これらの用語の示唆する内実だったのである。
しかしこれらの純然たる科学史上の事実と平行して、賢治の想念の中には、踊りと音楽で構成された一つのフィクションである演劇的な枠組みを持った寓話世界が、同時に展開しているのである。手水鉢の水底で身をくねらす蠕虫の動きは、何故か“タンツェーリン”というドイツ語(“舞手”、英語ならば“dancer”に相当する語である)を用いて語られている。あるいはホフマン原作、チャイコフスキー翻案の『くるみ割り人形』のようなバレー組曲作品か、もしくはアンデルセンの異境を舞台にした童話作品の世界でも頭に想い描いているのであろうか、正体不明の侍従のような人物によって “ナチラナトラのひいさま”というこれまた意味不明の異国的な名で呼ばれることとなっているのが、この心象スケッチの中で記述の対象とされている、謎めいた蠕虫なのである。そしてこれらの取りとめのない夢想を展開する、一個の観察者であり記述者である“私”は、“水晶体や鞏膜”という観測実験機器のアパレイタスを模して解剖学的に突き放したように客観的に語られ、その“私”の得た想念自体が作品自身の中でとりとめの無い幻想として明らかに否定されもしている。作者の想念としてある幻想と、その幻想を繰り広げつつある作者自身が双方向的にその姿を投影しつつある次元階層を延展した場が、そこに繰り広げられているのである。「真空溶媒」等の他の心象スケッチにも、この現実・幻想・仮構連続体の記述が及ぼす意味の豊穣の感覚を確認することができるだろう。このように語られた観測者/記述者の姿とその脈絡の無い幻想は、オルテガの語った“窓ガラス”とも、ハムレットの語った“自然を映し出す鏡”とも異なる、全く別種の定義に基づく機器であり“存在”であり“現象”なのである。かくして“意味”として物理的広がりを持たず、従って他のいかなる同一カテゴリーのものにも含まれることはなく、全体性の宇宙の意味の一様相として示される“モナド”にも似た意識の自覚として、“私”という独特のペルソナが想定されることとなる。
しかし取りわけこの詩の固有の成立条件をなすものとして印象的なのが、水底で蠢く蠕虫の姿を“エイト ガムマア イー スイツクス アルフア”という独特の言葉で描写している部分であろう。そこには身をくねらす蠕虫のとる様々の姿形が、ギリシア文字や英語の文字やアラビア数字記号になぞらえられて、“8 γ e 6 α”と見事な視覚的形象を与えられて表現されている一方、これらの文字・記号の本来の読みに従って、一種独特の音楽的旋律まで奏でることとなっているのである。身をくねらす孑孑をあえて学名を用いて“アンネリダ”と呼び、ドイツ語のタンツェーリンと強引に繋げて“アンネリダタンツェーリン”という独特の音韻効果を備えた語を用いて呼び替える、斬新な音楽的見立てと連動するのと同種の特異な言語的創造感覚がここにはある。様々な見立てと観念の連接と新しい意味の付加を行う“私”という“現象”が、世界の中で力学的因果関係に従って機械論的にもたらされた事象の一つであるばかりでなく、同時に遡及的に歴史と出来事の総体に対する意味連関を再構築する、能動的な作用をも及ぼす機能を果たすこととなっているのである。
こうして“心象スケッチ”においては、“連想”という精神活動と“言及”という実際の行動が、時空を超えた意味と精神の連続体である世界そのものに対する有機的な注釈賦与となる。世界から受動的に意味を読み取り、そこに内包された客観的真実とされるものを単一方向的に解明するばかりでなく、同時に世界の根源的原理の意味の豊かさを、自らが主体的に附託することができるのである。何故ならば局所的な作用による因果関係に頼ることのない、時間軸の方向性を跳躍した全方位的な関係性の構築が、思念と夢想の裡においてこそ可能となり、観測と記述による様相波動の収束が直裁に機縁と因縁を構築することにより、全一なる宇宙そのものの意味性賦与に貢献しているからである。つまり、参照して語る注釈賦与の行為が、紛れもなく根源的意味連関の構築として始原的な創世行為と等価のものであり得ることとなるのである。仮構とその創り手の生きる現実が分ち難く融合した和歌の世界の存在論的位相と次元軸を共有する、見事な脱現実的汎実存的生のあり方がここに成就されている。社会による功績の実利的認知や既存の思想や組織の判断基準による功利的評価などとは全く異なるものを射程に置いた、これらの無意識の深奥にある一種音楽的な霊的活動を語る想念こそが、賢治が“真の言葉”と呼んだものであった。このようにして思念の中で世界の複合的意味性の位相変換と再生産を行い、プレローマ的原形質における可能態の醸成と、現象界におけるメタモルフォシスの錬成を成し遂げることが実際に可能となるのである。
賢治が“心象スケッチ”を語るものとして演じた、和歌における“生活実感”を“歌に詠む”、あるいは叙情詩における“心情の吐露”の“記述”という体を装った実は巧妙な捻りのある“仮構”でもあり、あるいは徹頭徹尾突き抜けて純真無垢な即興的詠唱行為でもあるスケッチ的記述は、古典力学的世界観に基づく“リアリズム”と呼ばれるいびつな仮構とは、全く対照的な原理に基づくものだったのである。実は賢治という“現象”は“心象スケッチ”の記述/発話行為において、『最後のユニコーン』の第一章に登場していたあの饒舌な蝶のように、とりとめのない連想と奇想を一人つぶやく極楽蜻蛉を振る舞っていたのであった。そしてこのような疲れを知らぬ道化を演じてみせる天真爛漫な想念と、全てに対する興味と関心に溢れた比類ない上機嫌の精神活動においてこそ、浅薄な限りある実証主義的科学の理解にしか基づかない断絶の精神世界を根底から解体して鮮やかな再構築を成し遂げることが可能となり、世界に対する真の意味性賦与を導出する健全な精神の回復が見込まれることとなる。
かくして賢治にとっては、言葉と想いを用いて交響曲的な世界の意味の連鎖に没入し、そして自らの手によって外挿的にその世界を調律する試みが、紛れもなく科学と宗教の共通目的となるべきものとして芸術的生に連接することができていた。このような宇宙的オーケストレーションへの全人格的参入行為こそが、賢治の宣言にある“詩と科学と宗教を一つのものに”統合して観測/記述/創作行為を行う営み、すなわち“心象スケッチ”なのであった。他者の救済のために行う個人としての自己犠牲の行為につきまとうパラドクス(15)と、個別的存在性の引きずる行為の展開範囲の因果関係的限界のディレムマを解消し、この誠心からの根源的願望を補完し代替する方途を約束したのが、賢治の出会った新しい科学、相対性理論と量子論理だったのである。だからこそ賢治にとっては、音声のみならず観念と概念と、そして材質や属性すら自在に“オノマトピーア”(擬音)に変換する術、すなわちしばしば魔法の究極の原理とされる“メタモルフォシス”を具現する操作が、確かに存在し得ていたのである。賢治が“科学”という言葉を用いて語った理想郷の夢想を通して垣間見ることのできるものは、20世紀後半に空疎で浅薄な隆盛を極めることとなった科学的応用技術の成果による物質的豊かさとは根本的に異なったものだったのである。70年代以降アメリカを舞台として、芸術作品の特異な表現行為として仮構世界の中からの現実世界に対する浸透を企図したアクチュアリズ厶の手法が勃興したが、アクチュアリティの芸術と生の先駆的な実践者が、実は1920年代の日本に既に存在していたのであった。機械論的自然観の束縛を持たない言の葉の生きる国日本の、仮構と現実の融合を果たすばかりではなく、全体性の宇宙と仮象としての個である“わたくし”の融合を夢想する実践的アクチュアリストが宮沢賢治だったのである。
19:07:19 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks