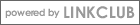Archive for February 2011
25 February
『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 4
省察18「終着の調べ」の冒頭では、ラプチャーらしきミサイルに攻撃されて壊滅する都市と廃虚を見つめる怪人の姿が示されている。その手には“?”のナンバーのあるペンダントがある。一方、旅の目的地モスクに漸く辿り着いたヴィンセントは、自らの故郷であった筈のこの都市の破壊の惨状を確認して旅の途上で目撃したラプチャーの航跡を思い浮かべる。「あの光だ。あの光がモスクを焼き払ったのかもしれない。俺の過去を消すために。」ロムドでは執国のコンピュータ達によって、ラプチャーの発射を実行したラウルの罪を問う審判が行われている。ラウルは臆することなく、モスクの難民を受け入れた執国の心の弱さを指摘する。「あの男、ヴィンセント・ローを受け入れたことが全ての悲劇の始まり。」さらにラウルはドノブ・メイヤーを問いつめて言う。「かつてあなたは神を求め、裏切られた。」/「私は違う。我等を救わぬ神など求めはしない。ただ滅ぼすのみ。」/「滅亡が必然だとしても、抗い続けるならばロムドは存在し得る。」/「だが、今は変わらねばならぬのです。神を必要としない存在へと。私に絶望はない。」執国とロムドの体制に反逆を企てたラウルが、被告としてコンピュータの哲学者達の裁きを受けながら、むしろ堂々と彼等の弾劾に対して自らの反逆行為の正当性の論証を行ってみせているのが印象的である。支配者によって下付される希望に縋る脆弱な心性を、絶望を用いて滅却しようとする強靭な意思には、もはや絶望はない。“神なき後の世界”に生きる人間の実存的生のあり方が、ここに語られたラウルの言葉に集約されている。
彼の主張する自立的な人間存在として選び得る悲壮な個人的決断は、実は19世紀末にニーチェ等によってキリスト教的束縛から解放され霊的自由を得た現代人がその自由と引き換えに直面させられることとなった、恩寵として賜った“生存理由”の放擲に対する覚悟として選び取るべきものであった。課せられた安寧よりもむしろ選び取られた痛苦の方を善しとする同様の思念が、アルベール・カミュの『シジフォスの神話』に描かれた永劫に続く苦役をこそ生き甲斐としようとする覚悟や、ウィリアム・フォークナーの『野生の棕櫚』の中で語られた「悔恨と無との間からならば、悔恨の方を選び取りたい」という台詞などに窺うことができる。神の支配による束縛を被ることの無い霊的に自由な世界とは、ラウルがこのような決死の覚悟として理解せねばならない残酷な内実を秘めたものであった。信仰の桎梏を取り払った“与えられた自由”の中に必然的に生起するこのあまりにも苛酷な現実をすっかり忘れさせてくれようとするのが、ディズニー・アニメに代表されるアメリカの享楽的な現世主義の怖いところなのだが、実はその意味では教育委員会やPTAと同様政府の教育政策も全く変わるところは無い。ラウルの決死の覚悟を認め彼の権限復帰を認めたものの、ラウルの糾弾に対しては一切の返答を試みようとしないまま無言を通していた執国は、ラウルが去った後に漸くアントラージュの声を借りて絞り出すようにして言う。「ラウルよ、お前はやがて知るだろう。…我らの真の絶望を。」自らは言葉さえ発することのない執国ドノブ・メイヤーの胸の裡に秘められた絶望の内実は、未だ明かされていない。
ロムド・シティのウーム・シスをこれまで稼働させていたのは、外部から強奪してこのドームにもたらされたプラクシーなのであった。この事実は、プラクシーの秘密を語るデダルスによってリルにも既に示されていた。「我々は、あれを“モナド・プラクシー”と呼んでいた。」/「そしてあれは、モスク・ドームから我々が奪い取ってきたものだ。」そのモスクに辿り着きヴィンスをセンツォン号に残してモスクの塔の上の部屋にやって来たリルは、怯えるピノに「私には懐かしいな。」と不思議なことを言う。玉座に腰をかけたリルの周囲に、ロムドから侵攻してきたオートレーブの兵士達の発射した銃弾が飛び散る映像が映し出されるが、これもまたラウルの眼前に姿を現していたヴィンセントらしき者の映像と同様に、果たして彼女の幻想なのかあるいは記憶の残像であるのか定かではない。ヴィンセントに記憶を呼び戻すように促していたリルであるが、リル自身もお爺様のことばかり語っていて、自身の両親のことは全く頭にないのはやはりどこか不自然である。さらに「何故プラクシーがなければ人は生きられないのか?」と、プラクシーの謎と人間存在の関係に飽くまでも人として考え込むリルなのだが、彼女もまたラウルと同様に自分たちの現状の背後にある残酷な真実を確証し得ていないのである。
破壊し尽くされたと見えたモスクの都市の中に奇跡的に保全されていた建物の一室があり、何者かがヴィンセントの持っていたペンダントをキーとして使い、部屋の入り口を開けようとしている。隔離された聖域を守っていた“記憶の番人”アムネジアは、やって来たものを迎え入れて言う。「あなた様をお待ちしていたのです、お客人。分かれたものは、一つにならなければなりません。」ヴィンセントの放擲した記憶の守護者として配置されていたこのオートレーブが語る言葉の中に、宇宙の物理現象とさらに人間心理内部の情動的メカニズムにまでも通貫して機能する、超物理法則パターンがあることを形而上界面において確認することができるだろう。ウィリアム・ブレイクの『4ゾア』やエドガー・アラン・ポーの『ユリイカ』等にも語られている、分裂と再統合の作用の裡に潜む引力と斥力の原理として現れる、自と他の関係性を支配する心霊的力学とその過程に関与すると思われる“知”の本源的特質については、ルネサンス哲学における“個と宇宙”の関係性について統括的な洞察を成し遂げたエルンスト・カッシーラーが極めて示唆的な着眼を語ってくれている。
認識論に関して言えば、すでに中世の新プラトン主義的―神秘主義の文献 は、認識と愛を相互に分ちがたく結合していた。と言うのも、精神は愛のはたらきによって対象へ駆り立てられなければ、純理論的な考察においてその対象に向かうことはできないからである。このような根本直観は、ルネサンス哲学のうちでは、パトリツィの教説においてその再興と組織的展開を見ることになる。認識のはたらきと愛のはたらきは目標を同じくする。両者とも存在の諸要素の役割を解消し、それらの本源的統一へと還帰することを目指すからである。知とはこうした還帰の道における一定の階程に他ならない。それは志向の一形態ですらある。実際、いずれの知にとってもその対象への「志向」は本質的である。最高の知性が知性となり、思惟する意識となったのは、まさにそれが愛に駆り立てられてそれ自身のうちで自己を二分化し、一つの知的対象の世界を自らに考察の対象として対置することによってであった。しかしながら、本来の一性を多性へ引き渡すというこうした二分化を堤立する知のはたらきは、再びこの二分化を克服するものでもある。なぜなら、一つの対象を認識するとは、その対象と意識のあいだの隔たりを否定し、その対象とある意味で一つになることだからである。「認識とは、いわば認識可能なものとの合一に他ならない」のである。
ここには“知”という抽象概念の存在そのものが世界の分裂と分れた“個”の再統合を不可欠なものとする、宇宙論的根本原理の存在が示唆されている。さらに“分かれたものが一つになる”という局所的因果関係の連鎖を越えた動作原理は、仮構内部の意味的関係性における普遍法則の存在を暗示するものでもある。仮構世界内の意味的機構においては、失われたものを求めて辺境の地へ赴く探求の旅/冥界への下降/天上への上昇/禁忌の場所の侵犯などの試みの全てが、真の結末を隠し持つ最終目的地が出発地点であった故郷であることを教える鍵として機能するという物語的原型パターンが、“還帰”の相対物として同定されるからである。分裂と統合/引力と斥力を支配する“知”の自己充足の原理が、物理現象としての宇宙存在と精神現象としての意識と人の準創造行為である仮構のそれぞれにおいて共変的実質として統括して関連づけられた時、“仮構論”はその究極的なシステム理論としての意義性を改めて主張することができることになる。“分かれたものが一つになる”ことは、物理法則意味論と仮構力学を通貫した“原型質宇宙”に対して適用可能な原理法則の存在を示唆しているのである。
ラウルは重大な決心を抱いて、局長としてデダルスに命じることになる。「文字通り変わるのだ。我々自身をあるべき姿へ変身させてみろ。」不完全な人間性からの脱却を企て、完全性を具現する神性に対する還帰を目指すのは、人間存在の精神の奥裡に潜伏する本源的な作動因である知の作用の反映に他ならない。しかし局長室に戻ったラウルのもとに、再びヴィンセントの姿をしたものが現れる。ラウルはこれを「立ち向かうものの象徴」と呼び、「いいだろう、滅ぼしてやる。」と宣言する。だが“立ち向かうもの”として覚知される“象徴”の実態を、ラウルはまだ把握していない。ラウルが語る彼の主観の中の“象徴的存在”は、我々が視認しつつあるこの仮構世界における客観的物理存在として、意外な正体を示すこととなるのである。
アムネジアの部屋に入ったリル達は、そこに破壊された記憶の番人の残骸を見出す。かろうじて起動したアムネジアは、ただ同じ言葉を繰り返すだけである。「分かれたものは一つにならねばなりません。」リルは、壁の上に書き込まれた “awakening”の文字を見て言う。「残されたメッセージ。同じものをロムドで見た。」その時、アムネジアの発する言葉が変化する。「別れたものは、ロムドへ、ロムドへ…」リルもまた、失われた真実探求の目的地が彼等の出発地点であったロムドであることを知る。「モナドとヴィンセントを繋ぐ鍵、その答えはきっとあの場所にある。」様々の神話的物語の祖形に従って、思弁的映像作品『エルゴ・プラクシー』もまた、出発点への還帰をその終結の場所として選ぶのである。
00:00:00 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
24 February
『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 3
一見したところ“旅物語”的なシチュエーション・コメディの形式を踏襲しながら、仮構映像作品『エルゴ・プラクシー』は各々のエピソード毎にプレゼンテーションの手法そのものを大胆に変化させて、独特の主題提示の展開を図っていく。しかし省察16「デッドカー厶」(無風)においては、動力源を持たず風力のみを用いて推進するセンツォン号が完全な無風状態に陥り停滞する中で、新天地への到来も新事件の生成も全くもたらされることのない、“旅”の要素の全てを棄却した特殊条件の許でヴィンセントとリルのセンツォン号内部での日常を描くことにより、見事に反転的な“旅物語”の様相が提示されることになる。目的地へ接近する術の全てが閉ざされた圧倒的な無為の時間を強要されて、いかにも人間的な焦燥の感覚に支配されて苛立つリルの心情が描かれたこのエピソード“Dead Calm”は、ロマン派の詩人・哲学者であるサミュエル・テイラー・コールリッジが書いた高名な哲学詩「老水夫行」の存在をさりげなく背景に暗示しているものと思われる。信天翁を意味なく殺害した罪の罰として、無風の海洋上で強いられた“無為”を通して世界の実相と対峙することを余儀なくされた一人の水夫の物語は、このアニメの心情面の主役というべき人間の人間性たるものの代弁者であるリル・メイヤーの心霊的位相を、裏側から補完するものであるのかもしれない。
目的追求の進路を閉ざされた中でリルがプラクシー=ヴィンセントの行動実態の観察に続けてオートレーブ=ピノの利き腕について観察を行うエピソードは、取り分け印象的なものとなっている。三次元的に捉えれば鏡像である反転文字は絶対座標軸を定めない限りは同形である筈なので、人間社会の慣習に染まることのない幼児などは、これらの“鏡文字”を区別する感覚を知らなかったりするのだが、高分子化合物として多糖類のあるものは“右巻き構造”を持つ“dextrose”と“左巻き構造”を持つ対称的な変異形のそれぞれを持っていることが知られている。この“変異形”は、語義的には“dexter”(右)に照応させて“sinister”(左)を冠して“sinistrose”と呼ぶべきものである筈だが、この名称は病理学的な意味の専門用語としてフランス語で“悲観主義”の意で用いられ、英語の“pessimism”に相当する異界面の意味を担わされて用いられることになっている。しかし生物体が対称的構造体であるこれらの高分子化合物を消化・吸収し同化作用を行おうとする際には、鏡面的組成を持つ物質が生体活動に不適合を及ぼすことが知られている。このように純粋に物理的な形象として見れば客観的に同形である筈のものたちも、宇宙全体を支配する偶発的なモメントの影響を受けて現象世界の基幹設定の中では決定的な差異性を条件づけられていることは、よく知られた事実である。現宇宙における“物質”と“反物質”の存在比にみられる圧倒的な偏りも、同等の隠された選択原理を暗示するものであるように思われる。太陽や星々の示す旋回方向として自然に対する観察結果と経験則から得られた憶測を反映して、英語の語彙においては“右”を表す“dexterous”が“器用な”という意味で肯定的に捉えられ、“左”を表す“sinister”は“不気味な、不吉な”という意味で否定的に捉えられているように、左右の物理的対称性は決して現象世界の位相における同格性を示すものではない。ちなみに中世の日本では“左大臣”は“右大臣”よりも格上であったりもした。純粋知性の理解の外側で世界を支配して偶奇性を選択する“モメント”の存在に想いを馳せずにいられないのが、否応無くその支配下に身を投じている“人間”なのであった。プラクシー=ヴィンセントとオートレーブ=ピノに対してリルが行う人間的知解追求衝動に根ざした観察行為と、彼女自身が行ういかにも人間的な行為である化粧を真似るオートレーブ=ピノとプラクシー=ヴィンセントの模倣行為と、そして自分の仕草を真似るピノをリルが観察する折り畳まれた観察シーンは、“観察”する人間とその人間を“模倣”する神の姿にもう一つの存在軸を加えて、“人性”の中に潜伏する原存在的“神性”の拡張解釈を目論むものとなっている。神の行う人の行動に対する模倣行為は『エルゴ・プラクシー』の最終的主題を暗示することになる訳だが、充電中のピノの示す印象的な無機質の表情やこのエピソード最後のあたりで示される見事な風の描写などを加えて、16話「デッドカー厶」は生半可な概念で括って主題解説とすることを許してくれない、映像を用いた完成度の高い“純文学”的な出来映えになっている。祖形の規範を転覆するジャンル破壊的要素を意図的に採用したエクストラバガンザとして、映像作品『エルゴ・プラクシー』は『ドン・キホーテ』や『白鯨』等の文学史上の傑作と並んで、仮構の伝統の中に独個の位置を主張する挑戦的な企図を含むもののようである。
省察17「終わらない戦い」の冒頭は、管理局局長ラウルが官警に追われているシーンから始まる。ラウルは彼を追ってきたアントラージュを銃撃して破壊し、宣言する。「手遅れですよ、執国。私はもはや、良き市民ではない。」ラウルのロムド秩序に対する反抗の決断がいかにしてもたらされたのかが、この後に時間軸を遡って描かれることになっている。ロムド・シティの管理責任者としてラウルは検体逃亡とこれに関連して生起した一連の事件の内実の把握を試み、この管理された楽園都市の裡に秘匿されていた悲しい真実を暴くこととなる。
ラウルはデダルスに案内をさせて人間生産装置“ウーム・シス”の検証をする。それは独立して機能する力は持たず、プラクシーの存在を核にして初めて効果を及ぼす装置なのであった。一方的にプラクシーに依存して生を送っているのがラウル達ロムド・シティに生きる“人間”たちの実態だったのである。「プラクシーなしで、我々は存在維持すら困難。」しかしラウルは、移民のヴィンセント・ローがこのプラクシーそのものであることを知ってしまった。「ヴィンセント・ロー、彼女が追っていた存在。彼がプラクシーだった。代表がロムドに渇望した存在。」さらにラウルはもう一つの秘密についても語る。「ラプチャーは既に封印された過去の遺物。」デダルスとの会見の後、局長室の中で15話の舞台となっていたクイズ・ショーの有様をテレビ中継で観ているラウルの姿がある。何者かの手によって「悪夢のクイズ・ショー」の有様は衛星中継されて、ロムド・シティでも視聴されることになっていた。クイズのヒントとして提示されていた“勝ち組”の文字を背景に、ラウルの眼前に侮蔑的な表情をしたヴィンセントの姿が現れる。文章による記述とは異なり映像による表現では、この姿がラウルの主観が投影した幻影なのか、あるいは何らかの実体の残した実際の映像なのかは定かではない。ここに現れたヴィンセントの姿をしたものの正体は、この物語の終結のあたりでようやく開示されることになるのであるが、ラウルの視線の先には画面の中の“Rapture”の文字も見えている。
ロムドでのラウルの動向と平行して、旅の途上にあるリルとヴィンセントが新たな小世界を発見する様が描かれる。姿の見えなくなったピノを探して入った洞窟の中でヴィンセント達が見つけた生物は、デダルスが管理していた人工子宮の内部に利用されていた生体と同一のもののようである。ラウルはその姿を見て、嫌悪感を隠すことができないでいた。人々は自らの力では子孫を残すことさえもが叶わず、この生物の体組織を利用することによって、かろうじて人間の生産を可能にしていたものであるらしい。1話における愛玩用オートレーブのピノを検査するヴィンセントと局長の妻と名乗る女性の会話や、8話のハロスの塔における司令官オマカトルとパテカトルの会話などを総合すると、個別の生物種としてはなはだ不完全な機能しか与えられておらず、極めて歪んだ生を送ることを強いられている、この世界の人間達の悲惨な生の実情が分かってくる。ラウルは執国の前に進み出て語る。「考えていました。ロムドの意味を。我々は市民なのではなく、囚人だったのではないかと。」/「環境の回復を待つために建設されたこのロムド。我々はここを離れては生きていけない。」/「外の世界は回復し始めている。なのに、我等にとっては未だ死の世界。」謁見室で厳しく執国ドノブ・メイヤーを問い詰めるラウルの前には、執国と並び立つように再びヴィンセントの姿をした者が姿を現している。
ドーム・シティ=ロムドの閉塞した環境の不自然な実態を厳しく指摘するラウルの言葉と重なるように、洞窟の中に細々と生息を続けていたらしい生物の哀れな現状をリルは見て取る。「彼等は正常な大気のもとでは生きられない。毒に冒されながらも、洞窟から離れることができない。」リルとヴィンセントが発見した、有毒ガスの発生する洞窟の中でしか生存することができず、外気にさらされると即座に死を迎えてしまう生物は、非酸素系の生物の名残として知られる、深海のマグマ噴出口周辺に生息する“チューブ・ワーム”を連想させるものである。本来の地球上に生成した原初の生命は、メタンガスの中で代謝活動を行う“メタン系”の菌類であった。生存競争の結果、他の種に対する攻撃的な機能として酸素という毒物を放出する新種の生命体が誕生し、競合する菌類を駆逐して地球の大気が酸素で覆われるようになった環境の劇的変化の後に生まれて来たのが、現在地球の大半を占める酸素系の生物達であった。酸素の供給を絶たれた特有の環境の中でのみ生き延び続けて来た数種類の嫌気性細菌や古代生物の残滓であるチューブ・ワームなどの研究から、これらの酸素を毒物として認識する生物達こそが地球の生物の始祖であったことが判明したのである。惑星の本来の主として認めるべき生息生物の基本属性に対する認識の激烈な転換を示すこの例に従えば、プラクシー=人間=オートレーブのそれぞれがそれぞれの環境と条件内における“造物主”であり“被造物”であり、また“原種”であるという解釈を許すことにもなるのだろう。
ラウルが執国に対する反逆の最終的な意思表明として、“全てを絶望で覆い尽くす”目的のために発射したミサイルの名が“ラプチャー”であった。今では不要のものである筈の大量破壊兵器が、“ラプチャー”(歓喜)という名で呼ばれて保管されていたのは、映画『猿の惑星』で活力を失い果てた未来人達の信仰の対象として核ミサイルが残されていたことを思い出させる。“ラプチャー”は聖書『テサロニアン』の終末論にその記述が見られ、末世における神の裁きとして人々の魂を地上よりさらっていく行為として理解されていたものである。“ラプチャー”の本来の意味が“連れ去る”というものであったことは、世界の破滅でもって予言の成就が叶えられるとする、現世否定的なキリスト教の世界観を暗示している。ラウルはこれと同様に、あるいはある意味で全く正反対に真正の“絶望”を用いて、ロムドにおいてドノブ・メイヤーによって維持されて来た偽りの信仰を転覆しようと企てるのである。反抗と逃走と、引き続く自らの拘束までをも巧みにその手段に用いて、ラウルはラプチャーの発射と目的物の破壊を成功させることになる。
00:00:00 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
23 February
『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 2
省察15「悪夢のクイズSHOW」において思弁的映像作品『エルゴ・プラクシー』の採用する世界とプラクシー存在の表象は、さらに観念的な抽象的特質を先鋭化させたものとなっている。この回のエピソード自体が一編のクイズ番組の形で提示され、この仮構作品の基幹設定そのものがクイズ問題の設問の各々として司会者MJQによってヴィンセントに質問され、作品の鑑賞者である我々に対してばかりでなくこの仮構の中心人物であるヴィンセント自身に、模範解答の形で物語世界の基本情報が教授されることになっているからである。そのようにして与えられた『エルゴ・プラクシー』世界の基幹設定に属する諸事実は、例えば以下のようなものである。それは未来の地球を舞台に起こった運命的悲劇と、人類の辿った悲惨な行く末なのであった。「メタン・ハイドレイト層の連鎖崩壊により、地球上の生物の85パーセントが死滅した。」/「荒廃した地球環境を見捨てて人類が宇宙空間に避難するのに用いた宇宙船の名は“ブーメラン・スター号」/「人類再生の計画“プラクシー・プロジェクト”によって全世界に放たれたプラクシーの数は300体。」/「世界再生を果たした人類にとってプラクシーは最も不要な存在となった。」/「“始まりの鼓動”とは、プラクシー・プロジェクトの終了。」/「“唯一の勝者”はプラクシー・ワン。」
ここで“プラクシー・ワン”という未知の存在がゲームの設問に対する正解の一つとして唐突に語られるのは、SF的仮構理解の基本ルールにおいては当然許され得ない逸脱行為である。15話「悪夢のクイズSHOW」のクイズ設問と解答の中で与えられている諸情報が、典型的SF的背景に属するものとなっていることをいかに評価するかが重要課題となる。観客に対して何らかの表現行為を行う作品としての自己言及的行為として、この映像作品は自身をSFとして読解されることを拒否する姿勢を表明していることになるからである。『エルゴ・プラクシー』の基軸となるべきほとんどのSF的設定がクイズ番組の設問という形で提示され、番組内に示された解答例としてあっけなく実態が明かされてしまっている。この作品の展開する主題はSFの代表する自然科学にあるのではなく、哲学的には自然科学の対照概念の位置を占めるものとなる宗教の分野に属する関心が展開されることが暗示されているのである。つまり質量点として変換記述し得る空間的延長性を持ち、座標上の空間的位置関係を一意的に特定することができる“存在物”という粗形を用いて世界の全てを捉えようとするデカルト・ニュートンの構想した科学に対して、そのような描像を得ること自体が原理的に不可能なものとして世界と個物それぞれの関係性を捉えようと試みるのが、“心霊的”理解に基づく宗教的発想であった。心霊的解釈によれば一つの存在物が、例えば肉体の死と共に魂が分離して蝶の姿で分かれていくプシュケーとしての様相を取り得るように、あるいは死後鳥の姿になって飛んでいく日本武尊の魂の位相遷移の例のように、跳躍的かつ多面的に分化して具現することが可能となる。つまり空間的延長性や意味的一意性を保持する必要がない、現象世界において複数の並列的な“様相”を多元的に示すことができる原存在として、“心霊”の原理的特質は理解されるのである。
SF的設定要素を多分に含んだ観念アニメである『エルゴ・プラクシー』は、このエピソードにおいて自然科学的方法論自身を変転させた“自己言及的作品解題”を試みているのである。フィクション世界はSFがそうであると信じられて来たように、必ずしも一個の独立した客観世界として現象世界と同様の完結した形を保持して具現している訳ではなく、作品の本体が意識の主体である観客に対する諸概念の提示という情報伝達形式をとった、様々に変換可能な意味構築の手法そのものであっても良い。各種アルゴリズムを通じて網羅的に様態の変化を現出することが可能な原形概念と変換記述手順の数学的定式化の間にある微妙な関系性は、ダグラス・ホフスタッターが『メタマジック・ゲームズ』(Metamagical Themas)において紹介と批判的論考を行った、ドナルド・クヌースの論文“メタフォントの概念” (Donald Knuth, “The Concept of a Meta-Font”)において提唱されたメタ存在概念の発想と照らし合わせて、“プラクシー”概念と深く関わるものであると思われる。14話「貴方に似た誰か」において出現したプラクシーの正体として、既にこの“メタ存在”に対する示唆が行われていたのであった。原理的には異種の仮構作品相互におけるジャンルを跳躍した変換記述や、任意の概念の全くの別次元界面に属する概念への位相変換の試み等が様々に“共変性”の原理に従って実現されることが可能であることを仮定して、ここでは『エルゴ・プラクシー』のSF的基本設定に相当する部分を“クイズ・ショー”変換した形式で観念伝達がなされる、一つの“ゲーム世界”が提示されていることを過たず理解しておく必要がある。
この後に続く省察17「終わらない戦い」において、我々観客が視聴して確認しつつある変換後のプレゼンテーション・モードを、フィクション世界内の存在であるはずのラウルやデダルス達が人工衛星による中継映像として“SF的”に認知している場面が挿入されることにより、典型的な“メタフィクション”の図式を“フィクション”という次元の制約外に拡張して異次元平面の跳躍的連接を企てるのも、やはり“現実=フィクション連続体”としての“ゲーム世界”提示の手法のアクチュアリズム的展開例の一つとして看為し得ることになる。我々は“SF的リアリティ”と“観念アニメ的アクチュアリティ”の位相のそれぞれのプレゼンテーションの成果を確かに見届けながら、知覚と意味の複合体である“擬似現象世界”としての仮構の実相を過たず受容していかねばならない。
『エルゴ・プラクシー』が純正のSF作品であったならば、プラクシーという存在の誕生や彼等が行った行為の具体的内容の実質的提示が科学的手法に則って正確に遂行されることが、読者/観客によって厳しく要求されねばならないことになるのだが、この作品の関心は、むしろこれらの概念の上に成り立つ“形而上的”思考の模索の方にある。仮構作品が特定の情報を特有の様式と技法に基づいた方式で受け手に伝達することで成り立っている意味世界であるならば、必ずしも現象世界として独立した別世界を一定の角度から瞥見し、記述するという過程を踏襲して描かれなければならない原理的制約がある訳ではない。むしろ厳密な意味におけるSF的設定に属する情報については最低限の枠組みだけ欄外で語っておけばいい、という制作者側の選択した自覚的なスタンスがここには窺われる。人類が地球を捨てて宇宙空間に脱出するのに用いた“ブーメラン・スター号”建造や、荒廃した地球環境との宥和を試みた“人類再生プラクシー・プロジェクト”に関するクイズ番組内での唐突な言及は、そのような意味で『エルゴ・プラクシー』が意味の複合体としての一編の仮構であることを先鋭に意識した、典型的なメタフィクション的記述の思弁的展開の一例であるに違いない。
しかしながら仮構世界としての概念的位相変換の操作を施されて“クイズ番組”変換された「悪夢のクイズ・ショー」が、総体としてのアニメ/ゲーム作品『エルゴ・プラクシー』の同一性を確かに維持していると看為し得る一貫性の要素は、“死の代理人”であるプラクシーのヴィンセントがやはりこの回においても他のプラクシーと思われるものの抹殺を実行する結果となっている点である。最終的にクイズ・バトルというこの勝負の勝者はヴィンセントと決定し、対戦相手である司会者はクイズ番組のルールに従って敗者として死を与えられることになる。司会者MJQは番組終了を宣言して最後に言い残す。「仕方ない、これもプラクシーの戦い方。」風刺や政治的批判を目的とするパロディーやバーレスクやカリカチュアなどの場合とは本質的に異なる独特の概念操作を施された、根源的基質において多面的な様相を無数に保持している潜勢力の一斑がこのような形で“観測”と“描写” に頼らず伝達し得ると理解するならば、同時にこのフィクション世界で導入されている“プラクシー”(代理人)という概念の暗示するものの実質が改めて見えてくることだろう。
だからこそクイズ番組の設問としてヴィンセントに課せられた様々の雑学的知識は、ドノブ・メイヤーやデダルスのアントラージュ達の名前に暗示されていた哲学者達の名と同様に、やはり観客の想念の裡で醸成されてこの意味の複合体である仮構世界の内実を複合的に構築することになっている。最初のクイズ問題の答えであるブルワー・リットンの“ペンは剣よりも強し”という言葉に暗示されるペンと剣の概念的位相変換が超現象世界的に可能であるという“共変性”の原理を掬い取ってみるならば、これらの設問はそれぞれが巧妙に反響し合って、この“観念アニメ”のフィクションとしての成立条件の妥当性を主張しているものと理解することができるだろう。“ドップラー効果”も、従来のニュートン力学的科学思想が前提としていた、いかなる視座から観測を行っても同一の描像が得られる“客観的現象把握”の成立不能性を指摘する検証結果の一つとして理解できるものである。“水の最高密度温度”が摂氏3.98度である事実は、宇宙の生成と知性体の誕生を可能とするために超越的な存在によって巧みに設定されたかのようにも思われる“宇宙定数”のファイン・チューニング説を支持する身近な例の一つとして採用されるかもしれない。ダーウィンの『種の起原』は、“適者生存”と“自然淘汰”という概念を提示することによって、従来のキリスト教のスコラ哲学的世界観や古代世界を支配していた意味のある世界としてこの宇宙を認識する万物の有機的連関を前提とする象徴哲学的な思想を、根底から覆すものであった。その結果選び取られた“科学思想”は、宇宙と自己の双方の存在の根幹的意味そのものを認めることを全面的に否定する“虚無主義”に基づく“新思想”だったのである。生物学者リチャード・ドーキンスの唱えた“利己的な遺伝子”などの説が、この無目的的宇宙観をさらに裏打ちするものとなっている。霊的内実の向上を前提とする“進化”などという幻想を打ち捨てたところにこそ、“進化論”の思想的意義性があった。このような世界認識を決定する諸見解を踏まえて様々な意味で未来の科学技術の進展と、そこで人類が直面する新たな問題点をSFとして予見した、アーサー・C・クラークの存在を集約して伝えてくれているのが、映画『スペース・オデッセイ』(『2001年宇宙の旅』)であった。この映画の中でコンピュータ“ハル”の反逆が描かれていたのは、『エルゴ・プラクシー』のオートレーブ達を冒すコギト・ウィルスとの関連を思い出させるものである。“冥界の帝王”のエピセットの保有者として語られた心理学者ユングは、単に人間個々の心の中の意識のメカニズムを研究したのではなく、むしろ従来の科学の果たした現象理解をも含めた“時空精神連続体”としての宇宙全体の“心霊的”理解を試みた思想家として理解すべきだろう。
これらの知識を反映して“私”と“世界”の内実に対する反省的考察が展開され、“プラクシー”という概念に示された意識体の特有の存在属性が掘り起こされていくこととなる。規定された基本設定の許にストーリーとキャラクターを配した現象世界的“物語”を通じてこれらの意味連関の構築を図ろうとするのではなく、むしろゲーム的な断片知識の羅列によって極めて直裁な情報伝達を図る“記述”の手法は、“仮構”という概念の意味拡張の可能性を見事に具現している。模擬実験的擬似現象世界として構想された19世紀的“リアリズム小説”や科学的世界観に準拠した“合理的”仮構であることを前提とした“自然主義”の産物のみが仮構としての意義性を認められねばならないことはない。むしろその本質においては、超自然の支配する歪曲された断片的小世界や決してあり得ない不可能世界の脱臼的見通し図のみならず、数式や抽象的思弁の中にこそより豊かな真正の“仮構”の展開を期待することも十分に可能な筈である。哲学体系や宗教的教義が純然たる知性的関心の対象として主張し得る本質的意義性もまた、そこに見出されるべきであると言わねばならない。
00:00:00 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
22 February
『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 1
科学とSFと哲学的省察:『エルゴ・プラクシー』における神と人と“自分”(2)“世界”と“私”という実は意識の主体にとって極めて捕捉困難な概念について形而上的な再認識を迫る省察において、特異な表象化技法を創出して知の位相の映像化を図ることを企てたアニメーション作品『エルゴ・プラクシー』は、科学的思考の類型を脱した存在・現象解釈を様々に展開していくこととなる。省察12「君微笑めば」と省察13「構想の死角」は、連続した一つのエピソードとして一方でプラクシーと彼等によって創造された“人間”存在並びにオートレーブ存在の間のより具体的な関連を明かす手がかりを与えると共に、もう一方では存在と現象そのものに関する新規の心霊的世界解釈を導入した統合的宇宙観を示唆する興味深い視点をも提供している。その潜伏した主題展開の伏線として機能しているのが、省察12終結部において描かれている空から降ってきた雪片がピノの顔に落ちて涙のように目の上を伝うシーンである。概念と現象あるいは存在の間のはなはだ微妙な関係性を再考察するための糸口が、ここにさりげなく示されているのである。
ヴィンセントとリルが次に遭遇したプラクシーは、荒廃した自然環境に新たな植物相を再生してロムド・シティやアスラの塔にあった“ウー厶・シス”と同等の独自の人間再生産設備を守護していた。しかしながらドームや塔と並んで森を表象とした小世界の支配者であるこのプラクシーは、一人のオートレーブをアントラージュとして従えてはいるものの自身は高度な知性を持たない野獣的な存在として描かれている。主と同様に口を利くことはないものの、むしろ思念と意図らしきものを備えてある意味で知的な行動を行っているのは、彼のアントラージュである少年の姿をしたオートレーブの方なのである。土地の神ゲニウス・ロキ的存在属性を備えた獣人的なプラクシーの登場は、ドームやタワーの管理者として特有の権能と職務を与えられたプラクシー達の保持する使徒的属性との対照から、この作品の導入したプラクシー(代理人)という概念の内実を語り返すことになっている。プラクシー=人間=オートレーブ間の支配・従属関系あるいは管理・統制関系は、この後微妙な偏差の存在を浮かび上がらせていくことになるのである。
しかしこの極めて思弁的な仮構作品の提供する純観念的な新機軸の発想は、リル・メイヤーが口にするコギト・ウィルスに冒された彼女自身のアントラージュ=イギーの死を宣告する言葉によって提示されている。これまでのように従順に自分の命令に従おうとはせずに、独自の判断と意思を持って行動を取り始めたイギーに対してリルは言う。「これがコギトによる変化なら、死にも等しい変化だ。」リルの発言は、図らずも有機生命体に限定されることのない存在物全てに対して適用可能な、“命”とその消失である“死”に対する概念の拡張論議の核を提供している。
生命体を判別する指標を一個体の存在物としての自立的な運動が観測される“自動性”の有無に対して認めるのではなく、対象の外部存在者に対する応順反応という特定の機能面に条件を限定してその生死を規定することを試みているリルの判断は、“生”と“死”そのものの本質的定義に新たな局相を加えるものとなっているのである。これによれば存在者の生死を決定するのは当該する本体自身の権能ではなく、飽くまでもその個体を客観的に観測する他者による概念操作なのである。リルの判断に従えば、自らの意図に順応する無機物あるいは環境に対して“生命”の存在を検知することも当然可能となるに違いない。
自らが死を迎えた後にも変わらずアントラージュの奉仕を受けている森のプラクシーと、主人の意思を拒絶することを選んだアントラージュに一方的に死の宣告をするリルは見事な対照をなしている。さらに自らがプラクシーであることを漸く自覚したヴィンセントに対してリルが語る「プラクシーでありながら、プラクシーが何かすら分からないとは、滑稽だな。」という辛辣極まりない言葉は、この指摘が自分自身にも適用されることに彼女自身が全く無自覚であることにおいてこの物語の以降の展開に対して折り畳んだ伏線を提供することとなっている。様々な意味でリルは『エルゴ・プラクシー』の主題展開上のキー・パーソンとしての職分を堅固に果たしているのである。
省察14「貴方に似た誰か」の冒頭は、リルの独白「小さい頃は、自分が死ねば世界も消えると思っていた。」から始まる。これに呼応するかのように、ヴィンセントの独白も以下のように続く。「俺は俺で、他の誰かじゃない。それがすごく不思議だったことをよく覚えている。俺の記憶は信用が置けないが、この記憶は古くて確かなものだった。」自分と世界、自と他の背後にある未知の心霊的関係性に対してリルとヴィンセントのそれぞれが胸の裡で語るこれらの思念は、このエピソードに登場する新たなプラクシーの担う興味深い存在論的位相を補完して語るものとなっているのである。世界があるからその中で世界を意識し世界について思考を行うこの私があるのか、あるいは私が“世界”という言葉を偶々発見しその定義と実際の経験との連係を構築したと妄想するが故にこの“世界”が存在するのか、という意味論上の測り知れない疑問に対して、因果関係的な制約を超出した弁証法的統合が果たされることとなる。それは“共変的”システム構造理解を様々の対象概念に全方位的に適用した結果得られるべき、統括的な全一性の存在/現象理念なのである。
一行が旅の途中で立ち寄った別のドームの中は、整然とした町並みがあるが人の姿は一切ない。手つかずの食料品が無傷のままに残されているスーパー・マーケットの中では、エスカレーターが動きレジのモニターの表示も活きていて、その画面の片隅には “Ophelia”の文字が記されている。マーケットの屋上の看板等を介して“Ophelia”の文字はこの街のシーンの中でさりげなく3度画面上に示されていたのであった。この無人の町の食料品の溢れたマーケットの名が“オフェーリア”なのだが、シェイクスピアの戯曲「ハムレット」の悲運のヒロインの名を冠したこのマーケットの名称は、ドノブ・メイヤーの4体のアントラージュ達の名やデダルスの2体のアントラージュ達の名の場合と同様に、ストーリー外の概念連係において特有の意味性を浸透して発揮することになっている。他のいくつかのエピソードと並んで、今回のエピソードも著名な文学作品の内実との間の潜伏した裏の関連性が、主題としての興を彩ることとなっているのである。
14話「貴方に似た誰か」においては、映像表現の特質を活かした殊に入念な演出が採用されている。観客として画面上に現出した映像のみを手がかりに物語の内容を読み取ろうとするならば、ストーリーの客観的な理解が困難になるように、意図的に仕組まれているからである。エピソード前半で画面上に視認されるヴィンセントやリルの姿のいくつかは、この町を支配するプラクシーが自在に姿を変えて彼等を攪乱するために装ったものであり、ヴィンセントとリルが陥った精神的混乱と平行した惑乱状態を観客も共有させられることとなっていたことが後に判明する。鑑賞者は決して仮構世界の出来事の中立の傍観者として、客観的判断を選択する特権を与えられている訳ではなかったのである。自在に人々の姿形を擬装することができるばかりか、それぞれの記憶と想念にも同調してそれを模倣することができるらしいこの閉鎖世界のプラクシーには、単なる変装や幻覚を操る能力以上の特殊な存在属性があることが暗示されている。この名の無いプラクシーの人格同定上の不定性の特質を理解した上で、改めて最初から本編を確認し直す作業を行って各々のシーンの内実と演出的捻りの効果を再検証してみることにより、ようやくこのプラクシーの本来の存在論的特性とマーケットの名に暗示されていたオフェーリアのイメージとの間の、捻転した関系性が特定されることになるのである。
プラクシーの企みに嵌って気を失ったまま湖に沈められようとしているリルは、ラファエロ前派の画家ジョン・エヴェレット・ミレーの描いた“オフェーリア”そのままの姿勢をとっている。水面上に仰向けに浮かんで横たわり肘を曲げて両手の平を上に向けているオフェーリアの姿は、ハムレットの示す冷たい素振りに耐えきれず、狂気に陥り小川に身を投げて水死を遂げた少女の自殺行動を象徴するものとなっている。自死を象徴する柳の木と共に画面上に数多く描き込まれた種々の植物の図像がそれぞれ固有の概念と結びつく象徴的意味性を背負っているように、人の顕示する姿勢や仕草もまた固有の概念を特定的に指示することとなる。これらの暗示的連関を巧みに応用した表象芸術であるコスプレや変装行為に対して指摘可能な発想と同様の、現象世界的“人格”や“個人存在”の同等性を拘束する概念を離脱した別次元の意味論的自己同一性である“セルフ”の多様性を暗示することになっているのが、この独特のポーズなのである。このポーズにおいてリルはピノの頬の上の水滴が彼女の涙であり得たのと同様の意味で、オフェーリアであることの同一性を確かに保持しているのである。何故ならば“羊”と呼ばれる“狼”は、正体が狼であるところの紛れも無い羊に他ならないからである。
オフェーリアの町のプラクシーは巧みにリルの知覚と状況判断を惑乱の中に陥れる。しかしAIであるピノは外観に困惑させられることはない。さらにピノは個人存在の複数性を当然のごとく受け入れてもいる。ピノが備えている個体同定上の認識機構においては、複数の存在に対する同一性認定が基本的に容認され得るものである。ヴィンセントの姿を装ったプラクシーにピノは語りかける。「リルリルは?」/「リルはもういない。これで楽になるんだ。」/「いるよ、もう一人。」/「何、言ってるんだ。」/「ヴィンスも、もう一人いるよね。お料理食べてくれたのは、別のヴィンスだよ。ヴィンスも二人、リルリルも二人、なのになんでピノは一人なのかなあ。」AIであるピノの個体認識においては、ヴィンスとリルがそれぞれ二人現出していることに何の疑問も感じられていない。確かに“愛玩用オートレーブ”という型番の一台であるピノにとっては、モビル・スーツ“ガンダム”や人造人間“百式レアリエン”などと同様に、自分と同一の存在が複数あることに特に異常の念は惹起されないのだろう。
しかし量産型機械の場合に限らず、概念の普遍相における“個体”あるいは“人格”における複数の位相発現性という可能性そのものについて、さらに敷衍してその妥当性を考えることもできるはずである。『エルゴ・プラクシー』においては“リル”という名で呼ばれた存在がすでに3体登場していたのであった。今回新たに姿を現したプラクシーもただ他のものの姿形を真似てみせるだけでなく、記憶や意識等の自己同一性を確定する軸となる筈の諸条件においてさえも存在論解釈上“同一”のものを保持し得ることが示唆されている。このプラクシーがいかなる概念の“代理人”であるのかを推測してみることによって、存在の個別性と“同一性”という認識の中に潜んでいる原存在的“多義性”の示唆する可能性を模索することができる筈である。解の展開例としては、全ての存在物の想念に同化することが可能な人格/神格の分離以前の原存在的不定性もしくは、意識体の全てに潜伏する否定的な負のエネルギーにおいて通貫する自殺傾向を全ての対象に投射しようとする病的性向等が、このプラクシーの概念的本性であるという推測等がなされ得るだろう。物理的特性としてその万物と同一性を共有することのできる特殊能力を記述するならば事象発現以前の“コヒーレンス”において偏在的な潜勢的存在として理解され、反転的にギリシア神話的神格イメージとして何でも誰にでもなることのできる能力を同定するならば変化と流動の神メルクリウスにも相当する、全ての存在の影たり得る汎用的存在性向の持ち主がこのプラクシーなのであった。彼自身が紛れも無く影なので、当然ながら自らの固有の影は持たないことになる。
水中から自分を助け出してくれたピノに、リルは現在地の座標を尋ねて彼女が本物のピノであることを確認しようとする。リルの要請に即座に応じてこの地点の客観的な座標を正確に答えるピノである。しかしピノの語る現在位置は、地球表面を2次元の平面と看做して任意の位置を2つの変数でもって特定する、デカルト座標の理念に基づいたものである。2次元球面としての実際の地球上の3次元空間上の物理的な位置関係を正確に反映させるためには、“多様体”として定義可能な関数の付加を行うことによって修正を加える必要を認めるのが、座標概念の本質であった。このように存在物の個別性を物質の延長性として捉え、座標的空間概念において存在性自体を分別することができることを前提としていたのがデカルトの科学的存在解釈であったが、『エルゴ・プラクシー』においてはこの制約を超出した純観念的な多様体概念をさらに拡張する存在理念が語られていくことになる。
ヴィンセントがプラクシーに引きずり込まれた水底には、かつてのこの都市の人々の生活する街がある。路上に降り立ったヴィンセントに、もう一人のエルゴ・プラクシーの姿をしたものが語りかけてくる。「僕らを受け入れてくれる世界はない。これは僕が見てきた風景だ。ずっと一人きり。誰とも話をしない。だから、自分が分からない。どうして僕は僕で、皆の好きな誰かじゃないんだろう?僕は、誰かのふりをして愛してもらうことを覚えた。でも気付いた。愛されているのは、僕じゃない。誰でもない僕は、誰にも愛されない。だから、僕は消えてしまおうとした。僕らは消えたくても消えることができない。皆を消して、皆の中の自分を消そうとした。でも、駄目だった。一番消したい自分だけが残る。」オフェーリアの町のプラクシーはヴィンセントが極めて有能なプラクシーの一人であることを認め、彼に誘いかけて言う。「その輝き。君となら、僕は消えることができる。僕と消えよう。君は僕だ。」しかしヴィンセントは彼を拒絶する。「俺は、お前とは違う。」プラクシーはさらに畳み掛けて言う。「僕らは一人きりだ。皆、僕らを置き去りにしていく。」ヴィンセントは改めてこの相手の本質を理解して言う。「お前みたいにならなくて、よかった。」スーパー・マーケットの名としてあらわれていたオフェーリアのイメージを通して繰り返し暗示されていたのは、ラファエロ前派の画家ジョン・エヴェレット・ミレーの描いたオフェーリアのポーズをとって水に浮かぶリルの保持する存在性向ではなく、むしろリルとは対蹠的な自己沈潜する不毛な憂愁症という極めて否定的な精神エネルギーの所有者であるプラクシーの持つ、水没による自死への願望なのであった。
“憂鬱”を原初的作動因として捉えて、その現象界面における派生的具現化を天変地異や疾病や超常現象等に看取して世界の総覧を図ってみせたのがロバート・バートンの『憂鬱の解剖学』であったが、ヴィンセントがこの万人の精神内部に潜むプラクシーとの遭遇を果たし、彼の心霊的本質を見抜いてその勧誘を拒否した経験は、『エルゴ・プラクシー』の最終的な主題の収束に大きな影響を与えるものとなるのである。
[Read more of this post]
23:47:26 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks