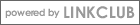Archive for 23 September 2010
23 September
『エルゴ・プラクシー』論 3
省察7「リル124C41+」で、ウィルスに冒されてロムドに帰還したリルを迎え入れたデダルスは、“アムリタ細胞模倣子”を注入して治療を行う。“利己的な遺伝子”という斬新な概念を提唱した生物学者リチャード・ドーキンスの提示したもう一つの重要概念は、模倣子“ミーム”(meme)であった。細胞内に組織的実体として存在する遺伝子“ジーン”(gene)に対応する、物理的実体を持たない概念上の形質伝達要素として導入された“模倣子”という述語は、文化や思想の模倣的伝播に対して適用された概念であったが、一方システム理論的な別側面においては、物質粒子という基礎概念を採用して宇宙の力学的理解を目論んだニュートン的科学の解式とは対蹠的な、物質と情報の相互遷移が可能な共役的原理に基づく原形質的宇宙像の原理性記述の可能性を示唆するものでもある。ドーキンス自身は明確に神を否定しているが、むしろ科学の枠を踏み越えた領域において“神”概念再考と“魔法”概念再検証に興味深く関わるのが、宇宙の全体としての存在原理に基づいた物質/情報の反転的描像を示唆する模倣子という単位概念の発想なのである。物質のみを世界構成要素として理解しようとする“唯物論”の発想においては、世界の存在単位は不可分の質量単位である“原子”という粒子において基本的に理解されることとなっていた。この記述システムによれば全ての存在と現象は粒子の運動と衝突という力学作用として表記され、“ラプラスの魔”という全能的観測者の存在として仮定されたように、現象の全てを精密に計算し予測することが可能となる。しかしこれとは異なる事象の観測者の想念との相互作用による全体性の宇宙の心象把握というモデルを構築すると、例えばライプニッツが提起したように、“モナド”という原子とは全く異質の単位概念が主張されることとなる。モナドは原子がそうであったように集合として他の概念に包摂されることのない、全体性の宇宙の一断面のような単一的様相として理解されるべきものであった。この発想はプラクシー存在の内実を理解する鍵となるが、興味深いことに本作品においては“モナド”という名称はさりげなく概念軸をずらして導入されることとなっている。デダルスはリルに回収された検体の名前が“モナド・プラクシー”であることを教える。この物語においては、モナドは様々の権能を持ったプラクシーの中の一個体に対して与えられた呼称として用いられているのである。さらに“プラクシー”という存在について、デダルスはリルに語る。「この荒廃した世界で我々が生き残るために必要なフィールドを維持する鍵。」このデダルスの言葉から示されるように、プラクシーは特定の行動や操作によって人間社会に何らかの力を及ぼすものではない。プラクシーの存在そのものが、ある意味で宇宙の自然法則や潜勢力と等質の作用を及ぼすものとして、人間の社会という場の維持に欠かすことができない原理的素因として機能しているのである。プラクシーの不在が直裁にロムドの秩序のゆらぎとコギト・ウィルスの蔓延をもたらすのである。事象の固有の選別的現象操作を司るプラクシーは、物理的事象界面における“マクスウェルの悪魔”の変化形とも見なし得るものであるが、プラクシーの暗示する存在原理が局所的作用による現象伝達しか認めない粒子論理的存在解釈を転覆するものであることに間違いはない。その意味でプラクシーそのものが、モナドという概念の一つの表象としても理解し得るものとなる。省察8「光線」においてモスク・ドームを目指す旅の過程で外の世界でヴィンセント達が見つけたロムドとは異なる都市構造物は、“ハロスの塔”と呼ばれるものであった。ハロスの塔の人々を指揮してロボット達との不毛な戦いを続けているのは、オマカトルとパテカトルという名の軍人達である。彼等の名前が由来するアズテク神話の始祖オマカトルとパテカトルの場合がそうであったように、全知全能で姿形を持たない抽象的イメージの神とはまた異なる、権能に限界があり特定の属性・形象を保持するばかりか人と交わり人の祖先となったりさえもする神の姿は、人間と神の間の関与のあり方をむしろ科学的に考えさせてくれるものである。神の存在証明のなされ方においても、人間理性によって捕捉可能な限界ある権能の具現化として、神概念は“空虚としての神”、“数式としての神”、“物理法則としての神”等のように、論理学的・数学的な様々な変換記述の方式を考案して理解され得ることとなる。そして純然たる科学としての枠組みから物理的に神存在そのものを捉え直して、“コヒーレンスとしての神”、“モナドとしての神”、“ペルソナとしての神”等の範疇の中に、新たに神概念を規定し直すことも可能となってくる。これらの思念の具体的な実例の一つが、『ピーターとウェンディ』に描かれた“ピーター・パン”という存在と“ネヴァランド”という世界であったが、『エルゴ・プラクシー』が企図しているのもこの知的なお伽噺と全く同様の形而上学的思弁なのである。このように人間知性によってその存在性向が科学的に捕捉され得る神とは、実際に“神殺し”、“神に対する恫喝”、“神との取り引き・交渉”、“神の監禁・封印”等の行為を行う可能性を示唆するものである。そうであるならば、人の行う技あるいは存在目的自身が、“神の鋳型の制作”、“新たな神の創作”、“人の神への進化”等の形をとって具体的に掲げられる結果をも招くことだろう。ここに挙げたような思想的目的措定の可能性に対する自覚は、反転して“神による人間の創造”から、“神の人間化”、“人の神格化”“神と人の分化”等の諸概念の実質に対する新たな角度からの考察の必要を迫るものになるのである。
[Read more of this post]
17:10:36 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
『エルゴ・プラクシー』論 2
省察3「無への跳躍」では、怪物との遭遇からロムドのシステムの根幹的矛盾に気付いたリルの処置に関して、執国の4体のオートレーブ達が協議を行う。 「勘が鋭敏すぎるのだ。」/「全く、誰に似たのかしら。」/「市民は全て並列化された情報を雛形にしている。局所的近似値には何の意味もない。」/「やはり情報局などには配属すべきではなかったのだ。」/「いや、教育的観点から考えても適切な判断だった。」/「その証拠に、市民レベルとしては最高の感受性を保持している。」/「素晴らしい結果だ。」/「しかし、そこから派生する行動力こそが元凶だ。」/「元凶というならば警備局はどうだ。」/「案ずることはない。あれだけ念押ししたのだ。」/「いずれにせよ、このロムドが揺らいでいることは否定できない。」/「一刻も早く事態の解決に向けた迅速な措置を。でなければ。」/「レゾン・デートルの崩壊。」ロムド・シティのような高度に統制されたシステムを管理する主体からすれば、システムの構造もシステムに含まれる構成要素の保持する位相も、可能な限り簡略化された一元的なものに収束させることができるほど、“管理”の作業自体は効率的となり、努力目標の達成は容易に、そして仕事内容に対する評価もより望ましいものとなる。親や学校や文部科学省や国家等が、子や生徒や学校や国民を“並列化”したがるのはこのような力学的要因が働いているためなのだと推測できる。しかしそのような並列化行程が極度に押し進められたシステム全体は、柔軟性(感受性)に乏しく、システム自体の改変を自立的に行うことを妨げるばかりか、システム全体に関わる突発的異変が生起した場合には、その危機対応能力は極端に低いものとなってしまうだろう。しかし管理体制は、管理システム外の干渉や影響を全て望ましくない排除すべきものとして認識するであろうから、このような内部のシステム改変的要因を無視するばかりでなく、むしろ危険分子として抹殺する方向に動くことが予想される。ここに見たような力学的作用の結果の典型例を、外部の“荒れ地”構造から隔絶された自律系である“ドーム”の構築として理解することができるだろう。“科学”や“理性”や“コスモス”などの概念も、様々な位相においてこの“ドーム”システムの相関物として理解することが可能なものとなる。ドーム外環境である“荒れ地”や“カオス”への脱出あるいはこれらのドーム内部への“侵蝕”に相当する現象と思われるものは、既存の概念や歴史的事実の中からも様々に指摘して検証することができる筈なのである。
ヘイフリック限界を失った癌細胞は、母体の生命機構の維持を顧みない自身の増殖を新たなレゾン・デートルとして選択し、無限増殖を基本原理として肥大化していくが、母体となる生命体の個体死と共に栄養の供給を絶たれ、本性的に予期し得ない筈の死を迎えることになる。プログラムとして“死”の要素を全く組み込まれていない存在は、システム外の要因である“死”の到来を予測することができないのである。同様にカオスを取り込み融和することを原理的に拒否する整合的な自立的プログラムは、バグとしてのカオスの排除に自身のレゾン・デートルを集中させることとなり、却って自律システムとしての飽和点への進行を加速することとなるだろう。 システムのこのような傾向は、社会組織の管理を行う者においてはしばしば芸術の最も感受性に訴えかける要素であるエロティシズムやグロテスクやナンセンスの部分に対する迫害という行為を招来するものとなる。システムが自身の安定を保障するために内部機構の並列化を進行させる過程では、個別的な生のエネルギーの奔出である“エロ”と、規格化され得ないあるがままの現実の実体を暴いた結果現出する“グロ”と、規範の抱え込む内部矛盾を暴いて嘲笑する“ナンセンス”の要素の排除が優先して実行されることとなる。市民としての権利を既得権として保持する高等遊民だけは、システム内自由を行使して“文化”や“芸術”の名の下に実体はエロ・グロ・ナンセンスと何ら変わることのない選別知識と占有快楽を特権的に享受することができるが、未だ市民権を得るに至っていない外部世界からの移民あるいは組織構成員末端の未成年者達は、市民として認知されるための条件を充当するために、倫理的に“正しい人”になろうとする努力を自覚的に差し止めてまでも、システムに対する屈服と迎合の身振りとして自らの感受性を封印し、社会的な“良い子”を演じ続けねばならないことになる。一方このような矛盾に満ちたドーム社会の実態をあるがままの姿で視認することができる“感受性”をあまりにも豊かに保持する構成員は、危険分子として保護観察の対象とされてしまうこととなるだろう。人間の構築する“社会”と“教育”と“管理”と呼ばれているものの実体を語る一つの指標が“並列化”である。
[Read more of this post]
17:07:54 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
『エルゴ・プラクシー論』
科学とSFと哲学的省察
『エルゴ・プラクシー』における神と人と“自分”(1)
『エルゴ・プラクシー』(Ergo Proxy)は、衛星放送局WOWWOWで2006年2月25日より8月12日にかけて全23話で放映された、プロダクション“マングローブ”(manglobe)制作のアニメーション映画である。このシリーズ・アニメ作品はガイナックス制作の『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)の場合と同様に、小説やマンガ作品等を原作としてアニメ映画化の手順が進められたのではなく、当初からスタジオによるオリジナルの企画として創出され、現代科学の様々の分野の最先端の知見を縦横に駆使して哲学的主題を掘り下げた、日本アニメーション・フィルムの中でも屈指の野心作である。精神現象学や遺伝子情報学や宇宙システム理論等から得られた知の統合的把握を目論み、人間存在と宇宙の存立機構の根底に関わる時代と地域を超えた普遍的な主題性を追求した本作は、アメリカでは英語版がFuse TVで2007年7月より放映され、オーストラリアとカナダでも2007年に放映がなされている。日本における意外なほどの知名度の低さにも関わらず、海外における評価の高さが印象的な本作なのであるが、実はアメリカにおけるこの実験的映像作品に対する反応も、必ずしもこの野心作の実質を正しく把握しているとは思えないふしがある。総じて好意的な批評的対応を勝ち取っているにも関わらず、この作品において最も印象的な意味深いエピソードとそこに用いられた表象と思われるもののいくつかに対して、イメージの現実性からの乖離を問題にした拒否反応とも言える批判的なコメントが与えられているからである。
実はそのあたりに“サイエンティフィック・アメリカン”を標榜する功利主義の国アメリカの、仮構とアニメ文化に対する理解の限界を見ることができそうにも思える。“科学”の前提のみを受け入れて本作品を純然たるSFとして読解しようとするならば、つまり仮構世界の鑑賞手順として自然法則に基づく因果関係の連鎖を抽出して連続的な擬似現実ストーリーを再構築することを目論むならば、その読解作業は原理的に破綻が避けられないものとなってしまうのである。この極めて思弁的な映像作品においては現代科学から得られた知見が豊富に語られているが、題材の中核をなすのは科学の成果である応用技術ではなく科学の成立基盤に関する原理的思弁であり、主題として表面に取り上げられるのは哲学そのものなのである。その結果、むしろ科学の根幹的前提から決定的に逸脱する形而上的存在原理が追求され、その発想が本作品の演出技法と記述システムの双方に直裁に反映されて、特異な表象を形成することになっているのである。
壊滅的な環境破壊の結果、人々が居住することが可能なのは外界から隔絶した“ドーム都市”のみになってしまった未来世界を舞台としたこの作品に登場するのは、実は一般の“人間”とは様々な点において異なる別種のもの達なのである。それにも関わらずこのアニメは、人間ならざる者達の有様を通して“人間”という存在の霊的位相の根源を深く考究するものとなっている。自然科学的人間観や宇宙観を根幹的に覆す新たな視点から、物質と精神の全てを統合すべき哲学的理念に基づいた人間存在原理が展開されているからである。物語世界においてストーリーの前面に現れて“人”としての位相を占めて行動するもの達は、実は“創造主”と呼ばれる超越的存在によって人間の存在意義を代替すべく造られた、人工生命体である。しかし彼等を造った造物主である筈の“プラクシー”と呼ばれる神的超越者も、さらに高次の別存在によって造り出された被創造物であることが示唆されている。プラクシーを生み出した“創造主”と呼ばれているものは、現生人類の子孫である未来の種族である可能性が高いが、興味深いことに彼等の有り様の詳細は作品中には明示されていない。この仮構世界において今を生き自身の存在の意義について想いを巡らし、さらに創造行為を手がけあるいは限界ある被創造者としての自身の存在理由を模索し続ける行動の主体となって描かれているものは、この『エルゴ・プラクシー』という仮構作品の根幹的主題を背負う存在プラクシーとその被造物たる“人間”と、さらに“オートレーブ”と呼ばれる機械生命体達の3者である。それにもかかわらずこの物語が人間の心霊的本質を語っていると判断される理由は、信仰とその裏面にある怨嗟の念が自己同一性概念の再検証及び存在理由(レゾン・デートル)の模索という主題と表裏一体となって掘り下げられているからである。本来は人ならざるものであるこれら3者の間の関係が、一方的な支配や従属という形で収束することなく時に双方向的なものとなって変転し、創造者と被創造者の位相を二重三重に折り畳んだ輻輳した様態を通して描かれているのは、従来“神”という概念を用いて理解されていたものと典型的人間存在の根底に実は連続体を構築してある筈の宇宙の原型的基質の示す、“物理的存在局面”と“意識的様相局面”の二つの現象的位相の重ね合わせなのである。そこでは“全体”と“部分”、“自”と“他”という従来の座標概念の包摂関係で捉えれば決して覆すことのできない基本前提であった筈の原理的制約に対するドラスティックな再検証の試みが企図されている。
『エルゴ・プラクシー』の舞台となるのは、4体のコンピュータ達の協議によって司政方針が決定される未来世界のドーム環境社会である。“ドーム”という閉鎖空間は、一つの支配原理に基づく安定したシステムを保証する領域ではあるが、同時に外部との隔壁を維持することを余儀なくされていることから、空間的・時間的あるいは自律システム的限界性を意味する、厳重な制約を与えられた不自由な系としての存立条件を暗示するものでもある。古代ギリシアの神々が人間達の信仰を支えとして展開していた、整然とした秩序のある理性的把握が可能なロゴス空間は、人々の信仰と神々の権能が失われた時には秩序の崩壊と“カオス”という無秩序の侵蝕を余儀なくされる不安を予知するものでもあった。ギリシア神話の神々は、タイタン族との熾烈な戦いの中でゼウスの開発した新兵器“雷”を武器に彼等の仇敵を駆逐し、かろうじて世界の支配権を手にすることになったのである。苛酷な抗争と必死の創意工夫の結果ギリシアの神々が打ち立てた内部秩序が“コスモス”と呼ばれるものであり、その整然とした安定性は人による信仰を土台として始めて維持されるものであった。当然の事ながら“コスモス外”には、他の神格の勢力圏であるコスモス的秩序とは別種の異次元空間が存在し、その敵対要素の反映はコスモス内においてさえも“カオス”の滲出としてしばしば認知されていたものである。理性の機能の保証された空間とは、実は普遍性の対極とも言うべき甚だしく閉塞的な場だったのである。結局のところ“科学”も、“全能”ならざるもの達の考案した制約ある権能を暫定的に増幅するために創出された、普遍的覚知の一断面に過ぎない不完全なものとして理解されるべきものだろう。現在我々が“科学”という言葉を用いて認識している一見したところ堅固な宇宙把握システムも、その基本的構造性自体は、これらの“ドーム”や“コスモス”などと同等の有限な閉鎖的なものであることを認めざるを得ないのである。無矛盾の完結したシステム構造体として、必然的にその外部に未知のメタ構造が存在するであろうことを否定することが決してできないからである。
生産と消費という形で定式化することができる人間の経済活動は、資本や労働力などのエネルギーの伝播と流動として観測すれば、ある種の熱力学として数学的演算操作の中に組み込んで、独立した科学的分析の対象とされることとなる。その結果、国家や資本主義体制などの何らかの限界性を備えた自律システムも、そのダイナミズムを図表化して可視化する変換操作を適用することにより、外界から隔絶した様々な種類の“ドーム”という形象でもって理解を図ることができるだろう。軍事的侵略行為と武力的支配によってではなく、文化的な冨と娯楽の播種を有効に活用して平和的属国支配を成し遂げ、“パクス・ロマーナ”という名の魅力的な世界統治を成功させた古代ローマ帝国も、あるいは軍事的圧力を背景に利用した高圧的な通商活動を展開して自由経済という名の下に現代の世界を支配している、イギリスからアメリカを経由して受け継がれてきた産業資本主義体制も、科学的定式化の結果においては全く変わることなくある特有のタイプの“ドーム”の形成作業として理解されることとなる。となれば我々現代人は、古代エジプト人がそうであったと決めつけられていた以上に、ある種のピラミッド造築を半強制的に強いられて生を送っている経済の奴隷であると言わざるを得ない。このアニメーション映画に登場する未来都市“ロムド・シティ”という表象に対しては、ここに例として挙げたような様々な具体的方程式読解作業を当てはめることができるものであるが、さらに同様の図式が科学の暫定的拘束を超出して全方位的に適用された結果、そこに生成される表象は“塔”、“森”、“書房”などのような種々の組織構造体や“クイズ番組”、“遊園地”などの概念構造体もしくは“夢”、“妄想”などの不定形の観念構造体の形を取ることともなるのである。このアニメーション作品の実体は、ニュートン力学にあったような客観的物質存在という基本前提を無条件に受け入れることによって成り立っている、科学の枠組みでのみフィクション世界を現象として捉えようとする“SF”という既存の文芸ジャンルの共通認識の枠を超えたものなのである。この映像作品が目論むのは、純観念的記号の奔放な組み合わせを活用して抽象的概念操作を行い、新種の意味の複合体の提示を示唆する形而上学的思弁を映像化することにある。そこでは個人存在と現象生成を司る原形質的存在原理に対する超出的記述の可能性が切実に模索されている。そして“仮構”とは、本来そのような観念操作が徹頭徹尾行われる場だった筈なのである。
[Read more of this post]
17:04:52 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks