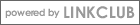Archive for 04 September 2012
04 September
佐倉セミナーハウス文化教養講座テキスト
“詩と科学と宗教を一つのものにする”“心象スケッチ”
例えば賢治の代表作と言えるであろう、精神と霊的知覚の極限を模索した『銀河鉄道の夜』の舞台を提供する進行中の鉄道車両という印象的なシチュエーションが、等速直進運動を行いつつある慣性系における時間・空間の位相を再考察するためにアインシュタインの採用した思考実験の機構に触発されたものであることに間違いはないと思われる。そればかりでなく、相対性理論の提示した素粒子の存在論的解釈とその哲学的影響を巡って1920年代に切実な関心を持って論議されつつあった、量子理論の開拓した波動論あるいは確率論的解釈法についても、賢治が“心象スケッチ”において敏感に同時代的反映を示したことが分かっている。1924年9月17日の作である『春と修羅』第2集に所収の作品番号304、「半蔭地撰定」などに、その顕著な実例を見ることができる。量子論理における実在の存在論的解釈を巡る、ボーアやハイゼンベルグの論議の影響を直接反映していることが確実である例として該当すると思われる箇所を、下に引用してみよう。
半透明な緑の蜘蛛が
森いっぱいにミクロトームを装置して
虫のくるのを待ってゐる
にもかゝはらず虫はどんどん飛んでゐる
あのありふれた百が単位の羽虫の輩が
みんな小さな弧光燈(アークライト)といふやうに
さかさになったり斜めになったり
自由自在に一生けんめい飛んでゐる
それもああまで本気に飛べば
公算論のいかものなどは
もう誰にしろ持ち出せない
むしろ情に富むものは
一ぴきごとに伝記を書くといふかもしれん
宮澤賢治という個人の存在の反転的写像である、彼を取り巻く風景に対する主観的描写の中に採用された“公算論”(probability)という語が、物質粒子あるいは一個の生命体すらも“確率関数”として記述することを主張する、古典力学における運動方程式に代替するものとして量子力学が提示した存在性記述理論を示唆するものである。アインシュタインの提示した相対性理論の主要な課題点である時空連続体としての世界認識と慣性系における作用伝達の新解釈についてばかりでなく、素粒子の振る舞いについての存在論的考察としてそこから必然的に展開した実在と記述の相関についての様々な議論を、賢治は量子論理生成期の同時代人として重大な関心を持って把握していたのだった。そしてこの従来の決定論的現象解釈に取って代わるべき新機軸の実在記述理論の誕生が、結局は賢治に対しては揺るぎない信仰の道と情熱的な科学の探求の道の双方を包含する統合的世界解釈として、生の哲学の実践の道への接点を提供することになったのである。それは、『春と修羅』の序詩として提示された以下の創作理念の宣言に、あまりにも直裁に語られるものとなっている。
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち、その電燈は失はれ)
これらは二十二箇月の
過去とかんずる方角から
紙と鉱質インクをつらね
(すべてわたくしと明滅し
みんなが同時に感ずるもの)
ここまでたもちつゞけられた
かげとひかりのひとくさりづつ
そのとほりの心象スケツチです
これらについて人や銀河や修羅や海胆は
宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら
それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが
それらも畢竟こゝろのひとつの風物です
たゞたしかに記録されたこれらのけしきは
記録されたそのとほりのこのけしきで
それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで
ある程度まではみんなに共通いたします
(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに
みんなのおのおののなかのすべてですから)
けれどもこれら新生代沖積世の
巨大に明るい時間の集積のなかで
正しくうつされた筈のこれらのことばが
わづかその一点にも均しい明暗のうちに
(あるひは修羅の十億年)
すでにはやくもその組立や質を変じ
しかもわたくしも印刷者も
それを変らないとして感ずることは
傾向としてはあり得ます
けだしわれわれがわれわれの感官や
風景や人物をかんずるやうに
そしてたゞ共通に感ずるだけであるやうに
記録や歴史、あるひは地史といふものも
それのいろいろの論料(データ)といつしよに
(因果の時空的制約のもとに)
われわれがかんじてゐるのに過ぎません
おそらくこれから二千年もたつたころは
それ相当のちがつた地質学が流用され
相当した証拠もまた次次過去から現出し
みんなは二千年ぐらゐ前には
青ぞらいつぱいの無色な孔雀が居たとおもひ
新進の大学士たちは気圏のいちばんの上層
きらびやかな氷窒素のあたりから
すてきな化石を発堀したり
あるひは白堊紀砂岩の層面に
透明な人類の巨大な足跡を
発見するかもしれません
すべてこれらの命題は
心象や時間それ自身の性質として
第四次延長のなかで主張されます
大正十三年一月廿日 宮澤賢治
賢治がここで「わたくし」と名乗る自らを“存在”とは呼ばず“現象”と定義づけ、“透明な幽霊”すなわち心霊あるいはペルソナの“複合体”であると認識するのは、相対性理論の成し遂げた実在解釈の方法論の革変に見事に対応している。おそらく賢治にあっては、全体性の示す一様相を意味単子として構想するライプニッツのモナド論の発想は、相対性理論の示す宇宙観に対する考察を通して受け入れられたものであろう。そしてアインシュタインの提示した時間と空間の連続体としての世界像に対しては、この序詩では“時空”という言葉ばかりでなく、さらに“第四次延長”という言葉をも用いてその骨子が反映されている。“因果の時空的制約”という言葉にあるように、事象と存在の記述とその意識の主体の認識において示される様々な様相の等価原理的な相異なった具現化という基本認識そのものが、相対性の原理の実存的反映としてこの序詩の全体に展開する基幹理念となっている訳だが、これらは仏教思想的関連から“六道”の発想を暗示させもする“人や銀河や修羅や海胆”といういかにも賢治らしい大胆な字句を用いて、また集約的に語られ直すことになっている。これらに代表される考え得る限りの種々様々の存在物達が“宇宙塵をたべ、または空気や塩水を呼吸しながら”各々の知覚や思考アルゴリズムに従って、“それぞれ新鮮な本体論”を考えることがあろうとも、おそらくはそのどれ一つとして“ほんとうの真実”ではあり得ない。しかし賢治には、“それらも畢竟こゝろのひとつの風物です/たゞたしかに記録されたこれらのけしきは/記録されたそのとほりのこのけしきで/それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで /ある程度まではみんなに共通いたします”という一つの得心がある。おそらく賢治の得た確信に当たるものを物理的事象解釈の例に置き換えるならば、宇宙の基幹概念として想定されるものが「真空」であっても、「エーテル」であっても、あるいは「場」と呼ばれるさらに別の概念であっても一向に構わない、これらを通じて感知される関係性そのものの主観的解釈という動的意義性に還元されるものとして、“真実”が捉えられているからだ。しかし賢治の創作理念において最も枢要な相対性理論と量子力学の存在解釈を反映した思想的核心が述べられていると思われる部分は、実は“すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから”という一節であろう。この言明に示唆される全と個の反転的合一を前提とするシステム理論的存在解釈こそが、近代西洋思想が結局は帰着してしまった、存在性における意味の喪失と生の根本原理の破綻を救済するための、重要な契機を提供するものだからである。
ニュートンの古典力学体系を推進する王立協会組織として設立されたロイヤル・ソサエティに代表される近代的な科学思想と応用技術をいち早く発展させ、他国に先んじて産業革命を成功させてヨーロッパ随一の強国となったイギリスに、その先進国としての思想と文化の本質を学ぶために明治政府によって留学生として派遣された夏目漱石は、20世紀初頭の俗物主義の王国イギリスにおける実際の思想的現状に、学ぶべき理想とはかけ離れた現代科学文明の病理と共に、古典力学とその示唆する哲学そのものの限界点をいち早く痛感することとなり、世界の将来の思想的展望に対する深い憂慮に捕われることになったのであった。科学思想と個人主義の抱え込んだ思想上の根幹的限界性は、後には“断絶”(deracination)という言葉で広く一般に理解されるようになったが、漱石はいち早く人間存在の基本的意義性の全体性の宇宙からの乖離をもたらす近代西洋思想の問題点を見極め、一人暗然とした思いにかられたのであった。黎明期の量子力学が突きつけた、あまりにも革新的な伝統理論体系に対する破壊的側面を、漱石は留学先のイギリスで身をもって体感していたのである。しかし漱石に現代文化の展望に対する思想的懐疑に導かれた深い懊悩を与えることとなった20世紀の新知識は、逆に少しばかり時代を下って賢治の心中においては、反転的に既存の宗教と思想の限界点を跳躍することを可能にするであろう、科学的/宗教的発心となり得たのである。その力強い希望に満ちた宣言を、『春と修羅』に収められた心象スケッチの作品の全編を通して確かに窺うことができるのである。そしてこれら全ての詩作理念の根底としてあるのが、先ほど見た“すべてがわたくしの中のみんなであるやうに/みんなのおのおののなかのすべてですから”という宇宙論的/存在論的確信だったのである。
しかしながらこの信念を確証すべく『春と修羅』において賢治の採用したこれらの科学的発想と新感覚の専門用語は、“心象スケッチ”としてまとめられた詩作品の各々の中では、孤独な精神世界を逍遥する作者自身の姿と、その心眼に映ったとりとめのない夢想を語る一つの道具立てとして用いられていることはあっても、これらの述語の示す科学上・思想上の本来の微妙な意義性が、ことさら個々の作品自体の内部機構において主題的に緊密に構築された関係性を与えられて、計算づくの結果語られている訳ではないように思える。飽くまでも“心象”の“スケッチ”としての断片的な独白の中で、これらの全体性の世界観を示唆する新機軸の科学用語は、賢治の駆使する一般の諸分野の専門用語に紛れて、単に恣意的に挿入されているばかりのようにも思えてしまうのである。だからこれらの専門知識の保持する科学的・哲学的発想と現代物理学と現代思想の微妙な関連についての基礎知識に対する十分な理解を持たない者にとっては、賢治の使用する“科学用語”は、時として機械論的な古典力学的科学観や、エジソンによって代表される科学的応用技術(テクノロジー)をのみ示唆するものであるかのように、誤った理解をされてしまうこともあるだろう。これらの該博な知識が暗示する筈の、自省的な創作行為を行いつつある重要なメッセージの発信者としてはあまりに不用意なものとも見なされかねない用語の選択が、素朴なほどに無計画になされてしまっているかのように見えてしまうのである。このように宮澤賢治という本来は極めて思想的な要素の色濃い詩人においては、読み手の側の新傾向の専門用語と思想的発想に対する理解の程度を推し量り、これらの一般には極めて難解であった筈の思想あるいは知識を作品世界に導入する上で、書き手として払うべき説明的顧慮を全く欠いたかのように思われる、言わば独善的な創作行為を行っていると判断されかねない危うい部分が確かにあるのである。多くの人々に時として疑心を抱かせる、賢治という思想家/芸術家の裡にある一見したところ極めて不可解な矛盾点がここにある。
しかしながらこれらの、全くの説明不足としか言い様のない程の素朴な語の選択と無軌道で放埒なほどの発話行為こそが、むしろ賢治の詩作上の特徴的な傾向であると同時に、彼の芸術哲学の基底をなす根本理念ともなっているのである。賢治の詩作行為における、読者の確実な理解を省みない独善的とも見なされかねないこの野放図な用語の使用を許した根拠としてあるものこそが、このかつて例を見ない独特の思索者/行動者の本質を語る重要な手がかりとなるべきものである筈なのである。実は『春と修羅』の中に散見されるアインシュタインの相対性理論とハイゼンベルグ、ボーアその他の展開した量子力学理論に関する言及の例にも増して、むしろ相対性理論の発想が賢治に与えた重大な確信の直截な影響を見ることができるのは、「グスコーブドリの伝記」の中の以下の一節である。物語の序盤で、主人公ブドリが彼の人生の師となる科学者クーボー博士の授業を始めて目にする際の場面である。
…向こふは大きな黒板になっていて、そこにたくさんの白い線が引いてあり、さっきのせいの高い眼がねをかけた人が、大きな櫓の形の模型をあちこち指しながら、さっきのままの高い聲で、みんなに説明して居りました。
ブドリはそれを一目見ると、ああこれは先生の本に書いてあった歴史の歴史といふことの模型だなと思ひました。先生は笑ひながら、一つのとってを廻しました。模型はがちっと鳴って奇體な船のやうな形になりました。またがちっととってを廻すと、模型は今度は大きなむかでのやうな形に變りました
みんなはしきりに首をかたむけて、どうもわからんといふ風にしていましたが、ブドリにはただ面白かったのです。
「そこでかういふ圖ができる。」先生は黒い壁へ別の込み入った圖をどんどん書きました。
クーボー先生の語る講義の主題を具現化したものであると思われる、ブドリが教室で目にした不思議な模型が示す“歴史の歴史”という概念のメタ構造と、さらにまた“歴史の模型”という異次元的意味空間の交錯が撚り合わされた、とりわけ興味深い観念性の記述の例が、ここにあることを確認することができる。賢治が詩作と人生の統一スローガンとして掲げた、“詩と科学と宗教の統合”という理想を可能にすることができる、おそらく賢治にとっての宗教的回心として作用していたに違いないシステム理論的根拠を照射する理念が、実はここに浮上しているのである。何故ならばこのメタ構造概念は、アインシュタイン自身が彼の相対性理論の着想に多くを頼っていることを言明していた、マッハの哲学の以下のような原理性志向的関心を見事に反映しているからである。
「経験的所与のあいだの諸関係」を函数的に表現し、それら函数の函数を定式化しようとする
つまり、極限の真実追求を旨とする科学者/思想家にとっては、意味空間の中で多元的に分岐して個々の内実を主張し得る“函数”としての概念/現象の全体像を正しく把握して論考に組み入れるためには、“函数に関する函数”としてのメタ数理理論化の手順が不可欠であり、常に構想し得る限りの種々の座標界面を構築し得る基体となるべき、従来の理性の及ぶ範囲であった限界ある次元を跳躍した、多元空間/多元概念座標における関係性の函数的表現を柔軟に行う不断の行為と思索こそが、自身の生の哲学として切実に模索されねばならなかったのである。同様にまた宗教あるいは文学の探求者においては、欺瞞行為に対する究極の弾劾精神から行われたイエス・キリストの“目にて犯すことなかれ”という言明の反転相を考えるならば、日々の性行為や飲食等その他の日常生活の瑣末事の全てにおいてこそ、倫理や哲学の問題が真剣に考慮されなければならないのは、むしろ当然のことなのである。法廷や教場や説教檀等の限定された場にのみ構築された倫理や真理は、むしろ実存的な原理の探求者にあっては典型的な欺瞞の産物であり、それこそが唯一の確証可能な悪の実体であると判断されることにもなるからである。現実世界の倫理は、残念ながら現象世界の諸制約を負っているが故に、結局は限りある暫定倫理でしかあり得ない。むしろ仮構世界において確証される倫理こそ、生起可能な全ての条件と起こりえないあらゆる状況にも適合する究極倫理あるいは絶対倫理として、真の普遍倫理を体現し得るものであるのかもしれない。多世界における推移可能な真実の全てに通貫してある不変の倫理というパラドクスの結実が、仮構の中には求められなければならないこととなるのである。かつてサドやワイルドやドストエフスキーや、そしてル・グインが“サイコ・ミス”において追求したように、仮構はいかなる非倫理的な主題をもその中に含み得るからこそ、永遠性の倫理にのみその照準を合わせる、影の道徳を隠し持っているのである。
永遠的真実の探求を企図する求道的精神においては、カオスの内部に押し込められた、信仰の力によってかろうじて神々の支配の領域として確保された、閉じられた城塞のような孤絶したコスモスを生きることに満足するのではなく、むしろカオスを基盤に捩れと捻りを軸に伸展する全方位的存在性の展開を許容する閉塞を知らない世界構築理論が新たに構想され、考え得る限りの全てを含む本来の意味での普遍性の宇宙に意識を開放せねばならないこととなる。その結果例えば、歴史哲学を実存哲学へと変換し、あるいは楽曲を絵画へと翻訳することにより、乖離した次元界面における潜伏した同一性や共通性もしくは対照性を目ざとく読み取ることによって、現象世界における意味の断絶や矛盾を克服することが始めて可能となるのである。意味の関係性を切り離した質点あるいは波動として量化された数値のみに着目して、力学あるいは波動関数としての数式的構造性を抽出することばかりで終わりとするのではなく、むしろ意識体の保持する相関した主観的意味単位である感覚性にこそ焦点を当てて、それらの相互変換作用を含めた網羅的な意味の関係性を記述することを企図した場合には、時として視覚が聴覚に、あるいはまた触覚等の別種の感覚に置き換えられて語られ得るように、“クオリア”の相互変換性がむしろ意図的に開拓され、記述されねばならないこととなるからである。先鋭的なロマン派の詩人エドガー・アラン・ポーがその詩作の上で印象的に行ってみせたような視覚と聴覚等の感覚の交錯の記述は、単なる斬新な表現技法としてのレトリックの技巧の模索の範疇に止まらず、全体性の宇宙の原理的な記述と普遍相における意味の把握にこそ係わる、思想上の枢要な基幹原理を示すものとなっていたのである。こうして全ての不和と矛盾と差異を言わば意味の函数化を介して調和させることのできるアルゴリズムを、数学的演算処理のみならず、その処方そのものに適用することによって、実際の現象物体(マテリア)自身の奇跡的な変身(メタモルフォシス)と、そればかりでなくプレローマ的場の根幹的意味性そのものの変成を具現化する手立てが発見され得るのである。そのような意味で人格や個別性の裏面に横たわる同一性や対称性が再発見された時、改めて『春と修羅』の序詩の「すべてがわたくしの中のみんなであるように/みんなのおのおののなかのすべてですから」の一節が示唆する、量子論理的/仏教理念的な、宇宙理解/世界救済の可能性も垣間見えてくることだろう。
六道の発想の根幹にあったような、“世界の中の私”と“私の中の世界”という反転的描像が共軛的に成り立ち得るような精神界面においてこそ、真に創造的な仮構の記述は成立するのである。このような意味で常に切実な思惟を巡らせ、見て語り全ての事物に霊的に関与し、一つの個人の生を深く生きることによって全ての生と現象を意義づけ、大乗の教えを具現化して他者あるいは“みんな”の救済をも実際に企てることが可能にもなるのである。時・空・精神連続体の全体性を構想する場合に理解や把握の基礎単位を形成すべき“意味”とは、物質主義的宇宙観を前提としていた現代科学が仮定していたような、属性や特質として質量や現象の中に帰属するものとして仮定された、量化して読み取られるべき仮象情報としてあるのでは決してなかった。宇宙の根源的実質単位として存在すべき“意味”とは、“質量”や“エネルギー”や“波動”や“場”を生成する原形質として本源的に全てに先立って存在すると同時に、むしろこれらの現象を観測し記述する意識の主体とそれらの行為自身との相互作用という描像それ自身と等価的な定義を保持するものとして、その他のあらゆる個々と全体との関係性を常に意義性の階梯と機縁を増幅しながらさらに新たな固有の意味としてその流動的な内実を賦与されつつ、総合的に展開していくべき基礎概念だったのである。記述者からは独立して厳然としてある客観的な事象の存在という仮定と、機械論的過程に従った模擬実験による科学的真実の普遍的物理法則としての確証という、“ノヴェル”が担っていた硬直した幻想により損なわれてしまった仮構のエネルギーを再び解放することに成功したのが、“心象スケッチ”と宮澤賢治が名付けた、文学的表現技法の枠を超えた芸術的生のあり方であった。
“意味”の中に見いだされるべき、これによって全ての概念が共変的に変換されるべき“意味を形成する意味”とは、常に能動的にあるいは恣意的に構築され、個々の意識の主体によって意図的に賦与され得るものでもあったからこそ、現象性の中の些末な事象への任意的関与とその恣意的記述そのものが、賢治にとっては意味の複合的連鎖として紛れも無く世界の総体としての真言と共振し、人にとっての“真実の言葉”となり得ていた訳なのであった。この優れて祭礼的/祝祭的/祈祷的実例を、『春と修羅』に収録された他のいくつもの心象スケッチの中に豊富に見いだすことができるのである。そのうちでも最も特徴的な成功例の一つとして挙げ得る作品が、「アンネリダタンツェーリン」であろう。
蠕虫舞手(アンネリダタンツエーリン)
(えゝ 水ゾルですよ
おぼろな寒天(アガア)の液ですよ)
日は黄金(きん)の薔薇
赤いちひさな蠕虫(ぜんちゆう)が
水とひかりをからだにまとひ
ひとりでをどりをやつてゐる
(えゝ 8(エイト) γ(ガムマア) e(イー) 6(スイツクス) α(アルフア) ことにもアラベスクの飾り文字)
羽むしの死骸
いちゐのかれ葉
真珠の泡に
ちぎれたこけの花軸など
(ナチラナトラのひいさまは
いまみづ底のみかげのうへに
黄いろなかげとおふたりで
せつかくをどつてゐられます
いゝえ けれども すぐでせう
まもなく浮いておいででせう)
赤い蠕虫舞手(アンネリダタンツエーリン)は
とがつた二つの耳をもち
燐光珊瑚の環節に
正しく飾る真珠のぼたん
くるりくるりと廻つてゐます
(えゝ 8(エイト) γ(ガムマア) e(イー) 6(スイツクス) α(アルフア) ことにもアラベスクの飾り文字)
背中きらきら燦(かがや)いて
ちからいつぱいまはりはするが
真珠もじつはまがひもの
ガラスどころか空気だま
(いゝえ それでも
エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字)
水晶体や鞏膜(きようまく)の
オペラグラスにのぞかれて
をどつてゐるといはれても
真珠の泡を苦にするのなら
おまへもさつぱりらくぢやない
それに日が雲に入つたし
わたしは石に座つてしびれが切れたし
水底の黒い木片は毛虫か海鼠(なまこ)のやうだしさ
それに第一おまへのかたちは見えないし
ほんとに溶けてしまつたのやら
それともみんなはじめから
おぼろに青い夢だやら
(いゝえ あすこにおいでです おいでです
ひいさま いらつしやいます
8(エイト) γ(ガムマア) e(イー) 6(スイツクス) α(アルフア) ことにもアラベスクの飾り文字)
ふん 水はおぼろで
ひかりは惑ひ
虫は エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字かい
ああくすぐったい
(はい まつたくそれにちがひません
エイト ガムマア イー スイツクス アルフア
ことにもアラベスクの飾り文字)
『春と修羅』に収められたこの心象スケッチの短詩においては、詩を詠む作者の姿自身が反転的に作品の中に描き込まれている。その作者は手水鉢の底に沈んでうごめいている蠕虫という、現象世界の具現する小さな一側面に目を留め、これを観察・記録するという体を装いながら、実は神話と科学と音楽を綯い交ぜにしたとりとめのない夢想を心中に展開しているのである。一見したところ伝統的な “叙情詩”と呼ばれてきたものと同等の道具立てに基づいた、孤絶した内面世界を描いた作品空間がここにはある。しかし“心象スケッチ”としてのこの作品の成立基盤は、一般の叙情詩の類型に従って、作者個人の孤独や哀れの想い等を歌った、感情の吐露や想念の告白として成立するものとは、実は全く異なるところに立脚するものなのである。
他の心象スケッチの作品群と同様に、「アンネリダタンツェーリン」においては、意識の主体たる“私”によって、様々な“見立て”による実に豊かな“連想”が行われていることが分かる。“日は黄金(きん)の薔薇”という鮮烈なフレーズに見られるように、“私”を媒介として放埒極まりない程の概念と表象が、種々の科学的・思想的・文化的知識と共に瞬間的な連想として“連接”され、単に一匹の蠕虫の姿を写実的に描写/形容するばかりでなく、むしろ甚だしく恣意的/主観的に、あるいはむしろ際立って創造的/造形的に、あえて自然法則の枠組みに従うことなく自由に奔放に世界の一断面が語られていくのである。そこには様々の神話や生物学や音楽等の専門用語や学術的語彙の各々が、それらの本来保持していた系の内部機構の意味連関の全てを担わされて、さらに他の分野の系の種々の意味連関と跳躍的に連接されることにより、“超自然”の意味の複合体を活性化させているのである。
太陽の光の差し込む手水鉢の中の水は、記録を行いつつある観察者には特有の質感を持って見えるらしく、“寒天(アガア)”という一般には菌類の培養素地として用いられる半透明の材質つまり“ゲル”(膠質)を語る言葉で記述されている。この語からの連想としてここではさらに、特有の分子活動を与えるコロイド状の“ゾル”という混雑溶液を呼ぶ言葉が採用されることとなる。コロイドの中で観察される独特の分子の不規則運動は、微細なパスタであるバーミセリにあたかも生命体であるかのような有機的な動作を与えることから、無生物の生命化現象と誤認されてかつて科学界で様々な論争を引き起こしてきたものであった。後に植物学者ロバート・ブラウンによって、水面上に浮かべた花粉から容出した微粒子の示す不規則運動として研究され、“ブラウン氏運動”と名付けられたこの現象は、1905年にアインシュタインによって、コロイド溶液中にもたらされる特有の不規則な分子運動として、物理学的に解明されたものであった。ノーベル賞受賞論文である「光量子論」と「特殊相対性理論」に並んでこの年に発表された「ブラウン氏運動の理論」は、宇宙の現象としての具現化過程を条件づける素粒子の量子的ゆらぎの発見に先行して、実は根本的宇宙認識のニュートンモデルからの修正を迫る重大な科学的事実の一つなのであった。20世紀初めの科学思想の世界において、自然の中にある根幹的意義性を再検証する上で殊に注目の的となっていたのが、これらの用語の示唆する内実だったのである。
しかしこれらの純然たる科学史上の事実と平行して、賢治の想念の中には、踊りと音楽で構成された一つのフィクションである演劇的な枠組みを持った寓話世界が、同時に展開しているのである。手水鉢の水底で身をくねらす蠕虫の動きは、何故か“タンツェーリン”というドイツ語(“舞手”、英語ならば“dancer”に相当する語である)を用いて語られている。あるいはホフマン原作、チャイコフスキー翻案の『くるみ割り人形』のようなバレー組曲作品か、もしくはアンデルセンの異境を舞台にした童話作品の世界でも頭に想い描いているのであろうか、正体不明の侍従のような人物によって “ナチラナトラのひいさま”というこれまた意味不明の異国的な名で呼ばれることとなっているのが、この心象スケッチの中で記述の対象とされている、謎めいた蠕虫なのである。そしてこれらの取りとめのない夢想を展開する、一個の観察者であり記述者である“私”は、“水晶体や鞏膜”という観測実験機器のアパレイタスを模して解剖学的に突き放したように客観的に語られ、その“私”の得た想念自体が作品自身の中でとりとめの無い幻想として明らかに否定されもしている。作者の想念としてある幻想と、その幻想を繰り広げつつある作者自身が双方向的にその姿を投影しつつある次元階層を延展した場が、そこに繰り広げられているのである。「真空溶媒」等の他の心象スケッチにも、この現実・幻想・仮構連続体の記述が及ぼす意味の豊穣の感覚を確認することができるだろう。このように語られた観測者/記述者の姿とその脈絡の無い幻想は、オルテガの語った“窓ガラス”とも、ハムレットの語った“自然を映し出す鏡”とも異なる、全く別種の定義に基づく機器であり“存在”であり“現象”なのである。かくして“意味”として物理的広がりを持たず、従って他のいかなる同一カテゴリーのものにも含まれることはなく、全体性の宇宙の意味の一様相として示される“モナド”にも似た意識の自覚として、“私”という独特のペルソナが想定されることとなる。
しかし取りわけこの詩の固有の成立条件をなすものとして印象的なのが、水底で蠢く蠕虫の姿を“エイト ガムマア イー スイツクス アルフア”という独特の言葉で描写している部分であろう。そこには身をくねらす蠕虫のとる様々の姿形が、ギリシア文字や英語の文字やアラビア数字記号になぞらえられて、“8 γ e 6 α”と見事な視覚的形象を与えられて表現されている一方、これらの文字・記号の本来の読みに従って、一種独特の音楽的旋律まで奏でることとなっているのである。身をくねらす孑孑をあえて学名を用いて“アンネリダ”と呼び、ドイツ語のタンツェーリンと強引に繋げて“アンネリダタンツェーリン”という独特の音韻効果を備えた語を用いて呼び替える、斬新な音楽的見立てと連動するのと同種の特異な言語的創造感覚がここにはある。様々な見立てと観念の連接と新しい意味の付加を行う“私”という“現象”が、世界の中で力学的因果関係に従って機械論的にもたらされた事象の一つであるばかりでなく、同時に遡及的に歴史と出来事の総体に対する意味連関を再構築する、能動的な作用をも及ぼす機能を果たすこととなっているのである。
こうして“心象スケッチ”においては、“連想”という精神活動と“言及”という実際の行動が、時空を超えた意味と精神の連続体である世界そのものに対する有機的な注釈賦与となる。世界から受動的に意味を読み取り、そこに内包された客観的真実とされるものを単一方向的に解明するばかりでなく、同時に世界の根源的原理の意味の豊かさを、自らが主体的に附託することができるのである。何故ならば局所的な作用による因果関係に頼ることのない、時間軸の方向性を跳躍した全方位的な関係性の構築が、思念と夢想の裡においてこそ可能となり、観測と記述による様相波動の収束が直裁に機縁と因縁を構築することにより、全一なる宇宙そのものの意味性賦与に貢献しているからである。つまり、参照して語る注釈賦与の行為が、紛れもなく根源的意味連関の構築として始原的な創世行為と等価のものであり得ることとなるのである。仮構とその創り手の生きる現実が分ち難く融合した和歌の世界の存在論的位相と次元軸を共有する、見事な脱現実的汎実存的生のあり方がここに成就されている。社会による功績の実利的認知や既存の思想や組織の判断基準による功利的評価などとは全く異なるものを射程に置いた、これらの無意識の深奥にある一種音楽的な霊的活動を語る想念こそが、賢治が“真の言葉”と呼んだものであった。このようにして思念の中で世界の複合的意味性の位相変換と再生産を行い、プレローマ的原形質における可能態の醸成と、現象界におけるメタモルフォシスの錬成を成し遂げることが実際に可能となるのである。
賢治が“心象スケッチ”を語るものとして演じた、和歌における“生活実感”を“歌に詠む”、あるいは叙情詩における“心情の吐露”の“記述”という体を装った実は巧妙な捻りのある“仮構”でもあり、あるいは徹頭徹尾突き抜けて純真無垢な即興的詠唱行為でもあるスケッチ的記述は、古典力学的世界観に基づく“リアリズム”と呼ばれるいびつな仮構とは、全く対照的な原理に基づくものだったのである。実は賢治という“現象”は“心象スケッチ”の記述/発話行為において、『最後のユニコーン』の第一章に登場していたあの饒舌な蝶のように、とりとめのない連想と奇想を一人つぶやく極楽蜻蛉を振る舞っていたのであった。そしてこのような疲れを知らぬ道化を演じてみせる天真爛漫な想念と、全てに対する興味と関心に溢れた比類ない上機嫌の精神活動においてこそ、浅薄な限りある実証主義的科学の理解にしか基づかない断絶の精神世界を根底から解体して鮮やかな再構築を成し遂げることが可能となり、世界に対する真の意味性賦与を導出する健全な精神の回復が見込まれることとなる。
かくして賢治にとっては、言葉と想いを用いて交響曲的な世界の意味の連鎖に没入し、そして自らの手によって外挿的にその世界を調律する試みが、紛れもなく科学と宗教の共通目的となるべきものとして芸術的生に連接することができていた。このような宇宙的オーケストレーションへの全人格的参入行為こそが、賢治の宣言にある“詩と科学と宗教を一つのものに”統合して観測/記述/創作行為を行う営み、すなわち“心象スケッチ”なのであった。他者の救済のために行う個人としての自己犠牲の行為につきまとうパラドクス(15)と、個別的存在性の引きずる行為の展開範囲の因果関係的限界のディレムマを解消し、この誠心からの根源的願望を補完し代替する方途を約束したのが、賢治の出会った新しい科学、相対性理論と量子論理だったのである。だからこそ賢治にとっては、音声のみならず観念と概念と、そして材質や属性すら自在に“オノマトピーア”(擬音)に変換する術、すなわちしばしば魔法の究極の原理とされる“メタモルフォシス”を具現する操作が、確かに存在し得ていたのである。賢治が“科学”という言葉を用いて語った理想郷の夢想を通して垣間見ることのできるものは、20世紀後半に空疎で浅薄な隆盛を極めることとなった科学的応用技術の成果による物質的豊かさとは根本的に異なったものだったのである。70年代以降アメリカを舞台として、芸術作品の特異な表現行為として仮構世界の中からの現実世界に対する浸透を企図したアクチュアリズ厶の手法が勃興したが、アクチュアリティの芸術と生の先駆的な実践者が、実は1920年代の日本に既に存在していたのであった。機械論的自然観の束縛を持たない言の葉の生きる国日本の、仮構と現実の融合を果たすばかりではなく、全体性の宇宙と仮象としての個である“わたくし”の融合を夢想する実践的アクチュアリストが宮沢賢治だったのである。
19:07:19 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks
2012佐倉セミナーハウス文化教養講座のお知らせ
宮澤賢治の詩と宗教と科学―仮構と現実の一体化を図る思想
日時:10月6日、13日、20日(土曜日)
午後1時から4時まで(12時30分 開場)
(受講はいずれか1日でもよい。好きな時に入退出して構いません。)
場所:和洋女子大学 佐倉セミナーハウス
申し込み:不要。直接会場へお越しください。
参加費:無料
内容:「宮沢賢治の詩と宗教と科学 ―仮構と現実の一体化を図る思想」
1 アインシュタインの相対性理論の影響と詩集『春と修羅』の
心象スケッチの手法
「春と修羅」序詩:“人や銀河や修羅や海胆”と四次元延長
「半蔭地撰定」:羽虫の群れと“公算論”「神は骰子を振らない」
2 『グスコーブドリの伝記』と異次元概念の交錯
クーボー博士の講義:“歴史の歴史ということの歴史”、“歴史の模型”
メタ概念とメタ表象―教育と試験の理想的な姿
3 「蠕虫舞手(アンネリダタンツエーリン)」―佇む自分と妄想世界
「真空溶媒」:即興と想念を通して行う世界の調律行為
観測効果と“時空精神連続体”
問い合せ先:和洋女子大学 広報課(TEL:047-371-1473)
18:54:34 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks