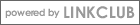Archive for 06 September 2012
06 September
召喚魔法と個人存在 ―『Fate/stay night』における存在・現象・人格概念 2
『Fate/stay night』においては、取り分け“魔術”という知と技術のメカニズムの裡に暗示される“召喚魔法”において具現化された“英霊”と呼ばれる存在の選別的特性が人格概念に対する再考察を要請する思弁的企図として提示されており、さらにキャラクターの保持する“萌え”要素、即ちエロ・ファクターの構築にも重要な役割を果たす結果になっている。『Fate/stay night』では本編が開始する前に予備的に展開されるプロローグとして、主人公とは異なる別の人物の視点を採用することにより、英霊召喚とされるものの具体的手順とその根本理念を紹介して、召喚技術と魔法原理に関する科学概念を跳躍した思弁的設定が語られることとなっている。しかしこの“プロローグ”は、一見したところ本編の物語開始以前の序章に当たる枠外のエピソードであると共に、実はメインストーリーの中で“バッドエンド”を迎える最初の分岐ストーリーの展開の役目をも果たしているのである。中心と辺境の概念的差異を失った現代的宇宙観の思想的位相を反映した仮構世界的対応物として、この演出的特質を踏み込んで捉えることも可能だろう。
プロローグの第1日目、聖杯戦争において主人公衛宮志郎のライバルとなるヒロイン遠坂凛がサーヴァント召喚を試みるあたりでは、この仮構世界の基本原理を形成すると思われる特殊な概念群とそれらの織りなす特有の関係性が様々な手法を用いて紹介されている。興味深いのは、文字列とそこに振られた読み仮名(ルビ)とが意味を乖離した二重構造を形成するという、独特のタイポグラフィーの工夫を活用してこの概念操作が試みられている点である。凛の用いる魔法の呪文はドイツ語表記を基本とするものになっているが、ドイツ語の文章に添えられた英語読みのカタカナ表記等の例に見られるように、様々な様相におけるルビの活用によって魔法の裡に秘められる概念次元の越境と存在様相の跳躍の可能性が示唆されることとなっているのである。例えば最初に凛の発する魔法の呪文は以下のような表記を用いて示されている。
「Schliessung(ロック). Verfahren(コード). Drei(3).」
これに続いて、召喚魔法の実施を試みようと魔法陣の敷設に臨む魔術師である東坂凛の独白を通して、魔法技術の基幹設定を暗示する諸概念とその基底にある原理機構が具体的に語られて行くことになる。
「聖杯戦争に参加する条件。それはサーヴァントと呼ばれる使い魔を招集し、
契約する事のみだ。サーヴァントは通常の使い魔とは一線を画す存在だ。そ
の召喚、使役方法も通常の使い魔とは異なる。」
魔術師同士の直接の対決よりもむしろその分身とも言える“サーヴァント”の間の抗争が中心となって競われるのが、このゲーム世界の中心主題となる“聖杯戦争”の仕組みだが、ここでは魔法を題材にした仮構世界にしばしば登場する魔法使いの下僕的存在である“使い魔”(familiar)を引き合いにして、召喚されるサーヴァントとの類似と相違がさりげなく語られている。この場合のような周知の類似概念に対する対比的言及に留まらず、この後には慣習的に容認された述語の本来の意味を乖離する意図的な越境的使用が行われていることが、『Fate/stay night』の採用したさらに巧妙なテキスト操作として指摘することができるのである。その布石として導入されていた語が、キリスト教伝説の中の秘跡である筈の“聖杯”であった。このような概念と表象の次元跳躍的連繋の試行は、この哲学的企図に基づくビジュアルゲーム作品における一つの創作戦略となっているようである。
「……サーヴァントはシンボルによって引き寄せられる。強力なサーヴァン
トを呼び出したいのなら、そのサーヴァントに縁のあるモノが必要不可欠な
のだ、かぁ……つまり、そのサーヴァントが持っていた剣とか鎧とか、紋章
とか、そういうとんでもない値打ち物だ。」
召喚魔法の施行に関する重要案件として、対象となるサーヴァント存在との歴史的な意味上の連関を備えた固有の物品の保持が、この魔法の成否に関わるものであるとされているのである。キリストが最後の晩餐の際に口をつけた器である聖杯であるとか、その亡骸を包んだとされる聖骸布とか、さらに延長概念としては磔刑に処されたキリストの掌と足の甲に残された聖痕等が、これと同様の意味的連係を備えた具象物である。ここに示唆されている事物の中に歴史を通して醸成された、通常“機縁”という言葉で理解されている意味性の保持する質料概念との相関あるいはそこから類推される概念と存在のアナロジーを介した原形質的変換記述の可能性は、宇宙の全体性の中で局所性を跳躍した存在物同士における相関として現れる“エンタングルメント”という概念を通じて、空間的断絶の裡にも主張し得る“同一性”の一側面に対する再考察を要求することともなるものだろう。ここに示唆されている物質的延長性を超越した相関性とその基盤にある相当性は、魔法概念の枢軸を形成する基本原理であると共に、人格概念そのものの意義性に関する根幹的検証にもこの後深く関わって来ることになる、『Fate/stay night』の中心主題なのである。
凛の発した次の魔法の呪文は、日本語表記に対してさらに異なった内実の日本語の読み仮名を重ねて配した、概念と記法の二重構造性をことさら強く意識したものとなっている。同一性と相違性の双方が重ね合わせ的に指摘し得る曖昧性の論理空間の中でこそ、魔法の原理はその特質を主張されるのである。
「閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。閉じよ(みたせ)。
繰り返すつどに五度。ただ、満たされる刻を破却する。」
存在と現象と概念の位相変換的相関を多義性の存在論空間の中に切実に模索することを意識した、科学が目を塞いだ/破却した裏の世界の多元的なシステム理論構造である魔法の原理の特質を端的に示唆している記述である。各概念が意味の多元立体空間に浮遊しており、それぞれの概念観の同等性と相当性を決定することになる論理座標軸もまた無数に漂っている。だからある特定の座標軸配置においては、“満たされる”が“破却する”に直裁に連接し得ることとなる。
「―Anfang(セット)」
「……指先から溶けていく。否、指先から満たされていく。取り込むマナが
あまりにも濃密だから、もとからあった肉体の感覚が塗りつぶされていく。
だから、満たされるという事は、同時に破却するという事だ。魔術刻印は術
者であるわたしを補助する為、独自に詠唱を始め、わたしの神経を侵してい
く。取り入れた外気(マナ)は血液に。始めよう。取り入れたマナを“固定化”する為
の魔力へと変換する。視覚が閉ざされる、目前には肉眼で捉えられぬという
第五要素。故に、潰されるのを恐れ、視覚は自ら停止する。」
凛の召喚魔法施行の過程を記述する上の文章において“外気”という日本語表記に添えて振り仮名として配された片仮名表記の“マナ”は、イギリスの宣教師コドリントンによって著書『メラネシア人』の中で報告された、太平洋島嶼において保持されている呪術的概念と重なるものだろう。東洋思想における“気脈”や古代ギリシア哲学における“プネウマ”とも一脈通じるところのあるこの概念は、科学思想が力学として仮定した存在単位としての座標性を備えた質量点相互の局所的作用として措定された“現象”という描像とは、全く相容れないものである。ニュートンの構築した力学的世界観の裡で厳密に定義づけられた存在物と現象という概念を超出する異界面の論理に従った言語体系の許で主張される、世界に漲る“被人格的力”に相当するこの概念は、他の同位体的概念との併置を通してさらにこの仮構世界における“魔法”と魔法使いの関連を暗示する主要概念として、意識存在と客観的物理存在の裡にあるさらなる緊密な関係性を物語ることとなるのである。そのための布石として“固定化”や“第五要素”等の語が用いられている。
引き続いて凛の行う呪文詠唱は、やはりドイツ語表記と日本語表記の併記を用いてその記述が行われている。
「Vertrag(令呪に告げる)….! Ein neuer Nagel(聖杯の規律に従い、) Ein neues Gesetz(この者、我がサーヴァントに) Ein neues Verbrechen(諌めの法を重ね給え)
--」
「―右手に刻まれた印が疼く。三つの令呪。聖杯戦争の要、サーヴァントを
律するという三つの絶対命令権が行使される。」
圧倒的な存在密度と力量を保持する英雄達を、一介の人間存在に過ぎない魔術師がサーヴァントとして使役することを可能にする基本原理が、上に語られた“霊呪”である。東洋神秘思想の裡で“書”や“護符”の中に仮定されていた、形象の中そのものに充填し時に放出することもまた可能な想念との相関を持つ“意味的エネルギー”の存在が、ここに暗示されている。この場面での凛のサーヴァント召喚は半分成功し、半分は失敗に終わるのだが、当初の意図とは異なり未知の要因に従って召喚されてしまった意外な英霊存在である“アーチャー”との会話を通して、次のように“霊呪”という言葉を通して魔術原理の核心と、召喚される英霊存在との間の潜伏した関係が語られることになる。
「……はあ。いいかね。令呪はサーヴァントを強制的に行動させるものだ。
それは“行動を止める”だけでなく、“行動を強化させる”という意味でもある。」
――
「そっか。サーヴァントは聖杯に呼ばれるけど、呼ばれたサーヴァントをこ
の世に留めるのは。」
「そう、マスターの力だ。サーヴァントはマスターからの魔力供給によって
この世に留まる。」
魔術師であるマスターは召喚された英霊であるサーヴァントに対して禁令の権限と彼等の能力促進の権能を同時に持つ訳だが、これらは実は同質のメカニズムに基づく潜在力であるのだろう。マスターはサーヴァントに対して“魔力供給”という概念を用いて語られる特殊な霊的関係性を持つとされているが、この魔力の授受という関係性は、力学的宇宙観による因果関係的能動/受動という構造に束縛されない、現象性を超えたメタレベルでのある種の“同一性”という概念をも示唆することとなるのである。
こうして『Fate/stay night』では魔術師によって召喚された“英霊”、つまり神話・伝説上の英雄的存在達が“サーヴァント”としてマスターである魔術師に仕え、戦いを繰り広げて行くことになる訳だが、ここで興味深いのは召喚の対象となる英霊達の素性である。彼等は、各々がギリシア神話や古代アイルランド神話等の中で活躍した、“英雄”と目されるものであったのだが、それぞれの存在する次元界面が異なっているために、本質属性においては密接な共通性を持つがためにむしろ互いに関わり合いを持つことがあり得ない、独立したキャラクター同士だった。しかしこの『Fate/stay night』という一つの仮構世界の中において、彼等の存在性向を束縛していた次元的断絶が超克され、聖杯を中心とした一つのルールと見通し図のもとに“戦い合う”という関係性を賦与されて、結果的にこれらのキャラクター達を媒介軸として、複数の神話・伝説の世界の統合と融和がなされる結果が招来していることになる。
そればかりでなく、聖杯戦争に召喚された英霊の一人の佐々木小次郎などは、本人が自分が神話や伝説を通して醸成された歴史上の存在とは根本的に異なる、純粋にフィクション作品の中に捏造された一切の現世的実体性を持たない擬似的存在であることを自覚しているのである。このビジュアルノベルにおいては、何らかの歴史的事実を核としてその存在傾向を民衆の想念の中に確定させていた神話・伝説上の存在達に加えて、さらにとりとめの無い個人の空想上の妄想的キャラクターまでもが同一空間に勢揃いして、互いの存在論的意義性を付託し合うことが可能となっていることになる。このような断絶した筈の世界間の跳躍が可能となるメタ可能世界次元として、『Fate/stay night』というフィクション空間を成立せしめている世界の肌理の構成単位、あるいは宇宙論的“場”がいかなる特質を持っているものとして仮定されているのかが、重要な論考の対象とならなければならないはずである。取り分けシステム理論的には、この『Fate/stay night』という伝奇活劇ビジュアルゲームにおけるオリジナルの“英雄”像であるアーチャーの存在までもが、召喚された英霊達の一人として潜伏してさらに付け加えられていることが、見逃すことのできない構造的特質となるのである。
凛パートのプロローグは更に引き続き2日目(2月1日)を迎える。魔法とサーヴァントとの関連が固有の専門用語の導入を通して語られている重要箇所と思われる部分のテキストを、続けて以下に示していくことにしよう。やはり殊に興味深いのが、“英霊”とされるものの存在論的内実を語る独特の概念と、その記述のあり方なのである。
「聖杯に選ばれた魔術師はマスターと呼ばれ、マスターは聖杯の恩恵により
強力な使い魔(サーヴァント)を得る。―――マスターの証は二つ。サーヴァントを召喚し、
それを従わせる事と。サーヴァントを律する、三つの令呪を宿す事だ。
アーチャーを召喚した事で、右手に刻まれた文様。これが令呪。聖杯によっ
てもたらされた聖痕(よちょう)が、サーヴァントを召喚する事によって変化したマスタ
ーの証である。強大な魔力が凝縮された刻印は、永続的な物ではなく瞬間的
な物だ。これは使う事によって失われていく物で、形の通り、一画で一回分
の意味がある。」
ここでは既に導入されていた“聖杯”という語と並んで、“聖痕”というキリスト教神話の中で語られていた特有の概念が導入されているが、そこには“よちょう”という異界面の概念を示すルビが施されている。“予兆”を暗示する振り仮名を配して呼ばれた英霊に対する命令権を具現した“刻印”は、手の甲に記された一つの記号であると共に、時間順序を跳躍して因果関係の顛倒を及ぼす超自然的な力を示唆する、現象性を超越した概念とも連接するものとなっているのである。そのようなプログラム記述を可能にする“場”でもあり、“エーテル”のように全てに充満して世界を満たしている材質/力とされているのが“マナ”であるのだろう。厳密な定義の許に純思弁的な記号記述を行う数学の記法とは対蹠的に、一般言語による暗示的な記法を通して既存の知識と連想の全てを参照しながら、いかなる既存の体系にも束縛されることなく独特の仮構記述を進めることができる、文学的創作技法の極まった手法がここに指摘出来るだろう。
凛のサーヴァントとして現れたアーチャーは、意外なことに本来の自身の素性を忘却してしまっていた。彼の正体である“真名”と彼が凛の召喚に応じることになってしまった隠された因縁と関係性が、このビジュアルノベルというフィクションのミステリー的要素として、さらに人格同一性に関する主題性を掘り下げる鍵となって機能することとなるのである。
「……あいつの記憶が戻るまでまで法具(きりふだ)は封印か……思いだせないんじゃ使いようがないしね。」
この仮構世界の中で採用された、サーヴァントの用いる魔力の籠った特殊な武器である“宝具”に対しては、“きりふだ”という振り仮名が適用されている。“きりふだ”と“宝具”の相当性が認められる概念決定軸は、魔術師の行動原理と英霊存在の属性記述が偶々合致する聖杯戦争という背景の裡において仮定される見通し図の一つである。主題形成上の要点となるルビの使用において統一的な一貫したメカニズムに従うことを避けて多元的なシステム構造を敢えて当て嵌め、自然言語の保持する多義性と曖昧性を見事に参照しながら独特の仮構記述の進展が図られている部分である。魔法概念に関する描写においては、一意的な推論手順に従った線的論理記述とは対蹠的な、言うなれば経路総和法的な過程が意図的に選択されているのである。
現界したサーヴァント存在の現象世界における存在様相は、“霊体”という特異な言葉を用いてその特質の一斑が語られることになっている。
「それも問題ではない。確かに着替える必要はあるが、それは実体化してい
る時だけでね。サーヴァントはもともと霊体だ。非戦闘時には霊体になって
マスターにかける負担を減らす。」
「あ、そっか。召喚されたって英霊は英霊だものね。霊体に肉体を与えるの
はマスターの魔力なんだから、わたしが魔力提供をカットすれば。」
「自然、我々も霊体に戻る。そうなったサーヴァントは守護霊のようなもの
だ。レイラインで繋がっているマスター以外には観測されない。もっとも、
会話程度は出来るから偵察ならば支障はないが」
現象世界にサーヴァントとして発現した英霊の姿は、言わばマスターの存在との相互作用として現象界面に投影された原形質存在の重ね合わせ的位相として理解されるものなのだろう。ここで“霊体”と共に殊更説明手順を弄することなくその概念の媒介軸として用いられた“レイライン”という語は、イギリスのウェールズ地方やフランスのガリア地方等に伝えられる地のエネルギーの“気脈”を呼ぶ“レイライン”(ley line)とは明らかに異なる、“霊”の原存在的連携を暗示する造語となっている。英霊存在の本来の姿であり、また彼等がサーヴァントとなった際に選択し得る位相の一つとして“霊体”という概念を持ち出し、さらにマスターとの関係性を“レイライン”という概念で語ることによって、科学的存在/現象解釈の超出を図ることを可能にする極めて戦略的な記述手法が用いられていることが確認出来るのである。そのような意味で、物理存在とは原理的に異なる“霊体”という言葉で仮称されたものが、既存のいかなる概念連合とどのような関わりを持つものとして読み取り得るのかが、この伝奇活劇ビジュアルノベルをプレイする上での最重要関心事項となるだろう。
英霊存在を周辺から定義づけることになるであろう補足情報を、このゲーム作品はさらにいくつか用意している。
「――――固有結界。魔術師にとって到達点の一つとされる魔術で、魔法に
限りなく近い魔術、と言われている。ここ数百年、“結界”は魔術師を守る防御
陣と相場が決まっている。簡単に言ってしまえば、家に付いている防犯装置
が極悪になったモノだ。もとからある土地・建物に手を加え、外敵から自ら
を守るのが結界。それはあくまで“すでにあるもの”に手を加えるだけの変化
にすぎない。だが、この固有結界というモノは違う。固有結界は、現実を浸
食するイメージである。魔術師の心象世界――心のあり方そのものを形とし
て、現実を塗りつぶす結界を固有結界と呼ぶ。……周囲に意識を伸ばす。精
神で作り上げた糸を敷き詰め、公園中を索敵する。」
サーヴァントが保持する空間を操作する魔術的な能力の成果である“固有結界”についての凛の言葉の、“現実を浸食するイメージである”という部分から、英霊自身の持つ霊体としての存在性と等質の形而上的存在論仮説に基づいた“場”の理論が想定されていることが理解できる。それは敵対的な攻撃に対して防壁を施す、単なる“バリヤー”のような物理的機能とは明らかに異なるものである。ニュートン物理学的3次元空間とは位相を違える、意識との連続体として定義可能な拡張次元空間が、魔術で用いられるという“固有結界” なのであろう。これは重力定数やシュヴァルツシルツ半径等の規定値によって出現が確定するブラックホール等の事象地平現象とはまた異なる、時空と精神の統合体が時に発現し得る想念の一種の概念的相転移を暗示する発想であると思われるものである。あるいはまたこの造語は、科学の世界でも実験の結果として確証されている、物理現象の生成に関与する意識体による“観測効果”の事例を反映した概念として理解することもできるだろう。宇宙に現出する客観的物理現象とされるものの生成における欠かせない要因として、知性を備えた意識存在の関与が仮定されねばならないことは、既に周知の事実になっているからである。観測効果が及ぼされて波束の収束を得る以前の量子的“原存在”は、相反する無数の可能性が互いを打ち消し合っている中和状態にある。このような多義性の原形質“存在”を“現実”の事象として確定させるのが、“コヒーレンス”である。これは高等な知性を備えた意識の干渉という、観測効果による可能性の一部の抽出としてもたらされる。“シュレーディンガーの猫”の名で知られている逸話が、この観測者による原形質への干渉と事象発現のメカニズムの原理を語る著名な例である。効果的な量子的干渉によって具現化した特定の現象的様態が同期性を失って崩壊した状態が、“デコヒーレンス”“と呼ばれるものである。エヴェレットの唱えた“多世界解釈”の発想の発端となった量子存在の多義的特質による重ね合わせ的打ち消し合いという特質と、その数学的記法として採用された全ての可能な運動経路を素粒子である電子の軌跡として仮想的に記述する手法であるファインマンの“歴史総和法”にも多大な影響を与えた原形質次元での量子存在の“不確定性”という認識は、既に多くのエロゲーにおいて様々の優れた仮構的反映が試みられているものである。“魔術師の心象世界――心のあり方そのものを形として、現実を塗りつぶす結界”という表現が、意識が現実世界の具現化に作用する根本原理をさらに踏み込んで導入した、『Fate/stay night』の選んだ文学的記述である。オッカムのウィリアムに代表される直裁な一意的論理至上主義の影響の許に、20世紀に至るまで唯物論的発想と共に唯名論的世界観が支配していたモダニズム的思想状況の後を受けて、ポストモダン以降の特質としてこれに対立する多義性と実念論的発想の復権が強く認められるのが、現在のエロゲー界の趨勢のようである。
続いて凛パート第3日目(2月2日)では、人間存在あるいは英霊を規定する概念の中で、“たましい”と“せいしん”という言葉がいかなる背景のもとに関連づけられているかが、殊に興味深い魔法原理の構造的枠組みを構築するものとなっている。対応すべき歴史上の類例としては、霊的組成において“魂”と“魄”を分別するような形而上的思弁における意識と精神の複合的関係性に対する考察があったことなどを挙げることもできるだろう。あるいはウィリアム・ブレイクの成し遂げた心霊的位相により構築された神話体系として語られた宇宙像を思い浮かべることもできるだろう。世界を物理現象として力学的作用に還元して記述する操作に対する反転的試行として、心霊的作用として全一的宇宙論の構築を企図する方策は様々な表象と仮想的概念を生み出してきたのである。
そのような思惑の許に試みられたと思われる『Fate/stay night』の次の概念操作例は、凛とアーチャーが他の魔術師の仕掛けた攻撃性の固有結界を発見した際の、凛の独白による記述である。
「一時的にこの呪刻(けっかい)から魔力を消す事はできるけど、呪刻(けっかい)そのものを撤去さ
せる事はできない。術者が再びここに魔力を通せば、それだけで呪刻(けっかい)は復活
してしまうだろう。内部の人間から精神力や体力を奪うという結界はある。
けれど、いま学校に張られようとしている結界は別格だ。これは魂食い。結
界内の人間の体を溶かして、滲み出る魂を強引に集める血の血の要塞(ブラッドフォート)に他な
らない。古来、魂というものは扱いが難しい。在るとされ、魔術において必
要な要素と言われているが、魂(それ)を確立させた魔術師は一人しかいない程だ。
魂はあくまで“内容を調べるモノ”、“器に移し替えるモノ”に留まる。それを抜
き出すだけでは飽き足らず、一つの箇所に集めるという事は理解不能だ。だ
って、そんな変換不可能なエネルギーを集めたところで魔術師には使い道が
ない。だから、意味があるとすれば、それは。」
上の記述においては、“呪刻”という漢字表記に“けっかい”という平仮名表記がルビとして添えられているのが興味深い事実である。主観意識にとっては動作目的として措定される対象とその結果をもたらすために選択される手段は概念地平において全く異なるものとなることもあるが、原因と結果あるいは手段と目的に対して超出的に包括的な看取を行い得るメタレベルにおける視点においては、これらは一つの上位概念の許に統合記述の方策を得ることも可能なのである。そのような意味で示唆に富むのは、“魂”に関する「調べる」、「移し替える」、「集めるという事は理解不能」等の具体的記述であろう。奇しくも現代物理学が“エネルギー”という概念を用いて存在物の示し得る様々な様相の位相変換を上位概念による統一記述として語ろうと試みたのと同様の発想で、ここでは“たましい”が物質あるいは“意識”に変換される統合記述を可能にする“エネルギー”の等位概念として用いられ、この仮構世界の魔術的システム機構の核心が言及されていることになる。“光”というエネルギーと同様に“たましい”も“移し替える”ことはできるものの、そのままの形で“蓄積する”ことは想定不能なのである。
次はこの場面に引き続く凛とアーチャーとの会話を通して、英霊存在そのもののシステム理論的特質を示すと思われる基幹情報が、さらに“たましい”という語を軸にして語られている部分である。
「アーチャー。貴方たちってそういうモノ?」
知らず、冷たい声で問いただした。
「……ご推察の通りだ。我々は基本的に霊体だと言っただろう。故に食事は
第二(たましい)、ないし第三(せいしん)要素となる。君たちが肉を栄養とするように、サーヴァン
トは精神と魂を栄養とする。」
“マナ”が先程“第五要素”とされていたのに対応して、“たましい”は“第二要素”、せいしんは“第三要素”とされている。ここでアーチャーによって語られている“霊体”という概念と“たましい”及び“せいしん”という概念をそれぞれ分別しながらも魔法を媒介軸として統括的に記述することを可能にする心霊的“統一理論”の構築が、『Fate/stay night』では極めて野心的な創作戦略として企図されているのである。それは当然のことながら英霊存在の定義を語るのみならず、我々人間存在の人格特性再検証にも深く関わることとなるだろう。現実―仮構統一場における存在・現象・人格同一性を連続的に記述する包括的システム理論が、そこに提示されようとしているからである。
このような認識手順を経ながら、凛は愈々結界消去の魔術を発動させることになる。
地面に描かれた呪刻に近寄り、左腕を差し出す。左腕に刻まれたわたしの魔
術刻印は、遠坂の家系が伝える“魔道書”だ。ぱちん、と意識のスイッチをい
れる。魔術刻印に魔力を通して、結界消去が記されている一節を読み込んで、
あとは一息で発動させるだけ。
「「Abzug(消去) Beldienung(摘出手術) Mittelstnda(第二節)。Es ist gros(軽量). Es ist klein……(重圧)!!」
英霊存在の特有の心霊的位相あるいは超物理的様相を理解する上で重要な鍵となるのが、聖杯戦争のために彼等を召喚する際にその“器”として用いられるという、“クラス”という概念である。“役割”という語に添えられたルビとして、“クラス”という語は導入されている。
サーヴァント。七人のマスターに従う、それぞれ異なった役割(クラス)の使い魔たち。
それは聖杯自身が招き寄せる、英霊と呼ばれる最高位の使い魔だ。
サーヴァントとは、それ自体が既に、魔術の上にある存在(モノ)なのだ。率直に言
おう。サーヴァントとは、過去の英雄そのものである。神話、伝説、寓話、
歴史。真偽問わず、伝承の中で活躍し確固たる存在となった“超人”たちを英
霊という。人々の間で永久不変となった英雄は、死後、人間というカテゴリ
ーから除外されて別の存在に昇格する。……奇跡を行い、人々を救い、偉業
を成し遂げた人間は、生前、ないし死後に英雄として祭り上げられる。そう
して祭り上げられた彼らは、死後に英霊と呼ばれる精霊に昇格し、人間サイ
ドの守護者となる。これは実在の人物であろうが神話上の人物であろうが構
わない。英雄を作り出すのは人々の想念だ。
東坂凛のような魔術師達が用いる“魔術”という“技”の“上位レベル”のものとして、サーヴァントとして召喚可能な“英雄”存在があるというのである。魔法を支配する原理的視点上には動作手段と行動目的対象の間に概念的差異は存在せず、魔術という技法とその行使の結果顕現する英霊は、連続的な“同一”概念の上に配置されたそれぞれの位相なのであろう。ここから理解出来るように“英雄”という概念は、個人の成し遂げた業績や達成などに関する厳密な具体的行為からのみ定義付けられるものではない。本来の人間存在からはむしろ乖離した、“人々の想念”によって形成された願望の集積体である“情報存在”として位置づけられているところに、召喚の対象となる“英霊”存在の特質がある。さらに英雄が人間存在から“除外される”という断絶があると共に“昇格”して“精霊”となるという部分には、存在と概念の間に相転移的な位相跳躍を認めると同時に、確たる“同一性”が連続的に維持されている事実も示唆されているのである。このような人間/英霊存在の位相の類似と相違の内実を語る補助的概念として採用されているのが、上の記述に導入されている“クラス”という一際興味深い語である。
聖杯は英霊たちが形になりやすい“器(クラス)”を設け、器に該当する英霊のみを召
喚させる。予め振り分けられたクラスは七つ。
剣の騎士、セイバー。槍の騎士、ランサー。弓の騎士、アーチャー。騎乗兵、
ライダー。魔術師、キャスター。暗殺者、アサシン。狂戦士、バーサーカー。
この七つのクラスのいずれかの属性を持つ英霊だけが現代に召喚され、マス
ターに従う使い魔――サーヴァントとなる。サーヴァントとは、英雄が死後
に霊格を昇華させ、精霊、聖霊と同格になった者を指す。かつて、竜を殺し
神を殺し、万物に君臨してきた英雄の武器。サーヴァントは自らの魔力を以
てその“宝具”を発動させる。言うなれば魔術と同じだ。サーヴァントたちは、
自らの武器を触媒にして伝説上の破壊を再現する。
観測効果に従って意識体が原形質次元から現象性として確定させた事物を呼び出すように、“聖杯”と呼ばれる魔術の情報集積体は“クラス”として波形を収束させたサーヴァントを抽出する。英霊を呼び出す魔術も呼び出される英霊も、英霊が振るう“宝具”と呼ばれる武器もみな、“同じ”概念の集積体なのである。ならば英霊をサーヴァントとして呼び出し使役するマスターたる魔術師も、やはり“同じ”念積体であるのだろう。そしてそれら全てが無数の意識の主体によって共有される情報でもある。
敵サーヴァントを打破するには、その正体を知ることが近道となる。自分の
正体さえ知らないバカものは例外として、サーヴァントにとって最大の弱点
はその“本名”なのだ。サーヴァントの本名―つまり正体さえ知ってしまえば、
その英霊が“どんな宝具を所有しているか”は大体推測できる為だ。言うまで
もないが、サーヴァントは英霊である以上、確固たる伝説を持っている。そ
れを紐解いてしまえば、能力の大部分を解明する事ができる。サーヴァント
がクラス名で呼ばれるのは、要するに“真名”を隠す為なのだ。なにしろ有名
な英雄ほど、隠し持つ武器や弱点が知れ渡っているんだから。サーヴァント
となった英霊は決して自分の正体を明かさない。サーヴァントの正体を知る
のはそのサーヴァントのマスターのみ。
個別の伝説や仮構世界内部においては、神話や伝説の中に登場する英雄存在の例外的権能や弱点等の特質情報と、さらに彼等の運命を支配した存在特性の秘密に関する知識は、他の大部分の人々にとって未知のものであることが暗黙の了承とされている。しかしこれらの神話・伝説及びそれらを題材にした種々の仮構世界の存在を、文学的素養に関する情報としてむしろ鮮明に弁えているのが、現実の我々の教養的枠組みを成す集合的想念なのである。『Fate/stay night』においては、仮構世界の登場人物達の保持する意識レベルは、この点において現実世界の我々のものと何ら変わることがなく、仮構世界的特例や暗黙の了承を棄却しているという意味で、見事にメタフィクションの要素を具現している。そしてメタフィクションの特質を開示するフィクションは、存在論的位相としては現実世界と“同じ”ものを主張することとなる。
伝説を形成する抽象的な意味情報の集積の具現化したものが英霊であるならば、それは個人存在であると共に様々な人々の想念が醸成した幾多の矛盾を含む概念の複合体である。そのような情報集積体を一定の“器”の中に具象化することが、召喚魔法とされるものの内実なのであった。“器”と呼ばれるものは、その英霊存在達の、聖杯戦争という背景の許で発揮される選別的能力として濾過された特質の具象化である。さらにそれとは別個に、伝説存在が情報として保有する人格的基盤となるべき能力や特質や性向があるとされるというのである。そういう意味では“真名”は、聖杯戦争という背景とサーヴァントという枠組みを持たなくとも英霊存在が本来的に保持する、人格としての原初的な本体的位相ということになる。
そうした英霊存在が根源的に保持する願望あるいは指向が、召喚魔法において“クラス”という器にその情報集積体を移し入れる際のパラメータとなり、願望器である聖杯を勝ち取ることを意図するマスターとなるべき魔術師との精神的同調が行われることとなる。 機縁と指向性において時間と空間の次元的断絶を超えた“同一性”の許に結ばれた意味的関係性を担っているのが、召喚者のマスターとサーヴァントとなる英霊存在なのである。そして取り分け興味深いことは、この伝奇活劇ビジュアルノベルの主人公である衛宮志郎も、彼のライバルとしてあるいはサブヒロインとして重要な役割を果たすことになる東坂凛も、彼等と各々のサーヴァントとして召喚に応じた英霊達との“同調”の内実については、全く無知であったという事実なのである。偶然に凛のサーヴァントとなってしまったアーチャーと、衛宮志郎のサーヴァントとしてあまりにも思いがけなく現れたサーヴァントであるセイバーの“真名”が明らかにされるのは、聖杯戦争の成り行きがかなり展進した、後半になってからのことなのである。召喚魔法には、術者である魔法使い自身の思いの及ばない隠れた選択原理が存在していたのである。
多くの仮構の従う暗黙の了承を破却してメタ仮構的リアリティの構築を目論む『Fate/stay night』では、東坂凛が聖杯戦争に参加した動機とされるものも極めて例外的な判断基準に基づくものとされている。万能の願望器である聖杯を取得すべき根本動機について交わされるアーチャーと凛の会話は、以下に示すようにかなりちぐはぐなものとなっているのである。
「願い?そんなの、別にないけど。」
「――なに?よし、よしんば明確な望みがないのであれば、漠然とした願い
はどうだ。例えば、世界を手にするといった風な。」
「なんで?世界なんてとっくにわたしの物じゃない。
あのね、アーチャー。世界ってのはつまり、自分を中心とした価値観でしょ
?そんなものは生まれたときからわたしの物よ。そんな世界を支配しろっ
ていうんなら、わたしはとっくに世界を支配しているわ。」
凛の語る、手に入れた聖杯に対して要求すべき「願いや野望なんてものは別にない。」という醒めた認識が、かつての伝説を形成した英雄達の保持していた筈の限定的な価値観に束縛されていた世界観とは明らかに異なる、はなはだ現代的な生の感覚をあらわしている。神話や伝説の中で当然のごとく受け入れられて来た王国の再建や聖地の奪還や異教徒の駆逐などの高邁な願望は、残念ながら硬直した価値観に拘束された仮構世界の中の暫定目的ではあり得ても、生身の人間存在の想念を支配する具体的なパースペクティブを構築することはあり得ないのである。次元界面を違えた様々の伝説世界の英雄達が勢揃いする『Fate/stay night』の意識空間は、おそらく我々の生きる現実世界の価値基準を支配している富や地位などの脆弱な疑似原理の制約をも超出するものであるに違いない。神話世界を支配していた戦いの目的や偉業を成し遂げることばかりでなく、現代の産業資本主義の課する競争や達成や保有などの妄想的な暫定原理に対する率直な疑問を提示する、常に反省的な意識がむしろこのビジュアルノベルの基調となっているのである。偉大な業績を成し遂げたとされる“英雄”の蒙る本質的評価と、全方位的真実を備えているとされる筈の“正義”の内実の再検証が、このエロゲーの中心的関心事となっているのである。
凛パートのプロローグの終末は、凛とアーチャーが本編の主人公衛宮志郎のサーヴァントとなった強力な英霊との邂逅を果たす場面によって導かれる。志郎がそうと理解することなく無意識の裡に召喚してしまったサーヴァントであるセイバーが現界する様を、凛の視点から記述したのが以下の文章である。聖杯の持つ魔法の力によって、想念としての意味次元にあった英雄存在が魔術師自身の人格情報を触媒として現実世界に具現する様なのである。
気配が、気配にうち消される。
ランサーというサーヴァントの力の波が、それを上回る力の波に消されてい
く。……瞬間的に爆発したエーテルは幽体であるソレに肉を与え、実体化し
たソレは、ランサーを圧倒するモノとして召喚された。
ここで語られている“エーテル”という語も、“レイライン”や“聖痕”の場合と同様に、既存の内包と外延を持つ周知の概念を敢えて説明無しに異界面の意味性を担わせて導入するという、この作品の独特のレトリック操作を適用したものである。当然この場合のエーテルは、光を伝導する機能を持って全ての空間に充満していると仮定された、相対性理論完成以前に物理学の世界の関心を支配していたあの疑似物質概念とは異なるものだろう。むしろニュートン的宇宙論の提示した絶対真空空間に浮遊する質量点としての存在単位という基本発想以前に神学者達によって採用されていた、この世の存在物を構成する“コーポーリアル体”に対して天使や霊魂等を組成する非物質的別存在様態を示す材質として構想された“アストラル体”などの概念に近接するものを持つのが、ここで用いられている“エーテル”なのであろう。
アーチャーと遠坂凛は、いきなり姿を現した志郎のサーヴァントのセイバーに瞬時に切り伏せられて、ここでバッドエンドを迎えてしまうことになるのだが、『Fate/stay night』のヒロインとして中心的役割を占めるセイバーの凄みを持つサーヴァントとしての印象を敢えて外的視点から描き出すことに役立っていたのが、東坂凛を中心にしたこのプロローグであった。さらに、魔術師としての専門的知識を持つ遠坂凛の観点からストーリーの承前を描いたプロローグパートは、魔法という主題に関してかなり複雑な裏設定のあるこのゲーム世界を解説するマニュアルの役割を果たしていたようでもある。しかし実はプロローグであると同時に、本編として凛パートでゲームを進めた場合の、バッドエンドとしてゲームオーバーという結末を迎えなければならない一つの選択肢としても理解できるのが、ここまでの進行なのであった。
16:04:50 |
antifantasy2 |
No comments |
TrackBacks