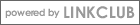Complete text -- "『エルゴ・プラクシー』論 2"
23 September
『エルゴ・プラクシー』論 2
省察3「無への跳躍」では、怪物との遭遇からロムドのシステムの根幹的矛盾に気付いたリルの処置に関して、執国の4体のオートレーブ達が協議を行う。 「勘が鋭敏すぎるのだ。」/「全く、誰に似たのかしら。」/「市民は全て並列化された情報を雛形にしている。局所的近似値には何の意味もない。」/「やはり情報局などには配属すべきではなかったのだ。」/「いや、教育的観点から考えても適切な判断だった。」/「その証拠に、市民レベルとしては最高の感受性を保持している。」/「素晴らしい結果だ。」/「しかし、そこから派生する行動力こそが元凶だ。」/「元凶というならば警備局はどうだ。」/「案ずることはない。あれだけ念押ししたのだ。」/「いずれにせよ、このロムドが揺らいでいることは否定できない。」/「一刻も早く事態の解決に向けた迅速な措置を。でなければ。」/「レゾン・デートルの崩壊。」ロムド・シティのような高度に統制されたシステムを管理する主体からすれば、システムの構造もシステムに含まれる構成要素の保持する位相も、可能な限り簡略化された一元的なものに収束させることができるほど、“管理”の作業自体は効率的となり、努力目標の達成は容易に、そして仕事内容に対する評価もより望ましいものとなる。親や学校や文部科学省や国家等が、子や生徒や学校や国民を“並列化”したがるのはこのような力学的要因が働いているためなのだと推測できる。しかしそのような並列化行程が極度に押し進められたシステム全体は、柔軟性(感受性)に乏しく、システム自体の改変を自立的に行うことを妨げるばかりか、システム全体に関わる突発的異変が生起した場合には、その危機対応能力は極端に低いものとなってしまうだろう。しかし管理体制は、管理システム外の干渉や影響を全て望ましくない排除すべきものとして認識するであろうから、このような内部のシステム改変的要因を無視するばかりでなく、むしろ危険分子として抹殺する方向に動くことが予想される。ここに見たような力学的作用の結果の典型例を、外部の“荒れ地”構造から隔絶された自律系である“ドーム”の構築として理解することができるだろう。“科学”や“理性”や“コスモス”などの概念も、様々な位相においてこの“ドーム”システムの相関物として理解することが可能なものとなる。ドーム外環境である“荒れ地”や“カオス”への脱出あるいはこれらのドーム内部への“侵蝕”に相当する現象と思われるものは、既存の概念や歴史的事実の中からも様々に指摘して検証することができる筈なのである。
ヘイフリック限界を失った癌細胞は、母体の生命機構の維持を顧みない自身の増殖を新たなレゾン・デートルとして選択し、無限増殖を基本原理として肥大化していくが、母体となる生命体の個体死と共に栄養の供給を絶たれ、本性的に予期し得ない筈の死を迎えることになる。プログラムとして“死”の要素を全く組み込まれていない存在は、システム外の要因である“死”の到来を予測することができないのである。同様にカオスを取り込み融和することを原理的に拒否する整合的な自立的プログラムは、バグとしてのカオスの排除に自身のレゾン・デートルを集中させることとなり、却って自律システムとしての飽和点への進行を加速することとなるだろう。 システムのこのような傾向は、社会組織の管理を行う者においてはしばしば芸術の最も感受性に訴えかける要素であるエロティシズムやグロテスクやナンセンスの部分に対する迫害という行為を招来するものとなる。システムが自身の安定を保障するために内部機構の並列化を進行させる過程では、個別的な生のエネルギーの奔出である“エロ”と、規格化され得ないあるがままの現実の実体を暴いた結果現出する“グロ”と、規範の抱え込む内部矛盾を暴いて嘲笑する“ナンセンス”の要素の排除が優先して実行されることとなる。市民としての権利を既得権として保持する高等遊民だけは、システム内自由を行使して“文化”や“芸術”の名の下に実体はエロ・グロ・ナンセンスと何ら変わることのない選別知識と占有快楽を特権的に享受することができるが、未だ市民権を得るに至っていない外部世界からの移民あるいは組織構成員末端の未成年者達は、市民として認知されるための条件を充当するために、倫理的に“正しい人”になろうとする努力を自覚的に差し止めてまでも、システムに対する屈服と迎合の身振りとして自らの感受性を封印し、社会的な“良い子”を演じ続けねばならないことになる。一方このような矛盾に満ちたドーム社会の実態をあるがままの姿で視認することができる“感受性”をあまりにも豊かに保持する構成員は、危険分子として保護観察の対象とされてしまうこととなるだろう。人間の構築する“社会”と“教育”と“管理”と呼ばれているものの実体を語る一つの指標が“並列化”である。
下級市民ヴィンセントは身に覚えの無いオートレーブ殺害の嫌疑をかけられ、官警に追われてロムド・シティから逃亡せざるを得ないこととなる。省察4「未来詠み、未来黄泉」では、ドーム外部のコミューンの住民フーディは、ロムドから脱出してドーム外部世界に蔓延しているウィルスに感染した移民ヴィンセントの看病をしながら、カルカソンヌの詩人・ジョー・ブスケの詩を朗読している。ロムドでの悲惨な記憶を辿りながらうなされるヴィンセントの耳に、フーディの声が聞こえてくる。「そこにあるあらゆるものは、町でも教会でも川でも、色彩でも光でも影でもなかった。」/「私はしばしば、身動きもせず、このえも言われぬ大きな海峡や大空の晴朗さやこの時刻のメランコリーが心地よく体に染み渡っていくのを感じていた。」/「それは、夢想であった。」/「私の精神の中で何が起こったのか分からないし、それを言う術を持たないが、それは自分の中で何かが眠ってしまって、また何かが目覚めたと感じる、筆舌に尽くし難い瞬間なのであった。」/「彼から生まれた世界の中で、人はどんなものにでもなることができた。」この言葉は本作品の採用した意識体の存在原理を示唆して極めて暗示的なものとなっている。現象と存在が分離する以前の原存在に対する超越的知覚とも言うべきものが語られている。フーディがその詩を朗読しているジョー・ブスケとは、第1次大戦で彼に半身不随という苦難をもたらした傷について、「“傷”は自分の存在以前にもともと有り、自分という存在がその傷を具現した。」という啓示的な言葉を語った詩人であった。そこには現象世界を支配する因果関係を超出する直観が語られている。社会制度と心霊存在の本質を追究した哲学者ドゥールーズは、その著書『意味の論理学』の一章「できごとについて」でジョー・ブスケを取り上げ、“できごと”と“存在”の関係に関する独特の哲学的考察を展開している。ドゥールーズによれば“深層”である身体と“表層”である記号的概念が、“私”という意識存在において結びつくことによって“具体化”されると考えられていた。
ロムド・シティの厚生管理を司る科学者デダルスの補佐を務める2体のアントラージュは、ドゥールーズとガタリという名を与えられている。ガタリは精神病理学者として、フロイト的な精神分析とは異なる環境全体を視野に入れた心霊解釈を追求した人物である。ドゥールーズとガタリは、資本主義と分裂病に関する論考を行った『アンチ・オイディプス』と『千のプラトー』の二部作を共著で残している。ジョー・ブスケが彼の詩に描いた宇宙との合一感覚について超越的な霊的認識についての論考を行った哲学者ドゥールーズと、彼と共に現象学的検証と著述を行った精神分析医ガタリの名がさりげなく背後で関連をなしている。仮構中の客観的なストーリーの進行とは直接の関連を持たない、観客の知的反芻作用においてのみ特有の意味を形成する概念の重ね合わせ操作が、このアニメ作品の追求する仮構的内実となっている。ロムドにある秘匿された真実の存在を嗅ぎ付け、その鍵となる人物としてヴィンセントの後を追ってきたリルも外部世界のウィルスに感染し、ロムドに送り返されることとなるが、オートレーブ達の“コギト・ウィルス”感染と、人間であるヴィンセントとリルが人の住み得ない環境とされていたドーム外部への脱出の結果被ったウィルス感染が、観念的対照を目論んで併置されているのである。
ドーム外部のコミューンで生活をしていた女クィーンによれば、フーディーは“センツォン・トトクティン”と呼ばれる乗り物を隠し持っているという。“センツォン・トトクティン”とは直訳すれば“400羽の兎”だが、アズテク神話によれば神々の一群を呼ぶ言葉でもあり、彼等は聖なる兎であると共に酩酊の神でもあったという。“酩酊状態”という言葉が暗示するように、これらの神々は様々の異なる風俗や気質を備えた、無数の姿を取り得る集合的存在であった。古代のアズテク文明の人々はこれらの神々を祀るために、彼等の首都テノクティテュランの近傍に寺院を奉ったとされている。これに相応すると思われる古代ローマ神話の酩酊の神バッカスは、ギリシア神話のディオニュソスに該当する神であり、コスモス内秩序の代表者であるアポロの象徴する理性に対する“反理性”あるいは“カオス”を体現するものであった。理性による整然とした概念的把握を可能とする意味性の一対一対応を破綻させ、多義性の“重ね合わせ”的意味/存在解釈を示唆するディオニュソスの神は、宇宙の根底にあってアポロの理性支配の背後に滲出する原存在の保持する不気味な基幹原理を代表していたのである。逃亡したヴィンセントと行動を共にすることになった感染オートレーブ・ピノが読んでいた『不思議の国のアリス』に登場する“三月兎”(March hare)は、春の訪れと共に繁殖期を迎えた兎達の狂気の様を呼ぶ言葉だが、酒による狂気と薬物による狂気は古代より宗教儀式に欠かせないものであった。しかし着ぐるみにすっぽり身を包んで兎の姿を真似ているピノは人工知能なので、フーディのような口から出任せや、想像力によるインスピレーション的創作行為は不可能である。ここには外形と呼称に表された兎のイメージを接点として、神話や宗教や人間心理のそれぞれにまたがる心霊存在の根源的様相が掘り起こされようとしている。シェイクスピア的な劇的状況が巧みな映像表現を用いて表象化の操作を加えられている省察5「召喚」においては、ハーマン・メルヴィルの“鯨学”の例にも似た衒学趣味的考証という形を模して兎を巡る“省察”がなされているところに、この作品の観念遊戯と表象造形に集約された独特の創作理念を読み取ることができるのである。オートレーブのピノには、生き物の死が理解できていない。コミューンの少年ティモシーが死んだことを伝えられたピノは言う。「もう一個ティモシーいないかなって。」工業生産物であるピノにとっては、同一存在が複数あることが当たり前のことである。しかし人工知能ピノにとっての偏った個体認識と思われるものは、この物語の主題のさらなる展開とともにむしろ物語の中心命題と目されるものであることが判明する。
17:07:54 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック