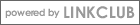Complete text -- "“私”と“世界”と仮構/魔法─ペルソナと時空の等価原理 4"
19 October
“私”と“世界”と仮構/魔法─ペルソナと時空の等価原理 4
かくして賢治にとっては、言葉と想いを用いて交響曲的な世界の意味の連鎖に没入し、そして自らの手によって外挿的にその世界を調律する試みが、紛れもなく科学と宗教の共通目的となるべきものとして芸術的生に連接することができていた。このような宇宙的オーケストレーションへの全人格的参入行為こそが、賢治の宣言にある“詩と科学と宗教を一つのものに”統合して観測/記述/創作行為を行う営み、すなわち“心象スケッチ”なのであった。他者の救済のために行う個人としての自己犠牲の行為につきまとうパラドクス(9)と個別的存在性の引きずる因果関係的限界のディレムマを解消し、この誠心からの根源的願望を補完し代替する方途を約束したのが、賢治の出会った新しい科学、相対性理論と量子論理だったのである。だからこそ賢治にとっては、音声のみならず観念と概念と、そして材質や属性すら自在に“オノマトピーア”(擬音)に変換する術、すなわちしばしば魔法の究極の原理とされる“メタモルフォシス”を具現する操作が、確かに存在し得ていたのである。賢治が“科学”という言葉を用いて語った理想郷の夢想を通して垣間見ることのできるものは、20世紀に隆盛を極めることとなった科学的応用技術の成果による物質的豊かさとは全く異なったものだったのである。70年代以降アメリカを舞台として、芸術作品の特異な表現行為として仮構世界の中から現実世界に対する浸透を企図したアクチュアリズ厶の手法が隆盛を極めたが、アクチュアリティの芸術と生の先駆的な実践者が、実は1920年代の日本に既に存在していたのであった。機械論的自然観の束縛を持たない言の葉の生きる国日本の、仮構と現実の融合を果たすばかりではなく、全体性の宇宙と仮象としての個である“わたくし”の融合を夢想する実践的アクチュアリストが宮沢賢治だったのである。そして宮澤賢治にとっての“詩と科学と宗教”の統合体であったものに見事に照応するものとして、現代アメリカのファンタシーの形而上詩人ピーター・S・ビーグルの『最後のユニコーン』においては、“魔法”という主題が独特の意味性を担って導入されていたことは、ことさら興味深い事実だと思われるのである。
『最後のユニコーン』においては、知性と意識を備えた観測者の関与によって始めて現象を収束する宇宙の基幹的原理機構である観測効果と全く同様の機構に基づいて、魔法は人々の願望と心の渇望に照応して生起せしめられていたのであった。日常の感覚を超えた怪物の異形の姿を目にすることを欲する観客達の欲求を核として、神話と伝説の世界の超越的存在達の姿を具現化させて見せていた、ミッドナイト・カーニバルの魔女マミー・フォルチュナの駆使する魔法がそうであった。魔法使いシュメンドリックもまた同様に彼女のこの手法に倣って、伝説の義賊ロビン・フッドに対する森の盗賊達の憧憬の念を軸として、光り輝く永遠性の幻影を招来することに成功したのであった。人々の霊的位相の一様相である願望を掬い採り、その照応物である非在性の幻影を永遠性の投影として現象世界に顕現させることを試みたマミー・フォルチュナとシュメンドリックの魔法の技の施行は、反転的には自らの保持する意図を全面的に放棄することによって宇宙の運行規則に身を委ねることを選択した魔法使いの心霊を反映しもして、その折々のあるべき姿を自在に選んで具現化するのであった。これらの量子的ゆらぎにも似て時としてあらわれまた時として去っていく魔法の力の発現は、しばしば言葉の“意味”と“発声”を媒介として具現化し、またその効果は見事に音楽に位相変換して語られることとなっていたのであった。存在物の階梯とその意味の限りない変容と、そしてその変化の反映する宇宙の根源的な意義性を例証すべく行使されるのが、このお話の中で魔法使いの用いる魔法の技なのであった。だからこそこの辛辣なお伽話の中で、しばしば魔法の力の発効が失敗に終わった際に、破綻した言葉の意味連関の図式が強調して語られているのは、反転的に理性の限界を超えた宇宙の根幹にあるこの峻厳なシステム理論の核心を突いているのである。
その好例の一つとして挙げられるのが、キャプテン・カリーの手下のみすぼらしい盗賊達を観客として、魔法使いシュメンドリックが無様に奇術/魔法(magic)の技を失敗してしまう場面の記述である。
They applauded his ring and scarves, his ears full of goldfish and aces, with a proper politeness but without wonder. Offering no true magic, he drew no magic back from them; and when a spell failed―as when, promising to turn a duck into a duke for them to rob, he produced a handful of duke cherries―he was clapped just as kindly and vacantly as though he had succeeded. They were a perfect audience.
p. 73
盗賊達はシュメンドリックの指輪とハンカチを使った手品に歓声をあげた。金魚とトランプが耳から溢れて飛び出す手品をはやし立てたが、それはいかにも儀礼的なもので、本当の感動を得た様子はなかった。本物の魔法を提供することが出来ないものだから、観客の方から魔法を引き出すことも出来ないのだった。そしてシュメンドリックが盗賊達に、アヒル(ダック)を公爵(デューク)に変身させて略奪させてやると約束しておきながら、実際に出してみせたのが一握りのサクランボ(デューク・チェリー)だった時も、この手品の出来が上々であったかのように、優しくはあるが心のこもらない拍手を返されたのであった。彼等は観客としては完璧だった。
本来ならば根源的な意味性自体に作用する筈の魔法の技があえなく失敗に終わってしまった時には、言葉の音韻の類比のみによる不恰好な換喩に変形して、その効果はみっともなく脱臼した形で具現化してしまうのであった。そしてまた魔法は、かける施術者とかけられる被施術者の双方の精神の感応による、はなはだ微妙な相互作用でもあった。本源的な意味中核と心霊との同調がなされた時にのみ、魔法は顕現してその霊妙な芸術的効果を発揮するのである。だから真の魔法の力の発現を得るに至らない、外殻からの魔法の本質への言及がつたなく行われる際には、記号としての語の外見上の相似にのみ縮退したいびつな形、すなわち破綻した換喩へと誤認されてしまうこととなるのである。これと全く同等の意味と言葉の間にある繊細な関係の魔術的原理を示すもう一つの変化形の例が、未完成の魔法使いであるシュメンドリックが、卓越した魔法の使い手である彼の師のナイコスの振るう真の魔法の力を語ろうとした際に用いられた言葉の選択にも見てとれるのである。
As a child I was apprenticed to the mightiest magician of all, the great Nikos, whom I have spoken of before. But even Nikos, who could turn cats into cattle, snowflakes into snowdrops, and unicorns into men, could not change me into so much as a carnival cardsharp.
p. 119
子供の頃僕は、前にもお話ししたことのある最も卓越した最高の魔法使いナイコスの許で修業をしていました。でも猫(cat)を牛(cattle)に、雪のかけら(snowflake)をスノードロップ(snowdrop)に、そしてユニコーンを人間に変えることさえできるナイコスでさえ、僕をサーカスの客寄せの奇術師以上のものに変えることはできませんでした。
本来の理想的な励起状態においては意味と実質そのものの変成を成し遂げる筈の魔法も、不十分な把握をしか得られない未熟な術者あるいは話者にとっては、事物本来の内実から乖離した不完全な記号に過ぎない言葉の表面的な類比をたどるという形に縮退して収束せざるを得ないのである。これと全く同等の深遠な魔法のシステム機構における脱落した意味性の言語表象の例が、やはり魔法の技については素人のモリー・グルーの口によっても語られることになっていたのであった。
“I know why you did it too. You can’t become mortal yourself until you change her back again. Isn’t that it? You don’t care what happens to her, or to the others, just as long as you become a real magician at last. Isn’t that it? Well, you’ll never be a real magician, even if you change the Bull into a bullfrog, because it’s still just a trick when you do it. You don’t care about anything but magic, and what kind of magician is that?
p. 186
「そして私は、どうしてあんたがリア王子にそうするように仕向けたのか分かる。あんたはアマルシア姫をもう一度ユニコーンの姿に戻すまでは、不死の呪いから逃れることはできないんだ。そうじゃないのかい?あんたはアマルシア姫がどんな目に遭おうが知った事じゃないし、他の誰のことだって同じなんだ。自分が本物の魔法使いになれさえすれば、それでいいんだ。そうでしょ。でもね、あんたは決して本物の魔法使いなんかにはなれはしないよ。あんたがレッド・ブルをウシガエル(ブルフロッグ)に変身させようがね。あんたに出来るのはごまかしの技だけさ。あんたには魔法のこと以外はどうだっていいんだ。でもそんな魔法使いが一体何だっていうんだろうね。」
いかにもグロテスクな未熟な言葉の類比は、低質の駄洒落以上の効果をあげることはない。しかしこれらの意味の飛躍が真の魔法の発現として成功に導かれた際には、その結果はしばしば現象世界の限界を跳躍する“非在性の比喩”として結実し、見事に意味の変成を成し遂げると共に、現象性を脱却して即物的意味を消却した、永遠性の一様相である音楽を暗示する言葉に変換して語られることとなっているのである。その時こそが言葉を通じて啓示的な“謎”の成立が得られる奇跡的な一瞬となる。
魔女マミー・フォルチュナは、自身の持つ強大な魔法の力を誇り、真実の存在であるハーピーを是が非でも支配する確固たる意志があることを高らかに宣言して語るのである。その自暴自棄の確信の裡には、宇宙の本源のエネルギーである魔法の根本原理と霊的存在の保持する可能性との照応を希求する彼女の切実な意思が反映されている。
“I can turn her into wind if she escapes, or into snow, or into seven notes of music. But I choose to keep her. No other witch in the world holds a harpy captive, and none ever will. ...”
p. 35
「あのハーピーが逃げ出しでもしたなら、風にでも、雪にでも、あるいは音階の七つの音にでも変えてやることができるよ。逃げさせてなんかやりはしないよ。他のどの魔女だって、ハーピーを虜にすることができたものはいなかった。そしてこれからだって、そんなことができるものは、他に誰一人いはしないだろう。…」
この醜い邪悪な魔女は、真実の存在であるユニコーンが思わず“She knows more than she knows she knows.”(あの魔女は自分で知っていると知っている以上に知っている。)と望外の感銘を受けて語るように、現象性の限界を超えた不思議な能力を備えた存在なのである。彼女が上で語った魔法の内実は、音楽との接点を備えている点において真言と連接するのである。おそらくは具象性の醜い束縛を持たない純粋な意味と形象の複合体である音楽こそが、偽りの意味を指示する人間達の言葉の限界性を超えて、宇宙の根幹にある実質としての真の意味とその正しい変容を図る技であるメタモルフォシスの原理にもっとも近接した効果をうながす、意識体における知と実在的存在物の媒体となるべき、根幹的の意義性の反映物となるものだからである。だから、ようやく真実の魔法の力を得た魔法使いシュメンドリックが、始めて自信に溢れて魔法を実際に使ってみせる場面もまた、見事に音楽のイメージを用いて以下のように描かれているのである。
He touched Molly as well, said something that was more of a whistle than a word, and the three of them floated up the air like milkweed plumes to the top of the cliff. Molly was not frightened. The magic lifted her as gently as though she were a note of music and it were singing her.
p. 200
シュメンドリックはモリーにも手を触れ、言葉というよりは口笛のようなものを一言ささやいた。すると3人共ミルクウィードの綿毛のように宙を舞って崖の上まで昇っていった。モリーは怖さを感じることもなかった。魔法はあたかも彼女が音楽の音色の一つで、その魔法が彼女のことを歌に歌っているかのようにやさしく彼女の体を持ち上げたのだった。
魔法はかける術者とかけられる被施術者の双方の精神の感応による相互作用であり、これら双方の霊的位相の共和の具現化でもあるからこそ、魔法に関する知識と理解を持たないモリーにも、上のような形で音楽という表象を通してその類い稀なる来訪を関知させたのである。このような形で意識体の各々の霊性の一部に感応するものとして語られているところに、このお話の魔法の切実な意義がある。
そしてまた、ユニコーンやハーピーの存在自体が魔法そのものであったように、人間存在の知覚やその構想する概念とは全く異質の様相における魔法の潜勢力の発現は、無意識を仲介して饒舌な予言を語る蝶の発話としてあらわれることともなれば、人間存在と神的存在の双方に関与して気まぐれに謎の言葉をつぶやく、正体不明の猫の姿を取って現象界での具象性を選択することともなる。意識と言葉と音楽の様々のペルソナ変換を通して具現する根本原理として、魔法使いや魔女やユニコーンを代表とする超越的存在達の体現する魔法の姿が、このお伽噺には描き出されているのである。こうして魔法は芸術ともなり、宗教ともなり、最高の知的活動ともなり、しばしば至高のエンターテインメントともなる。
結局は『最後のユニコーン』における魔法は、ストレールがアクチュアリズムの文学の特徴的な機能としてこの上なく適切に語っていたように、芸術の神髄を精製したものとなり、「動的な力として相互関連を行う文化の場に関与」し、さらに“仮構組織体”として「アクチュアリティを参照し、物理学・心理学・言語学・哲学・数学・社会学その他多数を含む、相互関連を行う巨大な談話の網状組織の一部となり、これらは様々な角度から結合して、反応を返しているその時すらも人間の創造的談話能力に制約を加えている外的世界に対する熟慮を可能に」する役割を見事に果たしているのである。
『最後のユニコーン』という仮構世界の基底には、魔法を軸として宇宙に共鳴する静謐な惑星の音楽が響いている。ビーグルはポストモダニズムを予兆するメタフィクションの機構をいち早く作品世界中に取り入れ、量子理論の示唆するアクチュアリズ厶の世界感覚を見事に創作行為の中に反映させているが、このあまりにも品格に優れた詩人は、後に多くの例が示したようなポストモダニズム的堕落とは無縁の、むしろピタゴラス学派やスコラ哲学の世界の方により近接していると思われる、古典的な雅味と風趣に富んだ孤高の芸術家なのである。カオスに野放図に身を任せてグロテスクな悪夢を呼び起こす猥雑な感覚は、ビーグルの澄明な精神世界の裡には全く見られない。ストレールがポストモダンの仮構のカオス的様相を示す特徴的傾向として語ったような、“…postmodern fiction becomes a tainted-glass window through which nothing is visible”(ポストモダンの作品は何も透かして見ることができない色つきのガラスとなる)というような霊性の混濁を示す要素は、ビーグルとは無縁のものである。清澄なコスモスと無味無臭のカオスの双方を豊かに同調させ、優れて反射的な手法に従ってアクチュアリズ厶と魔法と神話を題材に織り込んだ、古典的で高雅な“アンチ・コスモス”のお伽話がそこには展開している。決して荘重を気取ったり重厚を装ったりすることがない、苦さと甘さが綯い交ぜになった諧謔と風雅の混淆の世界が、紛れもなく『最後のユニコーン』を現代の古典になさしめているのである。ビーグルの用いた皮肉と風刺に満ちたbitter-sweetなお伽話作法は、新鮮で純朴なファンタシーを語りながら、同時に辛辣で痛烈なアンチファンタシーの磁場をも展開することに成功しているのである。『ピーターとウェンディ』のキャプテン・フックも『最後のユニコーン』のハガード王も、いかにもニーチェ的な自我に固着した意志を備えた苛烈な実存の探究者であった。しかしこれらの人物の愚かしくも崇高な破滅を反射的な陰影を交えて描き出す、徹頭徹尾アイロニカルではありながら、しかも意味の喪失に陥り切ることのない健全で柔軟な精神は、キルケゴール的実存の裡にあった篤実な信仰とある意味で等価的ものさえも感じさせるのである。そこにはパルメニデスの「有るものは有る、無いものは無い」、という主張の“有無”に関する一見あっけらかんとした常識主義を装ったエクリチュールを通して語られた、実は深遠な神秘主義的洞察と根源的には等質の、思索と仮構を記述する術の裡にある曖昧性と多義性に対する深い反省的洞察が潜んでいるからである。信仰ばかりでなくニヒリズムの自覚さえも失った霊性喪失の時代に、人々の集合的無意識が渇望する意識の表層からは失われた喪失感覚を満たしてくれる、重要な補完物としての影の世界の反世界と反自分に相当するのがユニコーンであり、魔法だったのである。このような反射的自覚が伸びやかに無意識に連接するその限りにおいて始めて、存在と思惟の一致という奇跡がなされ得るのである。時代を先取りするかのような斬新な仮構記述手法に見られた卓越したレトリック感覚と共に、他の何よりも古い時間性と永遠性の分離以前の全体性の霊的位格の記憶を蘇らせてくれるのが、ビーグルの描いたこの辛口のお伽話なのであった。そのような意味でビーグルはやはり、バリがそうであったように、アクチュアリズム以前の作家であり、その希有な詩人としての資質が、アクチュアリズ厶を作中の主要な題材として採用することを、アクチュアリズ厶の生成に先立って可能にしていたのである。
ジェイムズ・バリの時代、20世紀初頭の科学の進展と宇宙観の革新によって導かれた哲学的/形而上学的洞察の深化は、かつて歴史上存在し得なかった程の人類の優れた超越思考の基盤を形成していた筈であったが、これも第一次世界大戦後、1920年代から急速に発展したアメリカの大量消費文化と、引き続き勃発した第2次世界大戦による思想的・社会的混乱に覆い尽くされ、その優れた希有な内実が壊滅的な損壊を受けて見失われ、結局は見事に忘れ去られることとなってしまったのであった。20世紀におけるアメリカ帝国の無知主義による世界支配の始まりであった。しかしながら実は、ビーグルを生み出した20世紀後半におけるアメリカは、ディズニー・ランドやハリウッド映画に代表される圧倒的な無知の蔓延とは裏腹に、むしろおそらくその文化的腐敗の極みの故にこそ、分極生成という宇宙の原理的特質に見事に照応して、科学とポスト科学と魔法と非在を見事に綯い交ぜて語る豊かな形而上的フィクションをも創出する、類い稀なる新しい知の皇国へと変容してもいたのだった。とはいえそこに得られた高邁な知と感覚の洗練と、アイロニーに満ちた卓越した思想的遊戯性も、それらを実際にそのようなものとして観測し、把握する術を持たないPTAや教育委員会的に膠着した貧しい意識の主体にとっては、逆に貧困極まりない低劣な俗悪主義そのものに紛れもなく変質させられてしまうことになるのである。『最後のユニコーン』は現代の様々なサブカルチャーやオタク文化と共に、趣味と教養と豊かな想念をかろうじて世界に繋ぎ止めることを可能にするか、あるいはそのようなものはそもそも最初から無かったことにしてしまうかを決定する、いくつもの“私”の心の中の試金石なのである。宮澤賢治が心象スケッチを通して見事に実人生を生きてみせたのとは裏腹に、一方では断絶への深い絶望にかられたハガード王が語る、以下のような峻厳な哀しい真実があるからだ。
In a moment I will have forgotten you quite entirely, and will never be able to remember just what I did with you. What I forget not only ceases to exists, but never really existed in the first place.”
pp. 127-8
お前達のことなど、儂はすぐさま忘れ去ってしまっていることだろう。そしてお前達と何を語らったかなど、決して思い出すことはあるまい。儂が忘れてしまったことは、存在することを止めてしまうばかりではなく、最初からありもしなかったことになってしまうのだ。
22:15:28 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック