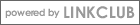Complete text -- "量子論理とパラドクスと不可能世界─アクチュアリズムとアンチ・ファンタシー2"
19 November
量子論理とパラドクスと不可能世界─アクチュアリズムとアンチ・ファンタシー2
ここに確認した大まかな年表上の経緯からも、1911年刊行の『ピーターとウェンディ』が、明らかに量子理論の完成に先立って、その独特の世界観と記述手法の完成に導かれていた事実が読み取れるだろう。
さらに、これらの科学史上の重要事件の周囲にあったと思われる哲学的論議の経緯について、今度はハイゼンベルグの『量子力学の哲学』(Physics And Philosophy, 1958)に焦点を当てて改めて追い直してみることにしよう。宇宙論と心理学を一つの連続体として捉える統括的な視点を保持する哲学者としてのハイゼンベルグは、本書においては“リアリズム”という概念に対する再検証の作業を行って、“実際的なリアリズム”、“独断的なリアリズム”、“形而上学的なリアリズム”などの呼称を採用し、むしろある意味で文学的なリアリズム解釈ともいえる論議をも展開することとなっている。その過程で、ニュートン以前にあった既存の宇宙論的観念の内実の再評価もが、確実に行われていくこととなるのである。例えば、マックス・ボルンの提唱した“確率波”という概念については、ハイゼンベルグはアリストテレスの唱えた“ポテンツィア”という概念を掘り起こして、以下のように語ることとなるのである。
(確率波は)アリストテレスの哲学における昔の「ポテンツィア(潜勢力)」の概念の量的な表現である。それは事象についての観念と現実の事象との中間にある或るもので、まさに可能性とリアリティとのちょうど中間にある、奇妙な一種の物理的リアリティである。
p. 16
このように、主として科学の領域から沸き上がったと思われていた実在解釈に関する議論を、ハイゼンベルグが見事に哲学的観点から捉え直してその意義性の再構築を果たしていることは、とりわけ注目に値する事実なのである。本来は数学屋であったアインシュタインが『特殊及び一般相対性理論について』(1916年)において哲学的に語ろうとして及ばなかった部分を、このバランス感覚に優れた教養人が、見事に補完することができていると思われるからである。こうしてハイゼンベルグは、デカルト批判、カントの空間論についての検証、マクスウェルの電磁気理論、マイケルソン・モーリーのエーテル検出実験、カントの先験論、ボー厶の配位空間と“リアル” 等を振り返り、アリストテレスの“質料”やデカルトの提示していた“物質”の概念を検証し、さらに“四次元多様体”という概念の提示による新規の実在解釈や、アンリ・ポアンカレやジョージ・フィッツジェラルド等の成し遂げた数学的業績を的確に勘案して、以下に示されたような相対性理論の提示する重大な哲学的課題に対する対処のあり方を、様々に模索しているのである。
同じ概念または言葉が二つのちがった組に現れるとき、そうしてそれら互いの関連や数学的表現について、ちがった形で定義されているとすれば、とういう意味で概念はリアリティを表しうるのであろうかという問題である。
p. 86
ハイゼンベルグがここに語っているように、この問題は特殊相対性理論が発表されたと同時に、当時の知識人達の心中に即座に発生したのであった。世界の本質に対する人間の知的把握のあり方に関する根源的疑問を突きつけられた20世紀初頭の人々は、様々な意味で二律背反した表記あるいは様相の形態の示す、真実あるいは実在の暗示する“パラドクス”の問題性に直面させられたのである。
不可解極まりない発現様態を示す現実の基底をなしていると思われる世界の原存在の不気味な実相に、20世紀人は歴史上かつてない驚愕と戦慄を体験せしめられることとなった。そして、質量・空間、運動・時間等の物理現象を規定する諸要素に通底するであろうと思われる、宇宙の内部関連の深層に厳としてある理解不能性というこの問題性は、反転的に思考システム自体の裡に内在する“パラドクス”という概念の措定の許に集約されることとなる。さらにこれらの物理的事象解釈に関する直接的な存在論的論議とは方向の異なる別界面からも、“パラドクス”という概念の内包する存在論上の様々な解釈の可能性が、自発的に掘り起こされていたのである。
このような相対性理論あるいは量子力学の誕生に関連してあった周辺的、あるいは同時発生的思想状況について、数理論理学としての側面からむしろより統括的に要点を語ることに成功しているのが、大出晃の『パラドックスへの挑戦─ゲーデルとボーア』である。大出の眼目は、その著書の表題にもあるように、“パラドクス”という概念あるいは現象の示す特異な問題性にある。大出によればまさしく、“20世紀始めはパラドクスの時代”であったのである。大出の主張に従って実際の20世紀初めのパラドクスの論理学の進展の跡をたどってみると、これらの数理論理学的成果が見事にアインシュタインの相対性理論に先行しており、『ピーターとウェンディ』の特徴的な概念構造を裏打ちしているばかりでなく、さらに後のファンタシーとアクチュアリズムの勃興を導く精神土壌にとっても、欠かす事のできない素地を形成してくれていることがよく窺えるのである。
大出はまず、様々なパラドクスの事例の発見の具体的な経緯を追うことから論の展開を図っている。1902年には、バートランド・ラッセルからゴットロープ・フレーゲへの手紙の中で、「ラッセルのパラドクス」と呼ばれている、“無限の順序数”の問題が語られていた。これは良く知られているように、フレーゲの著書『算術の基本法則』の中にある集合論の矛盾を指摘するものであった。集合論という数学の一分野と思われていたものの中に、重大な宇宙論の転換をももたらす鍵が潜んでいたのである。続いて1905年には、「リシャールのパラドクス」、すなわち“集合濃度のパラドクス”として知られている議論によって、実数の数列における数の一対一対応を追っていけば、部分集合の“濃度”は全体に等しいことになってしまう、という数学上のいかにも常識的直観からは乖離する、経験則に矛盾する事例の指摘がなされたのである。これは日常言語の“部分”と“全体”という概念の関係性に対して抜本的な再検証を迫るかのような、集合論からの人間知性に対する極めて挑戦的な事実の宣言であった。このリシャールのパラドクスにあるような、集合概念の定義に関わる意味論的パラドクスが、この後様々に顕示されていくことになったのであった。動的な世界理解の革変を示すそのような思想的地盤から、「ヒルベルトのメタ数学」にあるような、系としての数学それ自体を数学的に捉えようとする、メタ概念が論理学の中に浸透していくこととなる。
これらの数学あるいは論理学の内部に潜伏するパラドクスとメタ論理の存在の指摘は、現象面での実在解釈に関する物理的発見や自然現象の中の法則性の発見と、図らずも符合していくこととなった。大出がその例の一つとして挙げているのは、1900年に提示された「プランクの放射式」、つまりすべての波長に対して成立する、黒体放射のエネルギー分布則である。これは1900年ドイツ物理学会において、マックス・プランクによって発表されたエネルギーと振動数のあいだの関係式であり、プランク定数(h)を用いてE=hvという数式で表現されたものであった。この“波動”という概念に関する新理論の発表は、その本質において量子力学の基幹概念を形成するものであり、大出が“ゾンマーフェルトがこの日を《量子論の誕生の日》と名づけた所以である”と語る通りである。“偏光”という重ね合わせの様態の許に不可解極まりない現象を示すこととなる、“波動”という新たな物理量を示す概念は、従来の質料概念を転覆するような、極めて異様な特質を秘めていたのであった。周波数の合成から成り立つ波動として、現実の存在物それ自体が自在に合成することも、あるいは変換することもできることを示唆するこの属性記述の手法は、伝統的な物質観とは全く相容れないものであったからである。さらに1913年には、ボーアの振動数条件v=1/h(En-Em)が提示されることとなる。この理論は、1913年7月に「原子と分子の構造について」において語られたもので、「量子ジャンプ」、すなわち“原子の定常状態における力学的な均衡は通常の方法で扱われるが、定常状態から別の定常状態への遷移はプランクの理論にしたがう均質な放射によってなされる”という、「不連続的な推移」という特質を持つ典型的な量子論理に基づいた物理的事実の指摘だったのである。
このように“数学体系についての体系”を語る手法の実際の物理的実在に対する適用の応用例の充実が、伝統的な経験則的な科学理念に捕われることのない、量子力学の独特のシステム理論としての拡充へと導かれていくこととなったのである。このような背景のもとに、いよいよ1926年夏にはハイゼンベルグの行列力学と、シュレーディンガーの波動力学が相次いで発表されるに至るのである。さらに加えて1926年には、アーサー・コンプトンによる電子の角運動量とスピンという、全くの新種の属性概念の提示がなされていることも無視することのできない事実である。コンプトンは1923年に「コンプトン効果」の実験による確証を得て、アインシュタインの予測した光子の持つ運動量を測定することに成功して、光あるいは電磁波の粒子性を証明していたのであったが、その“粒子”の保持するさらに未知の属性の発見をも導くこととなったのであった。そして1927年においてハイゼンベルグによる「不確定性原理」とボーアによる「相補性」の原理が発表されるに至り、量子論理はその全くの新種の系としての姿を明確にすることになったのである。1927年の春にハイゼンベルクが発表した 『量子理論的運動学と力学の直観的内容について』は、ボーアとの2ヶ月の議論の果てに合意された、かつての“リアリズム”解釈のパラダイムを変転させる量子理論の確立をもたらすものであった。
このような革新的状況の中で“パラドクス”は、また異なった位相を示して実在解釈における思考メカニズムの問題点を洗い出すことともなった。それはアルベルト・アインシュタイン、ボリス・ポドルスキー、ネイサン・ローゼンの3人によって1935年に提示された、“EPRパラドクス”である。この場合にはパラドクスの論理学は、新興の量子力学の提示したあまりにも斬新な理論に対する、古典力学陣営からの反証の武器として採用されることとなったのである。大出のまとめてくれた表現に従えば、“EPRパラドクス”の骨子は以下のような記法を用いて示されるものである。アインシュタイン達3人は、“物理的実在の量子力学的記述は完全とみなされうるか”という命題について、「実在性の条件」と「物理理論の完全性の条件」という二つの案件を提示し、以下のような指摘を行ったのである。
1 実在性の(十分)条件:もしもある系にどのような仕方でも撹乱をあたえることなくある物理量の値を確実に(つまり、1に等しい確率で)予測できるならば、この物理量に対応する物理的実在のある要素が存在する。
2 完全性の(必要)条件:ある物理理論が完全であるのは、物理的実在のあらゆる要素がその物理理論にひとつの対応物をもつ場合に限られる。
このふたつの条件を基本的な前提として、議論は次の形をとる。
もしある物理理論が完全であって、xが物理的実在のある要素であるならば、その理論のうちにxをふくむ状態記述がなければならない。
量子力学的状態記述にはともにふくまれることのない物理的実在の要素x,y,が存在する。
それゆえ、量子力学は完全な物理理論ではない。
p. 175
しかしながら、ここでEPRパラドクスによって図らずも語られた“実在性”、“理論の完全性”そして物理的実在と物理理論の“対応”という概念は、これら自体がさらなる論議の対象として、その内実を考究されていかなければならないこととなるのである。そしてここに指摘されたような、系の内部にある論理を超出する矛盾例である“パラドクス”というシステム的様態の現出の例示は、結局のところ量子論理というシステムの妥当性を否定する方向にではなく、むしろ量子理論の基幹条件を示す顕著な特質を検知する一種の指標として、この後量子理論確立のための特徴的な条件として積極的に採用されていくことになったのである。そこに発展的に得られた新種の概念が、“実在性”を充当することもなくシステムとしての“完全性”という条件に該当することもない、量子的存在特有の重ね合わせの状態を容認する“多義性”であり、その原理的メカニズムを保障する“相補性”なのであった。そして非局所的に作用を行う“全体性”という概念が、新たに注目を浴びなければならないこととなった場合には、“対応”という概念の意味するものそのものをも、改めて見直す必要に迫られることとなったのである。
1935年には、ニールス・ボーアによって『量子力学と物理的実在』が発表され、この中でボーアの提示した“相補性”という概念は、時空座標の記述内容における因果関係性の解釈と、波動と粒子の現象あるいは存在としての描像を理解するための欠かせない基幹理念として、全体性の世界解釈の一つの規範を提供することとなるのである。これらの論議は“コペンハーゲン解釈”として、ハイゼンベルグの「実証主義的議論」とボーアの「実在論的議論」を大きな柱として、既にストレールが語っていたように、後の世界の宇宙論及び現実認識に多大な影響を与えることとなったのであった。
『パラドックスへの挑戦─ゲーデルとボーア』におけるパラドクス論議の展開に関する大出の指摘の中で殊に興味深いのは、これまでに存在し得ないと思われていた新規の論理システムの構築可能性の提示がなされた事実が具体的に語られていることであろう。伝統的な論理学を支える公理の一つであった“排中立”の否定が、大胆にも試みられるに至った例がそれであった(14)。大出は、ライツェン・エヒベルトゥス・ヤン・ブロウェルが新規に開拓した、これまでとは全く別種の公理に基づく集合論を紹介しているのである。大出によると、“オランダの数学者ブロウエルが排中律の妥当性にたいして異議を唱えたのは、集合論による数学の基礎づけというコンテクストにおいてであった。”ブロウエルは、従来の数学的論証の規範の一つであった“背理法”という“間接証明”の妥当性に対して、疑義を提出したのである。背反する命題のうちの一方の命題の反証がそのままもう一方の命題の証明へと結びつく、一意的な原理に則ったこの論証操作に対する彼の疑問は、“直観主義的論理学”という新しい系の生成に寄与することになる。大出によれば、このシステム破壊的発想はさらに時を経て、一つの新たなシステム理論としての完成へと導かれることになった。「このような発想の結果、排中律を認めない論理学の体系、いわゆる“直観主義的論理学”のシステムが提出されることになった。ブロウエルの努力は1912年以来つづけられていたが、その論理のシステムをはっきりと規則のかたちであたえたのはかれの弟子ハイティングであって、1930年のことである。」(pp. 194-5)実は、“排中立の否定”という論理操作を介して存在性発現条件の拘束を緩和し、重ね合わせの存在原理に基づく事象発現以前の可能性の束として宇宙の潜勢力の姿の描像を導くこの世界解釈は、伝統的な二者択一的論理展開と一意的存在解釈の原理を根底から覆す、“多義性”という統括的宇宙論の構築において枢要なものとなる概念に結びつくものとして、仮構世界存在論再考の全方位的論理地盤を模索する我々のアンチファンタシー論との関連において、殊に興味深いものとなるのである。
大出はさらに、この直観主義理論とゲーデルの定理とブール代数のそれぞれの系としての形式に注目し、以下のような興味深い指摘を行っているのである。
直観主義理論による数学の基礎づけは実数論の展開をめぐって困難があり、その意味では完全に成功しているとはいえないが、その論理システムそれ自体は通常の古典論理のシステムの部分系をなしており、その点では古典理論の構造についても得難い知見を提供してくれる。ゲーデルは本来古典論理論者といってよいであろうが、かれは同時に直観主義論理にも尋常でない関心を示していた。この関心の由来がどこにあるのかわたしにはわからないが、この事実は少なくとも直観主義が古典的数学の本質にたいするある理解をあたえてくれる証左と思われる。さらに、古典理論がブール代数と同型であるように、直観主義論理は位相空間の閉集合の族のつくる束と同型であるという事実も「論理の本質」についての新しい反省の材料を提供してくれる。
p. 195
ここで行われているような、古典理論・直観主義論理の間に確認することのできる系としての集合的包含関係と、さらに古典理論とブール代数との同型性、及び直観主義論理の位相空間の閉集合の族のつくる束との同型性に着目して、“同型であること”の同定条件に関与する“同一性”の考察から「論理の本質」への理解を語ろうと企図する大出の関心は、パラドクスの検出を積極的に系のメタ理解の考察へと繋げる次元軸の拡張を図ることによって、全体性の汎論理の存在に対する検証の糸口の導出を目論むものであろう。実質あるいは属性あるいは形象における同一性は、位相変換の操作を加えることによって他の任意の次元枠の任意の様相に遷移可能であることを示唆するものである。そして、“パラドクス”というはなはだ問題性の深い概念に焦点を当てた論理のシステム構造に関する大出の論議の、ファンタシーとフィクションの相関についての再検証を試みる我々の考察にとってとりわけ示唆に富むと思われる部分が、量子の存在論的・現象論的記述の上で無数に分岐した平行宇宙の存在を認める形で採用されることとなった、“多世界解釈”という斬新な宇宙論に対する、「純粋に論理のシステムのモデル論の立場から見たとき、量子論理のモデルは“多世界モデル”である」(p. 197)という言明となるのである。ここにおいて“対応”あるいは“同一性”は一対一対応に限ることなく、むしろ“一対無数”対応を行い得るような対応関係においてこそ、その意義を理解されねばならないこととなる。個々の量子の示す変動値のあらゆる順列組み合わせに対応して、分岐して生成されるものとして構想された、多世界間に通底して現出する事物のみならず、事象あるいは属性等の概念そのものの貫世界的“同一性”あるいは“個別性”という対応関係について、我々は改めて意味と存在の中にある未知の内実を洞察する必要があるからである。そのような意味において、以下の大出の指摘は極めて示唆に富むシステム理論的考察の手法の提示となっているのである。
ゴールドブラットの提出した量子論理のモデル[中略]はクリプキのアイディアにもとづく「可能世界論」に発している。このモデルの特徴は、可能な多くの世界のあいだを結ぶ“近接関係”が反射的かつ対称的な関係だ、ということである。これは注目すべき特徴である。というのは、おなじような方法で直観主義論理と古典論理のモデルを構成してみると、直観主義論理の場合にはこの近接関係は反射的かつ推移的であって、これは各世界が時間的に直線的な樹枝状に配置され、それら世界を通ずる「数学的真理の蓄積可能性」を表現していると解釈されるからである。数学の定理はひとたび証明されれば、以後、真理として承認されつづける。一方、古典論理のモデルの近接関係は、反射的、推移的、かつ、対称的であって、このモデルでは各世界が円環状にならんでいる。これはきわめてギリシャ的な宇宙像というべきであって、そこで確定した真理は「永遠に存続しつづける」ことをイメージしているといえよう。
それに反して、近接関係が推移生をもっていない量子論理のモデルは、このような真理の蓄積可能性も永続性も表現せず、むしろ真理が非推移的で、それゆえ、「反証可能」であることを表現しているということができる。そこでは、真理がなによりも経験依存的であると主張されているのである。
p. 197
こうして大出は、諸世界間の“近接関係”における“反射的”あるいは“対称的”という特質と、直観主義論理と古典論理という論理システム間のそれぞれが“反射的かつ推移的”という特徴と“反射的かつ推移的かつ対称的”という特徴を示すことの特質に注目して、そこから“真理の蓄積可能性と真理の永遠性”というモデルの抽出を行い、これらと比較して量子論理の近接関係が推移性を保持していないという特質から、この系が“真理の蓄積可能性も持たず、永遠性も表現せず、真理が非推移的でしかも反証可能であること”を指摘することにより、そこにある“真理の経験依存的な特質”という一種のパラドクスの形成さえも示唆することとなっているのである。
大出がこのように、論理構造体の各々のシステムとしての型を確認することによって、「真理」そのものの主張妥当性の再検証という作業を実際に行い得ていることは、極めて注目に値する事実だろう。経験的に絶対であることがその内包であるとして信じられて来た筈の“真理”を、条件依存的で相対的なものとして捉え直す大出の視点は、言説の“ファンタシー・モデル”の一つの典型を構築しているからである。さらにここで「真理」を「事象」あるいは「存在」あるいは「属性」と置き換えてみることによって、我々の仮構世界存在論に関する反射的考察は、論理学的あるいは超論理学的に有効な、さらなる論証手順あるいは次元軸拡張の方法論を付加されて、一つの“公理系”としてのファンタシーの位相を顧みることをも可能にする、内実ある文学作品論を展開することができるはずだからである。
そのような意味においてことさらに興味深いシステム理論の生成と発展の状況を、さらに別な角度から語ってくれているのが、ストレールの『量子論的宇宙における仮構』と同年に出版されたファンタシー論集『ファンタシーへ架ける橋』(Bridges to Fantasy)(15)に収められている、アーレン・J・ハンセン(Arlen J. Hansen)の「平行線の交点:科学(サイエンス)と仮構(フィクション)とサイエンス・フィクション」(“The Meeting of Parallel Lines: Science, Fiction, and Science Fiction” )(16)である。ハンセンは論理学における“システム理論”の拡充という面に着目して、閉鎖系システム(closed model)から開放系システム(open model)へ、さらにまた循環系システム(loop model)へ、というシステム理論の構造的規範の推移から、科学思想的パラダイムの劇的な変遷を指摘し、さらにファンタシーの根幹にあるはずの重要な形而上学的関心をも語ることに成功しているのである。今度はハンセンの展開するシステム論に従って、そのあたりの状況を追ってみることにしよう。
ハンセンはまず、1855年のケンブリッジ哲学学会においてジェイムズ・クラーク・マクスウェルが行った、「ファラデーの力線について」という論文の発表内容から論の口火を切っている。マクスウェルはファラデーの発見した電磁気の理論について、「純粋に仮想的な液体の幾何学的な運動」を考慮に含める一つの“科学的モデル”の採用を提唱したのであった。マクスウェルに従えばこの材質は、自由な運動性と圧縮に対する抵抗性以外のいかなる属性も有することのない、仮想的な特性の集合としてのみ理解されなければならないものであった。マクスウェルがここで提示したものが、ハンセンによれば“ファンタシー”の具体例として記されていることは、注目に値する事実であると思われる。ハンセンは、“結局のところマクスウェルは、一つのファンタシーを創出していたのである。彼は不自然なあり得ない現象を持ち出して論を展開していたのである。”(p. 52)と記述を進めている。ここにあるハンセンの表現によれば“ファンタシー”とは、“不自然”、つまり古典力学的な機械論的解釈(自然)によらない、全く別種の公理系に属する体系であり、さらに“不可能性”という際立った特質を備えていることがその規範条件ということになる。しかしここでのハンセンの眼目は、このファンタシー・モデルがその特徴として、「開放系」のシステム構造を備えていることを指摘することにあったのである。
In looking back over the past century, one can see three basic structures that have dominated scientific theorizing: the closed structure, the open-ended structure, and the looped structure. The late-nineteenth-century physicist and naturalist tended to prefer the closed model. In the 1920s some radical young physicists cast their theories in open-ended fantasy-models. And in the 1950s computer scientists and mathematicians embraced the loop model.
p. 54
過去1世紀を降り返ってみると、科学理論の形成を支配した3つの構造があることが分かる。閉鎖系構造、開放系構造、循環系構造の3つのシステム構造である。19世紀末の自然科学者達は、閉鎖系構造を好んで採用した。1920年代には、急進的な若い物理学者達が、開放系構造のファンタシー・モデルに基づく理論を打ち出した。そして1950年代には、コンピュータ科学者と数学者達は循環系構造を選んだのである。
ハンセンによれば、量子理論確立の黎明期にあった開放系のシステム構造に属することが、“ファンタシー・モデル”と呼ばれることの一つの理由にもなっていることが分かる。さらに量子理論の、古典力学の制約を跳躍する革新性を指摘するハンセンは、「マクスウェルの悪魔」と呼ばれる量子理論において容認される特有な偶発的変動に対しても、“fantastic coincidence”(突拍子も無い偶然)という言葉を当てはめて語っている。(pp. 55-6)これらの例におけるこの語の使用は、システム理論的位相においてファンタシーという現象を語ろうとするハンセンの論考において、従来の規範を覆すような新規のシステム構造の顕現を示す際の、一つの定式を形成しているものと見なし得るだろう。だからソルヴェイ会議の際にアインシュタインの固持した古典力学的主張に対して、その反論としてボーア達が唱えた事象記述モデルが、やはり“ファンタシー・モデル”と呼ばれることとなっているのである。
At the Solvay Conference, Bohr and his associates proposed a conception of things that ran counter to Einstein’s. They described some aspects of the physical world in a fantasy-model that incorporated indeterminacy and probability.
p. 55
ソルヴェイ会議の席で、ボーアと彼の協賛者達は、アインシュタインが提示したものに真っ向から反対する概念を提示した。彼らは不確定性と蓋然性を組み込んだファンタシー・モデルの中に、物理的実在世界のいくつかの様相を語ってみせたのである。
ハンセンがここで開放系構造を採用した量子論理に“ファンタシー・モデル”という呼称を当てはめてその構造特質を語っているのは、ストレールのアクチュアリズムに関する論議と結びつく、現実―ファンタシー間の微妙に潜伏した連続性あるいは相互依属性についての興味深い示唆が、量子論理の不確定性と蓋然性という概念の中に潜んでいることを明確に意識しているからであろう。その意味においては、アクチュアリズムはファンタシーの集合に含まれる部分集合であると呼び得ることにもなるだろう。
このようにハンセンは、従来の古典力学の規範から大きく逸脱した量子論理の構造性の変化を、“閉鎖系”から“開放系”への移行として捉えているのである。ボーアの提示した“相補性”という概念が“開放系”という特質を担うとされる理由が、電子の存在に確認されるように量子存在が粒子としての様相と波動としての様相の、相矛盾する双方を重ね合わせの原理として保持する、曖昧な構造性を秘めていることにあるのは疑いのない事実であろう。
Bohr’s notion of complementarity also requires an open-ended model. In addressing the question “Are electrons particles or waves?” Bohr discovered that they are either, depending on what we are looking for. An electron is both an orbiting bit of matter and a smear that appears to be all places at once. That is, we can measure electrons either as discontinuous quanta or, if we like, as continuous wavefields.
p. 56
ボーアの提示した相補性という概念は開放系システムの存在を必要とするものでもある。「電子は粒子であるのか、あるいは波動であるのか?」という疑問を提起するにおいて、ボーアは我々がいずれを観測しようとしているかに従って、電子はそのいずれでもあり得ることを発見したのである。電子は軌道を描いて運動する質量点でもあれば、同時にあらゆる場所に発現するかのように見える痕跡でもある。つまり、我々は電子を不連続的な量子としても、連続的な磁場としても恣意的に記述し得るのである。
ここに明らかなように、“相補性”という論理システムにおいて一意性の拘束を棄却する、多義性の存在論の原理をその裏面に示唆する概念が、ハンセンの指摘するシステム構造分析における“開放系”の検出の指標となっているのである。しかしながら、古典力学の特質であった閉鎖系のシステム構造に対して、ただ開放系の構造を持つことによってのみ、量子力学の構造的特質の全てが捉えられている訳ではないことが、以下の論の展開から分かるのである。ハンセンは量子論理のさらなる発展を示すものとして、ループ・モデル(循環系構造)の存在を指摘し、この構造体に対しても“ファンタシー・モデル”という呼称を同様に採用して紹介しているのである。ここにおいて“ファンタシー”という述語の定義不能性を示す、不定性の特質が意図的に活用されて、3つの異なる構造モデルと量子力学の相関が語られていることが改めて確認されるのである。ハンセンの論議においてむしろ興味深いのは、このようにして副次的に得られた“ファンタシー”という述語の内包性に関する、観念性理解の拡張の可能性の示唆なのである。
In the 1950s and ‘60s, while physicists continued to theorize in open-ended terms about gravitons that may or may not exist, about black holes that cannot be seen, and about foamy space that has no geometry, a new fantasy-model gained popularity among mathematicians and computer scientists. I am referring to the loop, a fantasy-structure that has made possible amazing developments in computer technology and artificial intelligence systems.
p. 56
1950年代から60年代にかけて、物理学者達が存在するかもしれないし存在しないかもしれない重力子や決して目に見えることのないブラック・ホールや、いかなる幾何図形的配置も持たない泡宇宙等についての理論化を、開放系構造を用いて行い続けていた時、新規のファンタシー・モデルが、数学者とコンピュータ科学者達の間で受け入れられるようになった。それはファンタシー構造である循環系モデルで、この理論はコンピュータ応用技術と人工知性研究において、驚くべき発展を可能とすることとなったのである。
こうしてハンセンは、バッハの音楽、ゼノンのパラドクス、エッシャーの絵画等におけるループ構造の発現の例を挙げ、さらにルイス・キャロルの寓話、ジョン・バース、ホルヘ・ルイス・ボルへス、アンソニー・バージェス、サミュエル・ベケット、ジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』等の文学作品の中に現れたループ構造の指摘を行うことにより、最新の発見であるループ構造理論の興味深い特質を述べることとなっている。(pp. 56-7)
当然のことながら、論理構造体の示す特有の形態に注目してシステム理論を指摘することによりファンタシー論を展開しようと目論むハンセンの議論は、“自己言及”という命題の特性に対して卓越した分析を行い、系の有する自己の正当性の論証不能性という制約について論証することに成功した、ゲーデルの定理へと集約して及ぼされることになるのである。系を指示する論理構造体と、そこに指示される対象としてある論理構造体それ自体が、紛れも無くその論議の意味性の中に見事な論理の一つのループを隠し持っているからである。ファンタシー論集の一つとして書かれたハンセンのこの小論は、ダグラス・ホフスタッターの刺激的な著書、『ゲーデル、エッシャー、バッハ』に対する参照で締めくくられている。
But it was Kurt Godel, the mathematician, who gave special scientific endorsement to the loop model in his 1931 attack on Russel and Whitehead’s Principia Mathematica. Godel demonstrated, in effect, that our logical systems, including mathematics, are loops whose power derives ultimately from some larger, external construction that contains the looped system. Godel’s proof opened the door to a new appreciation of set theory, to new ways of conceptualizing systems of logic and games, and to a new understanding of intelligence. Rather than attempt here to indicate the manifold and complex ways in which the loop model has revitalized mathematics and computer science, I direct you to a thorough and stimulating discussion of mathematical loops and their nonscientific isomorphs: Douglas R. Hofstadter’s brilliant book, Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid.
p. 57
しかし循環系システム(ループ・モデル)に取り分け大きな科学的裏付けを与えたのは、ラッセルとホワイトヘッドの『プリンキピア・マテマティカ』への批判を1931年に行った、数学者クルト・ゲーデルであった。ゲーデルは、事実上我々の論理システムは、数学も含めて、その機能が究極的にループ・システムを含む、より大きな外部構造に依存する、ループであることを主張したのである。ゲーデルの証明は、集合論に対する新規の理解の扉を開くこととなった。そして論理とゲームを改めてシステムとして概念化する手段を示し、知識の再理解へと導いたのである。ループ・モデルが数学とコンピュータ・サイエンスを再活性化させた様々の複雑な事例についてここで語るかわりに、数学的ループとその科学外同形体に関する包括的で刺激的な論議を紹介しておくことにしよう。それはダグラス・R・ホフスタッターの異彩を放つ著書、『ゲーデル、エッシャー、バッハ―永遠の黄金の組み紐』である。
ハンセンがここに選んだ結びの言葉の中で、ホフスタッターがループ構造の類例として見事に語ってみせた種々の文化的作物を呼ぶ言葉として、“同形体”(isomorph)という語が用いられていることが興味深い事実となる。システムとしての構造の形に着目して語る論議において、その構造の同形性に注目して形態あるいは実質の同一性を判別する際の、基準あるいは根拠の所在を如何に定めるかが改めて問題となると思われるからだ。外部のより巨大な系からの投影あるいは同一の上位の系に属する、位格的同等性を保持する他の系との変換記述という要素を含めた際に、“同形性”と“同一性”の差異をいかに認め得るか、という同定作業上の問題が生起することとなる。仮に貫世界的同一性が確証された存在あるいは概念があったとすれば、これらに対して等価原理に基づく実質と属性の相互変換を企てた場合と同等の原理に従い、超越的個別性内部における貫世界的発現可能条件という反転的な普遍的属性あるいは対応物を記述する試みも成立しそうだと思われるからである。こうして時間的連続性によって同一性を判別することのできていた“それ性”(haecceity)、あるいは概念の対応物を成り立たせていると思われる“そのもの性”(quiddity)等の言葉を用いてかつて語られてきたものの多世界解釈における貫世界的実相に対して、さらなる理解を深める必要が認められることになるだろう。殊に対象領域を現実・仮構の連続体空間に拡張した際に現実と仮構間、さらに仮構と他の仮構間の相似的なイソモルフ(同形体)の同定条件が如何に変質し得るかについては、未だ確かな論拠が得られていないと思われるのである。たまたま現実の中で創出された作品としての仮構世界は限定的に切り取られたもので、描かれた世界内事実の延長範囲は実はあまりにも狭小であり、記述の空白部分が殊の外大きいものであることが既に指摘されている。しかし可能態としてある断絶の無い総体としての本来の仮構世界は、むしろ現実を規定する諸条件の制約から自由であることから、その集合として占める領域はむしろ広大なものであり、その一部を参照した現実世界そのものをその内部に含む、現実世界に比して遥かに巨大な外部の系をなす集合であることが予測されるだろう。このように仮構世界と現実世界の相互の包含関係は、常時反転的な不定性のゆらぎの構造に似た特質を示しているのである。仮構世界の記述行為あるいは仮構世界に対する言及行為は、メタフィクション的な明示的自己言及の場合に留まらず、むしろその言及行為自体の中に自分自身の存在原理に背反してその存在の否定をも暗示する、自己生成と自己消却の両極を振幅するループ構造を凝縮した見事に完結的な二律背反的特質を含んでいるのであった。このようにして自己言及やメタ構造性に焦点を当てることによって検出されたループ(循環)という論理、現象、様態その他様々の姿で発現する特有の構造性は、あるがままの現実と仮構そのものに対しても適用可能なことが理解されるに至るのである。かくして同形成と同一性を再検証することにより、アクチュアリズムとアンチファンタシーの裏面に隠されていた重大な仮構的パラドクスの検出が成立するに至るのである。
註釈
(1)
本国アメリカにおいて決して十分な理解を与えられることのなかった、才気溢れた詩人であるばかりでなく卓越した科学思想家でもあったエドガー・アラン・ポーの著作と人生の哲学的・芸術家的神髄を、腐敗した旧世界の先進国フランスから正しく称揚した異国の批評家・詩人ボードレールが採用していた、ポーとその周囲の文化的環境の位相に対する1世紀以上前の評価のスタンスをここで踏襲しておくことは、ビーグルという希有な資質に満ちた芸術家自身の本質に対する現在の一般的評価と、さらに彼の代表作『最後のユニコーン』における最も謎に満ちた存在であったレッド・ブルの担っている主題的位相を再評価するにあたって、やはり欠かすことのできない前提条件であると考えられるのである。いささか独断的と思われるかもしれないこの国の文化的成熟度に対するこの総括に対する弁護としては、アーシュラ・ル・グインの“Why Americans Are Afraid of Dragons”(『夜の言葉』、The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction, 1992に収録されている。)におけるアメリカにおけるファンタシー受容を頑に拒む意識状況を語る論評を、その拠り所の一つとして挙げることができるだろう。この小論の中でル・グィンは、アメリカ人一般のファンタシー受容に抵抗する頑迷な反発的態度を指して、“Americans are anti-fantasy.”というフレーズを用いて語っている。ここで用いられた“antifantasy”という語は、“ファンタシー嫌い”程の意味で使用されていた訳であるが、この時点ではファンタシー自身の裡に潜む内在的な“反ファンタシー”の要素としての二極的対立の図式は、この語の内包としては考えられていなかったのであった。
(2)
この典型的な例が、いかに微小な作用であっても総体的な因果関係の複雑な連鎖の中では大変動を引き起こす引き金として機能し、重大なカタストロフィをもたらし得るという、“バタフライ効果”という言葉で知られている事実である。
(3)
ラテン語の「もの」に相当するこの語によって、認識や知覚の対象となり、現象を生起させる核となる根源的な存在としての確固たる概念が想定されてきたのであったが、この仮説的な概念を基底に置くことのない、知覚や認識という“作用”や現象の生成という“出来事”の存立可能性自身に対する全く異なった角度からの現象理解が提示されるに至った時、この語は一つの不完全な仮説としてその存在論における根幹的意義性を後退させられることとなった。
(4)
数学における“マトリクス”は、加法や乗法などの算術を行うことができる縦横の数列からなる表によって記された数量であるが、語源的には“基盤”、“母性”等の意味があり、ハイゼンベルグの関心にあった宇宙の原初的構成単位としての概念に様々な角度から相応している。
(5)
“プレローマ”という語は、元来はグノーシス思想において考えられていた、現世とは異なる天上界を指す神話的概念であったが、ユングによって全ての存在性の根幹としてある原存在物としての意味合いを持つ述語として用いられることとなった。ニュートン力学によって完成された意味の体系が崩壊した時、様々な歴史的に先行する概念と述語が新解釈の許に再選択されねばならなかったということを示す、説得力のある実例の一つであろう。ファンタシーの誕生と、後の復権の要因となったものを理解するための鍵となる発想がここにある。
(6)
これがいわゆる“物理学”(physics)の前提とするところであったが、ニュートン力学を規定する諸概念に対して拮抗して作用する相補的概念を新たに設け、例えば“materia”に対しては“spiritua”を、“atom”に対しては“monado”を、“gravity”に対しては“repulsion”等を構想して拡張された統括系の構築を図るのが、“形而上学”(metaphysics)の企図したところであったと言えよう。
(7)
Fiction in the Quantum Universe, p. 8
(8)
西洋における“自然”(Nature)は、合理的な運行規則に則って常に予測可能な結果をもたらす、世界の機械的な規則性を内包する概念であったが、これに反して東洋の文化的辺境国日本における全てを包含する全体性としての“自然”とは、むしろ人知を超えた神秘に満ちた予測不能な、すなわち“超自然”(supernatural)に相当するものであったことが興味深い。日本の伝統文化においては科学的世界観に則って展開された模擬実験的仮構、すなわち“小説”(novel)は実際には存在しなかったし、その対立物である“ファンタシー”も結局はあり得なかったと仮定することのできる一つの根拠がここにある。
(9)
CF. Tzvetan Todorov, The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, trans. Richard Howard (Cleveland; Case Western Reserve University Press, 1973)
トドロフは、“ファンタシー”に通底する基本概念として、“the fantastic”という語で規定された “that hesitation experienced by a person who knows only the laws of nature, confronting an apparently supernatural event” という定義を採用したのであった。これに対する“the marvelous ”という語で規定された“in which characters are confronted with unquestionably supernatural happenings”という定義に基づく仮構世界は、トドロフの関心の中核には無かったのであった。“アンチファンタシー”という指標はこれら双方の概念を含む統一場の構築を模索するものである。
(10)
20世紀以降に急速に発展した現代の集合論と論理学がこれに該当するものであるが、例えば古代ギリシアの思想家のパルメニデスが語ってみせたような、さりげない常識論の提示の裡に隠蔽された自己矛盾という言説の保持する論理的内包性をも考慮に含めるならば、その起源は遠く歴史を遡るのみならず、適合する事例も公汎に範囲を拡張して認知されることとなるだろう。
(11)
ハイゼンベルグは『現代物理学の思想』(Physics and Philosophy)において、量子論理の知見の導入した新規の概念とこれに対応する日常言語の関連について、丸ごと一つの章を割いて考察を行っている。(CF. 第十章:「近代物理学における言語とリアリティ」)ここで一般言語自身が新種の概念に対応する自律的な系としての修復・拡張機能を有していることが論じられていることは、殊に注目すべき事実である。ハイゼンベルグの提示した一つの印象的な具体例が、“シュレーディンガーの猫”の場合に示されるような量子の持つ重ね合わせ的属性の論理学的処理に関して、「ある」と「無い」の関連を記述するための新たな真偽値の策定として、ヴァイツゼッカーの導入した「真の程度」という概念であった。(pp. 188-9)
(12)
Cf. 『アンチファンタシーというファンタシー』。子供達個々の心の中の存在としてピーターという人格性を備えた個体としての意識体があり、そしてまた彼らをその裡に包含するネヴァランドという世界もが展開しているという機構や、大人と子供/快活と憂鬱等の抽象的な対立概念の分離という形で具現したペルソナ的位相におけるピーターとフックの間の心霊的関係性などがこれである。
(13)
Cf. 『アンチファンタシーというファンタシー』。ダーリング夫人の口許に浮かぶ“キス”とピーターとウェンディの意識の交わりの空間に現出した“キス”、そしてまたピーターとキャプテン・フックを結びつける“謎”(riddleとenigma)という概念、あるいは反転的に彼らの関係性を規定する“憂鬱”と“ハートレスネス”(無慈悲)という概念等がこれである。
(14)
当然ながら“排中立の否定”という原則のもとに新規に採用された暫定公理は、ガウスによる虚数の発明や、ロバチェフスキーやリーマン等による非ユークリッド幾何学の構築の場合と同等の、パラドクスを軸とした生成機構による公理系を示唆するものとして、拡張された裏の系の存立可能性を示唆するものとなる。物理学者スティーブン・ホーキングが“虚数時間”をビッグ・バン以前の状態にあった宇宙を記述する時間軸として選び、時空概念のさらなる拡張を図った例が思い起こされることだろう。
(15)
Bridges to Fantasy, 1982. Edited by George E. Slusser, Eric S. Rabkin and Robert Scholes.
(16)
“The Meeting of Parallel Lines: Science, Fiction, and Science Fiction” in Bridges to Fantasy, 1982.
01:18:45 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
びえぶ wrote:
凄かったw お姉さんのテクは凄かったww
色んな事やってもらったんだけど、蟻の門渡り舐められた時は思わず大声出ちゃった(^^;
結局お姉さんにまかせてずっと寝てるだけだったのに、10萬もらえたーーー!!!
というわけで10萬の軍資金を手にパチ行ったら見事大勝ちw
いやーいいバイトだわw これからはこのバイトやってからパチ行きやすw
http://transaqtion.com/muumuu/
色んな事やってもらったんだけど、蟻の門渡り舐められた時は思わず大声出ちゃった(^^;
結局お姉さんにまかせてずっと寝てるだけだったのに、10萬もらえたーーー!!!
というわけで10萬の軍資金を手にパチ行ったら見事大勝ちw
いやーいいバイトだわw これからはこのバイトやってからパチ行きやすw
http://transaqtion.com/muumuu/
01/23/09 10:38:19
イカチュウ wrote:
ぁはへあはぁあぁあはぁ!!!
ちょw ゴメww いきなりゴメンwwwww
さっきハメてきた子のスペックが最強すぎてテンション落ちないんだわwww
指ちょっと挿れたくらいでスゲエ声で喘いで潮ピュッピュ吹くし締まり抜群だしディープスロートやってくれるし顔はアヤたん似でEカップだし!! これ最強すぎだろwww
終わった後ヒクヒクしながら「また電話するね♪」だってよwwww
クアァァアア!!ウヒョー!!!てか、思い出だけでも十分シコれるレベルwww
http://cock.aportachannel.net/
ちょw ゴメww いきなりゴメンwwwww
さっきハメてきた子のスペックが最強すぎてテンション落ちないんだわwww
指ちょっと挿れたくらいでスゲエ声で喘いで潮ピュッピュ吹くし締まり抜群だしディープスロートやってくれるし顔はアヤたん似でEカップだし!! これ最強すぎだろwww
終わった後ヒクヒクしながら「また電話するね♪」だってよwwww
クアァァアア!!ウヒョー!!!てか、思い出だけでも十分シコれるレベルwww
http://cock.aportachannel.net/
01/31/09 10:29:41
野武士 wrote:
拙者ぁー先ほどクン.ニしてきたでござるんだけどぉー
穴に舌入れてレロレロしながら鼻でクリをクリクリしたらぁー
いきなりスケベな液体をシャーっと出して驚いたでござるよぉー( ゜д゜)
おかげでちょんまげがビショビショに濡れてヘニャヘニャになったけどぉー
チン.コはカッチカチでござったよぅー(・∀・)(・∀・)(・∀・)
http://chukuchuku.momiton.net/
穴に舌入れてレロレロしながら鼻でクリをクリクリしたらぁー
いきなりスケベな液体をシャーっと出して驚いたでござるよぉー( ゜д゜)
おかげでちょんまげがビショビショに濡れてヘニャヘニャになったけどぉー
チン.コはカッチカチでござったよぅー(・∀・)(・∀・)(・∀・)
http://chukuchuku.momiton.net/
02/14/09 11:16:12
ネ申 wrote:
ハイレベルな人間ですいませんw 本当に俺はレベルが高い人ですww
童.貞ニートで底辺の生活を送っていた俺がたったの2年で貯金額2000万ですからねm(_ _)m
今は某高級マンションに住んでて、女にフェ-ラ.チオをさせる毎日です^^
いやぁ、勝ち組って気分良いですよ本当に! ありがとうございましたーwww
http://korekiyo.onshaver.net/
童.貞ニートで底辺の生活を送っていた俺がたったの2年で貯金額2000万ですからねm(_ _)m
今は某高級マンションに住んでて、女にフェ-ラ.チオをさせる毎日です^^
いやぁ、勝ち組って気分良いですよ本当に! ありがとうございましたーwww
http://korekiyo.onshaver.net/
02/23/09 13:54:27
サラシ wrote:
> りょーさん
ええまさかwwwって思いながらも、俺もやってみました(笑)
凄い!ってか女の子超工ロすぎ羽振り良すぎ( ´∀`)
フェ-ラさせてあげただけで5万ゲットっすー★
http://mattari.churappa.com/
ええまさかwwwって思いながらも、俺もやってみました(笑)
凄い!ってか女の子超工ロすぎ羽振り良すぎ( ´∀`)
フェ-ラさせてあげただけで5万ゲットっすー★
http://mattari.churappa.com/
04/18/09 12:58:34
Add Comments
トラックバック