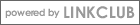Complete text -- "『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 1"
22 February
『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 1
科学とSFと哲学的省察:『エルゴ・プラクシー』における神と人と“自分”(2)“世界”と“私”という実は意識の主体にとって極めて捕捉困難な概念について形而上的な再認識を迫る省察において、特異な表象化技法を創出して知の位相の映像化を図ることを企てたアニメーション作品『エルゴ・プラクシー』は、科学的思考の類型を脱した存在・現象解釈を様々に展開していくこととなる。省察12「君微笑めば」と省察13「構想の死角」は、連続した一つのエピソードとして一方でプラクシーと彼等によって創造された“人間”存在並びにオートレーブ存在の間のより具体的な関連を明かす手がかりを与えると共に、もう一方では存在と現象そのものに関する新規の心霊的世界解釈を導入した統合的宇宙観を示唆する興味深い視点をも提供している。その潜伏した主題展開の伏線として機能しているのが、省察12終結部において描かれている空から降ってきた雪片がピノの顔に落ちて涙のように目の上を伝うシーンである。概念と現象あるいは存在の間のはなはだ微妙な関係性を再考察するための糸口が、ここにさりげなく示されているのである。
ヴィンセントとリルが次に遭遇したプラクシーは、荒廃した自然環境に新たな植物相を再生してロムド・シティやアスラの塔にあった“ウー厶・シス”と同等の独自の人間再生産設備を守護していた。しかしながらドームや塔と並んで森を表象とした小世界の支配者であるこのプラクシーは、一人のオートレーブをアントラージュとして従えてはいるものの自身は高度な知性を持たない野獣的な存在として描かれている。主と同様に口を利くことはないものの、むしろ思念と意図らしきものを備えてある意味で知的な行動を行っているのは、彼のアントラージュである少年の姿をしたオートレーブの方なのである。土地の神ゲニウス・ロキ的存在属性を備えた獣人的なプラクシーの登場は、ドームやタワーの管理者として特有の権能と職務を与えられたプラクシー達の保持する使徒的属性との対照から、この作品の導入したプラクシー(代理人)という概念の内実を語り返すことになっている。プラクシー=人間=オートレーブ間の支配・従属関系あるいは管理・統制関系は、この後微妙な偏差の存在を浮かび上がらせていくことになるのである。
しかしこの極めて思弁的な仮構作品の提供する純観念的な新機軸の発想は、リル・メイヤーが口にするコギト・ウィルスに冒された彼女自身のアントラージュ=イギーの死を宣告する言葉によって提示されている。これまでのように従順に自分の命令に従おうとはせずに、独自の判断と意思を持って行動を取り始めたイギーに対してリルは言う。「これがコギトによる変化なら、死にも等しい変化だ。」リルの発言は、図らずも有機生命体に限定されることのない存在物全てに対して適用可能な、“命”とその消失である“死”に対する概念の拡張論議の核を提供している。
生命体を判別する指標を一個体の存在物としての自立的な運動が観測される“自動性”の有無に対して認めるのではなく、対象の外部存在者に対する応順反応という特定の機能面に条件を限定してその生死を規定することを試みているリルの判断は、“生”と“死”そのものの本質的定義に新たな局相を加えるものとなっているのである。これによれば存在者の生死を決定するのは当該する本体自身の権能ではなく、飽くまでもその個体を客観的に観測する他者による概念操作なのである。リルの判断に従えば、自らの意図に順応する無機物あるいは環境に対して“生命”の存在を検知することも当然可能となるに違いない。
自らが死を迎えた後にも変わらずアントラージュの奉仕を受けている森のプラクシーと、主人の意思を拒絶することを選んだアントラージュに一方的に死の宣告をするリルは見事な対照をなしている。さらに自らがプラクシーであることを漸く自覚したヴィンセントに対してリルが語る「プラクシーでありながら、プラクシーが何かすら分からないとは、滑稽だな。」という辛辣極まりない言葉は、この指摘が自分自身にも適用されることに彼女自身が全く無自覚であることにおいてこの物語の以降の展開に対して折り畳んだ伏線を提供することとなっている。様々な意味でリルは『エルゴ・プラクシー』の主題展開上のキー・パーソンとしての職分を堅固に果たしているのである。
省察14「貴方に似た誰か」の冒頭は、リルの独白「小さい頃は、自分が死ねば世界も消えると思っていた。」から始まる。これに呼応するかのように、ヴィンセントの独白も以下のように続く。「俺は俺で、他の誰かじゃない。それがすごく不思議だったことをよく覚えている。俺の記憶は信用が置けないが、この記憶は古くて確かなものだった。」自分と世界、自と他の背後にある未知の心霊的関係性に対してリルとヴィンセントのそれぞれが胸の裡で語るこれらの思念は、このエピソードに登場する新たなプラクシーの担う興味深い存在論的位相を補完して語るものとなっているのである。世界があるからその中で世界を意識し世界について思考を行うこの私があるのか、あるいは私が“世界”という言葉を偶々発見しその定義と実際の経験との連係を構築したと妄想するが故にこの“世界”が存在するのか、という意味論上の測り知れない疑問に対して、因果関係的な制約を超出した弁証法的統合が果たされることとなる。それは“共変的”システム構造理解を様々の対象概念に全方位的に適用した結果得られるべき、統括的な全一性の存在/現象理念なのである。
一行が旅の途中で立ち寄った別のドームの中は、整然とした町並みがあるが人の姿は一切ない。手つかずの食料品が無傷のままに残されているスーパー・マーケットの中では、エスカレーターが動きレジのモニターの表示も活きていて、その画面の片隅には “Ophelia”の文字が記されている。マーケットの屋上の看板等を介して“Ophelia”の文字はこの街のシーンの中でさりげなく3度画面上に示されていたのであった。この無人の町の食料品の溢れたマーケットの名が“オフェーリア”なのだが、シェイクスピアの戯曲「ハムレット」の悲運のヒロインの名を冠したこのマーケットの名称は、ドノブ・メイヤーの4体のアントラージュ達の名やデダルスの2体のアントラージュ達の名の場合と同様に、ストーリー外の概念連係において特有の意味性を浸透して発揮することになっている。他のいくつかのエピソードと並んで、今回のエピソードも著名な文学作品の内実との間の潜伏した裏の関連性が、主題としての興を彩ることとなっているのである。
14話「貴方に似た誰か」においては、映像表現の特質を活かした殊に入念な演出が採用されている。観客として画面上に現出した映像のみを手がかりに物語の内容を読み取ろうとするならば、ストーリーの客観的な理解が困難になるように、意図的に仕組まれているからである。エピソード前半で画面上に視認されるヴィンセントやリルの姿のいくつかは、この町を支配するプラクシーが自在に姿を変えて彼等を攪乱するために装ったものであり、ヴィンセントとリルが陥った精神的混乱と平行した惑乱状態を観客も共有させられることとなっていたことが後に判明する。鑑賞者は決して仮構世界の出来事の中立の傍観者として、客観的判断を選択する特権を与えられている訳ではなかったのである。自在に人々の姿形を擬装することができるばかりか、それぞれの記憶と想念にも同調してそれを模倣することができるらしいこの閉鎖世界のプラクシーには、単なる変装や幻覚を操る能力以上の特殊な存在属性があることが暗示されている。この名の無いプラクシーの人格同定上の不定性の特質を理解した上で、改めて最初から本編を確認し直す作業を行って各々のシーンの内実と演出的捻りの効果を再検証してみることにより、ようやくこのプラクシーの本来の存在論的特性とマーケットの名に暗示されていたオフェーリアのイメージとの間の、捻転した関系性が特定されることになるのである。
プラクシーの企みに嵌って気を失ったまま湖に沈められようとしているリルは、ラファエロ前派の画家ジョン・エヴェレット・ミレーの描いた“オフェーリア”そのままの姿勢をとっている。水面上に仰向けに浮かんで横たわり肘を曲げて両手の平を上に向けているオフェーリアの姿は、ハムレットの示す冷たい素振りに耐えきれず、狂気に陥り小川に身を投げて水死を遂げた少女の自殺行動を象徴するものとなっている。自死を象徴する柳の木と共に画面上に数多く描き込まれた種々の植物の図像がそれぞれ固有の概念と結びつく象徴的意味性を背負っているように、人の顕示する姿勢や仕草もまた固有の概念を特定的に指示することとなる。これらの暗示的連関を巧みに応用した表象芸術であるコスプレや変装行為に対して指摘可能な発想と同様の、現象世界的“人格”や“個人存在”の同等性を拘束する概念を離脱した別次元の意味論的自己同一性である“セルフ”の多様性を暗示することになっているのが、この独特のポーズなのである。このポーズにおいてリルはピノの頬の上の水滴が彼女の涙であり得たのと同様の意味で、オフェーリアであることの同一性を確かに保持しているのである。何故ならば“羊”と呼ばれる“狼”は、正体が狼であるところの紛れも無い羊に他ならないからである。
オフェーリアの町のプラクシーは巧みにリルの知覚と状況判断を惑乱の中に陥れる。しかしAIであるピノは外観に困惑させられることはない。さらにピノは個人存在の複数性を当然のごとく受け入れてもいる。ピノが備えている個体同定上の認識機構においては、複数の存在に対する同一性認定が基本的に容認され得るものである。ヴィンセントの姿を装ったプラクシーにピノは語りかける。「リルリルは?」/「リルはもういない。これで楽になるんだ。」/「いるよ、もう一人。」/「何、言ってるんだ。」/「ヴィンスも、もう一人いるよね。お料理食べてくれたのは、別のヴィンスだよ。ヴィンスも二人、リルリルも二人、なのになんでピノは一人なのかなあ。」AIであるピノの個体認識においては、ヴィンスとリルがそれぞれ二人現出していることに何の疑問も感じられていない。確かに“愛玩用オートレーブ”という型番の一台であるピノにとっては、モビル・スーツ“ガンダム”や人造人間“百式レアリエン”などと同様に、自分と同一の存在が複数あることに特に異常の念は惹起されないのだろう。
しかし量産型機械の場合に限らず、概念の普遍相における“個体”あるいは“人格”における複数の位相発現性という可能性そのものについて、さらに敷衍してその妥当性を考えることもできるはずである。『エルゴ・プラクシー』においては“リル”という名で呼ばれた存在がすでに3体登場していたのであった。今回新たに姿を現したプラクシーもただ他のものの姿形を真似てみせるだけでなく、記憶や意識等の自己同一性を確定する軸となる筈の諸条件においてさえも存在論解釈上“同一”のものを保持し得ることが示唆されている。このプラクシーがいかなる概念の“代理人”であるのかを推測してみることによって、存在の個別性と“同一性”という認識の中に潜んでいる原存在的“多義性”の示唆する可能性を模索することができる筈である。解の展開例としては、全ての存在物の想念に同化することが可能な人格/神格の分離以前の原存在的不定性もしくは、意識体の全てに潜伏する否定的な負のエネルギーにおいて通貫する自殺傾向を全ての対象に投射しようとする病的性向等が、このプラクシーの概念的本性であるという推測等がなされ得るだろう。物理的特性としてその万物と同一性を共有することのできる特殊能力を記述するならば事象発現以前の“コヒーレンス”において偏在的な潜勢的存在として理解され、反転的にギリシア神話的神格イメージとして何でも誰にでもなることのできる能力を同定するならば変化と流動の神メルクリウスにも相当する、全ての存在の影たり得る汎用的存在性向の持ち主がこのプラクシーなのであった。彼自身が紛れも無く影なので、当然ながら自らの固有の影は持たないことになる。
水中から自分を助け出してくれたピノに、リルは現在地の座標を尋ねて彼女が本物のピノであることを確認しようとする。リルの要請に即座に応じてこの地点の客観的な座標を正確に答えるピノである。しかしピノの語る現在位置は、地球表面を2次元の平面と看做して任意の位置を2つの変数でもって特定する、デカルト座標の理念に基づいたものである。2次元球面としての実際の地球上の3次元空間上の物理的な位置関係を正確に反映させるためには、“多様体”として定義可能な関数の付加を行うことによって修正を加える必要を認めるのが、座標概念の本質であった。このように存在物の個別性を物質の延長性として捉え、座標的空間概念において存在性自体を分別することができることを前提としていたのがデカルトの科学的存在解釈であったが、『エルゴ・プラクシー』においてはこの制約を超出した純観念的な多様体概念をさらに拡張する存在理念が語られていくことになる。
ヴィンセントがプラクシーに引きずり込まれた水底には、かつてのこの都市の人々の生活する街がある。路上に降り立ったヴィンセントに、もう一人のエルゴ・プラクシーの姿をしたものが語りかけてくる。「僕らを受け入れてくれる世界はない。これは僕が見てきた風景だ。ずっと一人きり。誰とも話をしない。だから、自分が分からない。どうして僕は僕で、皆の好きな誰かじゃないんだろう?僕は、誰かのふりをして愛してもらうことを覚えた。でも気付いた。愛されているのは、僕じゃない。誰でもない僕は、誰にも愛されない。だから、僕は消えてしまおうとした。僕らは消えたくても消えることができない。皆を消して、皆の中の自分を消そうとした。でも、駄目だった。一番消したい自分だけが残る。」オフェーリアの町のプラクシーはヴィンセントが極めて有能なプラクシーの一人であることを認め、彼に誘いかけて言う。「その輝き。君となら、僕は消えることができる。僕と消えよう。君は僕だ。」しかしヴィンセントは彼を拒絶する。「俺は、お前とは違う。」プラクシーはさらに畳み掛けて言う。「僕らは一人きりだ。皆、僕らを置き去りにしていく。」ヴィンセントは改めてこの相手の本質を理解して言う。「お前みたいにならなくて、よかった。」スーパー・マーケットの名としてあらわれていたオフェーリアのイメージを通して繰り返し暗示されていたのは、ラファエロ前派の画家ジョン・エヴェレット・ミレーの描いたオフェーリアのポーズをとって水に浮かぶリルの保持する存在性向ではなく、むしろリルとは対蹠的な自己沈潜する不毛な憂愁症という極めて否定的な精神エネルギーの所有者であるプラクシーの持つ、水没による自死への願望なのであった。
“憂鬱”を原初的作動因として捉えて、その現象界面における派生的具現化を天変地異や疾病や超常現象等に看取して世界の総覧を図ってみせたのがロバート・バートンの『憂鬱の解剖学』であったが、ヴィンセントがこの万人の精神内部に潜むプラクシーとの遭遇を果たし、彼の心霊的本質を見抜いてその勧誘を拒否した経験は、『エルゴ・プラクシー』の最終的な主題の収束に大きな影響を与えるものとなるのである。
23:47:26 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック