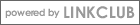Complete text -- "『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 3"
24 February
『エルゴ・プラクシー』論〔2) part 3
一見したところ“旅物語”的なシチュエーション・コメディの形式を踏襲しながら、仮構映像作品『エルゴ・プラクシー』は各々のエピソード毎にプレゼンテーションの手法そのものを大胆に変化させて、独特の主題提示の展開を図っていく。しかし省察16「デッドカー厶」(無風)においては、動力源を持たず風力のみを用いて推進するセンツォン号が完全な無風状態に陥り停滞する中で、新天地への到来も新事件の生成も全くもたらされることのない、“旅”の要素の全てを棄却した特殊条件の許でヴィンセントとリルのセンツォン号内部での日常を描くことにより、見事に反転的な“旅物語”の様相が提示されることになる。目的地へ接近する術の全てが閉ざされた圧倒的な無為の時間を強要されて、いかにも人間的な焦燥の感覚に支配されて苛立つリルの心情が描かれたこのエピソード“Dead Calm”は、ロマン派の詩人・哲学者であるサミュエル・テイラー・コールリッジが書いた高名な哲学詩「老水夫行」の存在をさりげなく背景に暗示しているものと思われる。信天翁を意味なく殺害した罪の罰として、無風の海洋上で強いられた“無為”を通して世界の実相と対峙することを余儀なくされた一人の水夫の物語は、このアニメの心情面の主役というべき人間の人間性たるものの代弁者であるリル・メイヤーの心霊的位相を、裏側から補完するものであるのかもしれない。
目的追求の進路を閉ざされた中でリルがプラクシー=ヴィンセントの行動実態の観察に続けてオートレーブ=ピノの利き腕について観察を行うエピソードは、取り分け印象的なものとなっている。三次元的に捉えれば鏡像である反転文字は絶対座標軸を定めない限りは同形である筈なので、人間社会の慣習に染まることのない幼児などは、これらの“鏡文字”を区別する感覚を知らなかったりするのだが、高分子化合物として多糖類のあるものは“右巻き構造”を持つ“dextrose”と“左巻き構造”を持つ対称的な変異形のそれぞれを持っていることが知られている。この“変異形”は、語義的には“dexter”(右)に照応させて“sinister”(左)を冠して“sinistrose”と呼ぶべきものである筈だが、この名称は病理学的な意味の専門用語としてフランス語で“悲観主義”の意で用いられ、英語の“pessimism”に相当する異界面の意味を担わされて用いられることになっている。しかし生物体が対称的構造体であるこれらの高分子化合物を消化・吸収し同化作用を行おうとする際には、鏡面的組成を持つ物質が生体活動に不適合を及ぼすことが知られている。このように純粋に物理的な形象として見れば客観的に同形である筈のものたちも、宇宙全体を支配する偶発的なモメントの影響を受けて現象世界の基幹設定の中では決定的な差異性を条件づけられていることは、よく知られた事実である。現宇宙における“物質”と“反物質”の存在比にみられる圧倒的な偏りも、同等の隠された選択原理を暗示するものであるように思われる。太陽や星々の示す旋回方向として自然に対する観察結果と経験則から得られた憶測を反映して、英語の語彙においては“右”を表す“dexterous”が“器用な”という意味で肯定的に捉えられ、“左”を表す“sinister”は“不気味な、不吉な”という意味で否定的に捉えられているように、左右の物理的対称性は決して現象世界の位相における同格性を示すものではない。ちなみに中世の日本では“左大臣”は“右大臣”よりも格上であったりもした。純粋知性の理解の外側で世界を支配して偶奇性を選択する“モメント”の存在に想いを馳せずにいられないのが、否応無くその支配下に身を投じている“人間”なのであった。プラクシー=ヴィンセントとオートレーブ=ピノに対してリルが行う人間的知解追求衝動に根ざした観察行為と、彼女自身が行ういかにも人間的な行為である化粧を真似るオートレーブ=ピノとプラクシー=ヴィンセントの模倣行為と、そして自分の仕草を真似るピノをリルが観察する折り畳まれた観察シーンは、“観察”する人間とその人間を“模倣”する神の姿にもう一つの存在軸を加えて、“人性”の中に潜伏する原存在的“神性”の拡張解釈を目論むものとなっている。神の行う人の行動に対する模倣行為は『エルゴ・プラクシー』の最終的主題を暗示することになる訳だが、充電中のピノの示す印象的な無機質の表情やこのエピソード最後のあたりで示される見事な風の描写などを加えて、16話「デッドカー厶」は生半可な概念で括って主題解説とすることを許してくれない、映像を用いた完成度の高い“純文学”的な出来映えになっている。祖形の規範を転覆するジャンル破壊的要素を意図的に採用したエクストラバガンザとして、映像作品『エルゴ・プラクシー』は『ドン・キホーテ』や『白鯨』等の文学史上の傑作と並んで、仮構の伝統の中に独個の位置を主張する挑戦的な企図を含むもののようである。
省察17「終わらない戦い」の冒頭は、管理局局長ラウルが官警に追われているシーンから始まる。ラウルは彼を追ってきたアントラージュを銃撃して破壊し、宣言する。「手遅れですよ、執国。私はもはや、良き市民ではない。」ラウルのロムド秩序に対する反抗の決断がいかにしてもたらされたのかが、この後に時間軸を遡って描かれることになっている。ロムド・シティの管理責任者としてラウルは検体逃亡とこれに関連して生起した一連の事件の内実の把握を試み、この管理された楽園都市の裡に秘匿されていた悲しい真実を暴くこととなる。
ラウルはデダルスに案内をさせて人間生産装置“ウーム・シス”の検証をする。それは独立して機能する力は持たず、プラクシーの存在を核にして初めて効果を及ぼす装置なのであった。一方的にプラクシーに依存して生を送っているのがラウル達ロムド・シティに生きる“人間”たちの実態だったのである。「プラクシーなしで、我々は存在維持すら困難。」しかしラウルは、移民のヴィンセント・ローがこのプラクシーそのものであることを知ってしまった。「ヴィンセント・ロー、彼女が追っていた存在。彼がプラクシーだった。代表がロムドに渇望した存在。」さらにラウルはもう一つの秘密についても語る。「ラプチャーは既に封印された過去の遺物。」デダルスとの会見の後、局長室の中で15話の舞台となっていたクイズ・ショーの有様をテレビ中継で観ているラウルの姿がある。何者かの手によって「悪夢のクイズ・ショー」の有様は衛星中継されて、ロムド・シティでも視聴されることになっていた。クイズのヒントとして提示されていた“勝ち組”の文字を背景に、ラウルの眼前に侮蔑的な表情をしたヴィンセントの姿が現れる。文章による記述とは異なり映像による表現では、この姿がラウルの主観が投影した幻影なのか、あるいは何らかの実体の残した実際の映像なのかは定かではない。ここに現れたヴィンセントの姿をしたものの正体は、この物語の終結のあたりでようやく開示されることになるのであるが、ラウルの視線の先には画面の中の“Rapture”の文字も見えている。
ロムドでのラウルの動向と平行して、旅の途上にあるリルとヴィンセントが新たな小世界を発見する様が描かれる。姿の見えなくなったピノを探して入った洞窟の中でヴィンセント達が見つけた生物は、デダルスが管理していた人工子宮の内部に利用されていた生体と同一のもののようである。ラウルはその姿を見て、嫌悪感を隠すことができないでいた。人々は自らの力では子孫を残すことさえもが叶わず、この生物の体組織を利用することによって、かろうじて人間の生産を可能にしていたものであるらしい。1話における愛玩用オートレーブのピノを検査するヴィンセントと局長の妻と名乗る女性の会話や、8話のハロスの塔における司令官オマカトルとパテカトルの会話などを総合すると、個別の生物種としてはなはだ不完全な機能しか与えられておらず、極めて歪んだ生を送ることを強いられている、この世界の人間達の悲惨な生の実情が分かってくる。ラウルは執国の前に進み出て語る。「考えていました。ロムドの意味を。我々は市民なのではなく、囚人だったのではないかと。」/「環境の回復を待つために建設されたこのロムド。我々はここを離れては生きていけない。」/「外の世界は回復し始めている。なのに、我等にとっては未だ死の世界。」謁見室で厳しく執国ドノブ・メイヤーを問い詰めるラウルの前には、執国と並び立つように再びヴィンセントの姿をした者が姿を現している。
ドーム・シティ=ロムドの閉塞した環境の不自然な実態を厳しく指摘するラウルの言葉と重なるように、洞窟の中に細々と生息を続けていたらしい生物の哀れな現状をリルは見て取る。「彼等は正常な大気のもとでは生きられない。毒に冒されながらも、洞窟から離れることができない。」リルとヴィンセントが発見した、有毒ガスの発生する洞窟の中でしか生存することができず、外気にさらされると即座に死を迎えてしまう生物は、非酸素系の生物の名残として知られる、深海のマグマ噴出口周辺に生息する“チューブ・ワーム”を連想させるものである。本来の地球上に生成した原初の生命は、メタンガスの中で代謝活動を行う“メタン系”の菌類であった。生存競争の結果、他の種に対する攻撃的な機能として酸素という毒物を放出する新種の生命体が誕生し、競合する菌類を駆逐して地球の大気が酸素で覆われるようになった環境の劇的変化の後に生まれて来たのが、現在地球の大半を占める酸素系の生物達であった。酸素の供給を絶たれた特有の環境の中でのみ生き延び続けて来た数種類の嫌気性細菌や古代生物の残滓であるチューブ・ワームなどの研究から、これらの酸素を毒物として認識する生物達こそが地球の生物の始祖であったことが判明したのである。惑星の本来の主として認めるべき生息生物の基本属性に対する認識の激烈な転換を示すこの例に従えば、プラクシー=人間=オートレーブのそれぞれがそれぞれの環境と条件内における“造物主”であり“被造物”であり、また“原種”であるという解釈を許すことにもなるのだろう。
ラウルが執国に対する反逆の最終的な意思表明として、“全てを絶望で覆い尽くす”目的のために発射したミサイルの名が“ラプチャー”であった。今では不要のものである筈の大量破壊兵器が、“ラプチャー”(歓喜)という名で呼ばれて保管されていたのは、映画『猿の惑星』で活力を失い果てた未来人達の信仰の対象として核ミサイルが残されていたことを思い出させる。“ラプチャー”は聖書『テサロニアン』の終末論にその記述が見られ、末世における神の裁きとして人々の魂を地上よりさらっていく行為として理解されていたものである。“ラプチャー”の本来の意味が“連れ去る”というものであったことは、世界の破滅でもって予言の成就が叶えられるとする、現世否定的なキリスト教の世界観を暗示している。ラウルはこれと同様に、あるいはある意味で全く正反対に真正の“絶望”を用いて、ロムドにおいてドノブ・メイヤーによって維持されて来た偽りの信仰を転覆しようと企てるのである。反抗と逃走と、引き続く自らの拘束までをも巧みにその手段に用いて、ラウルはラプチャーの発射と目的物の破壊を成功させることになる。
00:00:00 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック