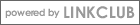Complete text -- "『エルゴ・プラクシー』論〔3) part 2"
21 March
『エルゴ・プラクシー』論〔3) part 2
プラトンの唱えたイデア説が仮定していたのと同様にあらゆる抽象概念に対応するプラクシーがそれぞれ存在するとすれば、抽象名詞のみならず固有名詞にもその適用が及ぼされることに取り分け不審を感じる理由はない。“ディズニー”というプラクシーと彼によって創造された“ディズニーランド”という被造世界が、システムとしての完結性を持つドームやタワー等と同様に規定された概念構造体として確かに存在し得るからである。しかしながらグッドと同様の人格に対応する種々のプラクシーの存在可能性が網羅的に認められるとするならば、「放たれたプラクシーの数は全部で300体」とされていたクイズ・ショーで語られた情報には信頼を置くことができないことになる。現存し得るプラクシーの数は遥かに大きいものでなければならないことになるだろう。もしかするとこのあたりの完全性からの“ずれ”が、プラクシー存在を創造した彼等の創造主である“人類”の限界を示すものであったのかもしれない。しかしながら『エルゴ・プラクシー』において登場していた数体のプラクシー達の保有する属性の傾向とその特質の多様性を見る限り、これらの“人によって創造された神”の内実にはその創作者としての人間存在の構想力の大きさを推し量るに値するものがありそうである。ルネサンスの万能の芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが創作行為の哲学的拠り所としていた、神ならざる人間の準創造行為の秘める意義が、この“個”たるもののなし得る宇宙の反映的創造行為であった。ルネサンスの神秘思想家フィツィーノが宇宙に看取した人の精神活動をも含めた総合的な知の自律進化の作用は、クザーヌスの構想した全と個の反転的合一の理念を見事に反映している。神あるいは宇宙と人との間にある潜伏した関係性を慮るにあたってさらに興味深いことは、このプラクシー=グッドが自ら造り上げた被造物達の叛乱にあって、その創造主としての権威を転覆される場面が描かれてしまっていることだろう。この支配/従属関系顛倒の事実も、『エルゴ・プラクシー』の中心的な主題を照射する伏線となっているのである。
被造物のアニメ・キャラクター達にスラップスティックの常套にある通りの演出で袋叩きに遭って、創造主としての誇るべき権能を剥奪された哀れな創造主グッドに対して、子供らしい優しい心を知ったピノは同情の念を覚えることになる。ウィル・B・グッドと死のプラクシーであるヴィンセントとの遭遇を避けるために、センツォン号の前方の視界に現れたスマイル園に進路を向けることを止めるように訴えるピノの目に落ちた雨の雫は、省察12「君微笑めば」の雪の欠片がそうであったのと同様に彼女の流した涙のように見える。座標概念に基づいたデカルト的存在物解釈によらない、様相と属性の相当性にのみ同一性条件を認める心霊的存在解釈に従えば、人形や絵姿に人格や魂を感じ取る主観心理の意味性賦与の原理が教える通り、狐の姿に化けた狸が“正体が狸であるところの狐である”と判断されるのと同様に、あたかも涙のように流れる雨の雫は“正体が雨であるところのロボットピノの流した涙”ということになる。絵画や彫刻において画布上や大理石の表面に現出した涙は、実在する人間達の眼から無様に垂れ落ちる水滴よりも、遥かに“涙”の本源的な特質を満たしたものであるに違いない。現象世界で具現化される人の涙は、所詮眼から垂れ落ちる塩水でしかないからである。
これに続くエピソードである省察20「虚空の聖眼」において『エルゴ・プラクシー』は、その存在/現象再解釈における最も挑戦的な企図を現前させることになっている。これもまた新規に登場するもう一体のプラクシー存在の及ぼす影響を通してではあるが、省察の主軸となるものが示されるのはそのプラクシー自身の保持する特性や属性においてではなく、むしろ主人公ヴィンセントの“ヴィンセント性”自体に関する再解釈の要請においてなのである。ヴィンセントは、いつの間にか自分がリルの姿になっているのに気付く。病室のベッドに横たわったままで鏡の中を覗き込んだヴィンセントは、自らの外観がすっかりリルのものとなっていることを知る。「けれどそこでは俺の意志は全く反映されず、俺がリルの行動に影響を及ぼすことはない。」リルとヴィンセントはいつの間にかロムド・シティに帰還していたのであった。しかし彼の発見した重大な変化は、ヴィンセント自身の外観の変貌とは実は全く別種のものであることが判明する。リルを診察したセラピスト・スワンは、ヴィンセントの意識に呼びかけて語る。「リルは交替意識状態にあるのよ。簡単に言えば、二重人格。彼女の罪悪感、ヴィンセント・ローを裏切った事実が、自らの中にあなたというもう一人の人格を作り出してしまった。」このエピソードの冒頭でヴィンセントの意識として登場していたものは、実はリルの内部に生成した仮想的なヴィンセントの人格であったというのである。リルによって作られたリルの中のヴィンセントの偽りの意識は、リルの策謀に陥って実験室の中に拘束された姿で捕われている自分自身の姿を、リルの眼を通して確認することとなる。
さらにリルの中のヴィンセントの擬似人格は、ヴィンセントとしての願望に従ってロムドでの彼等の立場と周囲の環境をも改変し、奔放な妄想に基づいてあり得ない状況を捏造してしまっている。リルの意識の一部である疑似人格ヴィンセントが無意識に投射した欲望が、平行世界の一つをヴィンセントの意識を中心に創出してしまっているのである。しかしヴィンセントは、実体を持たない仮想的なヴィンセントの自覚として経験したこの異常な体験の全てが、新たに登場したプラクシーであるスワンが造り出した幻想であることに気付く。そのきっかけは、いつも彼が身に付けていたペンダントであった。「いくらリルさんでも、俺はこれを手放したりはしない。」多重人格症に陥っていたリルの偽りの自我の一つとされていた虚像のヴィンセントは、プラクシー=スワンに陥れられた暗示から逃れ出て錯乱の中から自身の本来の精神の回復を勝ち取ったかのように見える。しかし以下に示されるヴィンセントの幻想中のヴィンセントとプラクシー・スワンの会話は、巧妙な精神攪乱を仕組むプラクシーの及ぼした単なる暗示以上の“セルフ”の成立する要素の介在を示唆するものである。自らの妄想が造り上げて来た虚像を実体験として錯視していたことに改めて気付いたヴィンセントは言う。「こんな世界は存在しなかったんだ。」それに対してスワンが答える。「じゃあ、ここにいるあなたは誰?この世界が偽りだったら、あなたは誰かしら?あなたはここにいるわ。その存在さえ否定するの?」ここで彼女の語る通り、このヴィンセントの意識は現在の自分自身の実在感を否定する主張を行おうとしているのである。“多重人格障害”とも呼ばれる“交替意識状態”においては、催眠術の暗示にかかった場合のような喋り方や日常生活上の癖や思想のあり方などの主観的意識の変化のみならず、アレルギーや左右の利き手や眼鏡装着等の視力に関わる肉体的条件においてさえも、全く異なった“別人格”あるいは“個人存在”の状態を交替するものであった。この症状の特質の一つとしては、特定期間の意識と記憶の欠落が経験されることである。時空的断絶の介在に関わらず主張し得る意識存在の同一性維持の可能性を示唆するこの事実は、デカルトが考えたような「考える、故に我あり。」の自己の存在証明の図式を適用することを困難にする、科学的検証の結果得られた具体的観測例の一つと言えるだろう。ヴィンセントは想う。「我思う、故に君在りか?」バークレー司教が仮定したように世界そのものが神の思念であったとしたならば、その意識の中の被造物たちは己の意思に基づいて時には自らの現存性を証明し、考えるが故に存在する自分自身を確証するばかりでなく、考えるが故に存在する他者の全てを確証することになる。その考える主体は、時には他者の中の擬似人格ですらあり得るのである。“交替意識状態”も“多重人格障害”も、人間の被る“精神障害”として見れば“split personality”という言葉で記述される一現象であるが、描像を反転させて全体性の宇宙に対する汎神論的解釈からこの事例を把握し返すならば、“物質と精神”の分裂あるいは“神と人間の分裂”などという形而上的概念との関連から捉え直してもよいものだろう。本編に登場した精神内部に働きかける暗示能力を持ったプラクシーがヴィンセントの意識に示唆していたのは、“科学”の枠組みを越えた別界面の“個体”あるいは“存在・現象”解釈の可能性なのである。「虚空の聖眼」は“夢物語”と同じような構造性を呈して、一見したところ“暗示から醒めた現実”に収束するストーリーが語られたエピソードのようにも見える。“夢物語”はシステム構造的に、完結した“夢”という概念を内包する高次元世界の存在を外部構造として仮定するものであり、ゲーデルの定理に当てはめれば“夢を見ている間は、それが夢であるか否かは判断できない”こととなる。さらに“夢”と夢の絶対的外郭世界として想定された“現実”との関係性においても、“現実”の中に生きている限りはそれが夢であるか否かを判別する絶対基準は存在しないことと同様に、「この私は私が今考えている“私”を越えたより高次元の私の一部ではない」と確証することは決してできないのである。
「虚空の聖眼」においては、ウィリアム・ブレイクの『4ゾア』や、エドガー・アラン・ポーの『ユリイカ』等が掘り下げた、精神と世界の相関における分裂と統合についての形而上的思弁と等価の思念が提起されている。興味深いのはむしろ、スワンの暗示の中でヴィンセントによって経験された主観が示唆する、個人の存在解釈に関する新たな仮説である。他人の意識の中の“私”が紛れも無く“私”のもう一つの位相でもあり得る可能性を示唆するものとして、今回のプラクシーの及ぼした精神的干渉はこの『エルゴ・プラクシー』の根幹的主題に深く関わるものとなっている。自分がナポレオンであると妄想するものが、そのように思念する限りにおいて何らかのナポレオン性を充当するものであるとするならば、リルの意識の中のヴィンセントが紛れも無くヴィンセントであることの同一性を主張し得ることになる。ヴィンセントの中のヴィンセント意識もリルの意識中のヴィンセントも、一つの意識の所有者としての人格同定条件においては全く同一の“セルフ”だからである。時間・空間的延長性の束縛を超出して、意識体個々の“個体”としての座標的拘束を離れて無限の多世界間に貫通すると思われるヴィンセントの“メタセルフ”の存在を仮定し得ることを暗示する理念が、ここに示されているのである。
00:06:09 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック