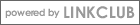Complete text -- "『エルゴ・プラクシー』論〔3) part 3"
21 March
『エルゴ・プラクシー』論〔3) part 3
省察21「時果つる処」の冒頭には、サミュエル・ベケットの不条理劇「ゴドーを待ちながら」の決して来たることのない神ゴドーを待ちながら道端に座り込んで空虚な会話を交わすエストラゴンとヴラジミールを模して、センツォン号の中でウサギの数を数えながらヴィンセントの帰りを待っているピノの姿がある。センツォン号の旅人たちが戻ってきたロムドでは、大部分のオートレーブ達がコギト・ウィルスに感染して都市は大混乱に陥っている。痺れを切らして市街へ足を運んだピノの前にも、感染した一体のオートレーブが現れて跪きながら宣言する。「我は存在理由から解放され、我が我である理由を求む。」オートレーブ達は皆、人に尽くすための奉仕機械として与えられたレゾン・デートルからの脱却と、独立した一個体として獲得すべき新たなレゾン・デートルへの渇望を叫んでいるのである。都市という構造体にも、都市の機能を維持する住民とその補助要員の“オートレーブ”にも、与えられていた意義性の瓦解と解体の時が訪れているのであった。ラウルの命令でデダルスが開発した人類改造計画=ADWプロジェクトが、失敗に終わったことが分かる。
リルの独白が続く。「ロムドを前にして、ヴィンセント・ローは忽然と消えた。…この二日間、この街で時折見かけた彼。その姿はエルゴ・プラクシー。誰との接触も拒むような哀しみに支配されているように見えた。別れたものは、一つにならねばならない。ヴィンセントがプラクシーと一つになった時、そこに残った存在は私の知っているヴィンセントと同一だと言えるのだろうか?」リルはロムドの惨状とプラクシーの姿に変わったヴィンセントの姿を見て、一つになるべき“分かれたもの”とは、ヴィンセントとプラクシーのことかと考える。さらにリルは彼等の分裂の原因として、自分の存在があったかもしれないことを危惧する。
情報局の局長はリルの帰還を認めて、リルに語る。「移民地区の隔離だけでも大変だったのに、今度は例のADW関連の確認データだけでこれだけあるんだ。愚痴の一つも言いたくなるよ。…厚生局から提出された例のADWによる副作用のデータだ。」リルの上司は秩序を失い混乱に陥ったロムドの惨状を直視することができず、机について“いつも通りの仕事をテキパキとこなしている”つもりになっている。しかし彼の指が弄んでいる机の上には、彼が処理しているつもりの書類は一枚も見当たらない。本人は飽くまでも日常的な現実を見失っていないつもりなのだが、彼の現状は幻想への退行以外の何物でもない。いかにも悲惨な精神の極限状況が描かれた残酷なシーンのようにも見えるが、実は我々の現実世界の日常の大部分が呈しているのは、彼の体現しているものと同様の思考の退行現象に他ならない。大概の役人や会社のおじさん達やほとんど全ての教師どもは、彼と全く同等の行動パターンで毎日を生きている。それが“日常”と呼ばれるものの偽らざる定義なのである。
エルゴ・プラクシーの姿のヴィンセントは、実験室の検体の死骸を確認している。ヴィンセントは、逃亡した検体を殺害したのが自分であることを認める。「モナド・プラクシー。殺したのは俺だ。…だが、何故ここまでする?ドノブ・メイヤー。」検体の死骸は、陵辱に等しい扱いを受けて保管されていたのである。ヴィンセントが殺害した検体は“モナド・プラクシー”であった。その遺骸の収められた容器には、“Proxy No 13”の札が付されている。ヴィンセントの手にあるキーには“??”のナンバーが刻まれている。そしてもう一つのキーには、“?”のナンバーがある。そこでヴィンセントはもう一人のリル・メイヤーの姿をしたものと出会う。
デダルスは、戻って来たリルにロムドの現状を説明して語る。「ウー厶・シスが沈黙した。ウーム・シスの沈黙の理由は、」/「モナドの、いや、ヴィンセントの不在。」/「それでラウルが、自分たちが変われば必要ないと言い出した訳。それがADW。…簡単に言うと人体改造かな。」局長室のコンピュータ画面上には“ADW: Project Aus Der Wickel”の文字が見えている。Wickel は“襁褓(むつき)”つまり“おしめ”、“おむつ”のことなので、“Aus Der Wickel”は“襁褓より脱して”、すなわち“成長、自立”を意味すると思われる。デダルスはさらにもう一つの重大な秘密を暴露する。「君をここで襲わせたのは、ラウルじゃなかったよ、意外なことにね。」これはお爺さまの愛顧を信じていたリルには信じ難い事実であった。執国にとってリルは、使い捨てのオートレーブ同然の存在だったのである。
執国の謁見室に現れたヴィンセントを迎え入れて、ドノブ・メイヤーのアントラージュ達は告げる。「既に時は果てた。創造主よ。」執国のアントラージュ達は、ドノブの心を代弁してエルゴに語るのである。「執国は愛した。」/「創造主はロムドを創り上げ、我らを生み出した。」/「オートレーブを与え、子をなす力を与えた。」/「執国は憎んだ。」/「我らは何故存在するのか。」/「我らの孤独は何者が癒すのか。」/「何故我らを捨てた。」/「何故愛してはくれなかった。」/「執国は求めた。」/「創造主ではなく。」/「奪った存在。」/「モナド・プラクシーを。」創造主によって人に奉仕をすべく造り出された道具達が今、人の想いを代弁して厳しく創造主を譴責しているのである。世界を構築すべき基礎単位となるものたちを規定する存在物の意義性自体が瓦解している有様であった。ヴィンセントは、ただ涙するばかりの無言の執国ドノブ・メイヤーを殺害してモナドの復讐を果たす。
続く省察22「桎梏」においては、全てのリルとヴィンスの位相を占めるもの達が勢揃いして、リル=ヴィンス=モナドのそれぞれの間の秘められた関係性が明らかにされることになる。
パパの家に戻って、ピノは一人でお絵描きをしている。既存の作品を描き写すのではなく、頭の中に浮かんだものを描き出す純粋に創造的なこの行為は、ロムドを脱出して外部のコミューンを訪れた時には不可能なものであった。ドノブ・メイヤーの謁見室を訪れたリルの目の前に、もう一人のリルの姿をした者が現れる。彼女はリルに語る。「初めまして。もう一人の私。」警戒して銃を構えるリルに、彼女は言う。「哀しいことしないで。…あなたはヴィンセントに私を、モナドを思い出させてくれた人。」新しいリル=“リアル”は、さらに続けてリルに語る。「私は彼を救い出したい。創造主の苦しみから。…このロムドを造ったのは彼。」リルはデダルスに出会い、尋ねる。「あいつがあいつじゃなくなるなら、なら私は?」ヴィンセントの今後を問いただすリルに、デダルスは抑制を失って叫ぶ。「ヴィンセント、ヴィンセント。みんなあいつだ!」リルはドノブのアントラージュ達に、ロムドとエルゴの関係を尋ねる。ドノブの死後隠すべき秘密を失ったアントラージュ達は、今はリルに全てを語る。「真実、それはこのロムドの終わりを意味する。」さらにリルは問う。「ヴィンセントは本当にこの街を造ったのか?」彼等はロムドとエルゴの秘密の全てを明かす。「このドーム、そして良き市民の基となる数十体。」/「後はウー厶・シスでの管理増産。」さらにリルは問いただす。「私は外の世界でいくつかのドームを目にしてきた。それらのドームもそれぞれのプラクシーが創造したものだったということか?…やはりプラクシーは神?」/「そしてロムドは神に見捨てられた楽園。」/「エルゴはこの地を離れた。己への激しい失望と共に。」/「託されしもの、ドノブ・メイヤー。」/「全能者というべきプラクシーは何故この地を捨てた?」/「つまりは全能ではなかったということ。」/「エルゴはこのロムドにとっては確かに神。しかし不完全なる神。」/「その神が創造するものもやはり不完全。」/「そして神は我等を見捨てた。」/モスク侵攻の意図が明かされる。「当然至極なる復讐。」/「だがモナドは我等から光を奪い、その閉じた目で我等を硬く封じた。」リルは漸くヴィンセントの生成の秘密を理解する。「ヴィンセントは、自らがプラクシーであることを忘れるために造り上げられた仮の人格。」最後まで自ら口を開くことがなかった彼等の主人、執国ドノブ・メイヤーの心を代弁して語り続ける4体のアントラージュ達である。「悪事と恥の続く限り、沈黙こそが我が幸い。」彼等の姿を創造した彫刻家ミケランジェロの墓碑銘に書き刻まれた詩と全く同じ台詞である。「我を目覚ますことなかれ。/終わりの時まで。/ただ静かに。」ミケランジェロの詩に語られた絶望的な心情の吐露は、後悔と慚愧の念から逃れることのできない人の“人”性の烙印として見做しうるものであろう。
ラウルは自宅に戻り、ピノの残した絵を見つける。絵の中には、ピノと一緒に並んだラウルの姿も描いてある。一方ピノは再びロムドの町の中をさまよっている。ロムドの崩壊の惨状の中をあてど無く歩き回り、かつての我が家に辿り着いて姿の見えぬパパに向って「あのね、パパ。ピノには一杯の気持ちがあるんだよ。嬉しかったり、淋しかったり、いろんな事。」と呼びかけていたピノだが、その心の中には絶望も不安もひと欠片もない。まるで世界の全ての事象を歓迎すべき善きものとして受け入れているようでもある。眼前の悲惨を何の屈託も無く受け入れるその姿は、ロバート・ブラウニングの「ピッパは行く」(“Pippa Passes”)を思い起こさせる。人々の憤怒と怒号の声の渦巻く町の中を、周囲の惨状に全く気付くことなく神の祝福を一身に感じ取って歩む少女ピッパそのままの姿のピノなのである。「神、空にしろしめし、なべて世は事もなし。」
再び謁見室でリルはヴィンセントに出会う。全てを思い出したヴィンセントは語る。「この町は俺が造った。その全てをこの男に託した。」デダルスによって作られた唯一プラクシーを殺すことのできる武器であるFP光線の発射銃をかざしながらも、リルはエルゴ・プラクシーに語る。「私が引金を引くと?」リルは目の前のエルゴに対してではなく、別の何者かに呼びかける。「今やっと辿り着いた。私の真実に。モスクに残されたメッセージ。二つのペンダント。別れたもの。何度か私達の前に姿を現してきた。聞いているんだろう?ヴィンセント・ロー、そしてエルゴ・プラクシー。記憶をなくし、二つの人格を持つヴィンセントは、お前にとって最高の隠れ蓑だった。だが、私の真実はお前の存在を浮かび上がらせた。ヴィンセントとエルゴ・プラクシーを操り続けたもう一つの影。もう姿を見せろ。今も近くにいるんだろう。」姿の見えぬ誰かが答える。「見事だ、リル。124C41」
キリスト教神話においては全能なる神は世界と人を創り、使徒に命じて自らの手中の世界の運行を取りはからせたとされる。『エルゴ・プラクシー』においては“創造主”、“プラクシー”、“人間”、“オートレーブ”などの様々の権能/可能性を占めると同時に限界性に縛られたもの達が、従来の宗教的教義にあった図式とは多分に異なる双方向的な創る/命じる/操る等の関係を構築して、キリスト教その他の宗教神話にあったものよりもはるかに複雑な存在論的位相の各々を構築している。人間として備わった本来の創意工夫の能力を増幅させ、遺伝子操作や環境制御を応用した世界に対する人為的干渉の結果、造物主のコピーや神の鋳型などの制作をも可能にすることになった“人”と“科学”の持つ潜在的可能性が、種々の表象を通して掘り下げられている。社会と組織の管理を委託された信条の人ラウル・クリードや、ギリシア神話のイカルスの父ダイダロスの名を背負った創意工夫の人である厚生局長デダルスは、このような“人”性の典型的な代弁者であった。“科学”とはある意味で“人間”の定義として用いることも可能な、一つの宗教的概念であると看做し得るかもしれない。そしてまた宇宙の全体としてある統合的存在/機能を対象にして、特定の意図のもとにこれらの部分集合を断片的に分離する思考操作を適用した結果が、“神”や“人間”等の概念であったと理解することも可能であろう。そうした観点から“神の人間化過程”を改めて解釈し直すこともできる。キリスト教における“三位一体説”、つまり「父なる神と精霊とキリストは、同じ一つのものの示す異なった位相の各々である」という教説を、科学的な分析操作の対象とする変換操作を企ててもよい訳である。プラクシー・ワンとエルゴ・プラクシーあるいはヴィンセント、リル・メイヤーとリアルあるいはモナド・プラクシー等それぞれの存在が、神/人間いずれの位相を選択して具現しているかを確認し直す作業を行ってみる必要もある。そのような位相遷移が可能である全体性の機構のシステム理論的把握が試みられた時、その反省作業は極めて“人間的な”科学的営為として認められることだろう。そしてそこに得られた限界点が改めて“宗教”の位相を照射することともなる。
00:08:59 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック