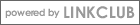Complete text -- "『エルゴ・プラクシー』論〔3) part 4"
21 March
『エルゴ・プラクシー』論〔3) part 4
最終章の省察23「代理人」では、ヴィンセントとリルの前に姿を現したプラクシー・ワンは、自壊装置を作動させてロムド・シティの破壊を開始したデダルスの行動を確認して語る。「来るべき時のために用意されたシナリオを囁いてやったのさ。彼もまた、破壊の衝動に目覚めたようだ。我らのように。」この言葉により、ラプチャーの発射を企てたラウルもまた、プラクシー・ワンの教唆に従って自らの行動を選択していたことが分かる。個人としての存在理由を自由意志によって選び取り、実存的決断を行使したと結果思われていた彼等の行動も、実際にはその能力を超えた超越者によって操られたものでしかなかった。プラクシー・ワンはヴィンセントに語りかける。「その時、全てを理解した。創造主が仕組んだ悪意の全てを。長き苦悩の末、漸く果たした代理人の使命。人類再生を成し遂げた瞬間に始まった体の変調。それが、始まりの鼓動。プラクシー抹殺プログラムの開始。」ヴィンセントは尋ねる。「では、お前は人類を?」プラクシー・ワンは続けて言う。「しかし、我々はそれに抗うことはできない。極めて合理的なシステム。皮肉なことだ。プラクシーは神の使いでありながら、使命を終えれば約束の地に導いた後に残った不必要な因子。それどころか、怪物であり、悪魔に過ぎない。」ヴィンセントは問う。「だが、その合理的な計画によって乗り捨てられた筈の箱船にも、心が芽生えていたとしたら?何故、創造主は我々に心など持たせた?心など無ければ、苦悩など。」プラクシー・ワンは答える。「分かっている筈だ。ああ、答えなど必要ない。何故なら、我々自身、その手で行った試みによって理解した。自らの手で造り出した出来損ない共から、崇められ、裏切られ、絶望に突き落とされ、それでも、愛している。…創造主も愛されたかったのだ。我々が孤独の中でそれを味わったように。だからこそ、彼等には罰を与えなければならない。」愛されたいが故に自らの創造物に心を与えた創造者は、被造物の愛を欲したところで神となるべきものとしての限界性を露にしている。だからこそ裏切られ、罰せられなければならないのである。ヴィンセントは問う。「今更何ができる?彼等が望んだ計画通り、お前が人類を再生したなら。」/「気付いたか?全てを忘れたヴィンセント・ロー。それこそが、予め捕われた影なる存在である証拠。そんなお前を操り、失敗作共の感情を発芽させ、再生した人類を再び抹殺した。」/「では、人類は?」/「影は死ぬ。神亡き世界で、神を望んだ報いを受けた者たちの運命を。人類は滅ぶべきだったのだ。あの世界を崩壊に導き、逃げ出したのだから。丁度お前がこのロムドという自らが生み出した世界から逃げ出したように。ヴィンセント・ローとは、かつての絶望したプラクシー・ワンの残像、いや、エルゴ・プラクシーがこの地に残した影武者、偽物に過ぎない。」ヴィンセントも全てを理解して、納得する。「確かに、エルゴ・プラクシーはお前であり、俺だ。プラクシー・ワン。」ヴィンセントが確認した己の正体は反逆者であり、復讐者であった。
デダルスは、愛想を尽かしたようにリルに言う。「見捨てられたのに。無意味なことだ。相変わらずだ。吐き気がするよ。…大体神々の戦いに、僕たち人間もどきに何ができる。僕たち歯車にできるのは、口をつぐむこと。そう、ドノブのように。」敬愛していたドノブの自分への愛が偽りのものであったことを理解したリルは、思わず語る。「お祖父様が望んだ創造主との邂逅。それが私を生み出した理由だったとしても、私は構わなかった。今まで、ずっとお祖父様を心の底から愛したかった。愛されていると感じたかった。ただ、愛されていると。」人を愛し、臆面も無く愛されることを心から欲するリルは、人間そのものである。デダルスはさらに、プラクシーに課せられた残酷な真実をリルに語る。「残念だな、プラクシーは青空の許で生きることはできない。アムリタがそれを許さない。」/「どういうことだ?」/「彼等もまた、この世界から排除されるべき存在。」その時、頭上に翼を広げて飛翔するリアルの姿を認めて、デダルスは語る。「僕は神を創り上げた。」
戦いを始めたヴィンセントとプラクシー・ワンのもとを訪れて、リアルことモナドが言う。/「止めて、もうプラクシーの役目は終わったのよ。」/「またお前か、モナド。」ヴィンセントも新しいモナドに気付く。「モナド?」/「やっと会えた。ずっと探していたの、あなたのことを。」/「邪魔をするな、モナド。確かに、代理人の役目は終わった。そして、私が再生した人類も絶滅し、不死身の勝者も滅びる。」/「これが筋書き?」/「これが俺の復讐だ。後はお前次第だ。それがお前の世界となる。」/「お前は、お前はまた俺に全てを背負わせるのか。」/「こんな世界、救わなくていい。分かっているの。あなたにそんなことできない。だから、もういいの。」/「止めろ、モナド。」/「みんな終わったの。もう誰の悲しみも見たくない。」/「モナド!」/「また逃げるのか?」空高く舞い上がったモナドは、空中に飛来した飛行物体を認めて呟く。「聞こえる。計画。受け皿と。呼んでいたのは、あなた達だったのね。…ヴィンセント、あなたの選んだ未来は、やはり。迎えましょう。創造主を。」
頭上のモナドの姿を見上げて、デダルスは言う。「駄目だ。その空では、君は。」作り物の翼をつけて飛翔したものの、太陽に近づきすぎて墜落したイカロスの父親がダイダロス(デダルス)であった。ギリシア神話の発明家と同様に、デダルスは自ら造り出したモナドを墜落の運命から免れさせることはできない。空から戻ってきたヴィンセントを迎えて、プラクシー・ワンは言う。「戻ったか。」/「ああ。」/「ヴィンセント・ロー、お前は正に影。影は不死身の我を倒し、鼓動の呪縛を解き放った。」/「それは、お前を苦しめ、そして愛した不完全なる者たちの開放でもあった。」/「その通りだ。未来を見通す女か。確かに彼女が、お前、ヴィンセント・ローの現実だ。太陽が戻る。俺達の世界は終わる。だが、生きろ。ヴィンセント。お前が生きることが、創造主への罰となる。」創造主を運ぶ飛行物体を見上げながら、ヴィンセントは言う。「これが、俺達が向いあう現実という名の世界だ。…だが俺は、リルや生き残った者たちと共に、世界と向き合う。」『エルゴ・プラクシー』の幕を閉じるのは、ヴィンセントであったものが語る以下の言葉である。「再生の時を迎えつつある大地へと、数千年ぶりに人類が戻った今、本当の戦いが始まる。我は、エルゴ・プラクシー。死の代理人である。」
『エルゴ・プラクシー』に導入されていた“人―神”概念変革に対する形而上的理解を探る糸口として、“ATフィールド”という興味深い概念が採用されていたアニメーション映画『新世紀エヴァンゲリオン』と、厚生局長デダルスの姓として暗示されていた夢野久作の小説『ドグラ・マグラ』を参照することができる。『新世紀エヴァンゲリオン』が中心主題として採用していた、“絶対恐怖領域”として自と他を分つ精神的機能あるいは自閉的病理である“ATフィールド”は、『エルゴ・プラクシー』の「分かれたものは一つにならなければならない」という発想において示されている“分離と統合”という概念と深く関わっている。さらに『ドグラ・マグラ』において“神を追放した脳髄”について語られていたものをそのまま反転させて“自我を滅却した神性”と呼び換えることにより、これらの概念の裏面に通底するシステム原理の把握を試みることができる。ATフィールドの発動によって全ての他者のATフィールドを侵蝕し宇宙の全ての分別機能が失われた場合を考えてみると、以下に挙げるような諸概念の混淆あるいは統合が導かれることとなる。〔自分と他人/世界と自分/仮構と現実/妄想と事実/狂気と正気/原因と結果/記憶と予知/行為者と被行為者/意味と実質/可能性と現存性/同一性と類似・相似性〕これらの区別がおしなべて失われる時、時間という次元のみを特定的に解放していた際に観測されていた“ループ”という構造体は、時間次元を内部に含む統合連続体においては相似的な同位体が無数に散乱する多義的な不定形の概念/実質/属性の混淆体として等価的な記述を施すことが可能であることが推測される。『ドグラ・マグラ』においては、律儀にこれらのそれぞれの条件の順列組み合わせ的展開がなされていたのであった。人が主観において経験する“夢”の場合のように、あるいは人が時として陥ることができる“狂気”という状態において可能なように、個々の要因を連結する関係性が解けてしまった時空を超越する開放的直覚において世界の全体像が捉えられた状態、すなわち“理性”による描像に従えば“ゲシュタルト崩壊”が来されたフィールドの投影像とされるものにおいては、相似形のループからループへの跳躍とも全方位的反転原理を秘める捻れ構造とも様々の形で受け止めることが可能な種々の矛盾の併置から成り立つ“多義性”の超越世界が直覚されるのである。『新世紀エヴァンゲリオン』と『ドグラ・マグラ』において具現されている諸場面から、これらの要素の反映と思われるものの検証を試みることができた。“ドグラ・マグラ”が連想させる“ゴグマゴグ”は、古代世界の伝説の巨人もしくは神の名として語り伝えられているものである。しかしこの名で呼ばれていたものは、“ゴグ”と“マゴグ”という双子の存在であったとの異説もある。“ゴグマゴグ”として顕現することもあれば“ゴグとマゴグ”として具現することもあるという存在原理のドグマを特定することにより、『新世紀エヴァンゲリオン』と『ドグラ・マグラ』に照合される同位体的記述を洗い出して、『エルゴ・プラクシー』において展開していた全体性を補完することになる様々の存在概念の実相と関係性を語り返すことができるのである。
プロメテウスは人間に火を与え、神々によって罰せられて山頂で永遠の責め苦を負わされることとなった。ルシフェルは人間に知恵を与え、至高の神によって罰せられて地上に堕とされて悪魔として神に抗うこととなった。プラクシーは火と知恵に代替するものとして人間にオートレ―ブを与え人類再生の使いとして働いたが、その役目が終了すると共に創造主によって無用のものとされた。『エルゴ・プラクシー』においては、人と使徒と人に与えられた道具である機械意識体オートレーブが科学を媒介として様々な位相を保持して相互の関与を行っている。神ならざるものとして、ラウルは追従する堕落を拒み大量破壊兵器ラプチャーを用いて抗い続ける生き方を選んだ。デダルスは自分自身のための神“リアル・メイヤー”を我が手で造ったが、モナドによって見捨てられた。ドノブ・メイヤーは、創造主によって遣わされた使徒の一人と邂逅し、“小世界”ロムドの管理を託されたが、同胞の人間達と共に自らの創造主に見捨てられることとなったため、他の使徒によって建設された別の小世界モスクに侵攻し、自分達の神とすべきものを強奪してきた。そして行方をくらました神/使徒をおびき寄せるため、モナドからリル・メイヤーを造り出し、神/使徒を欺き、操ることを試みた。さらに使徒の分身であるリル・メイヤーが囮としての用をなさないことが分かった時、創造主に体する復讐としてモナドを陵辱し、神/使徒/被造物であるリル・メイヤーの殺害を企てた。
全能の神ならざる使徒プラクシー・ワンは、完全ならざる創造主を罰するための反逆を試み、自らの影としてヴィンセントを生成させた。しかし彼の反逆と復讐も、自らが造り、見捨てた不完全な存在である“人間”ドノブ・メイヤーが既に実際に行った行動の後を追う模倣行為となっている。神は往々にして人を真似るのである。リル・メイヤーは、モナドから造られた使徒の分身でありながら、最後まで自らを人として認識し、飽くまでも人間として足掻き続けている。ヴィンセント・ローは、プラクシー・ワンの分身であるエルゴ・プラクシーとしての存在に目覚めたが、再生されたモナド・プラクシーの誘いを断り、人間リル・メイヤーと共に創造主と再生されるべき人間達と抗い続ける“死の代理人”として自らを“人間化”することになる。当然ながらそれは、創造主によってレゾン・デートルを施された世界を統べるべき“人”とは異なるものである。“一神教”という硬直した思想の受容の結果、キリスト教支配の中で人の中の“神性”は歪められ、病理や怪異や天変地異に堕してしまうこととなっていた。しかしヴィンセントが選び取った存在原理は、神として人に拘束されることも人として神に拘束されることもない存在である。プラクシーとしての本来のレゾン・デートルは、神としてあることも人としてあることも捨てた“デモーニッシュ”な存在として求められるものだろう。阿諛追従する“人”性を不器用に模倣していたプラクシー・ワンの影の存在であるヴィンセントが、飽くまでも傲岸不遜なままに人として振る舞うリルの“人”性を模倣した結果、“デーモン”としての自らの存在原理を見出すのである。かくして分かたれた人と神が、人と神との分別を持たないデーモンという一つのものに還帰する神話が語られることになったのであった。
00:10:11 |
antifantasy2 |
|
TrackBacks
Comments
コメントがありません
Add Comments
トラックバック